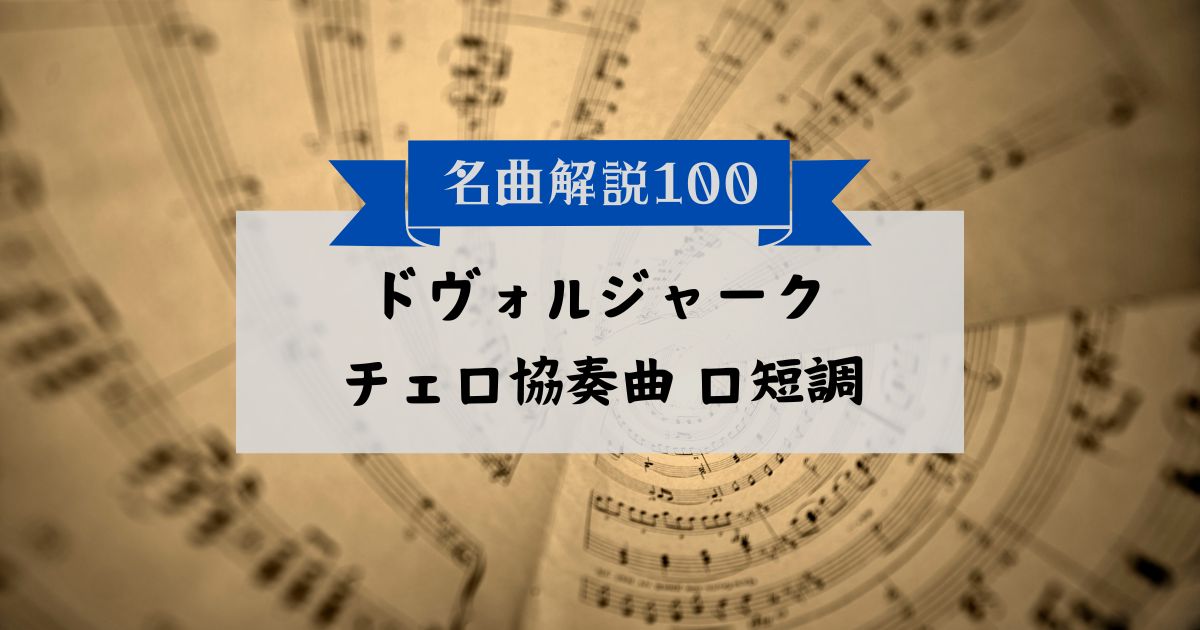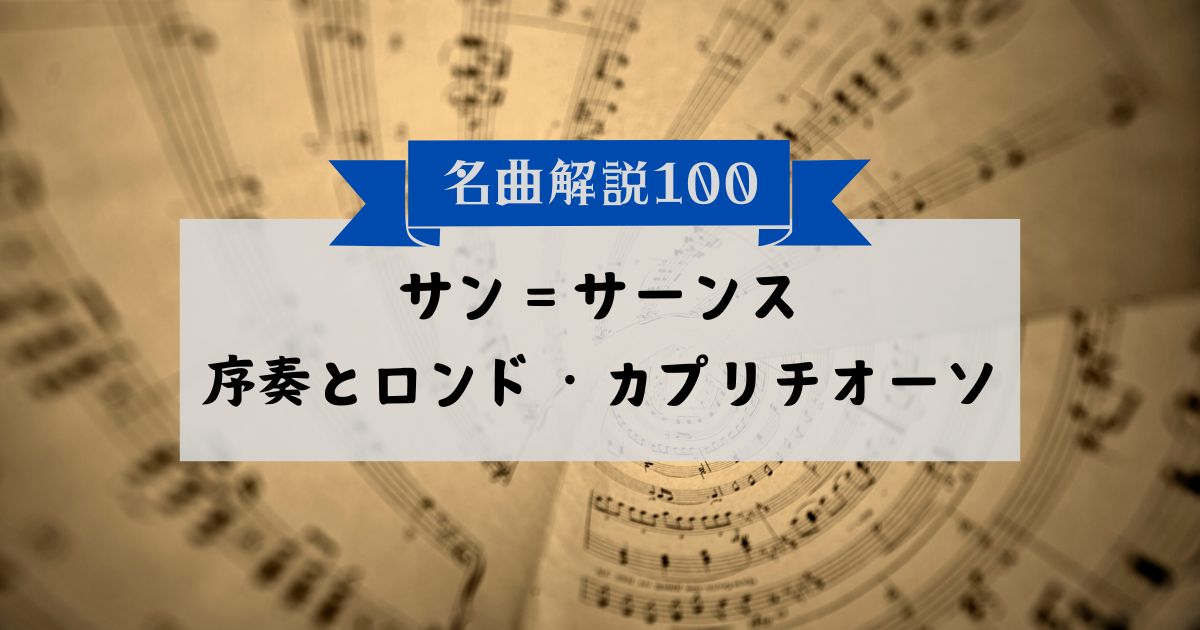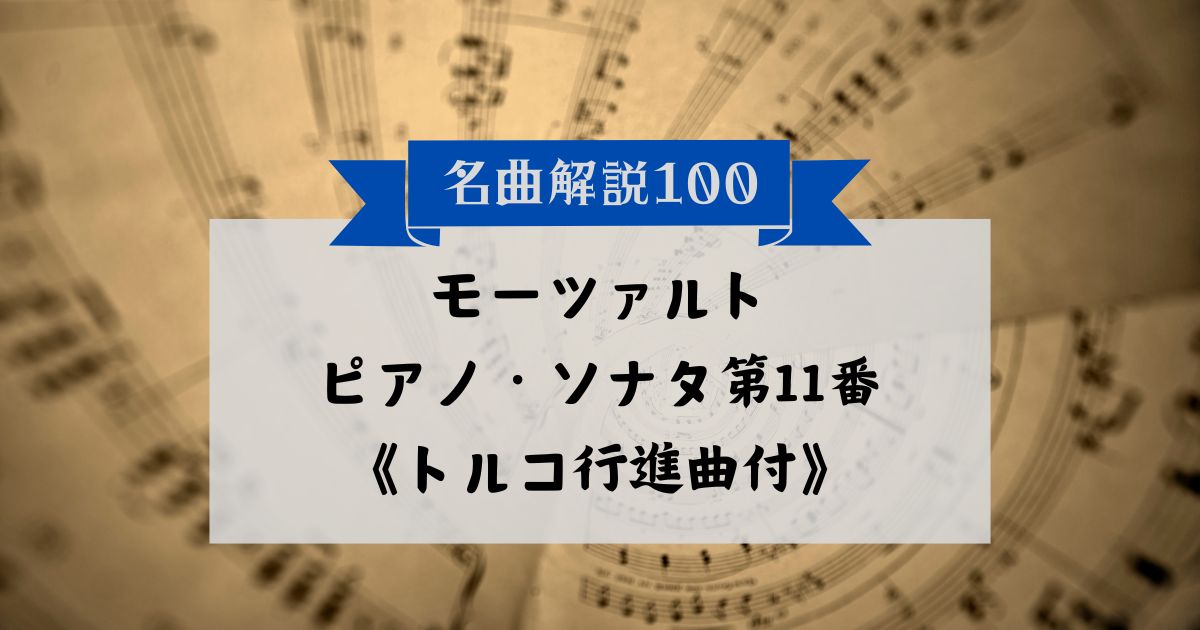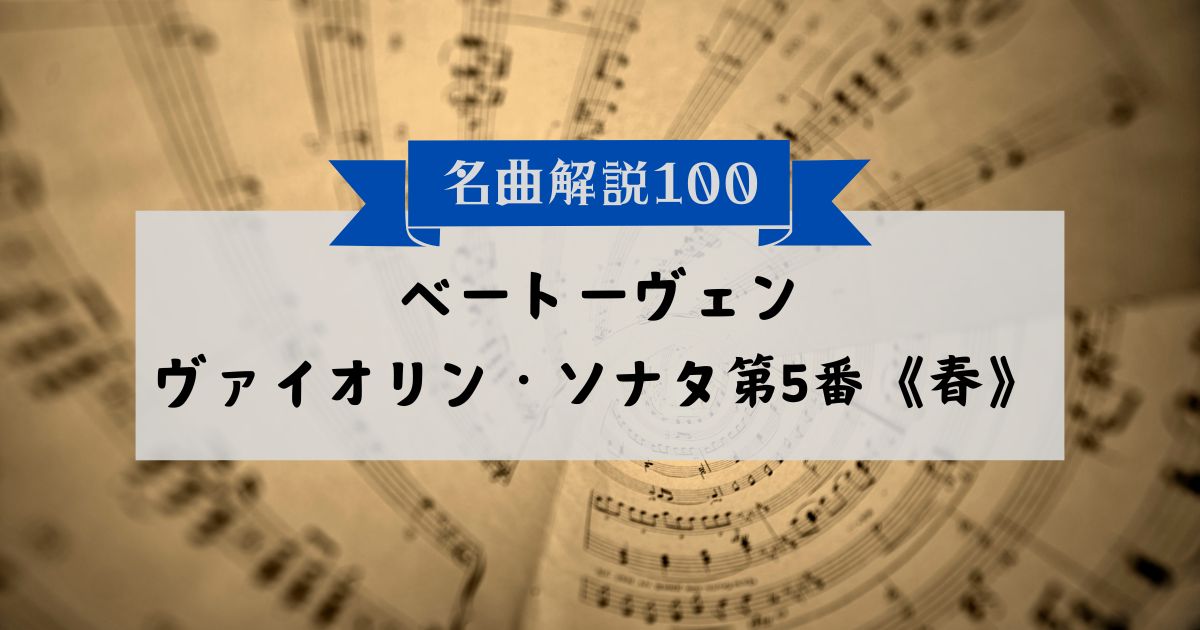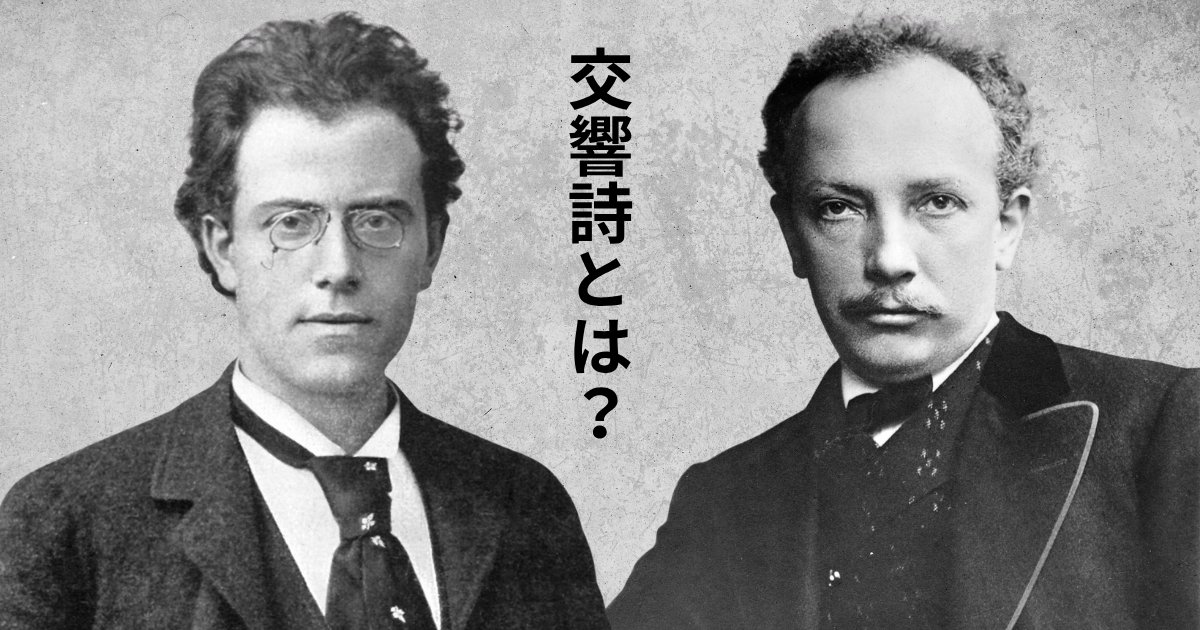ショパンコンクール第3ステージ~日本人3名と海外の通過者のショパン演奏をレポート

10月14日から16日まで、第19回ショパン国際ピアノコンクールの本選第3ステージが開催。日本からは3名が出場しました。現地取材を行なっている音楽評論家の道下京子さんが、日本人コンテスタントの演奏とともに、海外の第3ステージ通過者、そして惜しくもファイナル進出には至らなかったものの、印象に残ったピアニストの演奏をレポートします。

2019年夏、息子が10歳を過ぎたのを機に海外へ行くのを再開。 1969年東京都大田区に生まれ、自然豊かな広島県の世羅高原で育つ。子どもの頃、ひよこ(のちにニワトリ)...
美しく、緻密に音楽を織り上げた 日本人3名の「ソナタ」
【桑原志織】「ソナタ第3番」は圧巻の演奏
桑原は、第1ステージから安定した演奏を披露している。第3ステージのこの日も堂に入ったパフォーマンスであった。「スケルツォ第3番」では、諧謔さを活かしつつ、叙情的な側面も引き出す。続いて「マズルカ」作品33。第1曲や第2曲では、音の芯を心地よく弾ませながら、淡さを漂わせる。呼吸の細やかさとともに、メロディラインを活かした表現が印象的であった。
「ピアノ・ソナタ第3番」は圧巻の演奏! 第1楽章では、彼女らしい堂々とした音楽を構築。第2楽章中間部におけるコラールの優美な趣、ショパン作品特有の高貴さを際立たせた第3楽章、そして第4楽章では、圧倒的な推進力とともにアーティキュレーションを丁寧に描き上げた。
(10月14日午後・スタインウェイ)

【進藤実優】「ソナタ第2番」で客席から拍手が沸き起こる
深く音楽の内面に肉薄した演奏であった。彼女の指から紡ぎ出されるメロディは、途切れることのない緊張感に満たされている。「マズルカ」作品56は、ペダルを抑制して音の遠近を巧みに醸し出し、叙情性あふれる音楽を創出。
「ピアノ・ソナタ第2番」では、卓抜なペダリングを通して豊かな響きを生み出し、音楽を立体的に築き上げていく。第2楽章中間部などでは、作品からさまざまな声を巧みに引き出し、美しく音楽を織り上げていた。進藤がこのソナタを弾き終えた後、客席から拍手が沸き起こる。
そして《アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ》では、リズムに細やかな彫琢を施し、若きショパンの美しいリリシズムと清々しさにあふれる演奏を披露した。
(10月15日午後・スタインウェイ)

【牛田智大】持ち味の構成力が際立った「ソナタ第3番」
「前奏曲」作品45から「マズルカ」作品56へ移っていくところが気に入っていると、牛田は以前に話してくれた。透明感あふれる音のグラデーションによって、美しいショパンの世界を繰り広げていく。「幻想曲」では、音楽の大きな流れにさまざまな感情を美しく一つに束ね上げた。
「ピアノ・ソナタ第3番」は、牛田の持ち味のひとつである構成力が際立った。全体を通して、メロディをたっぷりと歌い上げている。また、内声部における緻密なアプローチも牛田ならでは。
(10月16日午前・スタインウェイ)

関連する記事
-
インタビューワルシャワ・フィルのファゴット奏者がショパンコンクールを振り返る
-
インタビューワルシャワ・フィルのファゴット奏者がショパンコンクールを振り返る
-
インタビューワルシャワ・フィルのコンマスがショパンコンクールを振り返る
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest