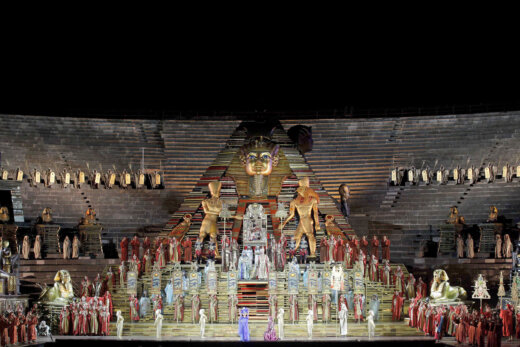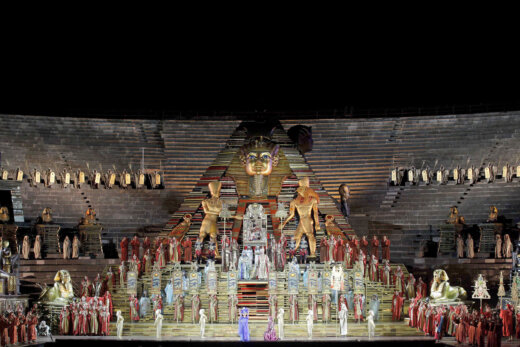
ラファエル・ピション指揮、マスネ《ウェルテル》がパリのオペラ=コミック座で上演

フランスの1月の音楽シーンから注目のオペラ公演をレポートします。

1941年12月創刊。音楽之友社の看板雑誌「音楽の友」を毎月刊行しています。“音楽の深層を知り、音楽家の本音を聞く”がモットー。今月号のコンテンツはこちらバックナンバ...
パリのオペラ=コミック座はジュール・マスネ(1842-1912)の《ウェルテル》(1892年、ウィーン帝立・王立宮廷歌劇場で初演)を上演した(1月23日所見)。
物語がゲーテ原作で、ワーグナー流の半音階や、人物や状況を示すモティーフが使われるというドイツ的な側面は誰の耳にも明瞭だが、当時新しい楽器だったサクソフォーンを使った新たな音色の探究や、18世紀末のフランス人作曲家メユールによる歌劇の影響も受けるという多面性を持った作品で、いまだに人気は衰えていない。
演出は、今夏エクサンプロヴァンス音楽祭の総監督に就任するアメリカ人テッド・ハフマンが行った。ハフマンは長いテーブルと椅子の置かれた富裕な家族の広い食堂を単一の装置として使い、オルガン(第2幕)やクリスマスツリー(第3幕)を付加した。この無駄のない、現実味はあるが抽象的な舞台で、現代の衣裳をまとった歌手たちが自然に動いた。
こうして、母の遺言を守ってアルベールと結婚せざるを得なかったシャルロットと、彼女と相愛でありながら結ばれない主人公の苦悩が、音楽と台本に寄り添って視覚化された。
「胸に手を当てる」といった大げさで感興を削ぐ紋切り型の「演技」はいっさいなく、第1幕では、月の光に照らされた散歩の途中で主人公とヒロインのシャルロットがゆったりと踊り、思わず熱情に突き動かされてひそやかな接吻を交わした。
唯一気になったのはフィナーレで、本来ならウェルテルがアルベールのピストルで自分を撃つ場面である。その代わりに、主人公ウェルテルが手首を切ったところに、ピストルを入れた箱を持ったヒロインのシャルロットが駆けつけたのには思わず首を捻ったが、情感の高まった音楽がすべてを忘れさせてくれた。
題名役は歴代の名テノールが歌ってきたが、今回はサモア出身のペネ・パティが歌った。太陽の光を思わせる明るい音色、場面に応じた音量、きれいなフランス語は魅力的だが、ヨナス・カウフマンのような陰影のある声でないため、メランコリーにとらわれたロマンティックな主人公というよりも、旧弊な教会と社会の掟に叛逆する純真な若者という新しいウェルテルとなった。

批評家の間で意見は分かれたが、台本には178X年と明示されており、マスネの念頭にフランス革命があったことは、台詞のなかにあるキリスト教批判からもはっきりしている以上、一つの可能性であることは否定できないだろう。
対するシャルロットはフランスの若手メゾソプラノ、アデル・シャルヴェだった。台詞がやや不明瞭な点だけを除けば、広い声域を生かして、清らかな娘から若夫人へ、次いで自分の心の底にあった愛情に目覚めた女性というヒロインの変貌を渾身の演技と歌で表現した。
いっぽう、ソプラノのジュリー・ロゼはいままでバロック歌手として注目されてきた。今回はヒロインの妹でウェルテルに恋しているソフィーをオレンジのように香り高く清々しい高音としなやかな旋律線で歌った。この役に欠かせない乙女らしい清らかさと若さだけでなく、やるせない哀感をもにじませて絶賛された。裁判官役のクリスティアン・イムラーを始めとする脇役も隙がなかった。
しかし、マスネの歌劇ではオーケストラが大きな比重を占めている。公演の成否を左右する指揮はバロック専門家でありながら、すでにドリーブ《ラクメ》で成功し、19世紀末フランス・オペラとの親和性を示したラファエル・ピションに委ねられた。
初演時(19世紀後半)の楽器を手にした手勢のアンサンブル、ピグマリオンを率いたピションは、マスネが音色に託した情感を丹念に楽団から引き出すとともに、場面に応じた臨機応変のテンポによってドラマを盛り上げた。
第1幕では恋人二人の月夜の散歩に抒情味をあふれさせ、第3幕から第4幕のフィナーレにかけては破局に向かって緊迫感を高揚させ、観客の手に汗を握らせた。
指揮、歌唱、演出の三拍子が珍しくそろった公演は、仏独合同テレビ局ARTEが1月23日に実況中継した。7月22日までは、オンデマンドで観ることができる。
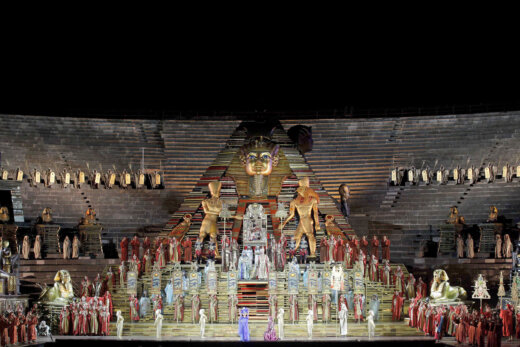




関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest