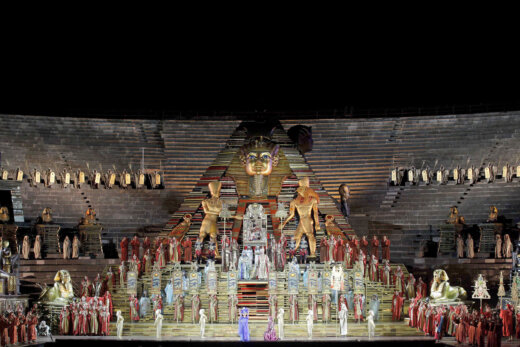オペラとワインの数奇な出逢い。小諸ワイナリーで語る「ソラリス」

オペラ《ソラリス》とワイン「ソラリス」。その2つを結ぶのは、時代を超えて私たちに問いかけてくる、スタニスワフ・レムの傑作SF『ソラリス』。来たる10月31日、東京芸術劇場における《ソラリス》初演を控えて、長野は小諸の美しいワイナリーで、スペシャルな対談が実現した。藤倉大×島崎大が、「ソラリス」の魅力の正体に迫る⁉

ONTOMO編集部員/ライター。高校卒業後渡米。ニューヨーク市立大学ブルックリン校音楽院卒。趣味は爆音音楽鑑賞と読書(SFと翻訳ものとノンフィクションが好物)。音楽は...
ワインを育む太陽の下で
ワインの魅力とはなんだろう。酒飲みとは言いがたい筆者も、ワインは折に触れて嗜む。親しい友人とワインを飲み交わす時間は、学生のときはじめてオペラを観にいったときの特別感をもたらしてくれる。
ロンドンを拠点に活動する作曲家、藤倉大さんのオールタイムベスト映画は、主人公がカリフォルニアのワイナリーを巡るロードムービー『サイドウェイ』と、ラッセル・クロウ演じる金融マンがブドウ畑を相続するところから物語が始まる『プロヴァンスの贈りもの』だという。
そんな藤倉さんが今回訪れたのが、マンズワインの小諸ワイナリーだ。ここで国産高級ワイン「ソラリス」が作られている。

小諸はワイン造りに適した土地だという。年間を通して降雨量が少なく、昼夜の寒暖差が激しい。取材に伺った10月下旬、東京を発ったときは肌寒く感じる程度だったが、小諸では日が傾くにつれて冬のような寒さになっていった。凛とした空気の中、フランス語やドイツ語の名前を冠したブドウの木が枝を広げている。光降り注ぐ美しいブドウ畑に、思わず息を呑んでしまった。

「ソラリス」は、もともと「太陽の」という意味をもつラテン語の形容詞。この地で太陽の恵みをたっぷり受けたブドウたちが、ワイン「ソラリス」になる。
藤倉大さんと島崎大さん――同じ名前(!)と『ソラリス』が生んだ奇縁については詳細を後に譲るとして、まずは島崎さんの後についてワイナリーを見学してみよう。
まるで「ソラリス」の宇宙ステーション? ワイン工場に潜入!
広大な畑の隣にたたずむワイン工場へお邪魔する。
大小さまざまのタンク群では、まさにワインが醸造されている最中。
ワインを楽しむ特別な空間
「ソラリス」のテイスティングは、マンズワイン内の日本庭園・万酔園の中にあるスペースで行なわれた。階段を降りていくと、そこは中世ヨーロッパのワインセラーを彷彿とさせる半地下壕。ワインを楽しむために設えられた秘密な空間といった趣きだ。
程よく酩酊状態になったところで、いよいよ藤倉さんと島崎さんにお話を伺う。
藤倉大×島崎大「ソラリス」を語る
《ソラリス》の世界観を表現する音楽的な仕掛けとは?
藤倉: 音大生のときに『ソラリス』の小説に出逢って、なぜか取り憑かれるように好きになってしまった。島崎さんは「SFが好きだった」とおっしゃっていましたが、僕は別にSFが好きだというわけでもなく、『ソラリス』はSFだと思ったことがないんですよ。
小説は、いきなり宇宙船が到着するところから始まる。で、主人公が心理学者。なぜ宇宙に問題があるのに心理学者を飛ばさなければいけないのかというのも不思議だし、その心理学者が宇宙に行って、エイリアンに遭遇するという話でもないじゃないですか。(宇宙ステーションで)寝て起きたら、自殺して死んだはずの妻が目の前にいるっていう。その妻と思われる人物は、殺しても殺しても戻ってくる。その妻であったハリーは、自殺ということにはなっているが、実際どうやって死んだのか?
これは僕の想像ですが、主人公は心理学者ですから、地球上でも尊敬されるポジションにいるんでしょうね。でもソラリスにいると、心の奥底で罪の意識を抱いていたものが、どんどん具現化する。ソラリスの宇宙ステーションの中では、キャラクターがみんな悩んでいるんです。
映画の描写を見ると、主人公はヒーローなんですよ。ハリウッド版はジョージ・クルーニーですし。
オペラ《ソラリス》は、勅使川原三郎さんが台本を手掛けているんですが、勅使川原さんと僕にとっては主人公はアンチヒーローなんですよ。だって自分が何かしたはずなんですよ、この女性に。一応自殺ということになっていますが、自殺に追い込んでしまったのか。
物語が進むと、彼女は、自分は本物の奥さんじゃないと自覚していく。単なるコピーだと。そのコピーである人に、主人公は惚れていくんですよね。
島崎: そこがすごいですよね。コピーが、自分自身が(コピーだと)わかっていくという。

藤倉: 主人公がアンチヒーローだっていうことをどう表そうか考えて、僕は、ケルヴィンを二人の歌手に歌ってもらうことにしました。
サイモン・ベイリーという素晴らしいバリトン歌手は、オンステージで朗々とヒーロー的に歌うんですよ。死んだ女性が聴きたいと思うようなことを。けれど頭の中では、まったく違うことを考えている。それをもう1人の歌手が、舞台裏でマイクを通して歌うんですね。客席の周りに設置したスピーカーから、声を変化させて流す。
私の愛する妻がどうのこうのと何事もなかったように話しているんですけど、頭の中では、死んだはずの妻がなんでここにいるんだ、と。それは面と向かって嘘をついているわけですから、それをどうやって描写できるかって。なぜか映画になるとヒーロー扱いなんですが、僕らはそうしたくなかった。
奥さんのハリー役は、純粋でイノセントな感じで歌うんですが、そこにコンピュータの力が入ってきます。時々ランダムに歌っている声を取り出して、パーンと会場に飛ばす。最初のうちは「ん?」って感じなんですけど、だんだん進むにつれて、僕が目標としているのはですよ、「この子、いい子だけどなんか変だよね」っていう違和感を観客に抱かせるということ。
そういうときってないです? すごく感じのいい本当に綺麗ないい人だね、って思うんだけど、5分か10分か観察していると、ちょっとおかしいっていう。何とは言えない。
彼女の歌のラインは凄く綺麗で、ゆったりと子守歌のように歌っているんですけど、時々歌っていない声が会場に飛んでいくっていう。人間の耳というのは面白くて、どこから音が聴こえてきたか、角度もわかるんですね。人間なのか人間でないのか。それを演出しようと思っています。

藤倉: 小説は結構難解なんですよ。中間部分には、いかにも本当にあった研究発表のような章(ソラリス学)があったりして。日本語訳をしたソラリスの大研究者である沼野先生は、その科学発表の部分に裏があるとお読みになっていますよね。
そんな中で、最後の3ページほどの短い章ですが、それを僕はオペラにしたかった。一番書きたかったところ。ケルヴィンが宇宙ステーションからソラリスに降り立って、ミモイド(ソラリスの「海」が形態を模倣するもの)がケルヴィンの腕や手の動きに合わせて絡まってくるというシーンがあって、そういうところは音楽的にできるかなと。
ソラリスというのは海に覆われているんですね。その海を表現するために、オーケストラにライヴ・エレクトロニクスを加えています。ソラリスとは地球とは関係ない場所で起こる話なので、何の楽器、何の音色かわからないというものを作らなければならないんです。
5人の弦がトレモロを弾く箇所があるんですが、それを増幅して、加工して、リアルタイムでホール全部のスピーカーに流しますこういった技術によって、「普通の海でない海」感が生まれたらいいなと思っています。
音楽と食に通ずるもの
藤倉: 僕はいろんな国で、ただ初演を観にきてくれと言われるんじゃなくて、プラスアルファでレクチャーをしてほしいだとか頼まれるんですが、お酒が飲めない生徒に教えるのって、僕にとって難しいんですよね。
僕にとって音楽って、いつも言ってることなんですが、食感なんですよ。書いた音をもし口の中に入れたらどういう味なのか。あと時間ですよね。口にしたときの味と、中間と、フィニッシュがどうなっているのか。音楽ではものすごく重要なことだと思うんですよ。音楽ってフレーズですから。
びっくりする味のものってあるじゃないですか。匂いをかいで、こんな味かなと思って食べ始めて。それで「ん?」となって、フィニッシュがあっさりしているものだとか、結構残るものだとか。そういう感覚が、頭の中で完全にコネクトしてるんですよ。そういう感じで曲も作っています。
先ほどワインをテイスティングさせていただきましたが、順番が大切じゃないですか? 最後の2つを最初に飲んでしまったら、物語が変わりますよね。それとまったく同じで、それが例えば5分とか10分の曲ならいいんですが、これがオペラという形になって、元になるストーリーもあったりすると、そういったことに気をつけないといけません。
それで特に若い作曲家を教えてる時なんかに思うのは、特に20代の時など若い時って作曲って大変なんですよ。証明しないといけない。ほかの奴らより俺が一番うるさい、一番よく鳴る、終わったときに僕の曲だけ覚えてくれていればいいって、みんなそういう人たちが作曲やってるわけですからね(笑)。だから楽譜を開いたときに白い部分(音符が書かれていない部分)があると不安になっちゃう。もっと書いちゃお、となったときに、キツい音、例えばトランペットの音とか、あれはどっちかというとスパイスなんですね。スパイスが利きすぎた後に、味があるのかないのかっていうようなレベルで楽しまなければならないものは楽しめないじゃないですか。
僕は威圧的にああやれこうやれっていうのは大嫌いなんで、こんなふうにすればどう? とかっていうんですけど、向こうは向こうで、特に若い作曲家なんかは、僕には僕の哲学的な理由があってこうするんですって反論してくるんですけど、イタリアの人たちとかは、「ガーリックが焦げてるよね、ここから」とか言うと「わかった、書き直す。その通り」って(笑)。

島崎: 藤倉さんのおっしゃった、「強い刺激の後に弱いものは鑑賞できない」というのは、音楽や料理以外でも、すべてそうですよね。クレッシェンドになっていかなければならない。ワインを味わうときも、甘さの少ないものからスタートして徐々に甘くしていかなければ駄目だし、渋みも同じですよね。味わい全体の複雑さや余韻の長さというのも、やっぱり弱いものから強いものへという。それはまったくおっしゃる通りだと思います。
「ソラリス」というブランド名が誕生したきっかけ
島崎: 先ほどSFが好きだという話をしたんですけれども、アシモフやクラークとかいったSFの王道という小説を好んで読んできて、SF関係の雑誌などを読んでいると、『ソラリス』という名作があって、と書かれているんですよね。それで読んでみると、やっぱり今まで読んできたものとはまったく違う。心理劇や、ホラー的な要素が強くて、正直難解で、そのときは面白いとはあまり思わなかった。ソラリスという名前が頭のどこかには残っていたと思うんですが。
私どものトップレンジのワインを作りましょうとなったとき、当時はラベルデザインも毎年ころころ変わってですね、あるときは日本のワインだから漢字の縦書きでとか、翌年になると同じワインなのにアルファベットで書いたりとかいうことがあって、それではお客様にも伝わらないし、ワインというのは作るのにすごく時間がかかるものだから、一貫性がないと結局評価もされないし、と。
2000年当時に出ていた、プレミアムと呼べるようなワイン群を集めて、共通のラベルデザインで、名前もつけて、ブランディングしていこうという話になったんですよ。
そのときにやっぱり、いかにもヨーロッパのワインの名前をもじったようなものにはしたくなかったんです。なんとか銀座とかなんとか富士みたいにですね、それって結局コンプレックスの裏返しじゃないか、みたいなネーミングにはしたくなかったんです。それでいろんな名前の候補を出していって、読みやすさや覚えやすさも含めて、どれにしようかと検討した結果、「ソラリス」になりました。
太陽がブドウを育んで、よいブドウがなければワインもできないという、マンズワインの商標に込められたメッセージにも親和性があったので、「ソラリス」にしようと。
18年経って、おかげさまでソラリスというブランドも浸透してきて、マンズワインではもちろん、キッコーマングループ全体の中でも、非常に大事な名前です。それが今回、作品そのものと、そしてオペラという形でご縁があって、しかも(私たちの)名前が同じというね。びっくりですよね。
実はこのソラリスっていう小説は、私が生まれた年(1961年)に発表されていて、それにも縁を感じます。

未来のクラシックを植えつづける
藤倉: よくトークなどで、「現代音楽ってなんですか」といったことを訊かれます。ワインを作るのは時間がかかると今おっしゃいましたが、よくそれに喩えて話すんです。
今親しまれているクラシック音楽は、その当時、現代音楽だったんですね。発表されたときは実験的で良くわからないと。たとえばドビュッシーの《海》なんかも、今は映画にもCMにも使われるし、毎日のように演奏されていますが、世界初演のときは確か新聞の批評が11個出て、全部酷評でした。
僕が一番好きな評が、「色彩に欠ける」(一同笑)。あともう1つが、「たえず不協和音である」。いま《海》を聴いて不協和音だと思う人はいないじゃないですか。長年経って、現在のように受け入れられているという。
海外の人は、例えばドイツでは、今さら「現代音楽とは」なんて、普通の人でも訊いてこないんですよ。日本だけなんですよね。商業的というか、チケットを買わせるなら売らなきゃ、という感覚なんでしょうが。
でも実は、皆さんの大好きなベートーヴェンの第九とか、当時は「変人がやっているよくわからない音楽」といった感じで、何百年もたった今、名作と言われるわけですから。

藤倉: それをよくウイスキーに喩えるんですが、30年もののウィスキーなら、30年前に誰かが作っている。誰かが作っていないと今楽しめない。それと一緒に考えてもらわないと。
ウイスキーなんて飲めばいいじゃんと言い始めたら、あと30年後には、30年もののウィスキーは存在しないじゃないですか。常に作っておかないと。日本では僕が説明しないとわからないというか。税金を納めるように、未来のクラシックを植えていかないと。
島崎: 今のお話とはちょっとニュアンスが違うかもしれませんけど、例えばこの日本ワインというのもここ15年くらいで認められるようになってきているんですね。それ以前は、日本でワインを一生懸命作っていてもなかなか評価していただけなくて、やっぱりワインはフランスでしょとか、プロの方もそういう認識でいる方が多く、最初から飲みもしないで日本ワインはスルーということもありました。ここ数年で品質もどんどん上がって、日本ワインが、本場のフランスとかそういったところのワインに比べて落ちるという言い方も減ってはきました。それでも、まだまだそういう考え方の方も少なくない。
藤倉: 僕はヨーロッパに住んでいて、ワインはフランスだけではないという認識は広がっているように思いますが、日本ではどうですか?
島崎: もちろん日本も世界中からワインが入ってきていますから、そういう意味では昔ほど、フランスじゃなければいけないというようなことはなくなってきています。それでもトップオブトップの部分ではまだまだ昔からの伝統国が強いですね。

実際にテイスティングもした藤倉さん。特にお気に召したのは、小諸メルロー、東山メルローと、カベルネ・ソーヴィニヨンとのこと。
島崎: 実は小諸メルローとカベルネ・ソーヴィニヨンがすごくよくできた年に、両方をブレンドしたマニフィカという商品があります。2012をリリースしたばかりなのですが、実は今日藤倉さんにお土産でお持ちいただきますので、それもぜひ感想をお聞かせ下さい。
藤倉: それはありがとうございます!
畑もご覧になってのご感想は?
藤倉: 感動的でした。ワイン畑がテーマの映画がいくつか大好きなもので、その一つ、『Good Year』(邦題『プロヴァンスの贈り物』。グッドイヤーはワインの当たり年の意)というのは、どの雑誌とか読んでもリドリー・スコットの失敗作と言われてるんですが(笑)、でも僕は大好きで。
銀行マンの主人公がブドウ畑を相続するんですが、こんなのいらないから、さっさと売ればいいからというところから始まる。が、ロンドンの金融の仕事を辞めて、ポイントのない人生というんですかね、だって金のために金作ってるわけじゃないですか。そういう人生は嫌だとフランスの田舎に移って、そこでずっと働いていたおじいさんと一緒に、畑を直していこうというところで終わる映画なんです。
奇縁が生んだ今回の対談。始まりはイギリスのドーヴァー
藤倉: 島崎さんがイギリスのドーヴァーでもワインが作られているとおっしゃいましたね。高校のときにドーヴァーにいたんですけど、そんなきれいな、美しいことができるような街じゃない。僕の知っているドーヴァーは違う(笑)。
そのときのイギリス人の同級生、しかも卒業してから会っていないんですが、Facebookとかで繋がるじゃないですか。僕が「ソラリス」って言っているのを見たんでしょうね。それで冗談のように、ソラリスのこのワインのラベルを送ってきたんですよ。
それで「ソラリスってワインあるんだ」って、東京芸術劇場の人やマネージャーの佐藤さんに送ったら、社長の島崎さんが大さんで同じ名前だから、これは何かしないといけないって。
――いろいろな偶然が重なった中での31日の公演がとても楽しみだ。日本にオペラ《ソラリス》が上陸する瞬間を見届けたい。
オペラ《ソラリス》公演開場時(18:00~19:00)には東京芸術劇場コンサートホール内カフェカウンターでワイン「ソラリス」を販売するとのこと。ぜひこの機会に味わってみては。

日時:2018年10月31日 (水)19:00 開演(ロビー開場18:00)
会場:東京芸術劇場 コンサートホール
チケット料金: S席 6,000円/A席 5,000円/B席 4,000円/C席 3,000円/D席 1,500円/高校生以下 1,000円(全席指定)
出演
ハリー:三宅理恵
クリス・ケルヴィン:サイモン・ベイリー
スナウト:トム・ランドル
ギバリアン:森雅史
ケルヴィン(オフステージ):ロリー・マスグレイヴ
指揮:佐藤紀雄
管弦楽:アンサンブル・ノマド
エレクトロニクス:永見竜生[Nagie]
オペラ《ソラリス》公演開場時(18:00~19:00)には東京芸術劇場コンサートホール内カフェカウンターでワイン「ソラリス」を販売します。
関連する記事
-
読みものオーストリア音楽トピック2024 本場で記念年の第九、ブルックナー、シュトラウス...
-
読みもの音楽ファン憧れの芸術の都 オーストリア・ウィーンで、うっとり音楽に浸る旅を
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest