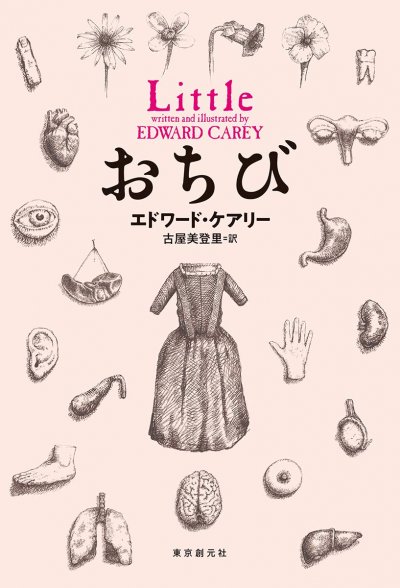革命を予言するモーツァルトのオペラとマダム・タッソーの蝋人形──エドワード・ケアリー『おちび』

かげはら史帆さんが「非音楽小説」を「音楽」から読み解く連載、第5回は伝説の蝋人形作家マダム・タッソーの生涯を描いたエドワード・ケアリー著『おちび』。時の最高権力である宮廷に、音楽家として関わったモーツァルトと蝋彫刻家として仕えたマリー(のちのタッソー)。2人がそれぞれのアートで予言したものとは?

東京郊外生まれ。著書『ニジンスキーは銀橋で踊らない』(河出書房新社)、『ベートーヴェンの愛弟子 – フェルディナント・リースの数奇なる運命』(春秋社)、『ベートーヴェ...
五歳のヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトがチェンバロのためのメヌエットを作曲した年、イギリス人がフランス領インドのポンディシェリを攻略したその年、きらきら星の歌が初めて出版されたまさにその年、つまり一七六一年に、パリのサロンに集まった人々は、城に住む野獣や青ひげや、眠りの森の美女や長靴を履いた猫、ガラスの靴、巻き毛のある王子、驢馬(ろば)の皮を身に纏(まと)った王女などの話に花を咲かせ、ロンドンのクラブに集まった人々は国王ジョージ三世とシャーロット王妃の戴冠式(たいかんしき)のことを話題にしていた。
エドワード・ケアリー著、古屋 美登里訳『おちび』(東京創元社刊)
なぜ蝋人形作家の人生はモーツァルトから始まるのか
この小説には、音楽がほとんど登場しない。
それにもかかわらず、本編の冒頭を飾るのはモーツァルトの名前である。
なぜモーツァルトなのか。その意味を深く考えようとするのは、よほどの音楽好きに限るだろう。しかし構想から完成まで15年を費やした、邦訳版にして600ページ弱におよぶ長編小説の出だしである。著者は相当な熟考の末にモーツァルトを選んだにちがいない。
ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト──1756年生、1791年没。短命な彼の生涯は、この小説の本編、そしてこの小説の主人公の波乱の前半生とほぼぴったり重なる。
主人公の名前は、アンナ・マリー・グロショルツ。通称マリー。あだ名は「おちび」。
今日では、マダム・タッソーの名で知られている著名な蝋人形作家だ。


18世紀のアーティストたちのキャリア形成
「五歳のヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトがチェンバロのためのメヌエットを作曲した年」──1761年。
アンナ・マリー・グロショルツは「活気のある街から遠く離れたアルザスの小さな村」に生まれた。
5歳でメヌエットを作曲したモーツァルトは、家庭環境からして音楽に恵まれていた。音楽家である父親のレオポルトはすぐにその才能に気づき、ヨーロッパじゅうの宮廷を訪ね歩いて息子を売り込んだ。芸事で王侯貴族を喜ばせる。それは当時の庶民が権力の世界に裏口から入り、成り上がるための唯一の手段だった。高位の人から寵愛され、安定した生活を約束される──それが目指すべきゴールだ。
モーツァルト: メヌエットヘ長調 K.1d
マリーの家庭環境には、最初から蝋人形があったわけではない。父親は軍人であったが、パレードの大砲で負傷し、つかの間の車椅子を送ったのち静かに亡くなった。未亡人となった母はベルンの医師クルティウスの住み込みの雑用係として採用され、マリーは母とともに彼の家に出向く。彼の仕事場で彼女が目にしたのは、展示ケースのなかに並ぶさまざまな内臓のパーツだった。まさか、人間の本物の臓器? マリーの母が青ざめているのに気がついたクルティウスは、あわててこう弁明する。
「これを作ったのは私なんです。ひとつ残らず。蝋から作りました。この手で。」
やがて幼いマリーはクルティウスの助手をつとめるようになる。彼は黄色い純蜜蝋のかたまりを手に、蝋という素材の不可思議で芸術的な価値を説く。「これは光景だ、これは記憶だ、肺の灰色や、肝臓の赤茶色になれる。なんにでもなれる。きみにだってなれる」──彼は自分の言葉を証明すべく、サンプルとしてマリーの頭部を蝋で作り上げる。マリーはその出来映えを見て、師の熱弁に納得する。「わたしがもうひとり出てきたみたい」
もともとはクルティウスの副収入だった蝋の胸像制作は、だんだんと世間から注目を集め始める。みな、蝋で作り出された人間の分身に興味津々だ。パリに移り住むと、著名な人の胸像を作る機会にも恵まれるようになる。作曲家のグルックに、政治家のフランクリンに、哲学者のヴォルテール。
そんな折、思いがけない見物客がやってきた。それはフランス国王ルイ16世の妹、王女エリザベートだった。王女からの強い希望に応えて、マリーは、彼女に彫刻を教えるためにヴェルサイユ宮殿に足を踏み入れる。王族の家庭教師。それはアーティストとしてもっとも名誉ある職だった。

フランス王太子ルイ・フェリディナンの末娘で、ルイ16世の妹。フランス革命では兄、義姉マリー=アントワネットと運命をともにした。
アートはフランス革命を予言する
しかし権力とアートは、ときに水と油さながら反目しあう。時流に敏感な生き物であるアーティストは、意図のあるなしにかかわらず、作品の性質によって権力に大きな傷をつけてしまうことがある。モーツァルトのオペラ《フィガロの結婚》は、1786年にウィーンで初演され、のちにプラハで大ヒットを記録した。ボーマルシェによる原作の戯曲は、フランス王妃マリー・アントワネットの大のお気に入りでもあった。しかしその内容は、貴族が平民たちにやりこめられるさまを描いた風刺的な喜劇だ。1789年のフランス革命を予言しているといっても過言ではない。
モーツァルト: オペラ《フィガロの結婚》
マリーが手がけた蝋の胸像たちも、また同じような宿命を帯びる。
師クルティウスの指示にしたがい、マリーはさまざまな権力者たちの蝋人形を制作すべく奔走する。国王ルイ16世の型取りに成功すると、こんどは王妃や伯爵たちの顔をスケッチし、頭部を粘土で作り、蝋の胸像を作りはじめる。その精力的な創作活動は、やがて想像もしていなかった因果に結びつく。フランス革命によって宮廷が倒され、王族たちの首が次々とギロチンで狩られはじめるのだ。国王も、王妃も、そして彼女の雇い主たる王女エリザベートも。
首から下を斬られ、大衆の前に血まみれで晒された頭部。それはまさにマリーが蝋で作ってきた胸像の相似形に他ならなかった。彼女は強いショックを受ける。宮廷の世界を彼女は彼女なりに愛していた。とりわけ自分と容姿が似た王女エリザベートに対しては、主従の関係を超えた熱い愛情を寄せていた。「わたしたちの心臓、小さな女の心臓は、そっくり同じ音楽を奏でていた」──それにもかかわらず彼女が手がけた作品たちは、意図せずして、革命と斬首の予言となってしまった。
マダム・タッソーを通して描く、社会とアートの奇怪な因果
宮廷が終焉を迎えようという時代に、社会とアートを結びつけた奇怪な因果。『おちび』は、アンナ・マリー・グロショルツの一人称の語りでもってその本質に迫っていく。文体はモーツァルトの音楽さながら平易かつ精密で美しく、激動する時代のうねりや蝋人形制作の技法、人びとの関係を淡々とした筆致で描き起こす。物語の終盤で、彼女はこう言う。
生と死とのあわい。それを蝋人形と呼ぶ
モーツァルトは1791年、フランス革命の直後に亡くなった。彼は自らの作品が現実化しようとする変革期のさなかに死んでいった。しかしマリーにとって、1791年はまだ人生の前半戦にすぎなかった。彼女はそれから倍以上の歳月を生き、イギリスに渡り、自作の蝋人形を抱えて地方巡業に明け暮れ、1835年に念願の展示施設を設立するに至る。ロンドンの観光スポットとして有名な「マダム・タッソー館」で、当時もいまも人気なのは、フランス革命の時代を再現した「恐怖の部屋」だ。蝋の胸像によって表現された斬首の現場。それはアートが社会と呼応し合う、恐るべき瞬間の再現だった。

関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest