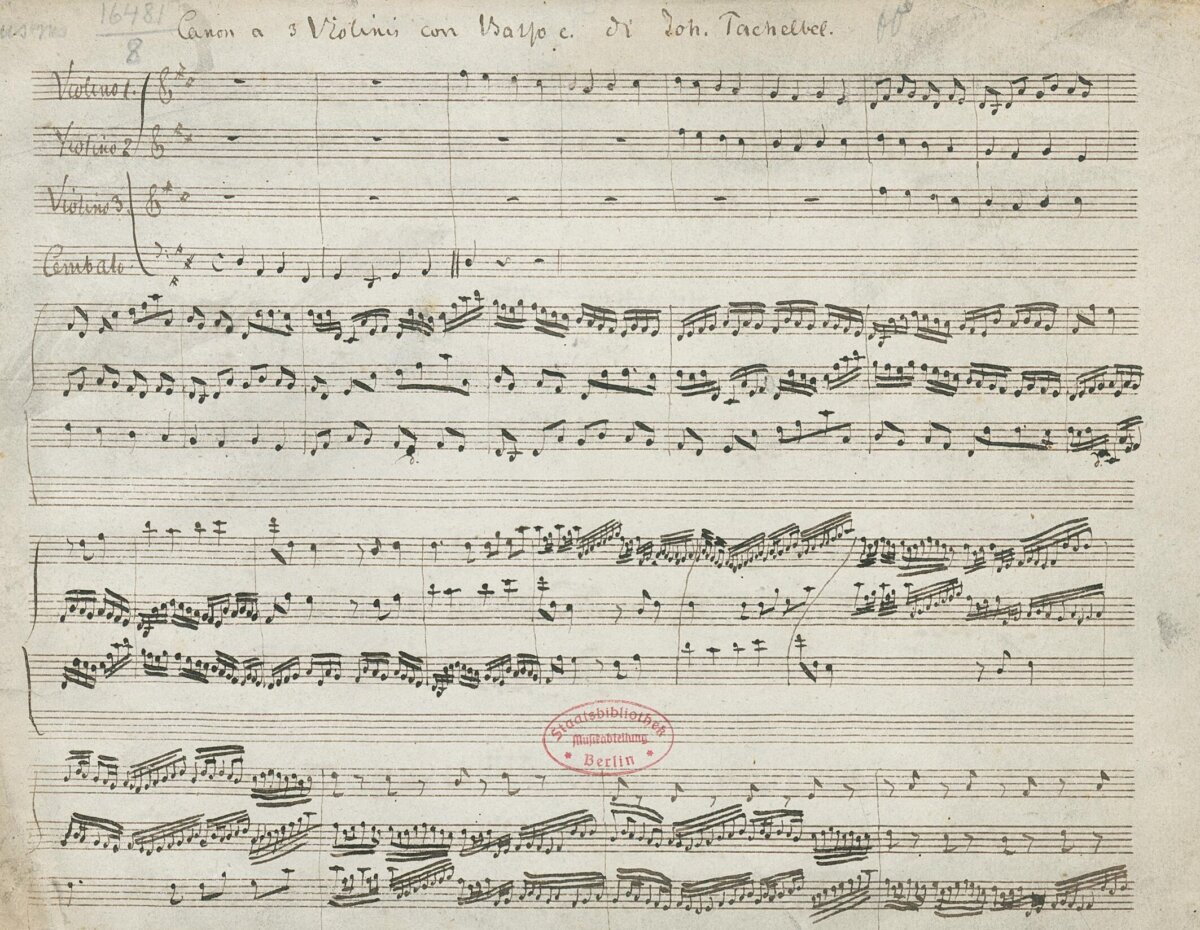ライブ好きの“私”が嘘をつく理由──八木詠美『空芯手帳』

かげはら史帆さんが「非音楽小説」を「音楽」から読み解く連載、第8回は2020年5月に第36回太宰治賞を受賞した八木詠美著『空芯手帳』。音楽ライブが好きな、ごくありふれた“私”はある日、「妊娠した」という衝撃の嘘をつく。その「嘘」が“私”にもたらすものとは?

東京郊外生まれ。著書『ニジンスキーは銀橋で踊らない』(河出書房新社)、『ベートーヴェンの愛弟子 – フェルディナント・リースの数奇なる運命』(春秋社)、『ベートーヴェ...
「しばたっつぁんさんのスマホケース、ライブグッズですよね。私もそのアーティスト好きなんです。だから絶対。その日くらいはお互い旦那に子ども預けて」
「そうだったんだ。じゃあ行こうね、絶対」
八木詠美『空芯手帳』筑摩書房、2020年(以下、すべて本書が引用元)
そして“私”は妊娠を切り出す
人間の妊娠は、たとえ医療技術を用いた受精であったとしても、男女の個体がいなければ起き得ない。しかし妊娠を最初に知るのはほとんどの場合、女性の側だ。身体の変調を自覚し、なんらかの方法で調べ、確信に至る。腹のなかの秘密をいつ誰に公表するかは、女性自身の判断にゆだねられる。祝われたい。そっとしてほしい。気遣ってほしい。普段どおりにしてほしい。希望はさまざまだ。空気をうかがい、ここぞという公表の瞬間を待つ。
「今妊娠していて」
『空芯手帳』の主人公 “私”が、職場で妊娠を公表したのは、ある日の午後4時半だった。
商談スペースに出しっぱなしのコーヒーカップ。誰が使ったのかわからないそれを片付けるよう遠回しに指示されたとき、“私”は、通りがかった課長を呼びとめて、こう切り出した。
「ちょっと無理です」
「どうしたの、急に」
「今妊娠していて。コーヒーのにおい、すごくつわりにくるんです」
「趣味はライブ」……ありふれた独身女性がつく異様な嘘
30代、独身、女性、会社員、苗字は柴田。趣味は音楽を聴くことで、ライブやフェスに行くのが好き。
日本のどこにでもいそうな、ごくありふれたプロフィールの“私”は、ごくありふれたストレスを抱えて生きている。
前職でセクハラに遭い、転職先としてエージェントに紹介された紙管専門メーカーの事務所は、「好きなアーティストのライブに平日でも行ける」程度には余裕のある、平和な、けれど長くいるにつれ古びた体質が目につく職場だった。会議がムダに長い。恋愛や結婚についてしつこく訊かれる。来客があれば女性の社員がコーヒーを淹れてもっていき、片付けまでしなければならない。
そんな会社で働いていたある日、“私”は、煙草の吸い殻が入ったまま放置されたコーヒーカップを前に、とんでもない嘘をつく。心のどこかでずっとくすぶっていた感情が、一気にほとばしるような嘘だった。
「今妊娠していて」
独身女性の妊娠。社員たちは動揺と好奇の目で“私”を見る。「そんな雰囲気ないのに意外とやることやってるんだな」男性社員が放つ下卑た野次をスルーして、「結婚してなくても、出産祝い金ってもらえますかね」と問いかけると、彼らはぎこちなく押し黙る。人事課に出産予定日を告げたついでに定時退社を求めると、少なくとも表向きはすんなり受理された。業務量は減らされ、コーヒー担当は若手の男性社員に交代された。
勝利、といえないでもない。“私”の嘘の目的が、独身女性の妊娠というイレギュラーな事態を職場に持ち込み、古い体質を変えることだとしたら。それは少なからず成功している。
しかし、“私”はアクティビストでも革命家でもない。“私”は会社にそれ以上強く出ることもなく、ただ淡々と、ニセの妊娠生活を送りつづける。ゼリーの箱に入った緩衝材やマフラーで腹をふくらませて人目をごまかし、定時で家に帰ってぼんやりと時間をもてあます。大好きな音楽さえも、どうやって楽しめばいいのかわからなくなってしまう。
自分は音楽が好きなんだと思っていた。今だって家から駅まで歩くときや、人や電車を待つときはスマホで音楽を聴いている。夏になればフェスに行く。しかしこうして時間ができてから誰もいない部屋で音楽をかけると、どうやって聴けばいいのかわからなかった。
「空芯」は古今東西の妊婦たちと共鳴する
“私”はなぜ妊娠という嘘をついたのか?
それは決して、社会へのレジスタンスのためではない。あくまでも自分自身が人生を耐えぬくためだ。「自分だけの場所を、嘘でもいいから持っておくの」そう“私”は言う。「その嘘を胸の中に持って唱え続けていられたら、案外別のどこかに連れ出してくれるかもしれないよ。その間に自分も世界も少しくらい変わっているかもしれないし」──
自分がついた嘘を腹に秘めて守りながら、世のなかが変わるのを静かに待つ。社会改革を訴えかけるパワフルなフェミニズム作品が続々と登場しているいま、“私”がとった生存戦略は、根本的な解決策を欠いた、こぢんまりとした退行的なものに見えないでもない。
しかし、“私”が腹のなかにこしらえた空洞は、決して孤独でもひとりよがりでもない。夜の銀座の街で、「三人の博士に囲まれて赤ん坊を抱く、有名なその女性」のステンドグラスを見つけたとき。あるいは通い始めたジムで、妊婦の友人たちとおしゃべりするとき。“私”の空芯は、子を宿した女性たちの腹と強く共鳴する。
ジムのマタニティ向けエアロビクスに参加するシーンの描写は、この小説のなかでも屈指の迫力がある。“私”は、妊婦たちといっしょに踊り、彼女たちの醸すエネルギーに圧倒されながら、同じビートを共有する快楽と興奮を見出していく。偽の妊娠を公表して以来、どうやって楽しめばいいのかわからなくなってしまった音楽は、このシーンにおいて、彼女たちと運命をともにするための決起のBGMに変わる。
ステップが激しくなるにつれ、教室が軽く揺れ始める。当然だ、目に見える人数の2倍の命がここにはいるのだ。汗がミラーボールの光を受けてダイヤモンドさながらに輝き散っていく。私は途中から膝が笑い始めてしまった。それでも一糸乱れぬ集団の中では、何よりビートが続く中では動きを止めることなど許されない。
「出産予定日」が迫ったある日。“私”は、もうすぐ里帰りするというエアロビクスの妊婦仲間に話しかけられる。
「しばたっつぁんさんのスマホケース、ライブグッズですよね。私もそのアーティスト好きなんです。だから絶対。その日くらいはお互い旦那に子ども預けて」
「そうだったんだ。じゃあ行こうね、絶対」
“私”は朗らかに答える。たとえ妊娠が嘘であろうとも、妊婦の仲間と分かち合った想いやビートは決して嘘ではない。空芯。それは、女性がこの世を生き延びるための手段であり、想像力であり、連帯するためのワイルドカードなのだ。





関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest