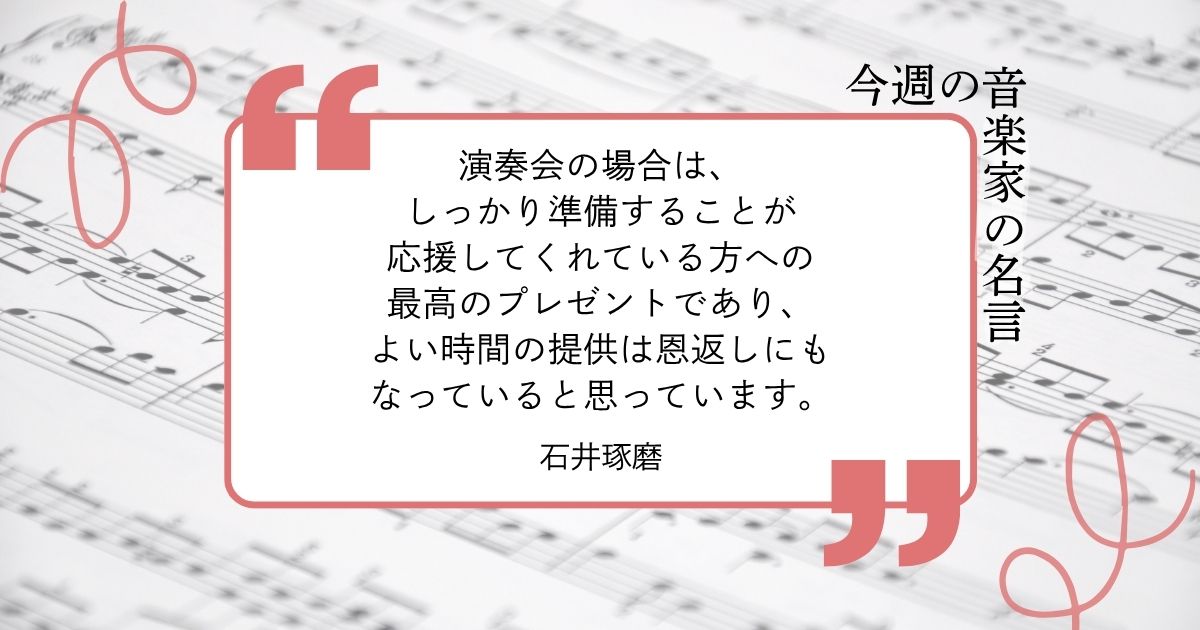2005年アメリカ発、左手のための “文学作品”集──J・ロバート・レノン『左手のための小作品集 ─100のエピソード─』

かげはら史帆さんが「非音楽小説」を音楽の観点から読む連載。第16回では、アメリカの作家J・ロバート・レノンによる掌品集『左手のための小作品集─100のエピソード─』を取り上げます。20世紀から徐々に作品数を増やしてきた「左手のための」ピアノ音楽との関連性とは?
一方教授は、左手のためのさまざまな曲がピアノで弾けるようになり、かつて両手で弾いていたときと同じくらい上手くなったと言われている
J・ロバート・レノン『左手のための小作品集─100のエピソード─』李春喜 訳、関西大学出版部、2020年(原著: 2005年)
ヴィトゲンシュタインの委嘱から認知され始めた「左手のための」ピアノ音楽
「左手のための音楽作品」として今日もっともよく知られているのは、モーリス・ラヴェルの『左手のためのピアノ協奏曲』だろう。献呈相手は、コンサート・ピアニストであり、哲学者ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタインの兄としても知られるパウル・ヴィトゲンシュタインである。

©️BFMI
彼は第一次世界大戦中に負傷して右腕を失ったが、当時ヨーロッパ一ともいわれた実家の莫大な資産を頼ってピアニストを続ける道を選び、ブリテン、プロコフィエフ、リヒャルト・シュトラウス、コルンゴルトら当時の一線の作曲家たちに「左手のための作品」をオーダーした。その1曲が、このラヴェルによるピアノ協奏曲である。
1932年1月5日に初演されたこの作品は、「左手」のイメージをくつがえすに足る衝撃を音楽界にもたらした。利き手ではない方の手、脆弱な方の手、伴奏の方の手が、ラヴェルの色彩豊かなオーケストレーションをバックに、これほどに生き生きと舞い踊ろうとは。
もちろんラヴェル以前にも、左手しか使わないピアノ作品は存在した。しかしヴィトゲンシュタインの金に糸目を付けない音楽活動と、そこから生まれた作品によって、左手は不器用な添え物でも不完全な片割れでもなく、ソロを担いうる独立した存在として社会的に認知されるようになった。一説によれば、左手のためのピアノ作品は今日3000曲程度が存在するという。
しかし、ここには勘定されない左手のための“文学作品”集が2005年に誕生したことはあまり知られていない。それこそが、1970年生まれのアメリカの作家J・ロバート・レノンによる『左手のための小作品集─100のエピソード─』である。
なぜ「左手のため」なのか
この掌編小説集には、音楽を直接的にテーマにした作品はほとんど登場しない。しかしクラシック音楽やピアノに親しんだ人であれば、『左手のための小作品集(Pieces for the Left Hand)』というタイトルがよくあるピアノ小品集のパロディであることにすぐ気がつくはずだ。また副題の『100のエピソード(100 Anecdotes)』が示すとおり、本作には邦訳版にして1ページから3ページ程度の掌編が100編収められている。1編あたり1、2分程度で読め、これもまたピアノ小品らしいサイズ感といえる。
100編の主人公は老若男女さまざまだが、舞台はおおむね現代のアメリカ。物語の作者はニューヨーク州のある大学町に住む47歳の男性である(という設定になっている)。秋から春への季節の変化を描いたリリカルな掌編もあれば(『木の葉』)、旧新の文明の利器の間で揺らぐノイローゼ気味の男を描いたシニカルな掌編もある(『道具』)。ほぼひと息で歌い切るような勢い重視の作品もあれば、ソナタ形式のごとくかっちりと構成された作品もあり、二重三重のオチで思いがけない穴に転がり落ちて終わる作品もある。100編が「地方と都市」「謎と混乱」「仕事と金」「運命と狂気」など7つの章立てで分類されているさまもまたピアノ小品集らしい。
しかしなぜ『左手のため』なのか? その謎を解くヒントになるのが、第六章「芸術家と大学教授」の1作「左利き」だ。とある大学教授が、本当は右利きにもかかわらずひょんなことから左利きと勘違いされ、「左利き協会」から講演依頼を受ける。彼はそのオファーを受けて協会の壇上に立つが、この協会は過剰な特権意識を抱いた人間の集団にすぎないとなじり、「人は、その人が生まれつき持って生まれたものではなく、その人が自らの努力で達成したことで評価されるべきだ」と喝破する。その後、事故で右手を失って左利きになった教授は、過去の発言について深く反省し、協会関係者や世間からの嫌味の声に耐えつつも左手のために書かれたピアノ曲の練習に取り組み、やがて達者に弾きこなすようになる。
この掌編は必ずしも、教授が猛省の末に偉大なる左手アートの前に頭を垂れた、という勧善懲悪のエピソードではない。壇上での失言を素直に認める一方、激しいバッシングとともに家に送りつけられる「左利きの人用グッズ」を一切無視して、自ら選んだ「左手のための曲」を情熱的に練習する教授は、「人は、その人が生まれつき持って生まれたものではなく、その人が自らの努力で達成したことで評価されるべきだ」というポリシーをいささかも変えておらず、ピアノの練習という鍛錬によって自分なりのアイデンティティを獲得したかのように見える。一方で「左利き協会」やその関係者は、教授に正義の鉄拳を振り下ろしているように見えるが、その攻撃は嫌がらせの域にまで達している。左利きをめぐって、どちらが正しいともいいかねるような対決が描かれているのだ。
どちらが正しいともいいかねる物語は、「芸術家と大学教授」章の別の掌編にも登場する。「ペテン師」では、ある作曲家の盗作を大学所属の批評家が暴き、しかしその批評家が調査内容を捏造していたことを彼の元ガールフレンドが暴き返したことで、一度は作曲家の名誉が回復されるが、その元ガールフレンドにも新たな調査のメスが入る──といういたちごっこのペテン合戦が繰り広げられる。語り口は決して大仰ではなく、むしろ淡々と事の顛末を告げるドライなテイストがおかしみを助長させる。
これらの掌編が描いているのは、正しさよりも正しさが内包する危うさであり、きまじめな道徳観よりも人を喰ったような皮肉とユーモアなのだ(今日的なポリティカル・コレクトネスの感覚でいえば、このやや冷笑的な書きぶりにも危うさを抱かないでもないが、原著の刊行が2005年である点も留意すべきだろう)。
関連する記事
-
プレイリスト田所光之マルセル×親愛なるエチュードたち
-
読みもの【牛田智大 音の記憶を訪う】自分の音楽に還る ワルシャワでの日々
-
読みものショパンコンクール予備予選に日本から出場する24名 どのようなピアニスト?経歴は...
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest