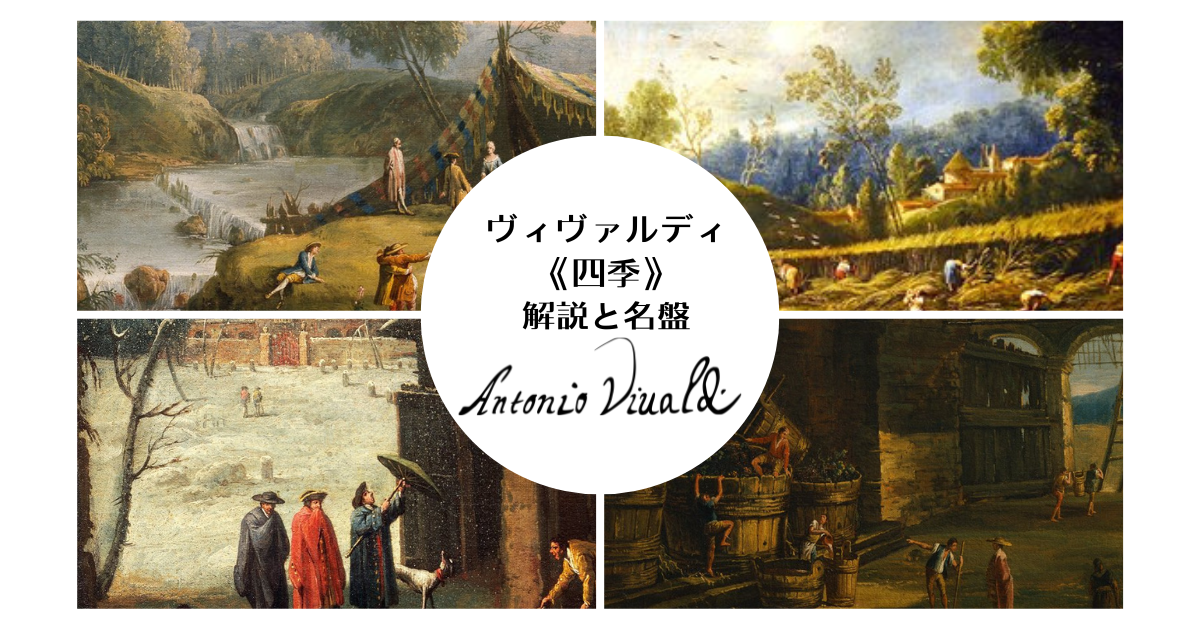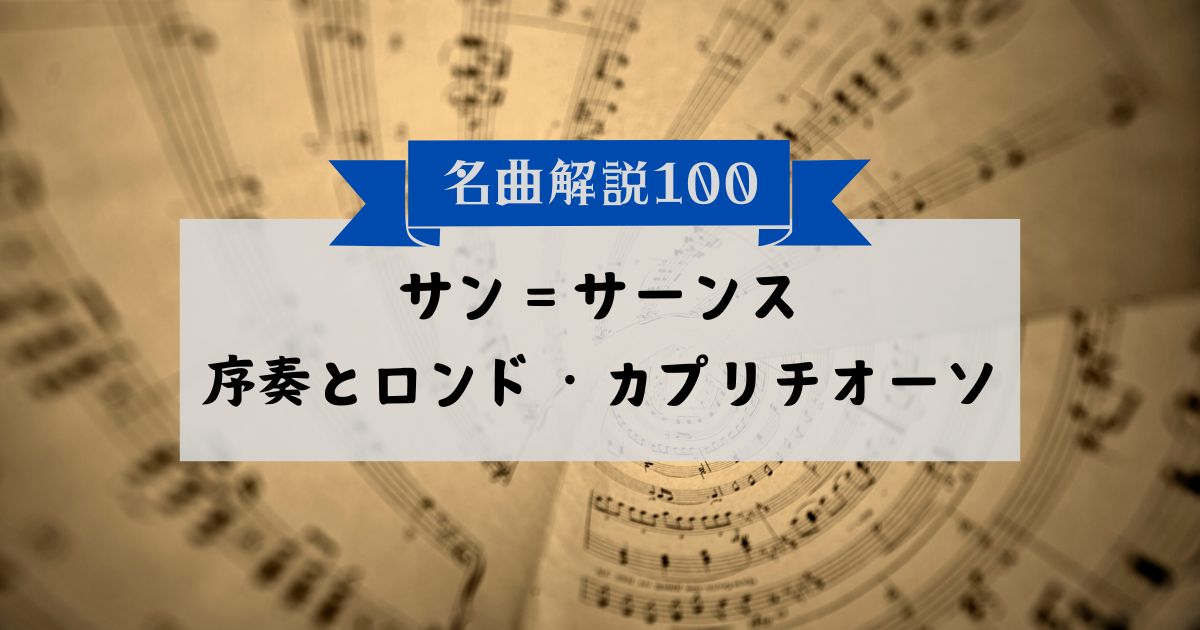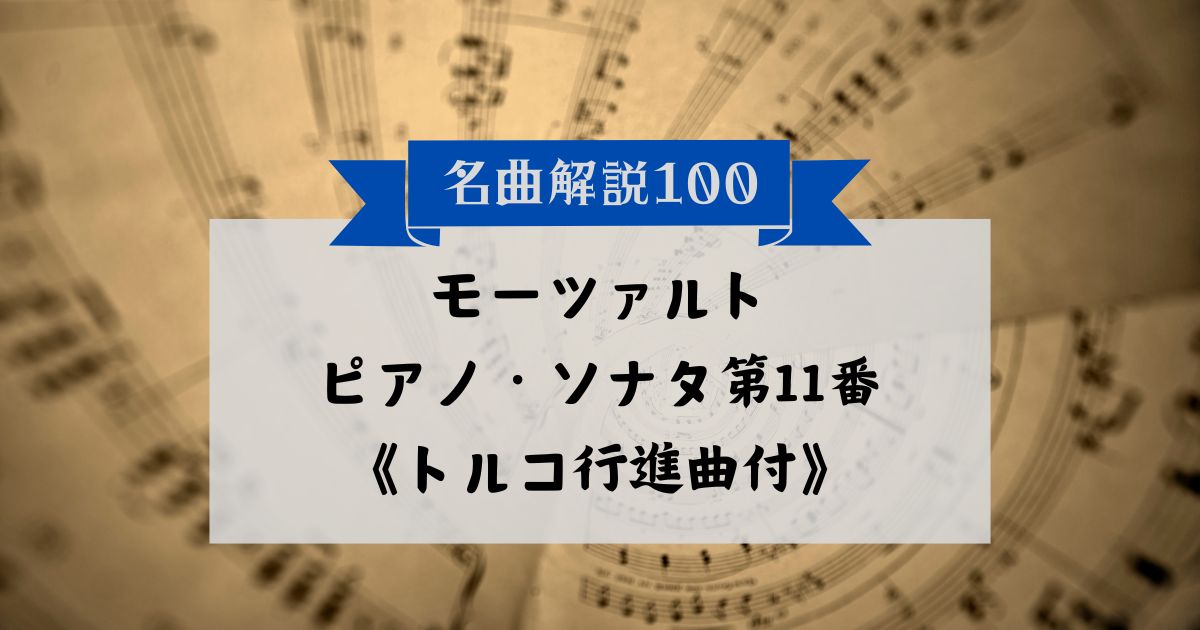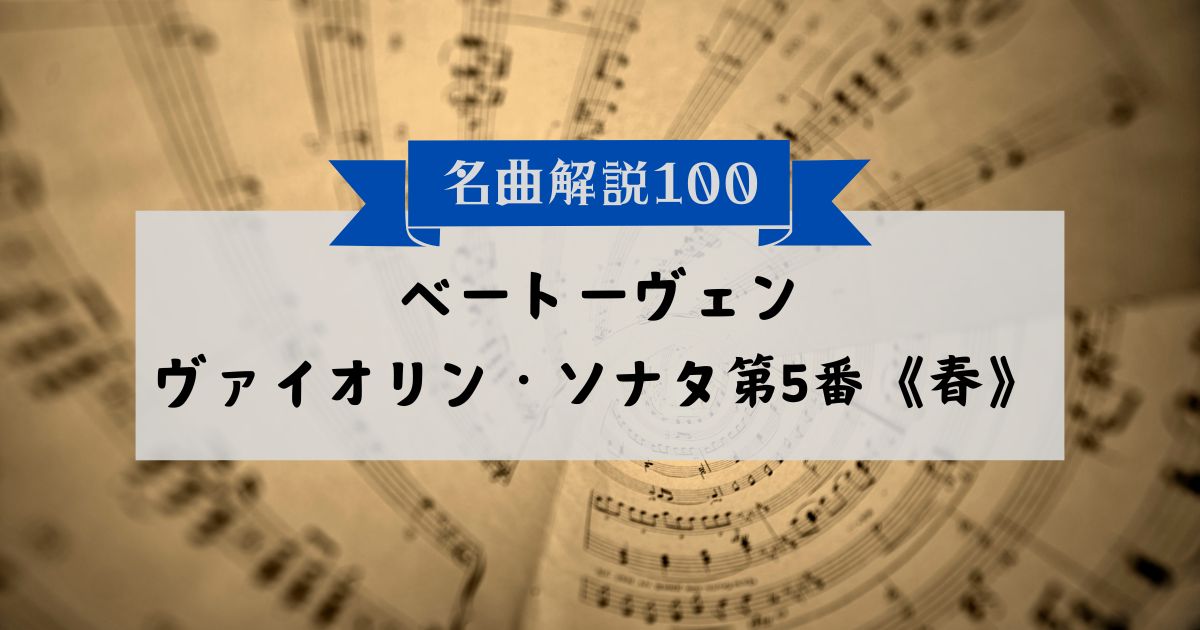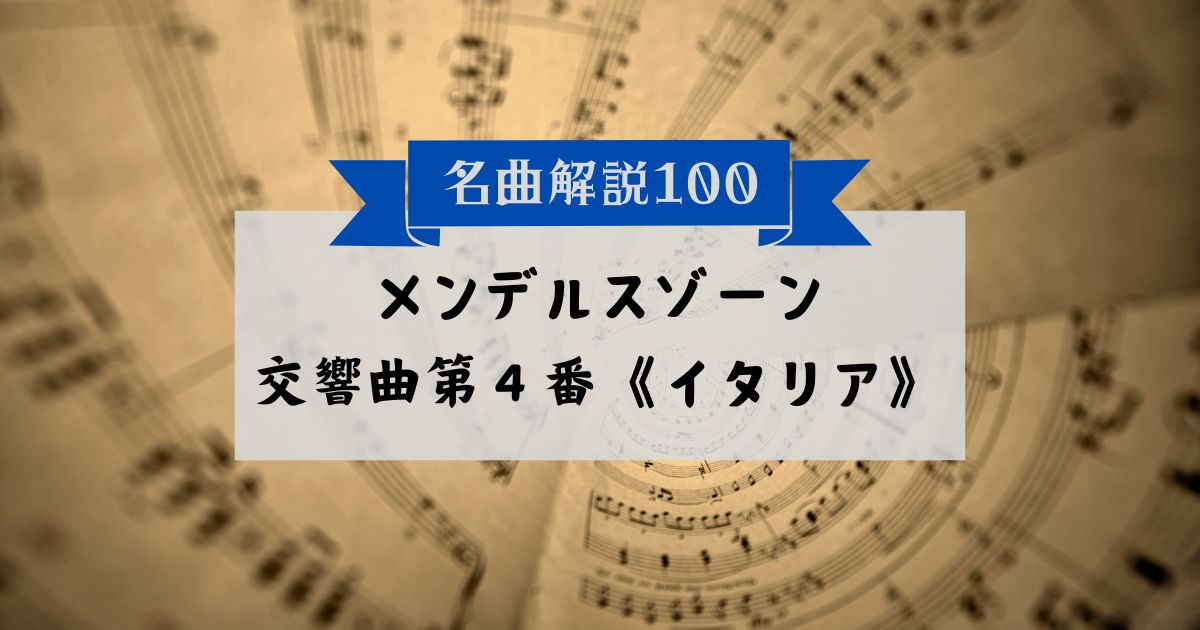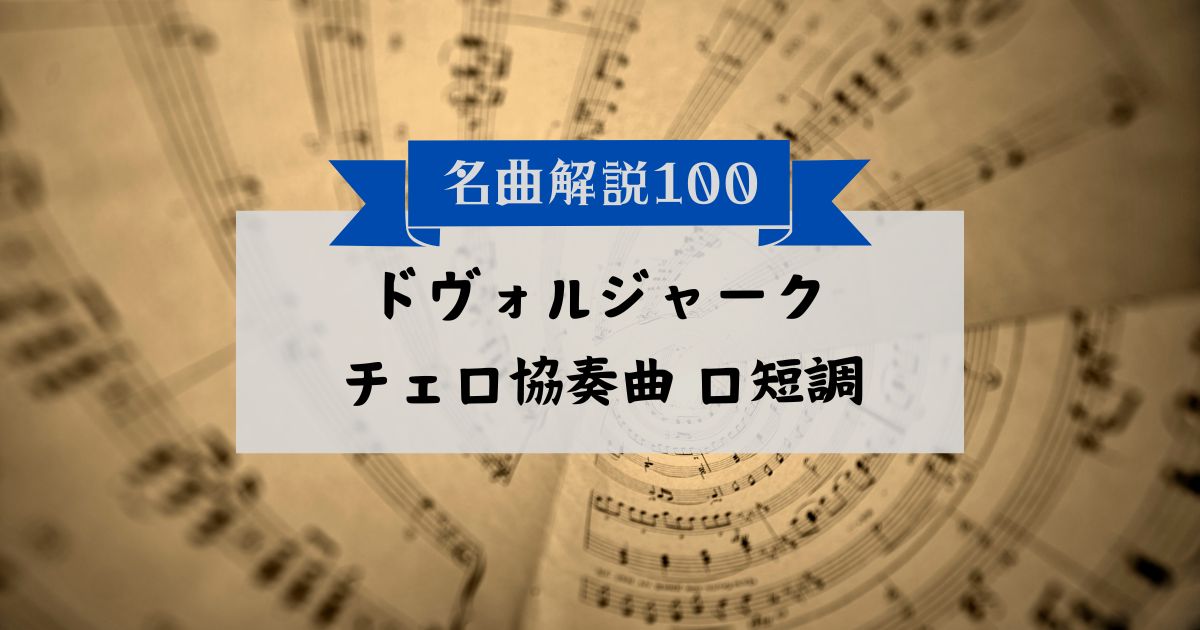
読みもの
2025.11.12
名曲解説100
30秒でわかるヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集《四季》
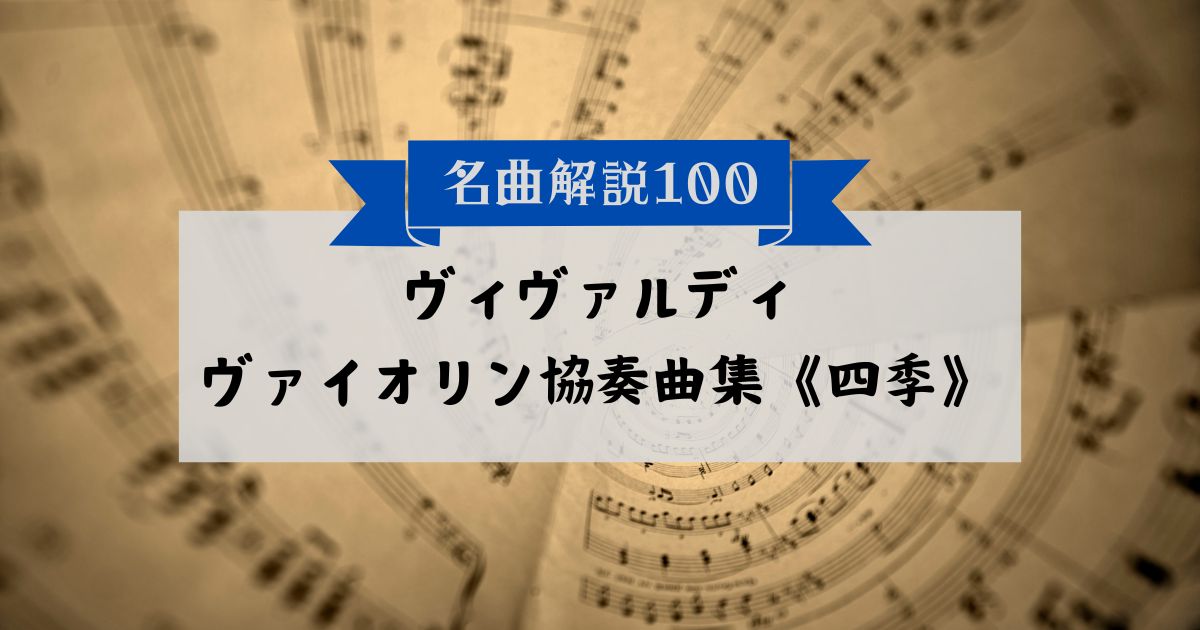
ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集《四季》について30秒で丸わかり♪
アントニオ・ヴィヴァルディ(1678~1741)は後期バロック時代のイタリアの作曲家です。彼は夥しい数のヴァイオリン協奏曲を残していますが、その中でもとりわけポピュラーなのが《四季》として知られる4つの協奏曲です。これは1725年出版の協奏曲集『和声と創意の試み』作品8に含まれているもので、バロック時代の独奏協奏曲のスタイルのうちに、四季それぞれの自然と生活を描いたソネット[14行詩]の内容を表現している点がユニークです。
第1番ホ長調「春」は春の訪れを描く第1楽章の後、羊飼のまどろみを描写する緩徐楽章を挟んで、田園舞曲で閉じられます。
第2番ト短調「夏」では夏のけだるさ、鳥の声、風の脅威を示す第1楽章、疲れた羊飼、嵐の予兆などを描く第2楽章の後、荒天を表現するフィナーレが続きます。
第3番ヘ長調「秋」は収穫を祝う村人たちを表す第1楽章、眠る酔払いの様子を描く緩徐楽章を経て、フィナーレでは狩の情景が活写されます。
第4番ヘ短調「冬」の第1楽章では凍てつく寒さとそのための足踏みや歯の震えが巧みに音化されます。炉端での団欒を彷彿とさせる中間楽章を挟んで、氷の上での滑走や南北の風の衝突を描くフィナーレが全曲を閉じます。
ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集《四季》
作曲年:不明
演奏時間:約40分
編成:弦楽4部、通奏低音、独奏ヴァイオリン
関連記事
名曲解説100
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest

イベント
2026.02.05
石田泰尚さんが横浜みなとみらいホールプロデューサー“ラストイヤー”への意気込みを...

読みもの
2026.02.05
スカラ座より熱い!? ミラノ五輪はサン・シーロから始まる

インタビュー
2026.02.05
ケヴィン・ケナーが語るショパン演奏「音楽はアイデアではなく、体験である」

読みもの
2026.02.04
ピアニストの久末航が日本製鉄音楽賞「フレッシュアーティスト賞」を受賞!

レポート
2026.02.04
京都コンサートホール2026年度ラインナップ発表
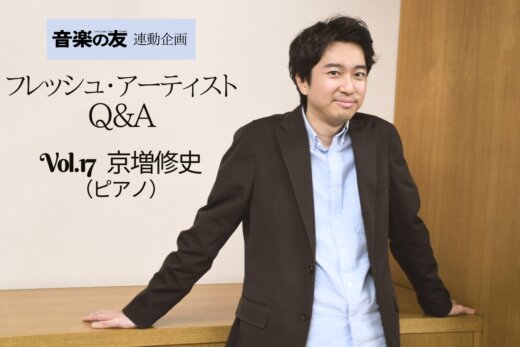
連載
2026.02.03
京増修史さん(ピアノ)、「もう一度聴きたい」と思われるような演奏家でありたい

インタビュー
2026.02.03
ネルソン・ゲルナーが語るショパン演奏と審査で大切なこと「音楽そのものに集中して理...

読みもの
2026.02.01
2026年2月の運勢&ラッキーミュージック☆青石ひかりのマンスリー星座占い