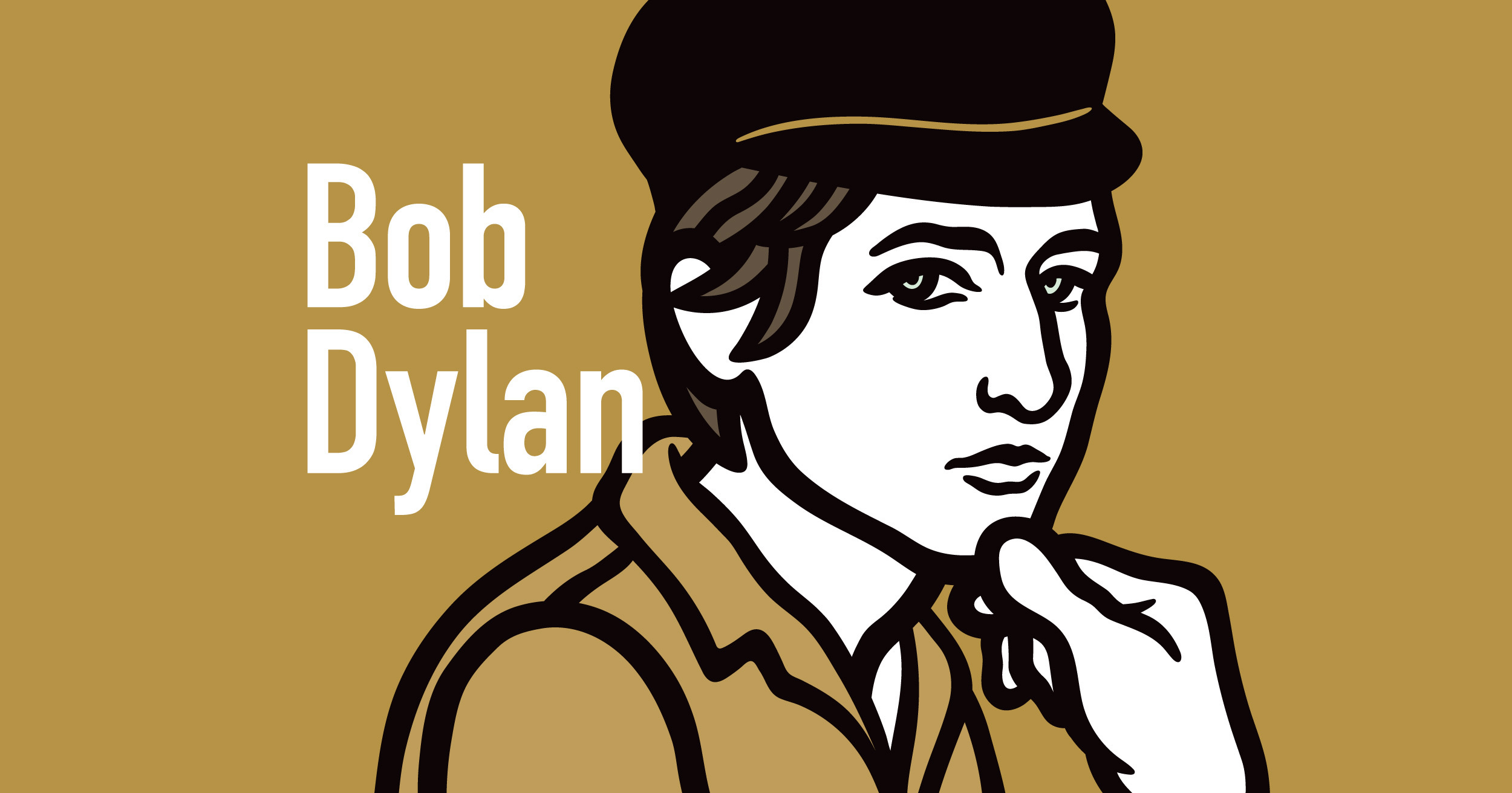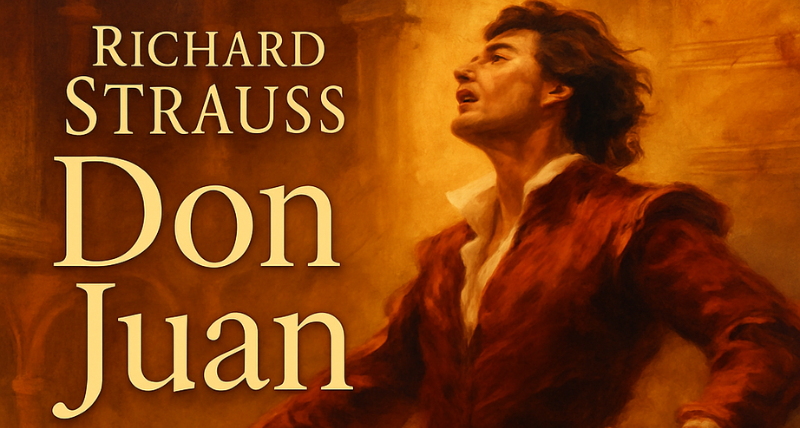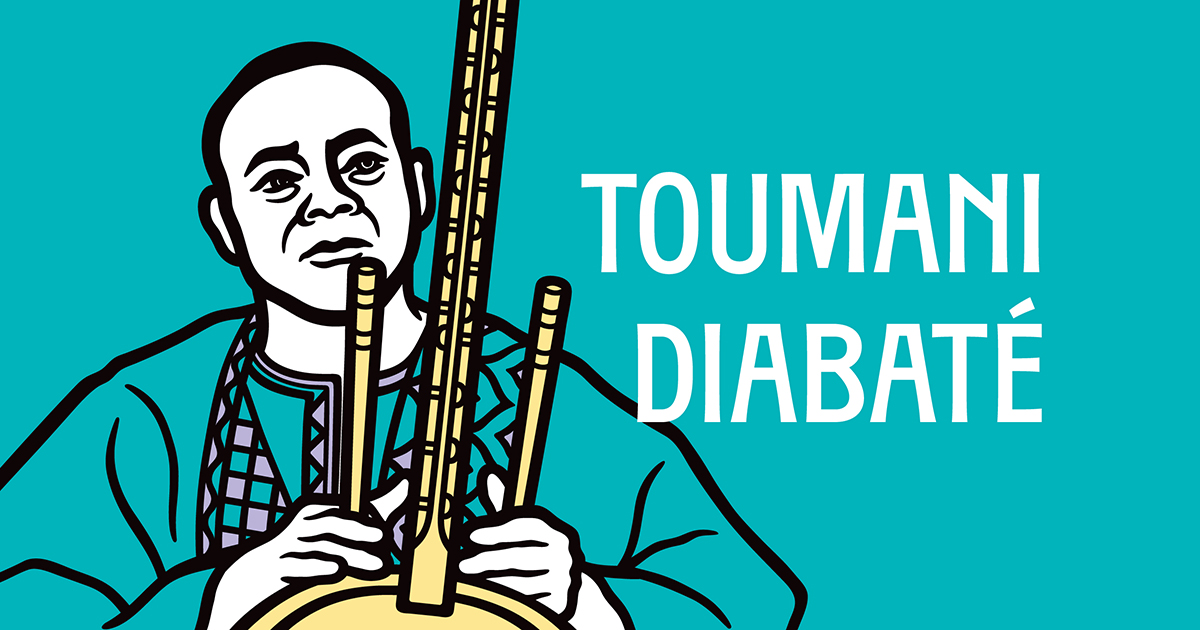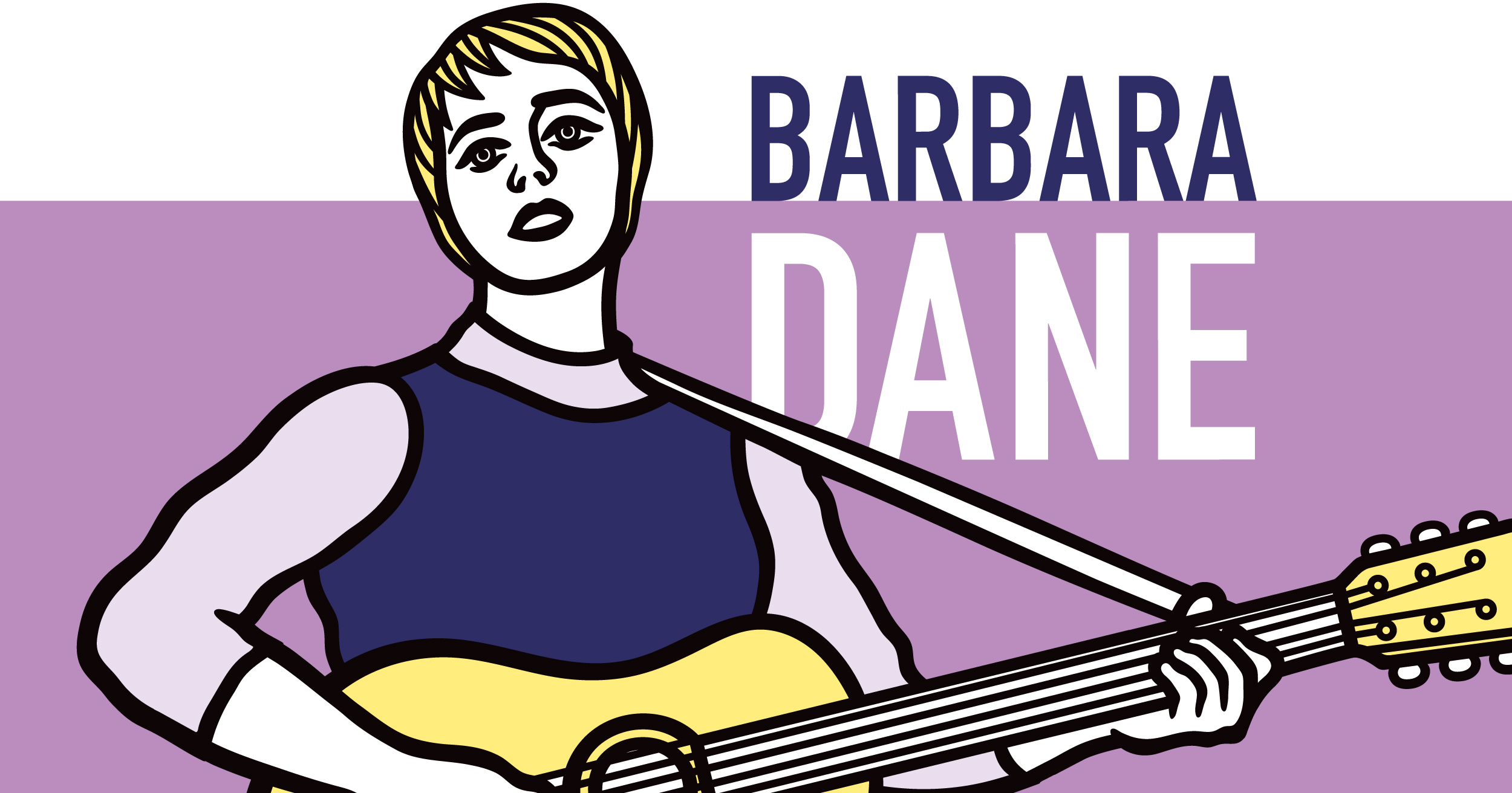
ジャズの巨匠マイルス・デイヴィス、ジョン・コルトレーン生誕100周年!

ジャズ史に燦然と輝く2大巨匠、マイルス・デイヴィスとジョン・コルトレーン。今年は「生誕100周年」という記念すべき年です。同い年でありながら、師弟として、そしてライバルとして互いの音楽観を磨き続けた両者の足跡は、現代のジャズシーンに影響を残しています。本記事では、2人のレジェンドの人生を名盤やエピソードとともに辿ります。

茨城県生まれ。東京音楽大学付属高校と同大学で作曲を学んだ後、同大学院では音楽学を専攻。修了後は東京音楽大学の助手と和洋女子大学の非常勤講師を経て、現在は桐朋学園大学 ...
2026年はジャズの歴史に燦然と輝く、2人のミュージシャンが生誕100周年を迎える。5月26日生まれのマイルス・デイヴィスと、9月23日生まれのジョン・コルトレーンだ。同い年でありながら、師弟のような関係性でもあった2人の生涯と代表的な名盤を、駆け足となってしまうが紹介していこう。

1926年5月26日イリノイ州アルトン生まれ、91年9月28日死去。トランペット奏者。モダン・ジャズの歴史を築いた史上最大のイノベイター。 ジャズの帝王 と呼ばれたカリスマ。ジュリアード音楽院で学び、チャーリー・パーカーのバンドで名を上げる。独立後に自己のグループを結成。クール・ジャズ、ハードバップ、モード・ジャズ、フュージョンなど、ジャズ史を形成したジャズ・スタイルの大半はマイルスが作り上げた。マイルス・バンドからジョン・コルトレーン、ハービー・ハンコック、キース・ジャレットなど有名ミュージシャンを輩出、“マイルス・スクール”と呼ばれた。『カインド・オブ・ブルー』『クールの誕生』『ビッチェズ・ブリュー』など歴史的な傑作が多数ある。ブルーノートには『マイルス・デイヴィス・オールスターズVol.1&2』を録音。実質上、マイルスがリーダーの『サムシンエルス/キャノンボール・アダレイ』もモダン・ジャズの大名盤。
(Universal Music サイトより一部引用)

1926年9月23日ノース・カロライナ州ハムレット生まれ。1967年7月17日没。55年にマイルス・デイヴィス・クインテットの一員だったジョン・コルトレーンは、57年に初のソロ作品のレコーディングを開始する。ハーモニーの研究にひたむきに取り組んだコルトレーンの努力は、59年の『ジャイアント・ステップス』で実を結ぶことになり、この画期的な作品は、光のように凄まじい速さでコード・チェンジする奏法から「シート・オブ・サウンド」と評された。その後も自身のプレイ・スタイルを常に進化させ、61年にはマッコイ・タイナー、ジミー・ギャリスン、エルヴィン・ジョーンズを迎え、新カルテットを結成し、マイルス・デイヴィスとの音楽活動から学んだアプローチに基づき、おもに旋法的なプレイをした。67年に早すぎる死を迎えるまでの間は、既成のリズムやコード進行から解放された即興演奏へとその演奏法を転向させる。また、ジャズの常識をくつがえし、卓越したスタイルを築いた偉大なイノベーターでもあった。
(Warner Music サイトより一部引用)
“モダン・ジャズの帝王”マイルス・デイヴィスの誕生
アフリカ系アメリカ人ではあるが、かなり裕福な家庭に生まれ育ったマイルス・デイヴィスは、父(歯科医)の親友(内科医)からのプレゼントとして、トランペットに出会った。高校卒業のおよそ半年後、地元セントルイスにやってきたビリー・エクスタインのビッグバンドで欠員が出たため、急に穴埋め要因で演奏することに。このバンドで聴いたチャーリー・パーカー(1920〜55)等の演奏に衝撃を受けて、彼らが普段活動しているニューヨークに出ることを決意。両親を納得させるため、1944年にジュリアード音楽院へ入学した。最初の学期こそ、ある程度真面目に音楽院にも通ったがジャズの最前線に身を投じるべく、1945年の半ばに自主退学。9月4日にミュージシャンズ・ユニオンに加入して、いよいよニューヨークでプロのプレーヤーとして演奏しはじめる。
活動の最初期はパーカーの五重奏団のメンバーとして。彼のような超絶技巧で圧倒することは自分にはできないと自覚し、抒情的なソロを自らの個性として見出していく。次第にパーカーのだらしなさに耐えきれなくなったマイルスは、独自の活動を模索。その成果のひとつといえるのが、スリリングな即興よりも、洗練された作編曲に重きを置いた『クールの誕生』(1949〜50年録音)だ。また、この延長線上にギル・エヴァンスと共作による人気作『マイルス・アヘッド』(1957)、『ポーギー&ベス』(1958)、『スケッチ・オブ・スペイン』(1959)が続いていく。
時間軸が前後してしまったが、1950年代前半〜半ばにはインディレーベルのプレスティッジ・レコード(Prestige)に『ウォーキン』(1954)や、いわゆるマラソンセッションによる4部作(『クッキン』『リラクシン』『ワーキン』『スティーミン』/1956年)といった初期の人気作が録音されたが、1957年発売の『ラウンド・アバウト・ミッドナイト』からメジャーレーベルであるコロンビア・レコード(CBS、ソニー)に移籍。ここから多くの名盤を生み出していく。なんといっても重要なのはモードジャズを象徴するアルバムにして、没後も含めると最大の売上枚数を誇る『カインド・オブ・ブルー』(1959)だ。
マイルスの背中から羽ばたいたジョン・コルトレーン
このあたりの時期、1955〜60年にかけてマイルスのグループに参加していたのが、主にテナー・サックスを吹いていたジョン・コルトレーン(愛称 トレーン)だ。「シーツ・オブ・サウンド(=音の敷物)」と評されたように細かい音符を敷き詰めていくような演奏を得意としていた。一時期脱退して、セロニアス・モンクのもとで研鑽を積んだ時期もある(1957年のカーネギーホール・ライヴも名盤だ!)が、マイルスのもとで才能を開花させ、独立して羽ばたいていく。ソプラノ・サックスをコルトレーンが演奏するようになったのもマイルスのお陰だ。
この頃の代表作といえば『ジャイアント・ステップス』(1959)や『マイ・フェイバリット・シングス』(1960)が有名だが、後者のタイトルチューン(もちろん作曲はリチャード・ロジャース)は、のちに何度となくライヴ録音されていくので、この1960年録音がベストとは言い難い。個人的には『セルフレスネス:Featuring マイ・フェイバリット・シングス』に収録された1963年録音がおすすめである。
1960年代前半のコルトレーンは、周期性を曖昧にしていく「モードジャズ」という新しい演奏スタイルの可能性を追求していたが、伝統的なスタイルに近しい『バラード』(1961〜62)や『ジョン・コルトレーン&ジョニー・ハートマン』(1963)といった甘く親しみやすい名盤も人気だ。しかし彼の本領はやはり「モードジャズ」、そしてより自由な「フリージャズ」へと変化していく過程にある。
コルトレーンの思想や宗教観が反映された『至上の愛 A Love Supreme』(1964)等を経て、いよいよ1965年6月28日に録音された『アセンション』以降は、本格的に「フリージャズ」の時期に突入。いきなり聴いても何をしたいのか伝わらないかもしれない。その場合は翌7月に同じ曲をパリで、今度は4人で演奏した際にはモードジャズのスタイルで演奏している動画があるので探してみよう。2つの録音を比較するといろんなことに気づかされるはずだ。この時期には「マイ・フェイバリット・シングス」さえもフリージャズになった。ところが1967年7月17日、コルトレーンは肝臓癌で急逝してしまう。まだ40歳だった。マイルスは後年、彼の死を振り返ってこう述べている。
「トレーンの死は本当に悲しかった。彼は偉大で美しい音楽家だっただけでなく、私が敬愛する優しくて美しく、崇高な人間だったからだ。彼のスピリット、クリエイティヴなイマジネーション、そして探求性、革新的なアプローチを懐かしく思うよ。彼はバード〔=チャーリー・パーカー〕のような天才だった」
マイルスが切り拓いた“その先”
いったん時を戻そう。1963年からマイルスはいよいよ本腰をいれて新しいメンバーを集めはじめ、いよいよ1964年9月にテナーサックスのウェイン・ショーター、ピアノのハービー・ハンコック、ベースのロン・カーター、ドラムスのトニー・ウィリアムスという理想の顔ぶれが揃った。スタジオ録音の『E.S.P.』(1965)、『マイルス・スマイルズ』(1966)、『ソーサラー』『ネフェルティティ』(1967)、ライヴ録音の『ライヴ・アット・ザ・プラグド・ニッケル』(1965)で、アコースティックなジャズの可能性を極限まで切り拓いていく。
実験的な過渡期にあたる『マイルス・イン・ザ・スカイ』『キリマンジャロの娘』(1968)を経て、電気楽器を大胆に取り入れた『イン・ア・サイレント・ウェイ』と『ビッチェズ・ブリュー』(1969)という2大傑作が誕生。特に後者は多くの賛否を巻き起こしたが、発売当時でいえばマイルスのアルバムのなかで最大の売上を記録した。また、これらのアルバムに参加したショーター、ハンコック、ジョー・ザヴィヌル、ジョン・マクラフリン、チック・コリアらが、1970年代を席巻する「フュージョン」(ジャズにロックなどの他ジャンルを「融合 fusion」させたスタイル)のグループを結成していくという観点から考えても、歴史的重要作とみなされている。
マイルスはその後、次々とメンバーを入れ替えながら多彩な音楽を生み出していく。ストレートなロックに接近した『ジャック・ジョンソン』(1970)、キース・ジャレットを擁していた時期の『ライヴ・イヴル』(1970)、ファンクとインド音楽と現代音楽(シュトックハウゼン)に刺激を受けた『オン・ザ・コーナー』(1972)など、一作として似たアルバムがない。
ちなみに1973年と1975年に来日して全国各地でライヴを開催していることもあり、この時期のマイルスの音楽に対する熱心なファンが日本には多い。1975年2月1日の昼夜公演は『アガルタ』『パンゲア』という2つのアルバムになっている。ところが同年の9月5日を最後にライヴ活動が停止。散発的にスタジオ録音がおこなわれたが、しばらくマイルスは引退状態となってしまう。
1981年7月にリリースされた『ザ・マン・ウィズ・ザ・ホーン』で本格的に復帰を果たし、1991年9月28日に65歳で亡くなるまで、マイルスは最後の10年を駆け抜けていく。この時期はジャズ・フュージョンのエレクトリックベース奏者マーカス・ミラーがプロデュースを務めたアルバム——『ザ・マン・ウィズ・ザ・ホーン』(1980〜81年録音)、『TUTU』(1986)、『アマンドラ』(1988〜89)——が特に重要だろう。
筆者が選ぶこの時期のベストは『アマンドラ』——特に「ハンニバル」と「ミスター・パストリアス」——だが、当時のヒット曲であるマイケル・ジャクソンの「ヒューマン・ネイチャー」、シンディ・ローパーの「タイム・アフター・タイム」をカバーしている『ユア・アンダー・アレスト』(1984〜85)も涙なしには聴けない。かすれ気味のトランペットから健康状態が万全でないことが伝わってくるのだが、それでも音楽をせずにはいられない情熱に心動かされてしまうのだ。
関連する記事
-
読みもの歌手バーバラ・デインを扱った秀逸なドキュメンタリー
-
読みものマリの卓越したコラ奏者トゥマニ・ジャバテは歌の伴奏だったコラをソロ楽器として認識...
-
イベント10年目の音楽フェスLive Magic最終回が2024年10月19日、20日に...
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest