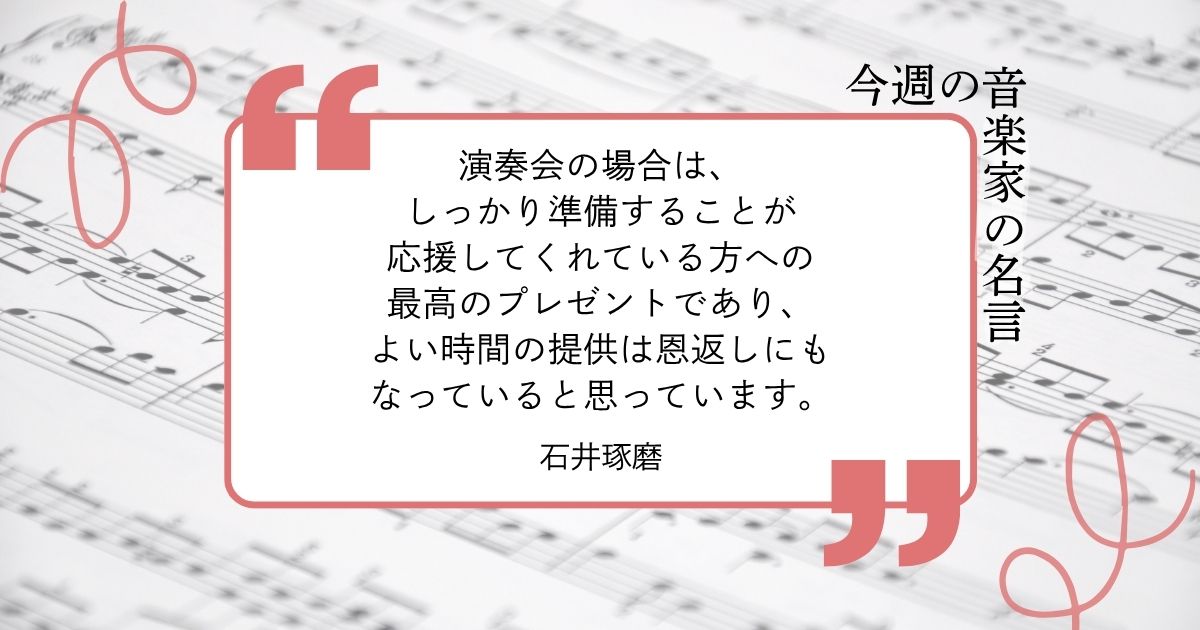インタビュー
飯森範親×角野隼斗 今度はジョン・アダムズに挑む、ふたりの音楽から目が離せない!

「ミニマル・ミュージック」は現代音楽の中でもひときわ聴きやすく、ポピュラー音楽のように親しみやすい音楽。その特徴は? どういう音楽のしくみになっているの? 作曲家の系譜は? この分野に詳しい音楽学者の柿沼敏江さんがわかりやすく整理して解説します!

カリフォルニア大学サンディエゴ校博士課程修了、PhD。専門はアメリカ実験音楽、20-21世紀音楽。著書に『アメリカ実験音楽は民族音楽だった』(フィルムアート、2005...