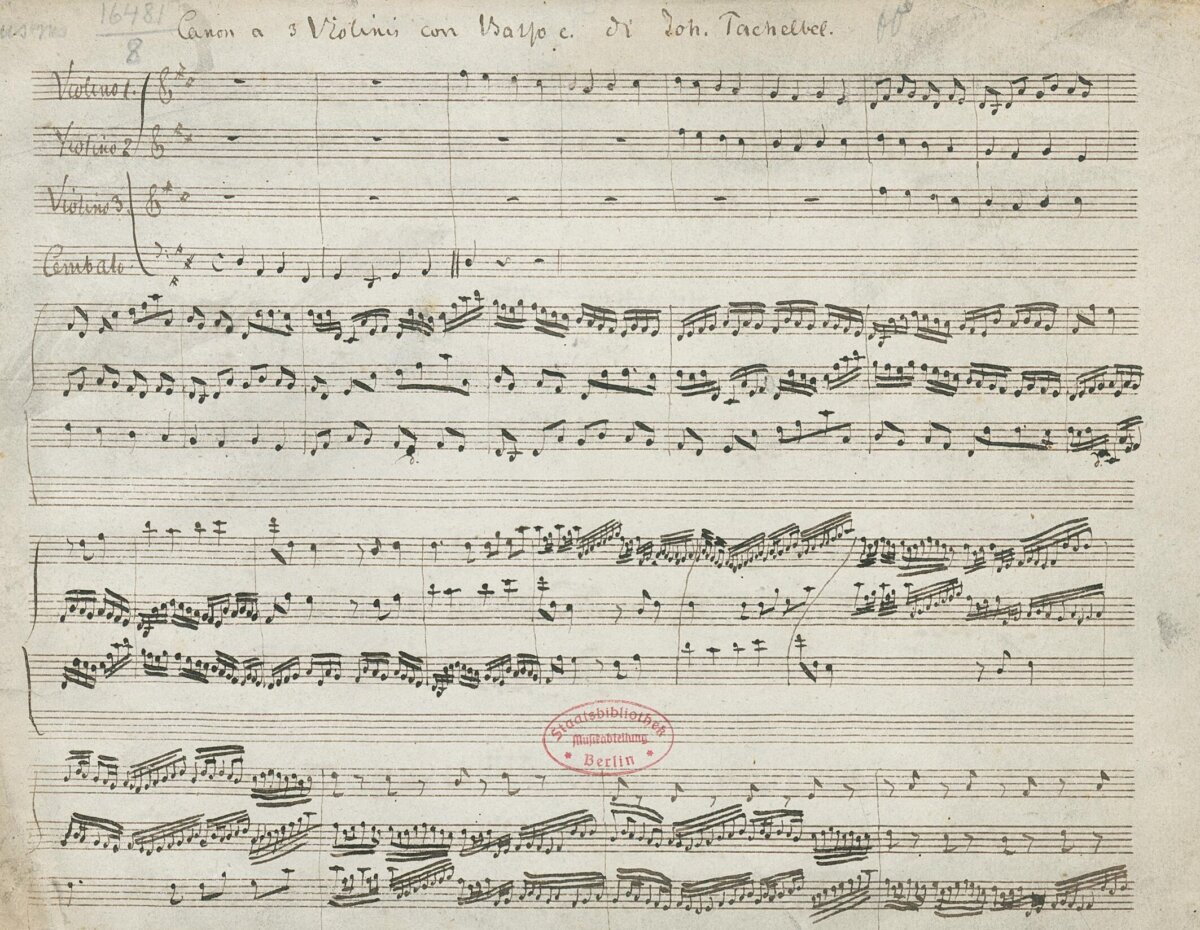「縄文—1万年の美の鼓動」展と、その土器や土偶の美に魅せられたクリエイターたち

ONTOMOエディトリアル・アドバイザー、林田直樹による連載コラム。あらゆるカルチャーを横断して、読者を音楽の世界へご案内。今回は、東京国立博物館の特別展「縄文—1万年の美の鼓動」について。すでに20万人を動員している縄文展。その魅力は、溢れ出る生命の喜びにあるのかもしれません。
芸術という考え方も、体系化された宗教もなかった時代の人々にとって、「祈り」とは何だったのでしょうか。音楽を通して縄文の美を見てみましょう。

1963年埼玉県生まれ。慶應義塾大学文学部を卒業、音楽之友社で楽譜・書籍・月刊誌「音楽の友」「レコード芸術」の編集を経て独立。オペラ、バレエから現代音楽やクロスオーバ...
東京国立博物館の特別展「縄文—1万年の美の鼓動」(9月2日まで)が大盛況だ。すでに来場者は20万人を突破している。
とにかく客層が幅広い。
夏休み期間中の子供たちとその両親、シニア世代の夫婦もたくさん。会場の雰囲気も楽しそうで、とぼけた表情の土偶を前に「かわいい〜」とつぶやく幼児を抱っこしたお父さん、木の皮で編んだ“縄文ポシェット”(中にはクルミの殻が残されていた)を前に「あら、お洒落ねえ」と感心するご婦人方など…真夏ということもあるけれど、ラフな格好にサンダルをつっかけたような、普段着な人たちが多い。

みんな、少しもかっこつけていない。なんだか和やかなのだ。そのなかに、いつも美術展に集まってくるような、いかにもアート好き、意識高い系な人たちも少しは混ざっている。その風景がいい。
これは、縄文時代の土器や土偶といった考古資料群そのものが、いかように楽しめる自由な雰囲気を醸しているからではないだろうか。
なぜって、これは芸術だから、と構える必要はないからだ。
そもそも、縄文時代には「芸術」という考え方は存在したのだろうか。

青森県教育委員会蔵(縄文時遊館保管)写真:小川忠博
青森市 三内丸山遺跡出土 縄文時代(中期)・前3000~前2000年
かつて1950年代に、岡本太郎がピカソに匹敵する「縄文の美」を発見したことが、縄文をアートとして捉えなおすきっかけとなった。つまり縄文とは戦後、新たに沸き起こった、新しい美の価値の象徴でもある。
今回の縄文展では、戦後の芸術家たちに縄文の美が及ぼした影響についても触れられていて、作家の川端康成がお気に入りの土偶を手元に置いて執筆していたことも写真展示で知ることができる。
展示にはなかったが、縄文にこだわりぬいていた作曲家として、武満徹を挙げないわけにはいかない。
生前、武満が作曲していた別荘のある長野県北佐久郡御代田町、すなわち浅間山麓の一帯は、かつて縄文人たちが大集落を数多く形成していた地域で、出土品も極めて多いことでも知られる(同地の浅間縄文ミュージアムはその歴史を今に伝える)。
武満の作曲活動には、この縄文ゆかりの豊かな森に恵まれた御代田の静かな雰囲気が欠かせなかった。
岡本太郎、川端康成、武満徹——日本の芸術界の巨人たちが、なぜ揃いも揃って縄文文化の影響を受けたのか? これは非常に興味深いテーマである。
とにかく縄文時代の出土品をたくさん見ること、そしてそこから直接感じ取れるものを、自分の感覚として確かにつかんでおくこと。それが大事だと思う。
*
今回の縄文展で強調されているのは、日本の始まりを稲作と弥生文化の始まりとする歴史観以前に、何と1万年にも及ぶ縄文時代が存在したという、その時間的なスケールの巨大さである。
1万年といえば、弥生時代から現代までを合わせたよりも長い期間である。そんなにも長い間、継続可能な文明の形態が存在したのである。
エジプトやメソポタミア、ギリシャ、インドといった世界最古とされる文明地域との比較コーナーもある。それと同じくらい古い昔から、こんなに豊かな文化が、私たちの祖先の住む列島にあったのだ。
特筆すべきは、土器や土偶の形状のユニークさである。有名な火焔型土器だけではない。土偶にも無数の種類がある。特に仮面の表情は面白い。

山梨・南アルプス市教育委員会蔵 山梨県南アルプス市 鋳物師屋遺跡出土 縄文時代(中期)・前3000~前2000年
そのひとつひとつが、何と大胆な精神に満ちていることだろう。そこから漂ってくるのは、生命のよろこびであり、造形の自由であり、人をほっとさせるような、とぼけたような、ユーモラスな表情である。
まるで、現代のゆるキャラ、あるいは漫画文化の原点を見るようであった。
その意味で、縄文人たちは、まさしく現代の日本人と同じDNAをもっている——そう私は確信したほどである。
*
今回の縄文展は、いくつかのテーマに分けて展示を行なっているが、その中に「祈り」というコーナーを置いていたのも、良いと思った。
縄文時代は、孔子も釈迦もマホメットもキリストもいなかったほどの大昔である。その頃の祈りとはいかなるものだったのだろうか?

青森・八戸市蔵(八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館保管)
青森県八戸市 風張1遺跡出土 縄文時代(後期)・前2000~前1000年
クラシック音楽のなかに、祈りについて触れた有名な作品がある。
ストラヴィンスキーのバレエ音楽《春の祭典》である。
1913年に発表された《春の祭典》は、有史以前の太古の昔のロシアで、春の訪れを祝う人々の、生贄の儀式が題材となっている。
それは、近代までのヨーロッパがとらわれていたキリスト教中心主義を脱し、既存のあらゆる宗教さえも越えた、人類にとっての宗教の原点を見つめるバレエでもある。
それは文化人類学の始まりでもあったかもしれない。
そう考えると、《春の祭典》の野性的な荒々しさは、そのまま縄文文化の生命力につながるものではないだろうか?
一つ違うとすれば、《春の祭典》が生と死の儀式として一種の厳しさに満ちているならば、縄文の仮面たちは、敬虔ではあっても、もっとユーモラスで朴訥な、ほのぼのした表情をもっていることだ。それが彼らの祈りの特色でもあったのかもしれない。
1万年にも及ぶ縄文文化のスケールは、この列島に住む人々の歴史の始まりについての壮大な想像力をかき立ててくれる。そして、芸術とは何か、祈りとは何か、歴史とは何かということについて、改めて考えさせてくれる。
会期: 2018年7月3日(火)~9月2日(日)
開館時間: 9:00~17:00(休館日:月曜日)
会場: 東京国立博物館 平成館
http://jomon-kodo.jp/index.html





関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest