
自然、作曲家との関係、恋…左手のピアニスト舘野泉の音楽が生まれるとき

2002年に脳溢血で倒れ、右半身不随となってからも、しなやかにその運命を受け止め、「左手のピアニスト」として、ますます旺盛な活動を繰り広げている舘野泉さん(1936年生まれ)。その左手のために捧げられたピアノ曲は、10か国の作曲家たちから、120曲以上にのぼる。
10月22日のリサイタルでも委嘱新作を初演する舘野さんに、生い立ちや近況、第二の故郷フィンランド、さらには人生観や音楽観について、貴重なお話をうかがった。

1963年埼玉県生まれ。慶應義塾大学文学部を卒業、音楽之友社で楽譜・書籍・月刊誌「音楽の友」「レコード芸術」の編集を経て独立。オペラ、バレエから現代音楽やクロスオーバ...
自然の中で暮らす
——舘野さんに捧げられた作品は、フィンランドの曲も、日本の作曲家の曲もみんなそうなんですけど、自然にまつわる曲のタイトルがすごく多いですよね。昔から自然に囲まれた暮らしをされてきたのですか。
舘野 いまから85年前に僕が生まれて育った自由が丘は、終戦を迎えて疎開から帰ってきた10歳の頃、このあたりは舗装もされてなかったし、車も通らないし、トンボやセミを採ったり、川でザリガニを採ったり、メンコをしたりベーゴマ回したり、そういう生活をしていました。
自然の中で暮らすっていう、特別な感じはなかったですけど。

クラシック界のレジェンド、84歳ピアニスト。東京生まれ。1960年東京藝術大学を首席卒業。1964年よりヘルシンキ在住。1981年以降、フィンランド政府の終身芸術家給与を受けて演奏生活に専念する。これまで北米、南米、オーストラリア、ロシア、ドイツ、フランス、北欧諸国を含むヨーロッパ全域、中国、韓国、フィリピン、インドネシアなどアジア全域、中東でも演奏会を行う。これまでにリリースされたLP/CDは130枚におよぶ。2002年に脳溢血で倒れ右半身不随となるも、しなやかにその運命を受けとめ、「左手のピアニスト」として活動を再開。尽きることのない情熱を、一層音楽の探求に傾け、独自のジャンルを切り開いた。“舘野泉の左手”のために捧げられた作品は、10ヶ国の作曲家により、100曲をこえる。2012年以降は海外公演も再開し、パリやウィーン、ベルリンにおいても委嘱作品を含むプログラムでリサイタルを行う。新刊『舘野泉フォトストーリー』(求龍堂刊)。
舘野 最近は、フィンランドの別荘には毎年夏の2ヶ月間、家内と2人だけで暮らしています。

舘野 森と湖に囲まれた自然の中で、白鳥やカナダガン(雁)が飛んできたりするようなところで、ほとんど人とも会わない。周りにあんまり民家もなくて、一番近くの小さな店に行くのに10キロ離れているくらい。
母屋から30メートル離れたところに僕の仕事小屋があって、そこにはピアノと机があり、そこに行けば一人になれるんです。
うちは水道がないんです。飲み水は湧水でおいしいですよ。100メートルぐらい母屋から離れたところまで汲みに行くんです。もちろん、生活用水は湖水からポンプで引くようにして、サウナに入るとか、食器を洗ってというのは、それを使っていますけど。


新しい曲を少なくとも10回は弾いて育てていく
——すごい別荘なんですね。素晴らしい音楽を育んでくれそうな気がします。
いま手元に舘野さんの最近のCD(オクタヴィアレコード)を3枚持ってきたんですが、日本人作曲家による『時のはざま 左手のためのピアノ珠玉集』、エストニアの作曲家ウルマス・シサスクによる『エイヴェレの星たち』、そして1988年録音の名盤『フィンランド・ピアノ名曲コレクション』。どれもこれも本当に綺麗な曲ばかりです。新しい曲がどんどん増えていますね。
舘野 左手だけになってからは、委嘱作が120曲、10ヶ国もの作曲家たちが書いています。
最初の頃は、たとえば間宮芳生さん、吉松隆さん、林光さん、あとはノルドグレンとか、30名ぐらいお付き合いがあった人に頼んでたんですけど、そのうちに東京だけじゃなくて、九州、関西、北海道などの、だんだん若い人に、いろんなルートで出会うようになった。
外国の作曲家にも新しく知り合いができて。あなた曲を書いてくれない? と頼むと、みんな喜んで書いてくれる。そんな風にして、自然発生的に広がっていきました。

——曲を頼むときに、条件とかテーマをつけたりとかは?
舘野 ほとんど何もしません。2005年頃、吉松隆さんに頼んだときには、北欧の冷たい澄んだ空気を感じさせるような曲を書いてくれ、と条件を付けたのが初めてですよ(「タピオラ幻景」)。
吉松隆「タピオラ幻景」(ピアノ:舘野泉)
舘野 光永浩一郎さんという熊本の作曲家、彼にも条件はつけなかったけれど、たとえば「苦海浄土に寄せる」や「サムライ」では、水俣のこと、隠れキリシタンのこと、西郷さんの西南戦争とか、そういう苦しい思い、歴史が浄化されてというか、長いこと蓄積があったものが出てきたりというのはあります。
光永浩一郎「サムライ」(ピアノ:舘野泉)
——新しい曲が出来上がったあとに、作曲家とやりとりがあったり、直してもらったりというのはありますか?
舘野 僕は何も言いません。新しい曲を見て、触って、自分の中で作品を熟成する。そういうことをやってから、変えてくれっていうことはしません。
吉松隆さんの「タピオラ幻景」は、死ぬような思いで苦労しましたが、オクターヴの跳躍を少し短くしてもらい、何回も弾いているうちに慣れてきた。その曲はやっぱりお客さんにもすごく喜ばれたしね。たぶん200回ぐらい演奏会で弾いています。

舘野 アコーディオンのcobaに書いてもらった「記憶樹」もすごくいい。それも100回ぐらい弾いています。少ないものでも10回ぐらいは弾いていますね。つまり1回引いて終わりっていう曲がないんです。
——それはすごいですね、曲たちも幸せですね。
舘野 何度も演奏会で弾くことによってね、曲が育つんですよ。大きくなっていく。
coba「記憶樹」を収録した50周年記念アルバム
自分が生きて生活をしてきた記憶から、音楽が生まれてくる
——誰も弾いたことのない曲に、これほど多く、いつも挑戦していらっしゃるのはすごいことです。
舘野 でもそれは若いときからやってたことでもあるし。
例えば、1960年のデビュー・リサイタルではエネスコのソナタを日本初演した。それから、1964年かな、メシアンの2時間かかる「幼子イエズスに注ぐ20のまなざし」も日本初演です。そういうことが若い頃から好きで、それが自然だった。
10歳のときに学生コンクールで2等をもらった。そのときに弾いたのがドビュッシーの「子供の領分」。
あの頃はベートーヴェン、バッハ、モーツァルト、ショパンくらいまでで、ドビュッシーを弾く子どもなんてそういなかった。あとはバルトーク、プロコフィエフ、ショスタコーヴィチとか。すごく面白いから、中学生の頃、随分弾いていましたよ。
——当時としてはそういう作曲家は、まだそんなにメジャーではなかった?
舘野 全然。藝大に入ってもメジャーじゃなかった。
——そうしたなかで、例えば安川加寿子さんに、「よくセヴラックのことを知っているわね」と驚かれたというエピソードがあったそうですね。
舘野 「どこで知ったの?」と言われたもの。セヴラックは今年が没後100年。来年生誕150年ですよね。
——舘野さんは、おそらく日本で最初にセヴラックに注目したピアニストですよね?
舘野 そうでしょうね。でも、最初に注目していた人は、例えば音楽評論家の大田黒元雄さんですね。それから秋田生まれの作曲家の石田一郎さん。
私がセヴラックを初めて知ったのは19歳のときです。僕は慶応高校を出て、藝大を受けたんだけど現役の試験は落っこちちゃって、浪人してた。そのときにいろいろ文献で読んで、セヴラックにとても興味を持った。自然の題材をとった曲が多いし、印象派の絵のようだし。
——そういう意味でも、真っ先にいろいろな新しいものを見出してこられてきた。でもその中でも、舘野さんにとってフィンランドは、なぜ第二の故郷になったんですか。
舘野 やっぱり北のほうの静かな、空気が澄んで、あまり物質的には恵まれず、その中で、人間が慎ましく生きていく、というようなことに惹かれたっていう点もありますね。
母が室蘭で育ったんですけど、「お母さんのいた頃の室蘭は静かで良かっただろうね」と言ったら、「いや、あの頃は、サハリン(樺太)に行くとね、もっと静かで、海が綺麗で、深い色をしていて、私たちは憧れていたんだよ」って。
そんな話を聞いてね、ずっと北に憧れていた。
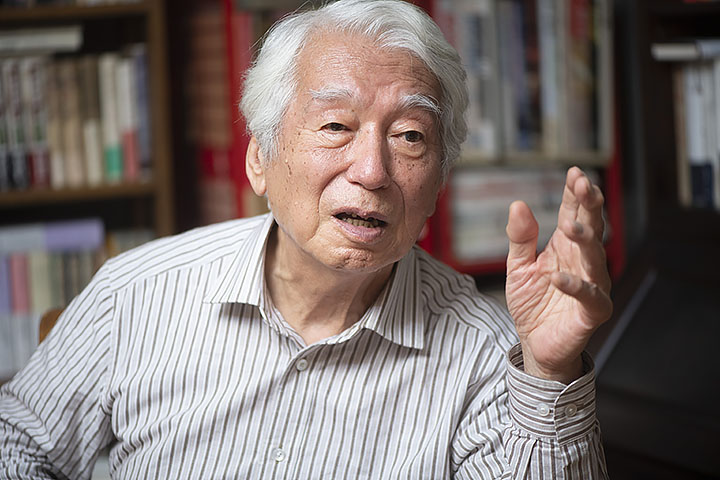
舘野 音楽を勉強するのに、ニューヨークだのベルリンだの、行く必要はないと思っています。チェコでもどこでも……。つまり、僕がいるところはどこでもいい。音楽は弾くことの勉強だけじゃなくて、自分の中に入ってくるものが全部音楽なんだと思っているわけだから。
別に音楽を聴かなくたって、とにかく自分が生きて生活をしてきたというのがちゃんと記憶として刻まれていれば、その中から音楽が、生まれてくるものです。
いまでは、またいろいろな音楽家とも知り合って、自分もいろんな場所で演奏して、それを聴いてくださる人たちからも、音楽を受け取っています。だから、僕はどこにいたって、音楽は勉強できる。ちゃんと自分が生きてるっていうことが、すなわち音楽です。
10月22日に初演する「静寂」と「鬼」の新曲
——フィンランドでは、素晴らしい作曲家たちと親交がありますね。ラウタヴァーラやノルドグレンなど。次の10月22日のリサイタルで「静寂の渦」を演奏されるカレヴィ・アホ(1949-)もその一人です。
舘野 アホのことはずっと前から、50年近く知っています。以前ピアノ・クインテットを書いてもらったので、今度は2作目でピアノ・ソロで書いてくれと頼んだ。そこで「静寂について書いてくれない?」と希望を言った。
そしたらアホが「静寂って音がなくてもいいのか」っていうから、「それでもいいよ。でも、静寂があるのは、森を揺るがすようなものすごい嵐もあるし、そういうものがあって、静寂がある」と言ったら、そうか。と。で書いてくれた。
——委嘱初演となる「静寂の渦」という曲ですね。
舘野 渦がずっと回っているんです。それがだんだんと広がって、大きさ、深さが出てきて、色が出てきて、細かい動きになって、音域が広くなって、音符が細かくなって、激しくなって、クライマックスに行ったら、そこからだんだんと音が少なくなって、最後は一番高い音で消える。すごく緻密に書かれてる。
この曲について彼が書いてくれた言葉に、「ブラックホール」とあって、そうなのかと。原初の渦がどんどん膨張して、最後にブラックホールに吸い込まれて、何もなくなる。
——宇宙的なビジョンですね。
舘野 そうです。その曲はすごいです。ものすごく気に入っている。
フィンランドの作曲家カレヴィ・アホのトップトラック
——今度演奏される、平野一郎さんの「鬼の生活」という組曲も面白そうです。これも委嘱初演ですね。
舘野 平野一郎君は、今50歳ぐらいかな。日本の民俗芸能をすごく知りたくて、全国を旅行して、そういうものに触れて歩いてるんですよ。それを知ってるから、鬼について書いてと頼んだ。
鬼っていうのは日本の文化に根付いて、たぶん1000年ぐらいです。鬼に関する伝説っていうのは全国にある。いろんな形の鬼がいて、非常に恐れられている面もあるけども、親しまれている面もありますよね。とにかくキャラクターがいろいろある。
この「鬼の生活」も13種類の鬼で描いた。鬼の共同社会の中では、恋もするし、情欲の世界もあるし、それから一緒になって、農作をする。例えば鬼には、私有、という観念がないから、恋愛も自由だと。それでも一生懸命生きてて、恐ろしく純粋なんだ。とても面白い鬼たちですよ。
左手はもっといろいろやれる
——2002年に倒れられて、右手が使えなくなって、それでどんなふうに音楽が変わったのでしょうか。
舘野 何も変わってないですよ。脳溢血で弾けなかった2年間を除いて、左手だけになっても、今までと全然変わりない自分がずっと続いてる。こっち(右手)が、ピアニストの花ですよね。でも、倒れたことで、そういうものがなくなって、それで失望したとか、もう力を落としたとか、そういうことじゃない。
——左手のピアニストになったことによって、左手の重要性とか役割とか、左手の意味が浮かび上がってきましたか?
舘野 左手の技術がどうとか、特別に考えたことはありません。でも、こうやったら、もっと音楽が全体として、いいものになっていくとか、それはもう常に考えている。でもそれは両手でやってるのと同じことです。1本の手だろうが2本の手だろうが、変わりません。
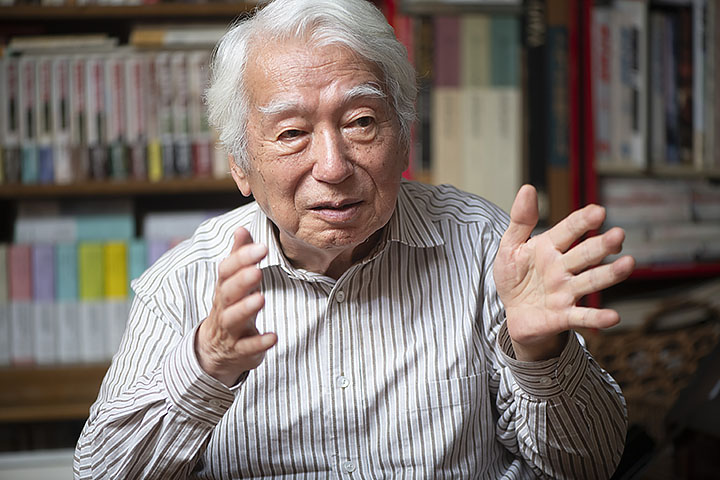
——これだけ左手のための曲を委嘱し続けたピアニストって世界中探しても他にないと思います。
でも、両手が使えるピアニストが、これらの曲を弾こうとするとき、右手を使わずにやっぱり左手だけで弾かなければいけないのでしょうか。それとも技術的に難しいと思ったら右手を使ってもいいものですか?
舘野 それは使ってもいいですよ。でもね、結局は左手だけでやったほうが弾きやすい。音楽が自然に生まれてくる。両手でやるとちょっと違う音楽になっちゃう。
——両手が使える人が、あえて左手だけのための曲を弾くことで何かやっぱり見えてくることがあるのかもしれませんね。
舘野 それは、さっきおっしゃった、左手の意味を再認識するいい機会だと思います。左手はもっといろいろやれる。
来年はセヴラックの生誕150年。トゥールーズから40キロほど離れた、彼の生まれたサン・フェリックスという町でフェスティバルが毎年あるんですが、来年は僕も頼まれて弾くことになっています。
そこで、僕が一番好きな《大地の歌》という30分ぐらいの曲を弾きたいので、左手だけのために編曲してくれと、光永浩一郎さんに頼んだんですよ。2年かかって、やっと6月に完成した。それをいま練習しています。
両手でやるものを、ほとんどそのままというか、とにかく音は減らさないで、素の姿がわかるようなものを、左手だけでやる。これはすごく大変です。原曲の3倍は難しくなってる。

セヴラックの組曲《大地の歌》の原曲(ピアノ:アルド・チッコリーニ)
——セヴラックの曲って、田舎から季節の果物が届いたような曲が多い感じがします。
舘野 (笑)そう、日常と季節感ですよね。全然気どりがなくて、優しい気持ちなんですが、その中で使われている和声、ハーモニーが素晴らしい。
それに、ドビュッシーがセヴラックの和声を素晴らしいと言っている。まさにそうだと思う。今その原曲を左手だけで解きほぐして弾いてみるとね。もう、たまらないですよ。
——「音楽の友」に舘野さんが書かれていた連載が最終回になりましたが、その中でセヴラックについて素敵なことが書いてありました。「何気ない日常の中に真の幸福があるということを語る、感謝の祈りを捧げる」。それと「恋する心を保ち続けることが、いつまでも若い秘密」と。その恋の感じも、ちょっとセヴラックの音楽の中にあるような気がします。
舘野 そうですね。やっぱりあります。
——舘野さんは今でも恋してらっしゃるんですか?
舘野 いつもしてます。それじゃなきゃ、生きてられないですよ。だって……素晴らしい人、いっぱいいるじゃないですか(笑)。
動画:最後の質問「いい音楽とは何でしょうか?」に答える舘野さん
舘野さんは、毎日料理をご自身で作られているのだという。「今日はアヒージョをこれから作ります」とおっしゃられていた。料理を好きな理由を尋ねると「素材に触れるのが好きなんです」とのこと。
毎日晩酌は欠かさない。脳溢血の後も、それは以前とまったく変わらないのだという。なぜお酒を止めないのですか、と聞くと、「今日も一日ありがとう、の意味だからね」と微笑んだ。
舘野さんの話をうかがっていると、不思議とこちらまでが穏やかなで自由な気持ちになってくる。音楽と人生のもっとも幸福な結びつきが、そこには感じられた。
- 日時: 2021年10月22日(金) 19:00開演
- 会場: 東京文化会館 小ホール
- 出演: 舘野泉
- 曲目:
-
- 吉松 隆:「アイノラ抒情曲集」(2006) Op. 95より
1. ロマンス
2. アラベスク
3. バラード
5.モーツァルティーノ - 吉松 隆:「タピオラ幻景」(2004) Op. 92より
1. 光のヴィネット
3. 水のパヴァーヌ - カレヴィ・アホ:静寂の渦 (委嘱作・初演)♪
- 林 光:花の図鑑・前奏曲集 (2005)
「ヒメエゾコザクラ」
「イヌタデ (あかまんま)」
「イヌノフグリ」
「サンザシ」
「ハス」
「ツリフネソウ」
「フキ」
「ノイバラ」 - 平野一郎:鬼の生活
~左手のピアノで綴る野帳 (フィールドノオト)~ (委嘱作・初演)♪
1) はしり鬼
2) はたらき鬼
3) くつろぎ鬼
4) わらひ鬼
5) ふざけ鬼
6) うたひ鬼
7) をどり鬼
8) ねむり鬼
9) うなされ鬼
10) いかり鬼
11) あばれ鬼
12) なき鬼
13) かくれ鬼
- 吉松 隆:「アイノラ抒情曲集」(2006) Op. 95より
詳細はこちら





関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest





















