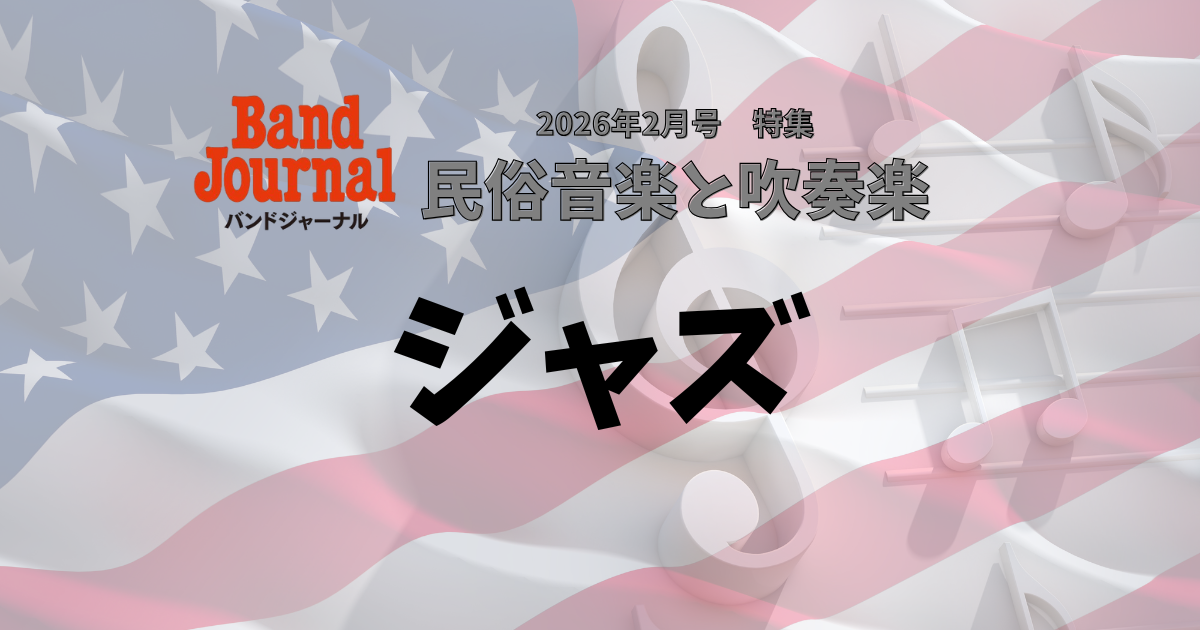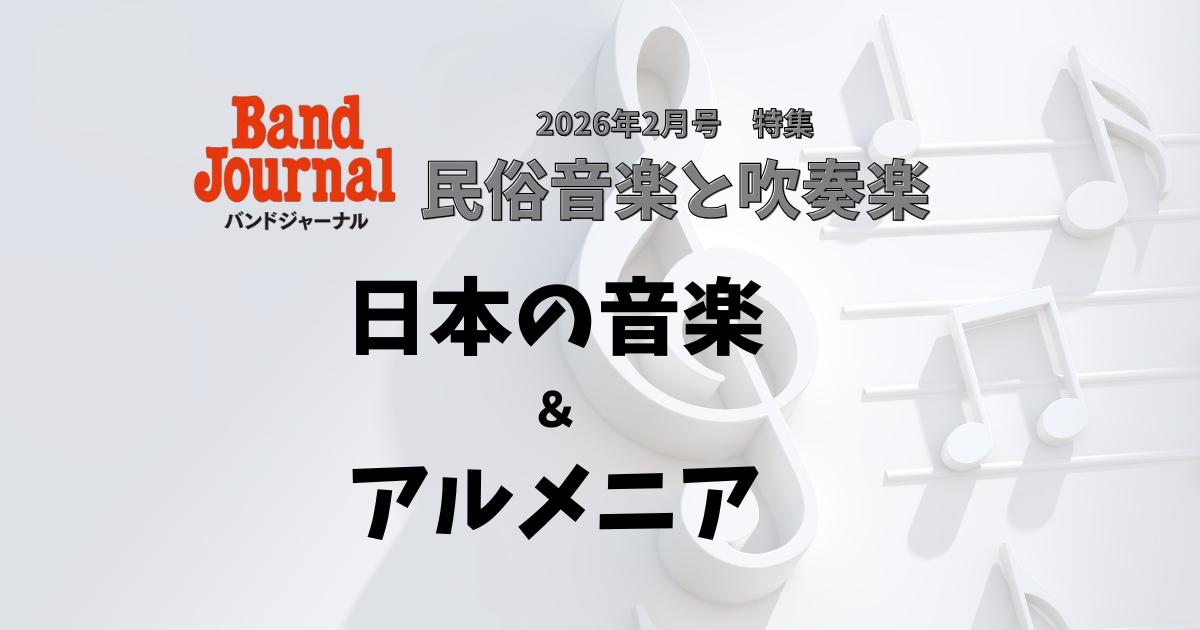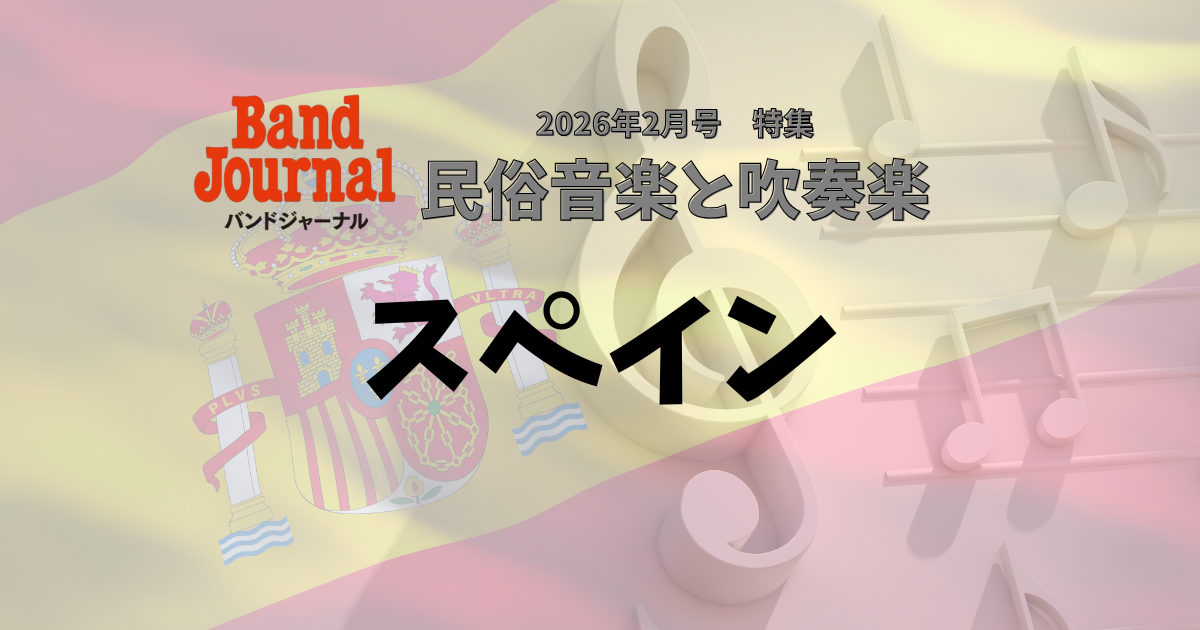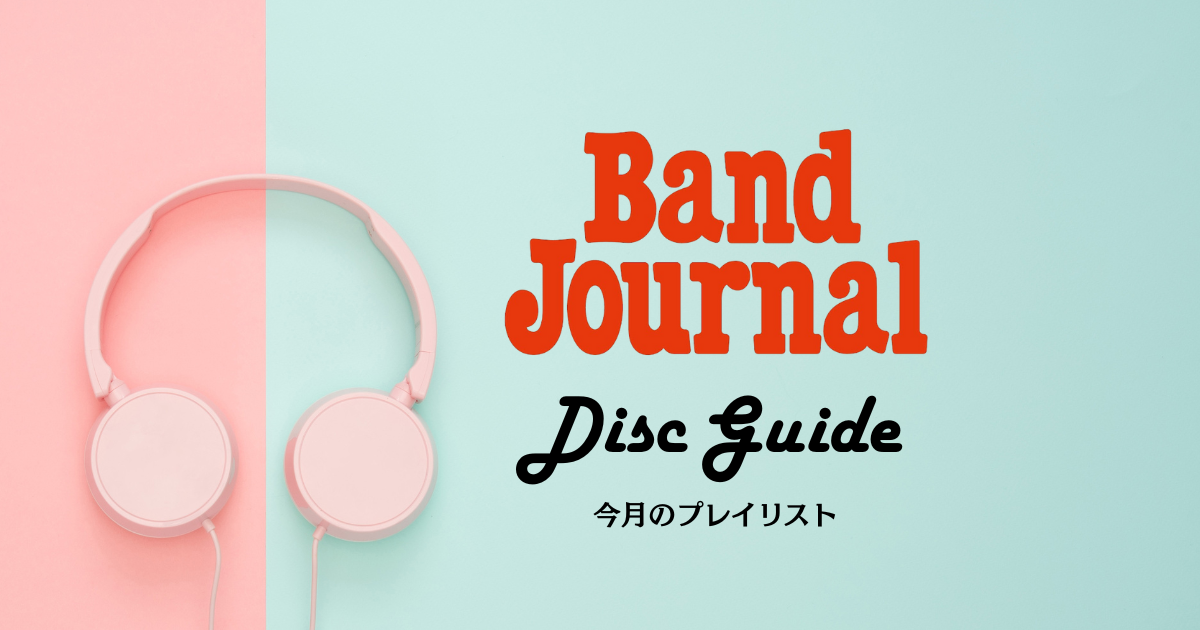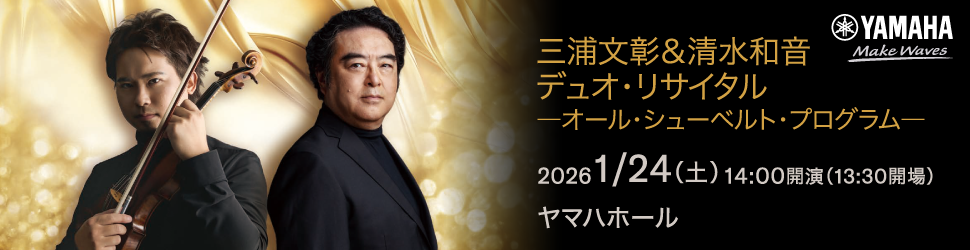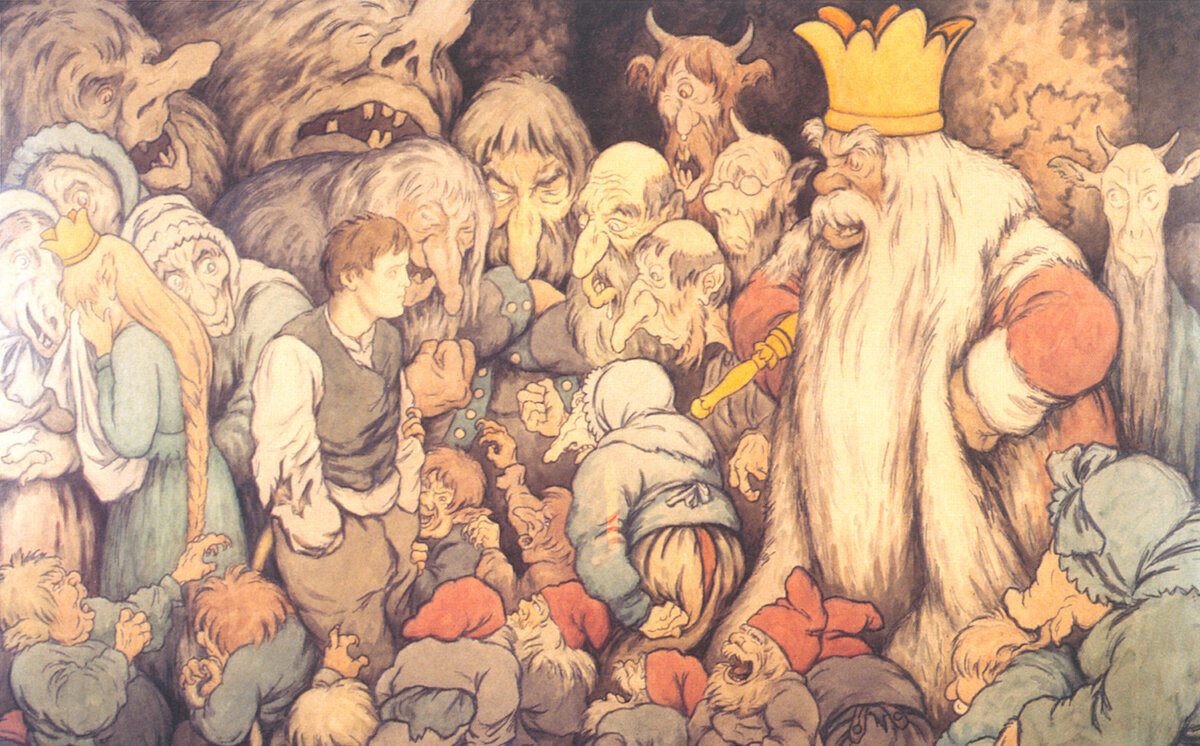服部百音に50の質問!〈前編〉音楽家になると決めた瞬間は? 思い出の曲は? 最大の試練は?

鮮烈な存在感を放ち続けるヴァイオリニストの服部百音さん。音楽の原点や演奏への想い、家族や人間関係についてなど、50の質問でその素顔に迫ります。
前編では、幼少期のお話から緊張との向き合い方、さらには耳コピであの名曲を覚えてしまった驚きのエピソードまで、情熱と繊細さをあわせ持つ服部さんの魅力に迫ります。

フランス文学科卒業後、大学院で19世紀フランスにおける音楽と文学の相関関係に着目して研究を進める。専門はベルリオーズ。幼い頃から楽器演奏(ヴァイオリン、ピアノ、パイプ...
サン=サーンスのヴァイオリン協奏曲をきっかけにヴァイオリンに夢中に
1. ヴァイオリンを始めたきっかけは?
服部 最初はバレリーナになりたくて、3歳からバレエを習っていました。ヴァイオリンは興味本位で触ってはいたんですけど、オイストラフのCDやサン=サーンスの「ヴァイオリン協奏曲第3番」の音源を聴いていくうちに、だんだん弾きたい曲ができて、それを弾くために練習をしてたら、結果的にヴァイオリンがどんどん上達していきました。バレエは本当に好きだったけど、最終的に6歳くらいのときにヴァイオリンと拮抗して、どっちをとるの? という話になったときに、ヴァイオリンをやるって自分で言ったらしいです。覚えてないんですけど(笑)。
——6歳でサン=サーンスのヴァイオリン協奏曲を弾きたいと思われたそうですね。
服部 そうなんです、それが最初に惚れた曲だったんですよね。1楽章も3楽章も大好きで、フランチェスカッティとミトロプーロスの演奏も、毎日擦り切れるほど聴いていました。最初、譜面が届く前に耳で覚えてしまい、弾きたくなっちゃったんだけど、ヴァイオリンを始めて1年くらいだったから、やはり弾ける技量が全然なくて。アルペジオもできなければ重音を弾いたこともない。発表会で3楽章を弾くことに決めて、1小節100回ずつ練習して挑みました。
——1小節100回ってなかなかできないことだと思います。
服部 それができたのは、曲があまりに好きだったから。弾けるようになりたいという一心だったので、にんじんをぶら下げてもらってたからできたけど、好きではない曲を100回は絶対無理です。

1999年9月14日生まれ。5歳よりヴァイオリンを始め、幼少期より辰巳明子、ザハール・ ブロンに師事。
8歳でオーケストラと初共演し、2009年にポーランドでのリピンスキ・ヴィエニャフスキ国際ヴァイオリンコンクールで史上最年少第1位並びに特別賞を受賞。10歳より演奏活動を始め11歳でミラノのヴェルディホールでリサイタルを行いグランドデビュー。ロシア、ヨーロッパに於いても演奏活動を始める。2013年にはヤング・ヴィルトゥオーゾ国際コンクールでグランプリ、新曲賞を受賞。また同年開催のノヴォシビルスク国際ヴァイオリンコンクールでは13歳でシニア部門に飛び級エントリーし、史上最年少グランプリを受賞。2015年にはボリス・ゴールドシュタイン国際コンクールでグランプリを受賞。2016年10月「ショスタコーヴ ィチ:ヴァイオリン協奏曲第1番、ワックスマン:カルメン 幻想曲」でCDデビューし、レコード芸術の特選盤に選出される。2017年新日鉄住金音楽賞、岩谷時子賞、2018年アリオン桐朋音楽賞、服部真二音楽賞、2020年ホテルオークラ音楽賞、出光音楽賞を受賞し2021年1月にはブルガリ アウローラ アワードを受賞した。現在はN響、読響、東京フィル、東響、日本フィルをはじめとする数々の著名オーケストラ、指揮者と共演を重ね海外でもマリインスキー劇場をはじめ様々な演奏活動を行っている。
桐朋学園大学大学院修士課程修了。使用楽器は日本ヴァイオリンより特別貸与のグァルネリ・デル・ジェス。
2. もしほかの楽器をマスターするなら何がいい?
服部 チェロかな。同じ弦楽器だけど、ヴァイオリンでは絶対に出せない音域と音色が出るので、痺れるなぁと。室内楽でうまい人が隣で弾いていると、この音をヴァイオリンで出そうと思っても、全部G線で弾いてもシャウトになってしまって、余裕のある器の大きい音が出ないなぁと思っちゃうんですよね。あとはヴィオラも好きです。もう少し体が大きかったらやってみたかったです。
3. 音楽家になっていなかったら、何になりたかった?
服部 いろいろあります。バレリーナは、ベースがクラシック音楽で、携わっている要素が似ている部分があるので、3つ先くらいの人生でいいかな。次はスキーヤーになりたいです。去年病気をして復活したあとにスキーにどハマりして、定期的に行って練習してたんです。いろいろなことができるようになってきて、とにかく気持ちよすぎて。ダイレクトに自然を感じて、直滑降でスピードを出して風がぶち当たってくるあの感じがたまらないです。
あとは、海もいいですよね。ダイバーも憧れます。体を使って、音楽は音楽でとても素敵なんだけど、自然の中でずっと過ごせる職業はけっこう憧れます。人間より自然があるところで動物と共存して、損得とか考えないで生きていけたらいいなって感じ。
関連する記事
-
インタビュー【Q&A】ヴァイオリニスト村田夏帆さん、世界が注目する17歳のオフ時間
-
インタビュー上野通明に50の質問!〈前編〉音楽家になると決めたのはいつ? 1日の練習時間は?...
-
記事チェリスト宮田 大にきく 多様なジャンルのプロ30人との“音楽の対話”から得たも...
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest