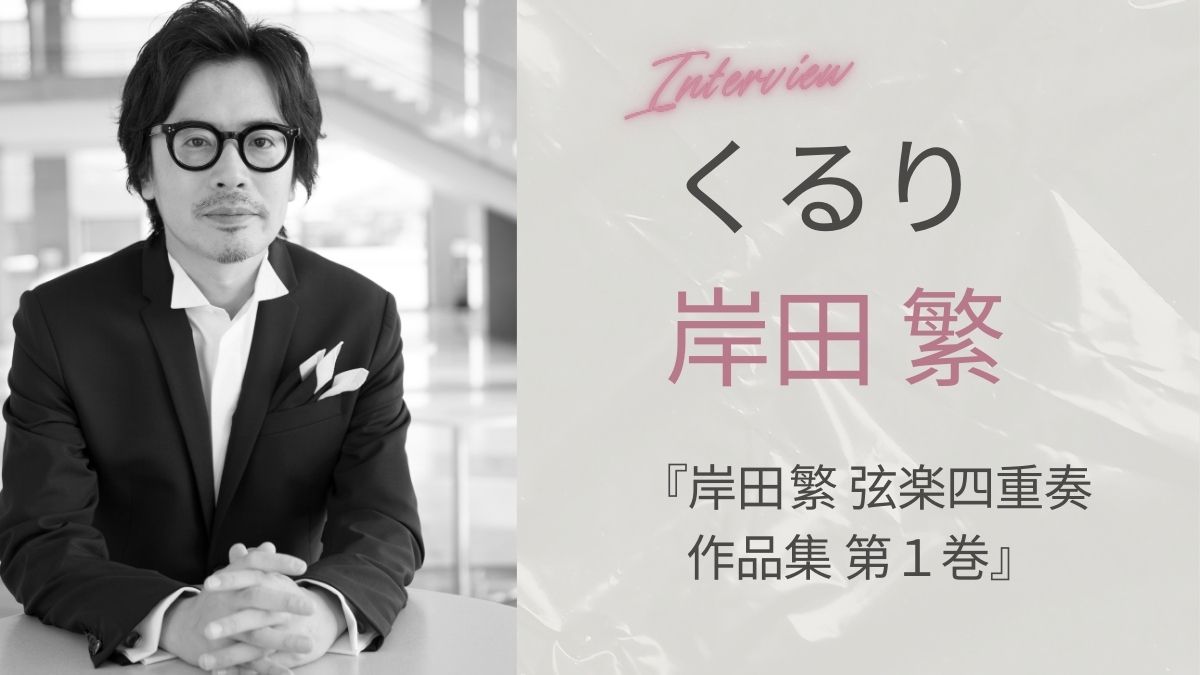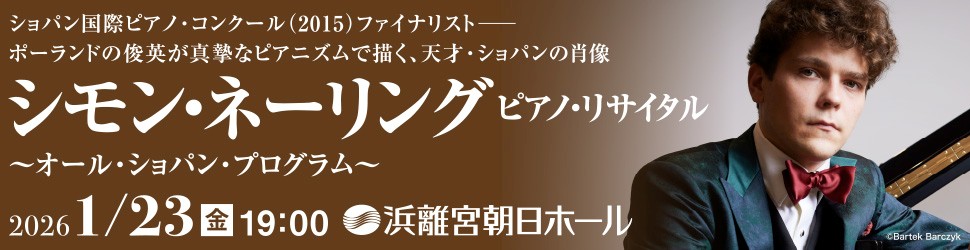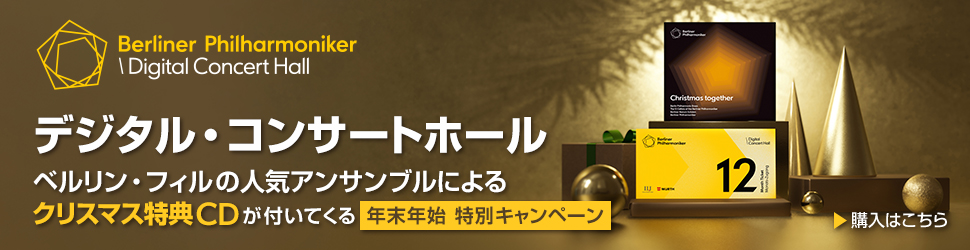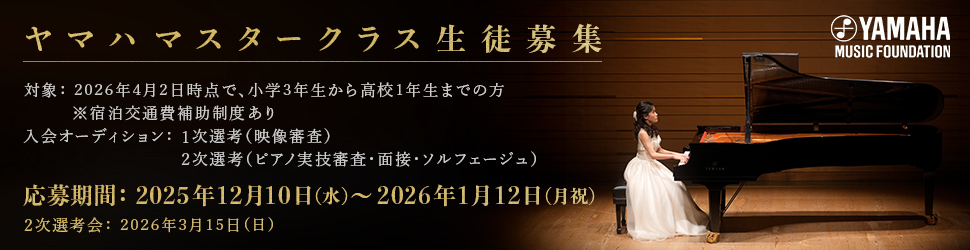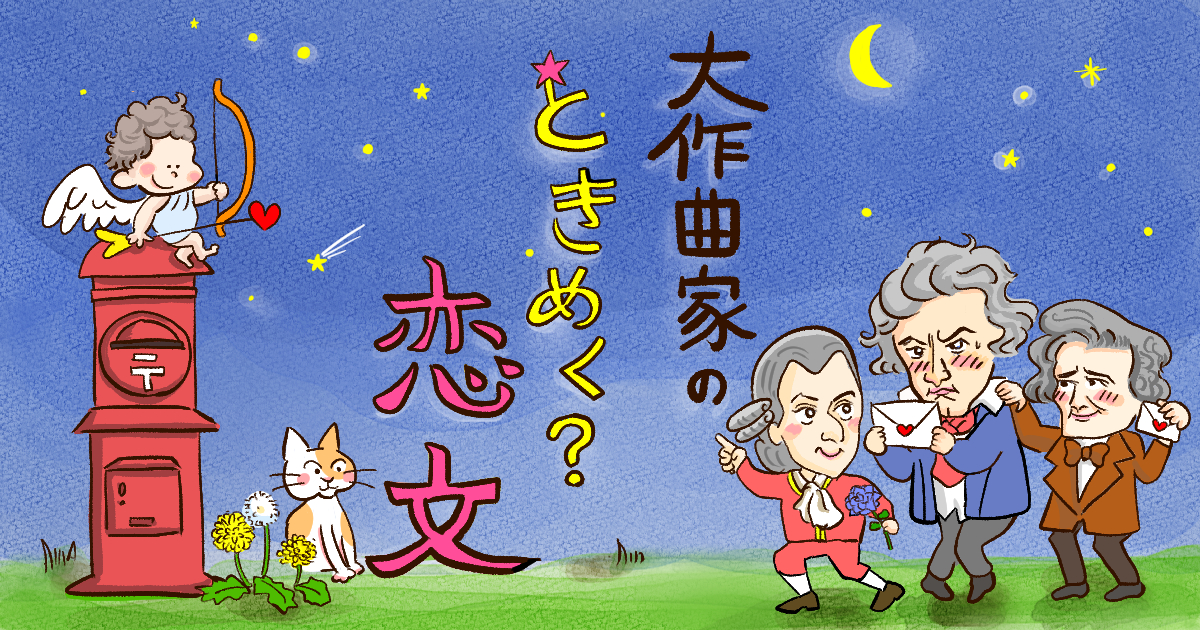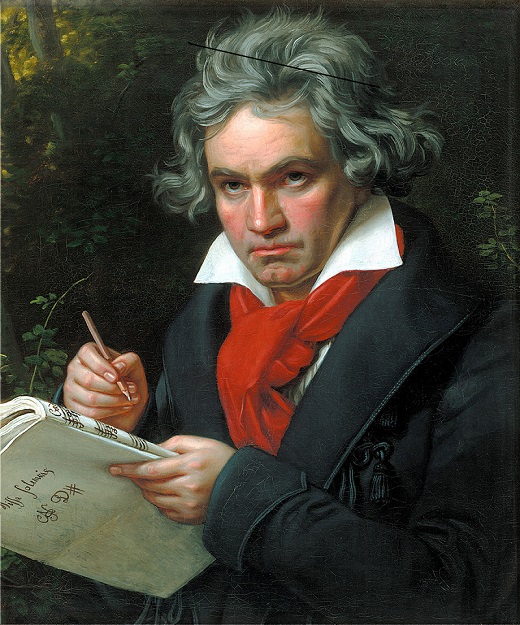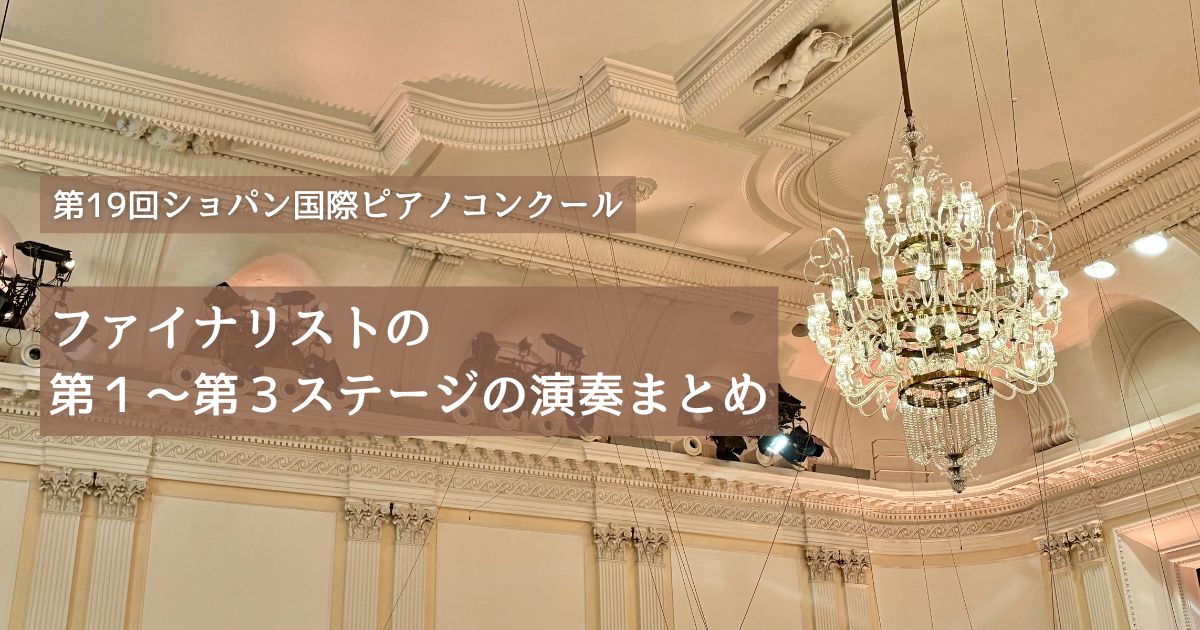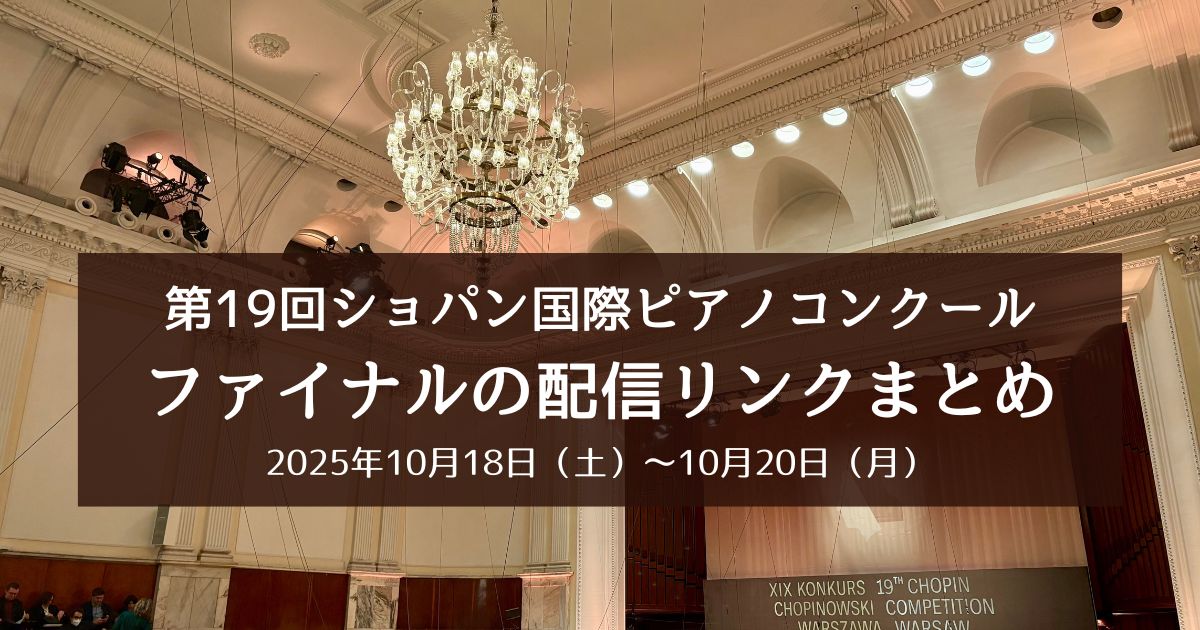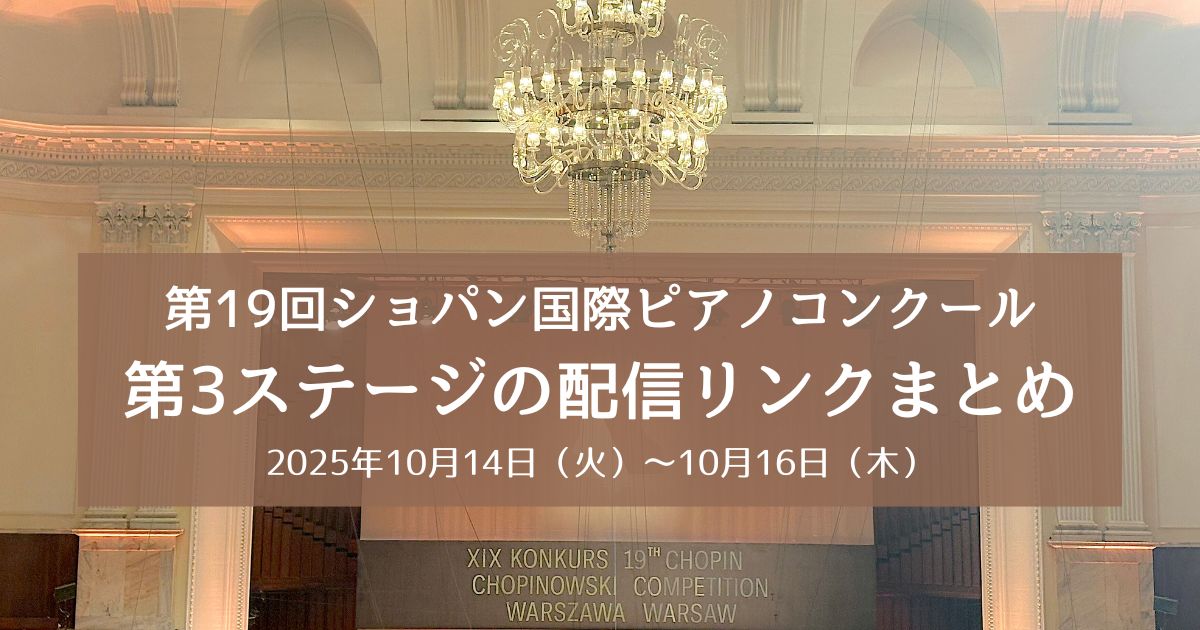ベートーヴェン弦楽四重奏曲を理解する6つのキーワード~芸術と存在をめぐる内なる旅

室内楽の祭典「サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン」(CMG)で毎年、その核となるベートーヴェン弦楽四重奏曲全曲演奏会。今年はドイツ最高峰とも称されるシューマン・クァルテットが8年ぶりに来日して挑みます。
今回注目されるのは、全6日間のコンサートにそれぞれ魅力的なタイトル――「アルファとオメガ(始まりと終わり)」「聖なる歌」「光」「影」「自由」「心より」――が付けられていること。これらはベートーヴェンの音楽を理解する上でのまたとないキーワードともいえます。
そこで、彼らへメール・インタビューを行ない、ベートーヴェンの弦楽四重奏曲を全曲聴くことから見えてくる、作曲家の生涯をかけた芸術と存在への問いを、さらに深堀りして伺いました。

1963年埼玉県生まれ。慶應義塾大学文学部を卒業、音楽之友社で楽譜・書籍・月刊誌「音楽の友」「レコード芸術」の編集を経て独立。オペラ、バレエから現代音楽やクロスオーバ...

「情熱とエネルギー。シューマン・クァルテットの演奏は驚愕としか言いようがない。きらめくような超絶技巧と、常に驚きを追求する姿勢を持ち、現在、無数に存在する弦楽四重奏団の中でも最高峰のひとつである」(南ドイツ新聞)
シューマン・クァルテットは、演奏から確定的な要素を排し、予想もつかない演奏を実現している。「作品が真に育つのは、生演奏のときのみであり、舞台では自然と自身に正直になれます。そうして初めて観客との絆が生まれ、音楽を通したコミュニケーションが可能になるのです」。
世界でも際立った注目を集めているのは、輝かしい受賞歴やCDのリリースのみならず、グループとしてのサウンド、アプローチ、スタイルが、コンサートの生演奏でこそ音楽を表現することができることに意義を見出しているからに他ならない。
マーク、エリック、ケンの3兄弟は幼少期から一緒に演奏しており、そこにヴィオラ奏者のファイト・ヘルテンシュタインが加わり、現在に至る。その開放性と好奇心は、師事したエバーハルト・フェルツやアルバン・ベルク四重奏団のメンバー、あるいはメナヘム・プレスラーのような共演者たちからも影響を受けている。
2007年にドイツのケルンで結成。「シューベルト&現代音楽」国際室内楽コンクールや、ボルドー国際弦楽四重奏コンクールで優勝。以降、ウィーン楽友協会、コンツェルトハウス・ドルトムント、ウィグモアホール、ベルリン・フィルハーモニー、コンセルトヘボウなどのヨーロッパ各地の名門ホールで演奏を重ね、クァルテットとしての国際的キャリアを築いている。18年にリリースされたCD『Intermezzo』は国内外で高い評価を得て、ドイツでもっとも権威のある「オーパス・クラシック賞」を受賞した。
©Harald Hoffmann
弦楽四重奏曲全16曲は、ベートーヴェン自身の芸術や存在をめぐる内なる旅
――第1日のテーマ「Alpha and Omega(アルファとオメガ)-始まりと終わり」(6/11)は、単に第1番と第16番を合わせたというだけでなく、ベートーヴェンという存在そのものについての象徴的な意味を伝えているように思えます。もう少し詳しくご説明いただけますか?
シューマン・クァルテット(以下SQ) ベートーヴェンの最初の弦楽四重奏曲第1番(作品18-1)と、彼が最後に完成させた弦楽四重奏曲第16番(作品135)を組み合わせるというアイデアは、時代的な流れだけでなく、ベートーヴェン自身の芸術や存在をめぐる内なる旅を、象徴しています。
1798年頃に作曲された第1番は、ベートーヴェンがハイドンやモーツァルトの伝統と格闘しながらも、すでに自分の個性を主張し始めている様子を示しています。若々しいエネルギー、優雅さ、そして深い感情があり、とくに第2楽章は『ロミオとジュリエット』の墓の場面に触発されたものです。
対照的に、ベートーヴェンの生涯最後の年に書かれた第16番は、静けさ、機知、そして内省的な明晰さが際立っています。病いと孤独に苦しみながらも、ベートーヴェンは穏やかな受容の光を放つような弦楽四重奏曲を作曲しました。「ようやくついた決心」と記された終楽章で到達した音楽的な問い「そうでなければならないのか?」に対しては、簡潔に答えが示されます――「そうでなければならない!」。
このように、「アルファとオメガ」は、彼の弦楽四重奏曲創作の始まりと終わりだけでなく、ベートーヴェン自身の精神的な軌跡――内面の平和を求める努力――をも象徴しています。それは、音楽という普遍的な言語で表現された、人生、葛藤、そして決意についての深い考察です。
ベートーヴェンの「祈り」は彼自身の経験と密接に結びついている
――第2日の「Holy Song-聖なる歌」(6/12)というテーマはひじょうに魅力的ですね。他の作曲家にとっての祈りと、ベートーヴェンの祈りに違いがあるとしたら、それはどういう点においてだと思われますか?
SQ ベートーヴェンの「祈り」は、それが深く個人的、実存的である点で、多くの他の作曲家の「祈り」とは異なっています。
第15番作品132の緩徐楽章(「聖なる感謝の歌」)のような作品において、ベートーヴェンは単に宗教的なイメージや形式を想起させるだけでなく、音楽を通してそれを「生きて」います。この楽章は深刻な病の後に感謝の賛歌として書かれ、その副題(「病より癒えたる者の神への聖なる感謝の歌」)を見ただけでも、彼自身の経験とどれほど密接に結びついているかが分かります。
バッハやブルックナーのような作曲家は、典礼のような体系化された言葉で信心を表現することが多いのに対し、ベートーヴェンの祈りはより人間的で、より壊れやすく、より切迫感があります。それは苦しみや孤独、目に見える世界の背後に意味を見出そうとすることからきています。
彼の「祈り」は必ずしも平和なものとは限りません。緊張に満ち、問いを投げかけ、探求し続けています。しかし、そこにこそ独自性がある。それは高らかに宣言するものではなく、一つの過程としての精神的な音楽であり、超越へ向かう旅なのです。

関連する記事
-
読みもの《第九》が年末に演奏される理由とは?《第九》トリビアを紹介!
-
読みものベートーヴェン《月光》の献呈相手ジュリエッタのことを友人に綴った手紙
-
読みものベートーヴェンの生涯と主要作品
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest