
若きシュトラウスが《ドン・ファン》に込めた情熱を紐解く
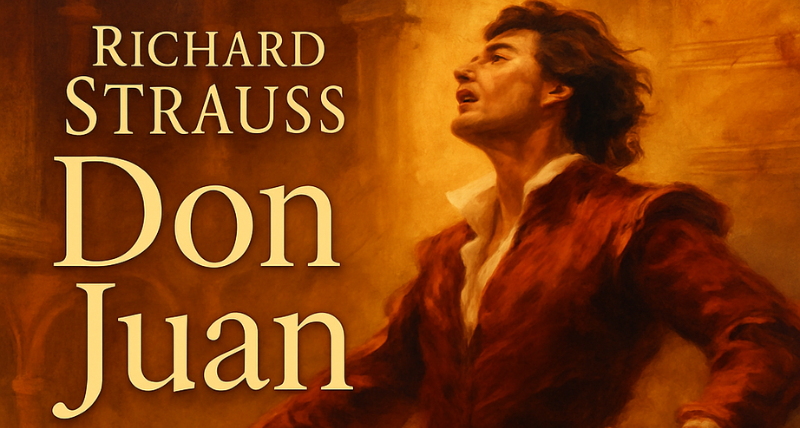
リヒャルト・シュトラウスの出世作《ドン・ファン》。若きシュトラウスは、ニコラウス・レーナウの叙事詩をもとに独自の音楽的ドラマを構築しました。作品全体がどう構築されているのか、シュトラウス自身による設計図をもとに、この交響詩を紐解きます。

青山学院大学教授。日本リヒャルト・シュトラウス協会常務理事・事務局長。iPhone、iPad、MacBookについては、新機種が出るたびに買い換えないと手の震えが止ま...
1885年、ドン・ファンの着想を得る
若き日のリヒャルト・シュトラウス(1864~1949)が《ドン・ファン》の素材にどの段階で巡り会ったかを辿っていくと、いくつかのきっかけが見出せる。
もっとも古いところでは、1885年6月13日、20歳を過ぎたばかりのシュトラウスが、フランクフルト・アム・マインで、指揮者ハンス・フォン・ビューローと、パウル・ハイゼの戯曲《ドン・ファンの最期》を観劇した、という記録がある。

1888年初頭から作曲が進められていたということしか判明しておらず、5月24日の日付が残る最初のスケッチ帳から、イタリア旅行の最中には本格的に手がけられていたと考えられる(このとき、交響的幻想曲《イタリアから》が同時に構想されていたことになる)。ヴェネツィアから次の滞在地パドヴァに向かい、その修道院で《ドン・ファン》の着想を得た、というエピソードが有名だ。
1888年9月30日にミュンヘンで作曲を終わらせたあと、初演まで14ヵ月、この作品はまったく顧みられることがなかった。
リヒャルト・シュトラウス《ドン・ファン》
翌年、ヴァイマールでの初演
本作は、1889年11月11日になってヴァイマールの宮廷劇場のオーケストラにより、ようやく初演された。このときの第2回定期演奏会は、ケルビーニの歌劇《アバンセラージュ族》序曲、ウェーバーの演奏会用序曲《イネス・デ・カストロ》、サン=サーンスの《チェロ協奏曲第1番 イ短調》作品33、シューベルトの歌曲、そしてようやく《ドン・ファン》の初演、締めにベートーヴェンの《交響曲第6番》というプログラムであった。
キャリア初期にあっても、シュトラウスの作品のオーケストレーションの斬新さは際立っており、とりわけ小さなヴァイマールのオーケストラにとって、これだけの曲を練習することは大きな負担であったに違いない。なお、献呈者のルートヴィヒ・トゥイレは、シュトラウスよりも3歳年長のオーストリアの作曲家。若き日のシュトラウスと親交が深かったが、室内楽を中心とする作風はかなり保守的であった。シュトラウスのもっともよき理解者であったが、1907年に心不全で急逝する。

オーストリアの作曲家・教育者。リヒャルト・シュトラウスと同様、一時期は「ミュンヘン楽派」と呼ばれる作曲家群の主要なオペラ作曲家の一人に数えられた。
叙事詩の断片から独自の場面を選び出す
この作品の成立を考える際、問題となるのは、シュトラウスがこの作品の内容を示すものとして掲げたニコラウス・レーナウの叙事詩《ドン・ファン》からの3箇所の引用と、実際に描かれた音楽的内容があまりそぐわないように感じられる点である。シュトラウスが引用した箇所は、具体的な物語を含んではおらず、単にドン・ファンそのひと、そして女性に対しての人生哲学を披瀝した箇所であるに過ぎない。だが、音楽には女性との愛の場面(2箇所)、仮面舞踏会の場面、そして、ドン・ペドロとの決闘で剣を投げ棄て、胸への一突きで死を受け容れる場面(587小節目)が明瞭に描かれている。
以下、レーナウの叙事詩から、シュトラウスが初版の総譜用に選び出した場面を記す。

オーストリアの詩人。法学・医学を学ぶも職業には就かず詩作に専念。母の死や恋愛の挫折で憂鬱を深めるが、祖母の遺産で創作を続ける。自由を求めアメリカ移住を志した。
Den Zauberkreis, den unermesslich weiten,
Von vielfach reizend schönen Weiblichkeiten
Möcht’ ich durchziehn im Strome des Genusses,
Am Mund der Letzten sterben eines Kusses.
O Freund, durch alle Räume möcht’ ich fliegen,
Wo eine Schönheit blüht, hinknien vor jede
Und, wär’s auch nur für Augenblicke, siegen.
はかり知れぬほど広い 魔法の国を
幾重にも魅惑的な 麗しき女性的なるものを
快楽の嵐のなか くぐり抜けよう
最後の女に口づけて 死を迎えよう
おお友よ あらゆる場所を越えて跳ぼう
美が花咲く国で 女の前に跪き
ただひとときなりと 従わせたいもの
Ich fliehe Überdruss und Lustermattung,
Erhalte frisch im Dienste mich des Schönen,
Die einzle kränkend schwärm’ ich für die Gattung.
Der Odem einer Frau, heut Frühlingsduft,
Drückt morgen mich vielleicht wie Kerkerluft.
Wenn wechselnd ich mit meiner Liebe wandle
Im weiten Kreis der schönen Fraun,
Ist meine Lieb’ an jeder eine andre;
Nicht aus Ruinen will ich Tempel bauen.
この身は 飽満と快楽から離れ
心も新たに 麗しきものに仕えながら
それぞれに心痛めつつ 次なる冒険を求めてさすらう
とある女の息吹に 春の息吹を感じても
明日には 重苦しい牢獄のようにこの身を拉(ひさ)ぐ
麗しき女が集う 広きところ
わが愛も 女をもとめて移(うつ)ろう
廃墟から 寺院を建てたいとは思わぬ
Ja! Leidenschaft ist immer nur die neue;
Sie lässt sich nicht von der zu jener bringen,
Sie kann nur sterben hier, dort neu entspringen,
Und kennt sie sich, so weiß sie nichts von Reue.
Wie jede Schönheit einzig in der Welt,
So ist es auch die Lieb’ der sie gefällt.
Hinaus und fort nach immer neuen Siegen,
So lang der Jugend Feuerpulse fliegen!
そう 情熱はつねに新しく
女から女へと 移るものではなく
ここで死に絶え あちらで生まれる
それを知るならば 悔いもまたなし
それぞれの美は この世で唯一無二
その美を有する恋人も またひとり
出でよ 探し 新たに勝ち得よ
若さ 燃え出でる鼓動が 飛立つ限り
Es war ein schöner Sturm, der mich getrieben,
Er hat vertobt und Stille ist geblieben.
Scheintot ist alles Wünschen, alles Hoffen;
Vielleicht ein Blitz aus Höh’n, die ich verachtet,
Hat tödlich meine Liebeskraft getroffen,
Und plötzlich war die Welt mir wüst, umnachtet;
Vielleicht auch nicht; – der Brennstoff ist verzehrt,
Und kalt und dunkel ward es auf dem Herd.”
美しき嵐が この身を駆り立てたが
いまは止んで 鎮けさのみ
願いと希望は すべて死に絶えたか
この身へと落ちた 天の高みからの稲妻が
わが愛の力に 死を与えたのか
突然この世は荒れ果て 闇に閉ざされた
いや そうではない 薪は燃え尽き
かまどは 冷たく暗くなった
シュトラウスの設計図と詩との関係性
シュトラウスが作曲にあたって書いた全体の構想を示す文章を読むと、「勢いよく始まる第1主題がハ長調の属音に始まり、放埒な主題が続く。喜びの歓声が愛の苦しみとため息に中断される。新しい愛のモティーフで最終的に閉じられる」といった類の細かな「設計図」が記されている。
とはいうものの、これも詩の内容とはっきり対応しているわけではない。むしろ、シュトラウスはレーナウの叙事詩から、実際のドン・ファンの死を表す詩句を2行分削っており(我が敵たる死はわが手に委ねられたが/これもまた生と同様に退屈)、音楽で描かれるドラマ的内容を、詩とリンクさせることを敢えて回避したように感じられてならない。ここに、若き日のシュトラウスが、リスト以来の交響詩に対してどのような創作態度を取ろうとしたのか、その本心を垣間見ることができるだろう。
実際、グスタフ・マーラーは、アルトゥール・ザイドル宛ての手紙(1897年2月)において、シュトラウスの音楽的な標題について「その詩はお世辞にも、『(音楽に対して)与えられた課題』とはほど遠い」と書いている。
音楽学者ヴァルター・ヴェルベックは、ドン・ファンのテーマにホ長調(ハ長調)、愛のテーマにロ長調(嬰ハ長調)、エピソード的に差し挟まれるト長調/短調、そしてドン・ファンの死を描くホ短調、という調性上の枠組みを先に作り、その中で音楽形式に従って推進していくシュトラウスの作曲技法が、後からの題材の急な変更にも対応可能なものであった点を指摘している。
《ドン・ファン》においては、先ほどの「設計図」にも「展開部において」などの記述が見られるとおり、シュトラウス自身がソナタ形式を念頭において作曲を進めていたことが窺える。一方で、冒頭のホ長調による、吹き上がるようなドン・ファンそのひとの主題(ホ長調、9小節目以降)は、ソナタ形式における第1主題ととらえるならば、全体の構成は以下のように考えることが可能だろう。
提示部
| 1~42小節 | 序奏、第1主題 | ホ長調 | ドン・ファン |
| 43~89小節 | 経過句 | 第1の女性の登場と誘惑 | |
| 90~168小節 | 第2主題 | ロ長調 | 女性との情事 |
展開部
| 169~196小節 | 第1主題の再登場 | ハ長調 | |
| 197~231小節 | 経過句 | ト短調 | 第2の女性の登場と誘惑 |
| 232~313小節 | 経過句 | ト長調 | 女性との情事 |
| 314~350小節 | 第3主題 | ハ長調 | ドン・ファンの新たなる冒険 |
| 351~421小節 | 経過句 | (386~)嬰ハ短調 | 仮面舞踏会 |
| 422~473小節 | 再現部への経過句 | 戦い |
再現部
| 474~585小節 | 第1主題(ホ長調)、第3主題 (ホ長調) | 戦い |
終結部(コーダ)
| 586~606小節 | ホ短調 | 剣の一突き、ドン・ファンの死 |
調性の面から考えるならば、この作品はかなりの程度までソナタ形式の約束事に従っている。3オクターブを軽々と、たった3小節で登りつめる序奏の主題に続き、ドン・ファンの主題たる第1主題は、シュトラウスが後々に至るまで官能の愛を描く際に用いたホ長調。これに対して、第2主題となる第1の女性との情事を描く90小節目以降はホ長調から見て属調のロ長調となる。興味深いのは、149小節以降がホ短調(ドン・ファンの調性・ホ長調の同主調)に移行し、結末のドン・ファンの悲劇が先取りされるところだろう。これを打ち消すように快活な第1主題が回帰し、展開部へと移行する。
展開部でドン・ファン像が深化
この作品をソナタ形式として捉える際にもっとも問題となるのは、展開部の構成をどのように考えるかであろう。
同じホ長調で第1主題が登場する再現部を474小節目からと考えるならば、実に全曲の半分程度が展開部に費やされることになる。169小節目からの第1主題がハ長調となっているのは、曲の冒頭が一瞬だけハ長調の主和音(第2転回形)のような響きを感じさせることと無縁ではあるまい。勝利や正義を司ってきたハ長調は、ドン・ファンという人物の自信の強さをも描く役割を果たしているとも言える。
新しい女性との出逢いと情事は、同主調たるト短調、そしてト長調が並置されることによって表現される。なお、236小節以降のオーボエの印象的な旋律は、この後《英雄の生涯》の回想シーンでも主要主題として用いられた。
リヒャルト・シュトラウス《英雄の生涯》終曲
音楽学者ノーマン・デル・マールも主張するとおり、若きシュトラウスの本当の創意は、このエピソードの後に、ドン・ファンの英雄性を表現するため、314小節からホルンによる勇壮な新主題を用意したことだろう。351小節からは、いわゆる「仮面舞踏会」の場として親しまれ、グロッケンシュピールによるドン・ファンの主題(357~361小節)などが有名なところ。
最後の戦いでの再登場した姿とは
ドン・ファンにとっての最後の戦いは、実質的には386小節の主題から始まっていると考えられる。これが官能の愛、ドン・ファンその人を示すホ長調の平行調である嬰ハ短調から始まっているのも示唆的である。438小節でイングリッシュ・ホルン&ファゴットが演奏する第2主題(ただしニ短調)が、悲恋に終わった過去の女性の回想なのだろう。
457小節以降、すなわち再現部に至る前には、延々とホ長調へ至るための属七和音が用いられ続け、いやがおうにもその再登場への期待を駆り立てる。そして、474小節で第1主題が(かなり短縮された形ではあるが)登場し、再現部となる。
第2主題の代わりに用いられているとおぼしき、ホルンとチェロによる第3主題が、第1主題と同じホ長調で再び高らかに登場することで(510小節以降)、変則的なソナタ形式の形を保ちつつ、曲を最後の高揚へと導いていく。
全休止の後に続く終結部(コーダ)において、ホ長調の調号こそ維持されるものの、586小節で鳴り響くのはホ短調の下属和音(IV)。この和音に含まれないFの音が鋭く、だが弱々しく、トランペットで奏され(587小節)、前述の通り、ドン・ペドロの前にドン・ファンがその身を投げ出し、剣を受けたことが示される。調号はホ長調のまま、音楽は第3音が低く取られ、ホ短調で静かに終わっていく。ほとんどこの部分だけが唯一、前掲のレーナウの詩の最後の2行と、音楽的に対応する場所ということになるだろう。
この作品では、ドン・ファンの主題が登場する箇所をリトルネッロ(反復)ととらえれば、各エピソードを間に挟むロンド形式と解釈することも可能である。ソナタ形式を第1主題と第2主題の闘争、そしてその止揚、ととらえる解釈に従うならば、シュトラウスは再現部において第1主題と第3主題(すなわち同一人物)を中心的に取り上げることでその止揚を敢えて回避しているとも考えられる。女性によって男性が高められることなく、悲劇的な結末を迎える、という筋書きに従うならば、本質的にリトルネッロ主題(ドン・ファン)が変化しないロンド形式ととらえるほうが、よりシュトラウスの意図には近いのかもしれない。
その意味では、次作《死と浄化》のほうが、ベートーヴェン的な意味でのソナタ形式をよりはっきりと踏襲しており、シュトラウスが交響詩においてどのような作品を生みだそうとしたのか、その目指した方向性が窺える。
リヒャルト・シュトラウス《死と浄化》
関連する記事
-
インタビュー東京都交響楽団ヴァイオリン奏者・塩田脩さん「都響と石田組の両方で成長できる」
-
読みものラヴェル《ボレロ》の「新」名盤3選〜楽譜や楽器のこだわり、ラヴェルの故郷のオーケ...
-
連載【音楽が「起る」生活】読響とN響の演奏会形式オペラ、シフの親密な室内楽、他
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest















