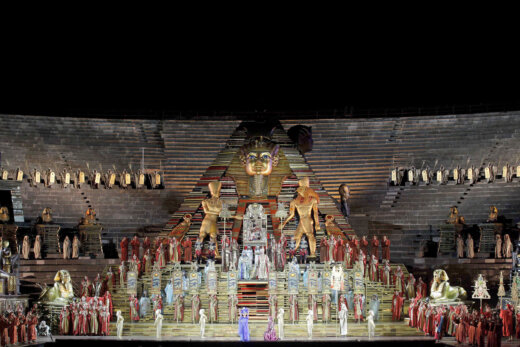ヴィオラの「声」は楽器や時代を超えて―続々と現れる新世代のヴィオラ奏者たち

音楽評論家の鈴木淳史さんが、クラシック音楽との気ままなつきあいかたをご提案。膨大な音源の中から何を聴いたら分からない、という方へ。まずは五感をひらいて、音のうつろいにゆったりと身を委ねてみませんか?
サッカーでいえば花の中盤
現在使われている年号が決まる前夜、こんな妄想が突然襲ってきた。
官房長官が記者を前に厳かに口を開く。「新しい元号は……ヴィオラであります」。掲げられた額には、カタカナで太々と「ヴィオラ」と書かれている。会場はどよめいた。そもそも元号は漢字二文字ではなかったのか。
確かに、これから天皇に就く方がヴィオラを愛奏していることはよく知られていたが、採用の理由はそれだけではなかった。ヴィオラという楽器の魅力にふさわしい世の中を作る。あるいは、世界をオーケストラに見立て、この楽器に与えられた役割を日本という国が担う。そうした理想が現れた元号だという。
ヴァイオリンとチェロという花形楽器のあいだの音域を往還するヴィオラ。どちらかといえば地味な存在。オーケストラでも、パンデミックが明けてもマスク着用率が全パートでいちばん高かった、といえばなんとなくイメージがつかめるか。
ヴィオラ・ジョークというものまであった(ヴァイオリンを盗まれたくなければ、ヴィオラのケースに入れておけば安心、といったように、つねにネタにされがちな存在なのだ)。
とはいえ、弦楽アンサンブルでは、文字通り中心を担う存在だ。サッカーでいえば花の中盤。オーケストラの善し悪しを判断するには、第2ヴァイオリンとヴィオラに注目すればいいといわれるほど。ヴィオラ・パートを基準に組み立てることで立体感のある響きを作り出す指揮者も多い。
もっとも人間の声に近い音域をもつ。朗々と歌わせることもできれば、エッジを立てた響きで打点を強調したり、金管のようにふくらむような響きも作り出せる。
渋いとか、地味な存在と思われがちだが、アンサンブルの要となり、さまざまなな響きを可能にする楽器。これを元号に決めちゃうなんて、なんてすばらしいアイディアなのだろう。これで日本は安泰だ。などと、我が妄想のなかの優秀な有識者たちには惜しみない賛辞を与えたくなってしまうのである。
歌うのにもっともふさわしい楽器
ヴィオラといえば、ユーリ・バシュメット、キム・カシュカシャン、今井信子、タベア・ツィンマーマンなどといった名ソリストも多い。さらに、その世代を継ぐ奏者も次々と登場し、この楽器の常識を覆すような、みずみずしい演奏を聴かせてくれる。
その筆頭にあげられるのが、アントワン・タメスティ。タベア・ツィンマーマンに師事したフランスのヴィオラ奏者だ。その特徴は、ヴィオラならではの中音域での美しい響きを生かしたニュアンスの豊かさ。
『ベル・カント~ヴィオラの声』というアルバムは、ヴィオラが歌うのにもっともふさわしい楽器であるということを証明してくれる。とりわけ神業のようなメッザ・ヴォーチェ(声量を落とし、柔らかい声で歌う)。さらに、オペラ・アリアの声楽パートをヴィオラで演奏したときの高域への繊細なアクセス。
ヴュータン:ヴィオラとピアノ伴奏のための「エレジー」へ短調
ベッリーニ:歌劇《ノルマ》よりアリア「清らかな女神よ」
ヴィオラ奏者にとっても重要なバッハ「無伴奏チェロ組曲」
バッハの「無伴奏チェロ組曲」は、ヴィオラ奏者にとっても重要なレパートリーだ。弦配列が一緒だから調性を変更することもない。ただ、チェロのような深々とした響きではなく、軽やかながら、どこか痩せ細った印象を与えてしまうという定説もなきにしもあらず。
しかし、タメスティの演奏からは、そんなデメリットはまったく感じない。繊細かつ楚々としたフレージングから生み出される響きの広さ、深さに、ひたすら耽溺してしまう。
J.S.バッハ:「無伴奏チェロ組曲」第1番よりサラバンド
J.S.バッハ:「無伴奏チェロ組曲」第3番よりアルマンド
ドイツのニルス・メンケマイヤーも、タメスティと同世代のヴィオラ奏者。彼も同じバッハ作品を弾いている。聴き比べてみよう。
J.S.バッハ:「無伴奏チェロ組曲」第1番よりサラバンド
J.S.バッハ:「無伴奏チェロ組曲」第3番よりアルマンド
タメスティとは異なり、バロック弓やガット弦を用い、ピリオド奏法を意識した演奏だ。とはいえ、滑らかなフレージングに、重音のサラリとした質感。泉に水が湧き出るような自若さで音楽は紡がれていく。
タメスティのバッハ演奏には、「これだけ麗しいバッハを弾くには、ヴィオラというすばらしい楽器こそがふさわしいのだ」という主張が見え隠れする。一方、メンケマイヤーの演奏はヴィオラという楽器の存在さえ感じさせない。聴き手とバッハを直接結んでしまうかのような、自然な流れがある。
その一方、太々とした筆致のなかに、色気さえ感じさせる歌い回しのヴィヴァルディの協奏曲もいい。
ヴィヴァルディ:ファゴット協奏曲 ト短調 RV.495より第1楽章(ヴィオラ編曲)
バロックから現代までレパートリーが広いのが、新しい世代のヴィオラ奏者の特徴でもある。では、すっぽりとロマン派、ブラームスのソナタはどうかというと、これもびっくりするほどに、ブラームスそのもの。諦念が支配するような澄み切った響きのなかに、ロマン派ならではの甘い音色をそっと添わせるのだ。
ブラームス:クラリネット・ソナタ第2番より第1楽章(ヴィオラ編曲)
名曲をヴィオラ版で味わう
ロンドン生まれのティモシー・リダウトは、さらに若い世代。彼の持ち味は、その究極といっていいほどの繊細な音色と、むんむんと豊かな歌謡性だ。
エルガーの「チェロ協奏曲」のヴィオラ版にも挑戦している。原曲の存在を忘れて没頭してしまうほどの完成度だ。
エルガー:チェロ協奏曲より第1楽章(ターティスによるヴィオラ編曲)
最新盤『ライオネル・ターティスに捧ぐ』では、その表現にさらに磨きがかかった。絹の手触りを思わせるような歌わせ方、甘やかなポルタメントがあったと思えば、力強い低音も響かせる。
シューマン:ロマンス 嬰ヘ長調(ターティスによるヴィオラ編曲)
フォーレ:エレジー ハ短調(ターティスによるヴィオラ編曲)
エリック・コーツ:ファースト・ミーティング(ジョン・ウィルソン再構築版)
このようなすばらしいヴィオラ演奏を聴きながら、昭和、平成から続く、激動のヴィオラ時代を生き抜いていきたいと思う(まだ完全には妄想から覚めきっていないようだ)。





関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest