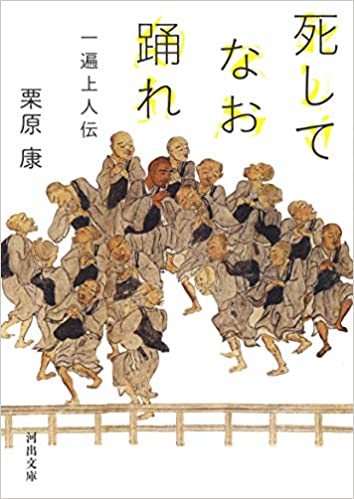著者が裸になったとき、文体が熱狂的に踊りだす──栗原康著『死してなお踊れ 一遍上人伝』

かげはら史帆さんが「非音楽小説」を「音楽」から読み解く連載、第6回は鎌倉時代中期の僧侶、一遍の評伝をとりあげます。踊り念仏を広めた一遍の生涯を描き出すために、著者の政治学者、栗原康は冒頭で衝撃の告白。そして、著者も文体も、裸になって踊りだす!?

東京郊外生まれ。著書『ニジンスキーは銀橋で踊らない』(河出書房新社)、『ベートーヴェンの愛弟子 – フェルディナント・リースの数奇なる運命』(春秋社)、『ベートーヴェ...
もっとたかく、もっとおおきく、もっとおおきく。さけんでうたって、おどってはねろ。
栗原康著『死してなお踊れ 一遍上人伝』河出書房新社
まるでモーリス・ベジャール、と思いきや
『死してなお踊れ』
往年のバレエ漫画のような書名だ。コンテンポラリーバレエの巨匠モーリス・ベジャールの振付作品に添えたら、きっとぴったりだろう。しかし、この本は評伝であり、主人公は職業ダンサーでも振付家でもない。鎌倉時代中期の僧侶、一遍である。
その評伝は、目を剥く一文からはじまる。
わたしはセックスが好きだ。
著者は、アナキズムを専門とする政治学者の栗原康氏である。彼が書くテキストの特性をすでに知っている人にとっては、「いつもの栗原節」だ。しかし知らない人は仰天するだろう。
いきなりセックスの話から始まるのも驚くが、それより何より、主語が「わたし」なのだ。著者の自己告白で幕を開ける評伝。出落ちといえば出落ちである。いったい、何事!?
フオオオオオオッ、エクスタシー、エクスタシー!!
一遍。時宗の開祖であり、踊り念仏を世に広めた人物。
歴史の授業で、そんな風に暗記した記憶が残っている人も多いにちがいない。「踊り念仏」という言葉にそこはかとないおかしみを感じながらも、それが一体どのようなものであるか、また一遍とはどんな人物であったのかを調べるに至った人は少ないだろう。
本書は、そんな一遍の生涯を揺りかごから墓場まで描いた評伝である。
冒頭の一文も面食らうが、読み進めるにつれ驚かされるのは、文体が醸すリズムのパワーだ。
音楽を聴いているうちに、メロディやビートが頭に残って離れなくなる現象は、誰しも経験したことがあるだろう。栗原氏の文章はそれと同じ力をもっている。政治思想を扱った本においては、その文体はあたかもシュプレヒコールのごとき効果を発揮し、読み手の社会意識にゆさぶりをかける。本書において、読み手がゆさぶられるのは「身体」だ。
はねて、はねて、ピョンピョンはねて、それでもこの地上に、現世におちてきてしまうこの身体。でもいくらおちても、そこにはかならずスッカラカンになった感覚がのこっている。いくぜ極楽、なんどでも。

これが「はじめに」の章の終盤に登場する「踊り念仏」の解説である。なんというリズム。なんという躍動感。ペンはそのまま一気に第1章へとなだれこんでいく。一遍の生涯のはじまりだ。少年期から青年期にかけて、師の聖達のもとで浄土教の修行を積んだ彼は、父の死を機にいったんは故郷に帰って還俗し、結婚する。子どももできて、順調な結婚生活だ。しかし文体はすでにうずうずしている。手が、足が、リズムを刻みたくてたまらない。
わが身がだいじ、わが子がだいじ、わが家がだいじ。それをまもるためだったら、なんだってやってやる、やらなきゃいけないんだとおもいこまされる。もがけど、もがけどあらがえない。おもたい、だるい、いきぐるしい。
一遍はふたたび修行に出る。妻を連れ歩くことによって、彼は、仏教の世界におけるマイノリティ差別をはじめて実感し、貧民やハンセン病の患者たちも時衆(時宗の構成員)に加えるようになる。この経験が、念仏を唱えればどのような者も阿弥陀仏の慈悲の力につつまれるという思想に彼を導いていく。
あの美声はオレの声。あの風の音もオレの声。ああ、念仏ってこんなにきもちいいものなのか。もっといけるんじゃないか。もっとはやく、もっとたかく、もっとおおきく、何分でも、何時間でも、何日でも。
その思想が、やがて法悦の極致たる「踊り」に行き着く。平安時代に空也上人によって始められ、一遍によって世に広められた踊り念仏は、鉦(かね)や太鼓、鉢などをリズミカルに打ち鳴らして、人びとをダンスに導いた。あたかもライブツアーのように、一遍は全国津々浦々を遊行してまわり、庶民たちを熱狂の渦に巻き込んでいく。歌い、楽器を奏で、踊りまくることによって達するエクスタシー。「ボレロ」さながらの狂乱がそこにある。
もっとはやく、もっとたかく、もっとおおきく。さけんでうたって、おどってはねろ。そうやって、一遍が時衆をあおりまくっていると、念仏房ともうひとりのお坊さんも、お椀と棒きれをとってきて、輪のまんなかにはいり、ホラッホラッと、そいつをガンガンとたたきはじめた。もっとはげしく、もっと乱雑に。もっとくるしめ、もっとくるしめ、死ね、死ね、死ね。フオオオオオオッ、エクスタシー、エクスタシー!!
モーリス・ベジャール振付《ボレロ》
ダンスの対価としての自己告白
さて、政治学者である栗原康氏は、なぜあえて一遍を評伝の主人公に選んだのか? リズミカルな文体と踊り念仏の悪魔の合体はなぜ起きたのか?
栗原氏は「おわりに」の章ですべてを明らかにしている。きっかけは20代の頃、友人たちと京都観光に出かけ、たまたま六波羅蜜寺で空也上人像を見たからだという。栗原氏は失恋したばかりで、友人のひとりは仕事で悩んでいる最中だった。そんな傷心の彼らに、この像はなぜか不思議と訴えかける力をもっていた。「ああ終わった、死んだ、もうダメだ。ひとはいつだって、そういっていいんだとおもわせてもらえた」。

そして彼のペンは失恋の回想へと移っていくのだが、その3歳年上の女性との恋愛劇が、これが本編でもいいのでは、と思ってしまうくらいに読み応え(?)がある。もし純文学作家なら、この個人体験のほうをメインテーマにするだろうし、逆に一般的な研究者であればこの個人体験を注意深く取り除こうとするだろう。しかし彼はちがう。自分の体内にある創作動機のマグマを、一遍の生涯を語ると同時に全部ぶちまけてしまう。そうでなければ、一遍と一緒にダンスする資格はない、一緒に極楽へ行けない、といわんばかりに。
「わたしはセックスが好きだ」と告白し、自らの失恋を暴露し、裸になったときにはじめて、文体のリズムが本物になる。一遍を敬愛する時衆のひとりになって、鉢を鳴らし、念仏をうたい、踊り狂うことができる。それは、ひとが誰かの人生について書いたり、あるいは誰かの作品を歌ったり演奏したり踊るときに、本来ならば出し惜しみしてはならない対価なのかもしれない。

関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest