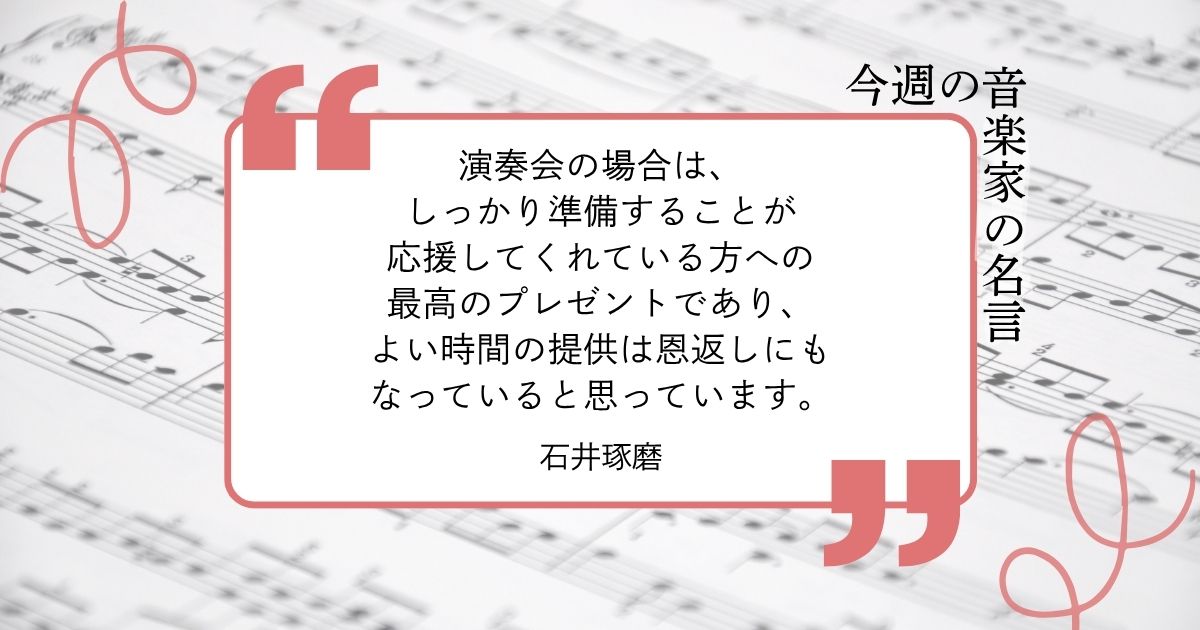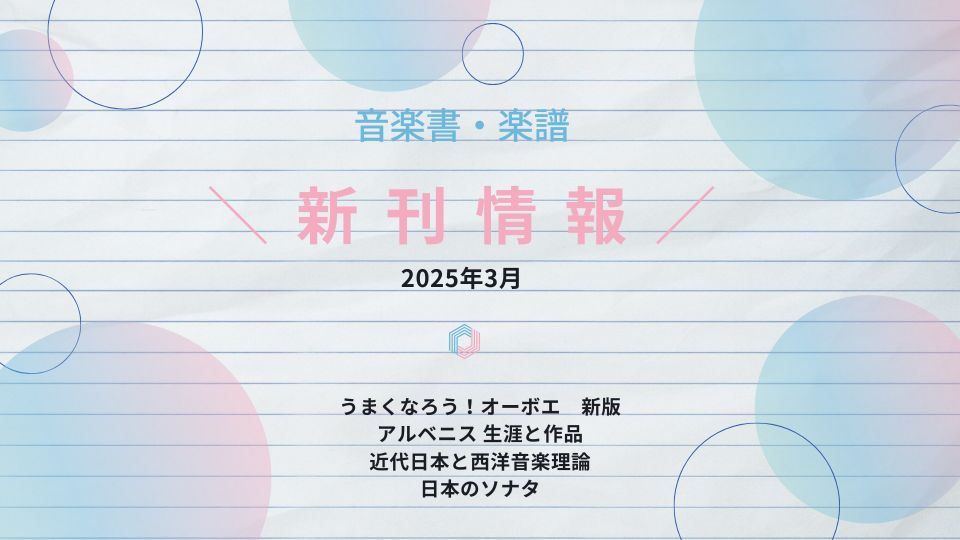失われた“知らない音楽”を求めて──深緑野分『カミサマはそういない』

かげはら史帆さんが「非音楽小説」を音楽の観点から読む連載。第18回は深緑野分(ふかみどり・のわき)の短編集『カミサマはそういない』の中に収められた「新しい音楽、海賊ラジオ」を取り上げます。
水没によって文明が一度終わり、少ない陸地に残った「陸民」たちは、配信される音楽までコントロールされている時代。「“僕らのために用意されたんじゃない音楽”が聴きたい」と願い、旅に出る少年が伝えるものとは?

東京郊外生まれ。著書『ニジンスキーは銀橋で踊らない』(河出書房新社)、『ベートーヴェンの愛弟子 – フェルディナント・リースの数奇なる運命』(春秋社)、『ベートーヴェ...
僕はただ、知らない音楽が聴きたい。“僕らのために用意されたんじゃない音楽”が聴きたいんだ
──深緑野分『カミサマはそういない』河出書房新社、2021年
音楽を選ぶために割くリソースなんて、ない。
サブスクリプションの音楽サービスが普及しつつある今日、私たちはもはや音楽に飢えることはなくなった。どちらかといえば、持て余しているというほうが実態に近い。
1億曲近い選択肢をもつアプリは、容量でいえばわずか200MBほどだが、なんでも選んで聴けるという自由は、疲れきった金曜日の朝には重くてかったるい。音楽の役目は満員電車の苦痛を緩和すること、仕事や勉強の時間にほんの少し潤いを与えること、安眠をサポートすることであって、生活の主体ではなく補助的な存在にすぎない。選ぶためにリソースをわざわざ割くなんてやっていられない。
結局いつも同じプレイリストの再生ボタンを押している、という人も少なくないだろう。たとえば「波の音でリラックス」とでもいうような。そうしたプレイリストは適度にキャッチーで適度に単調で、不快にさせず飽きさせず、リスナーをあの手この手で引き止める選曲の工夫がなされている。リスナーが再生をやめれば、会員をやめれば、サービスの収益が痩せ細る。長く聴き続けさせるのはサービス運営者の最大の責務だ。
しかし、こうしたプレイリストを聴き続けているとどうなるか。アプリのトップ画面も、「あなたにおすすめ」と自動で表示されるトラックも、みな似たようなテイストの曲で埋まっていく。運営者は再生が多い曲のプライオリティをますます上げ、その動向を見たアーティストは再生されやすい曲を作るようになる。つまり、リスナーの選択肢はますます狭まっていく。多くのリスナーはそれに気づかないか、気づいたとしても、余計なものが排除された環境を心地よく感じる。それが一概に悪いともいいきれない。文化はいつも、そうした淘汰を繰り返し、社会の波を泳いでいくのだから。
けれど、狭く小さくなっていく世界を“無為”のうちに受容し続けたら。
自分の知らない音楽、新しい音楽は、波のなかに呑まれて消えてしまう。
「ほぼ完璧にウケる音楽」しか作られなくなった世界の物語
深緑野分の「新しい音楽、海賊ラジオ」は、短編集『カミサマはそういない』に収められた1編である。
都内の築50年の民家。海辺の街の端にある古びた遊園地。見張り塔を備えた戦時下の防衛地区。現代日本からSFやファンタジーの世界まで、さまざまな場所を舞台に、若い男性たちの葛藤や恐怖や冒険を描いた全7編の最後をしめくくるのが、この短編である。
物語の舞台は、陸がほとんど海に水没してしまったあとの世界だ。
沈んでしまった原因が天災なのか、人為によるのかは、はっきりしない。わかるのは、この世界にも、かつてはわれわれの現代社会と同じような“文明”があったが、50年前の“災厄”によってそれが失われたということだけだ。 その“災厄”は一瞬で陸を飲み込んだわけではなく、半世紀が経ったいまも、少しずつ水没は続いている。主人公の16歳の少年ムイ(名前の由来は“無為”だろうか)は、小さな頃に砂浜で城を作って遊んだ記憶をもっていた。しかしその思い出の砂浜も、4年前に水没してしまった。
水没したあとの世界は、「陸府」が支配している。一見すると彼らの統治はうまくいっており、経済活動も平和もテクノロジーもある程度は保たれているようだ。ムイは学校に通い、最新OSのデジタル・デバイスを持ち、「アカザカナ」をはじめとする仲の良い友だちとつるんでいる。企業が運営する音楽配信サービスもあって、ムイはいつも無線イヤホンで音楽に耳を傾けている。
しかしムイは、自分が音楽を本当に好きなのかわからずにいる。
僕はたぶん、かなり音楽が好きだ。“たぶん”と確証が持てないのは、本当に好きな音楽に出会える確率が低いせい。
たしかに音楽配信サービスはある。けれど、新曲は月に5曲、年間60曲しか配信されない。どの曲も、音楽会社の厳しいオーディションを通過しており、質が高く、「顧客である僕ら陸民たちの好みや聴きたい音楽をリサーチして分析、流行を先取りするから、ほぼ完璧にウケる」曲ばかりだ。
おそらくは世界人口も大幅に減少している、つまりサービスの会員も少ないであろう世界。もはや企業ですら音楽制作に充分なリソースを割ける状況ではなくなってしまったこの世界では、新曲を絞ることで収益をコントロールしているのかもしれない。
当然ながら、ムイは新曲の数が少ない状況を不満に感じている。「ツボにはまる曲を探すより僕のツボを音楽に無理やり合わせることの方が多い」——けれど、一方でこうも思っている。「人間の歌がなくなろうと、海の子守歌さえあればいいって思ってしまいそうになる」——
四方八方を海に囲まれた陸の世界は、どこにいても潮騒が聴こえる。陸民たちは、波の音は人をリラックスさせる効果があると学校や陸府ラジオで教えられている。波の音にストレスを感じる少数の陸民を除き、大半の陸民はその効果を信じ、窓を開け放って波の音を聴き続ける。その結果、ますます新しい音楽は不要になっていき、海鳴りが苦手な少数者は、頭痛や精神的な症状に苦しめられる。
むろん、本作は現代の音楽受容の風刺を目的とした短編ではない。
しかし、音楽を好きと言いきれない16歳の少年は、50年の歳月をかけて失われていく陸は、波に思考力を奪われる陸民たちは、貧していく音楽は、現代の、いまのところまだ“たぶん”を付けずに音楽が好きな人びとにとって、一寸先にある危機以外の何ものでもない。音楽だけに限らない。人口の減少。産業の衰退。多様性の喪失。それらは現代のあらゆる文化が抱える問題に通じている。
そんな状況下で、ムイは、ある海賊ラジオがインディーズの新曲をひそかに流しているという噂を聞きつける。彼は友人の大伯父の倉庫からラジオを入手し、友人のアカザカナを誘って、海賊電波を拾うための旅に出ようとする。ムイの提案に驚き、からかうように笑ってやり過ごそうとするアカザカナを、彼はこんな言葉で説得する。
僕はただ、知らない音楽が聴きたい。“僕らのために用意されたんじゃない音楽”が聴きたいんだ
新曲はカミサマを越えるために
内にこもっているだけだと本当は見えるはずのものも見えなくなってしまう。男同士の友情というものを否定するのではなくて、「一緒に外に出ていこう」という方向に向かっていければいいなと思っています。
──「恐ろしさ」の背後を見つめる――深緑野分さん『カミサマはそういない』刊行記念インタビューより
著者の深緑野分氏は、本作「新しい音楽、海賊ラジオ」について、そう語っている。(「恐ろしさ」の背後を見つめる――深緑野分さん『カミサマはそういない』刊行記念インタビュー)
民家でルームシェアをする若い男たち3人の、陰湿な感情のぶつかり合いを描いた第1作「伊藤が消えた」とは対照的な、さわやかな希望が、この最後の第7作にはある。短編集のタイトル『カミサマはそういない』の「カミサマ」は、「神様」の意にとどまらず、「お上」と呼ばれるものへの疑念をも内包しているという。「お上」とは、陸府であり、音楽配信サービスの運営者であり、大人たちであり、マジョリティであり、少年たちにやんわりと諦めを促してくる世界そのものであろう。
ムイが楽器の演奏者や歌い手ではなく、あくまでもリスナーだというのは、本作の面白い点のひとつだ。彼は学校の音楽部には興味がない。あくまでも彼は受容者としての音楽ファンであり、彼の葛藤はリスナーの自意識とプライドに根ざしているのだ。
海賊ラジオが実在したとしても、そこで流れている音楽がムイの好みに合うかどうかはわからない。しかし、彼が求めているのは“僕らのために用意されたんじゃない”という特性そのものだろう。むしろ見つかる音楽は、彼にとって異物であればあるほど望ましい。合わないかもしれない音楽をディグる(掘る)という欲望を胸に、ムイは縮小していく世界を広げようと前へ進んでゆく。カミサマからも、公式プレイリストからも、AIのアルゴリズムからも、それまでの自分自身からも遠く離れた音楽を求めて。





ランキング
- Daily
- Monthly
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest