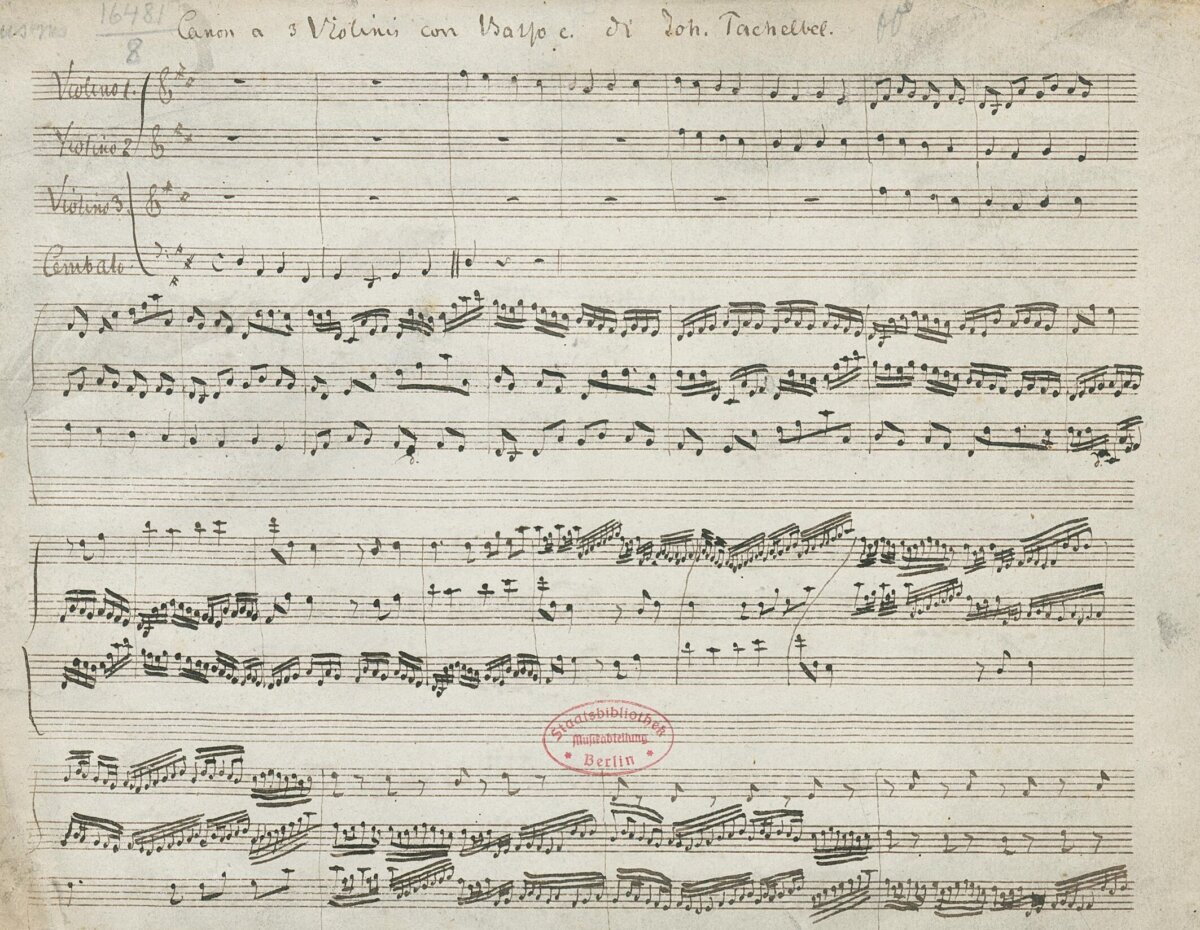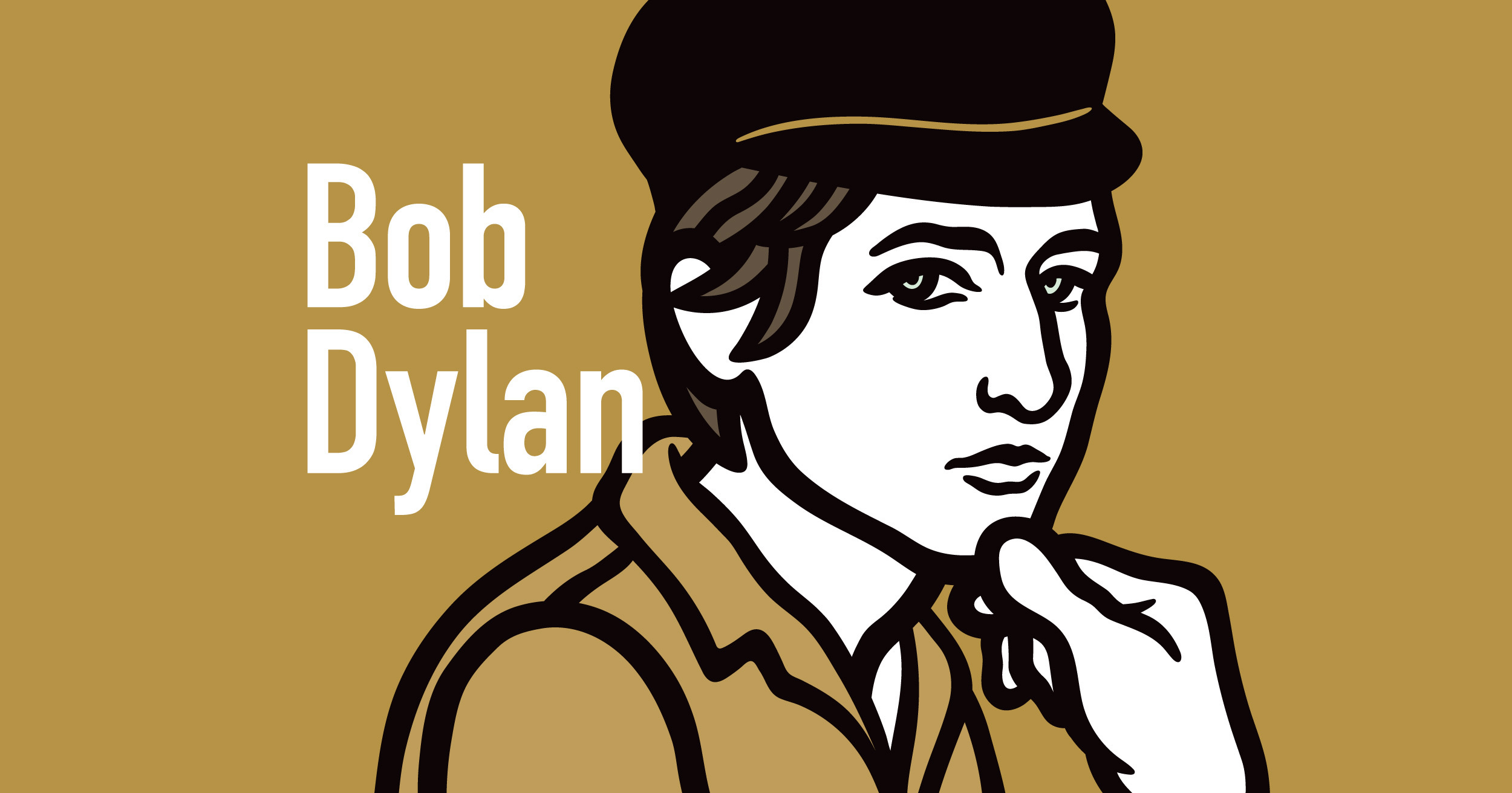バティアシュヴィリとゴーティエ・カプソン、ティボーデが最高レヴェルの室内楽

スイスの11月の音楽シーンから、注目のコンサートやニュースを現地よりレポートします。

1941年12月創刊。音楽之友社の看板雑誌「音楽の友」を毎月刊行しています。“音楽の深層を知り、音楽家の本音を聞く”がモットー。今月号のコンテンツはこちらバックナンバ...
取材・文=中 東生
Text=Shinobu Naka
10月31日にトーンハレで行なわれた室内楽コンサートは、世界的ソリストが組んだアンサンブルとしては最高レヴェルであろう。ジャン=イヴ・ティボーデのピアノに、ゴーティエ・カプソンはみずからのチェロを織り込ませ、ロマンティックに溶け合う。リサ・バティアシュヴィリのヴァイオリンだけが尖っていたが、ショスタコーヴィチ「ピアノ三重奏曲第1番」を宝石が散りばめられているような輝きで演奏した。
続くドビュッシー「ピアノ三重奏曲」は絵本を描いているような色彩を帯び、作曲家と同郷の二人が貢献した。第3楽章では押し付けないチェロのロマンティシズムが光る。和音進行も、導音で焦らして主和音で解決させる微妙なテヌートが効果的だ。ヴァイオリンもフレーズの紡ぎかたは匠の技で、第4楽章でのアジタート(激しく)では泣ける、切ないアパッショナート(熱情的)な楽章となった。
後半のドヴォルジャーク「ピアノ三重奏曲第3番」はバティアシュヴィリが本領を発揮し、3人の一糸乱れない共演は興奮を呼ぶ。第3楽章でのカンタービレも聴かせ、カプソンもスラヴ的音色で、いつになく熱い。この名演は暫く聴衆の記憶に残り続けるだろう。
谷口朱佳がジュネーヴ・コンクールのヴィオラ部門で第2位
今年はヴィオラと指揮部門で開催された第79回ジュネーヴ国際音楽コンクール。ヴィオラ部門では本選に進んだ36人中3人の日本人がいたが、セミ・ファイナルに進んだのは谷口朱佳(たにぐち あやか、23歳)だけだった。
セミ・ファイナル2日目の11月7日、谷口はステージいっぱいに広がるスケールで、エネスク「演奏会用小品」を弾き始めた。全般的に表情が豊かだが、しばしば上のほうを凝視して弾く。室内楽審査のあとに尋ねると、ホールに響く音が見えるのだという。楽しそうなオーラに包まれ、青いドレスもあいまって、青い空が広がるような演奏だった。
ピアニストもすばらしく、抜群の相性だったが、偶然、谷口のフランクフルト芸術大学での師、タベア・ツィンマーマンとも録音しているトーマス・ホップに当たったのだそうだ。
次のヴェラ・ガイゲロヴァ「ピアノとヴィオラのための組曲」もすばらしく、匂い立つようだ。第2楽章は詩的に、第4楽章は泣いているような、なにかを見据えた訴える目をして弾ききる成熟した音楽性に打たれた。
そしてヴュータン《ヴィオラ独奏のためのカプリッチョ》遺作のソロは、遠くを見つめながら物凄い集中力で有名なメロディを美しく弾き上げた。
最後はヒンデミット「ヴィオラ・ソナタ」(1939)でこれまでの曲より骨太の音楽作りを聴かせた。第2楽章では音楽が体からにじみ出てくるように、身体中で表現し、その音を遠くまで飛ばす器の大きさを見せた。「数週間前のヒンデミット・コンクールで優勝した」と知らせてくれたツィンマーマン氏も満足そうだった。
11月9日の室内楽審査、モーツァルト「ディヴェルティメント」KV563では、第1楽章からすべてのパッセージに表情があり、主旋律でなくても、常になにかを訴えかけている。
ヴァイオリンのコリーナ・ベルチャとチェロのリオネル・コテを交互に見ながら、友達同士のようにフレーズで会話している。立派な音で情景を描写する力が演劇的な効果も与えていた。
第2楽章では長いフレーズを聴かせ、ヴァイオリンに美しく寄り添う。谷口が主旋律を弾かない部分では音楽的に平坦に感じてしまうほどで、第3楽章でも成熟したソロを聴かせた。
続いてベリオ「ナトゥラーレ《自然》」では打楽器奏者のティル・リンゲンベルクとしっかり息を合わせる。大きなフレージングで、シチリア民謡が挟まれると、一緒にヴィオラで語っているようだ。ベリオの即興的音楽を、しっかり自分のものとして作り上げていた。
谷口がフィナーレに進むのは予測されたが、サラ・ストロームが強敵だと感じた。結果的にはストロームとブライアン・イザックが第1位を分け、谷口は第2位となった。ほか、エトリアール財団賞、ヒンデミット賞、オディッセイ・フランク・マルタン賞も併せて受賞した。






関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest