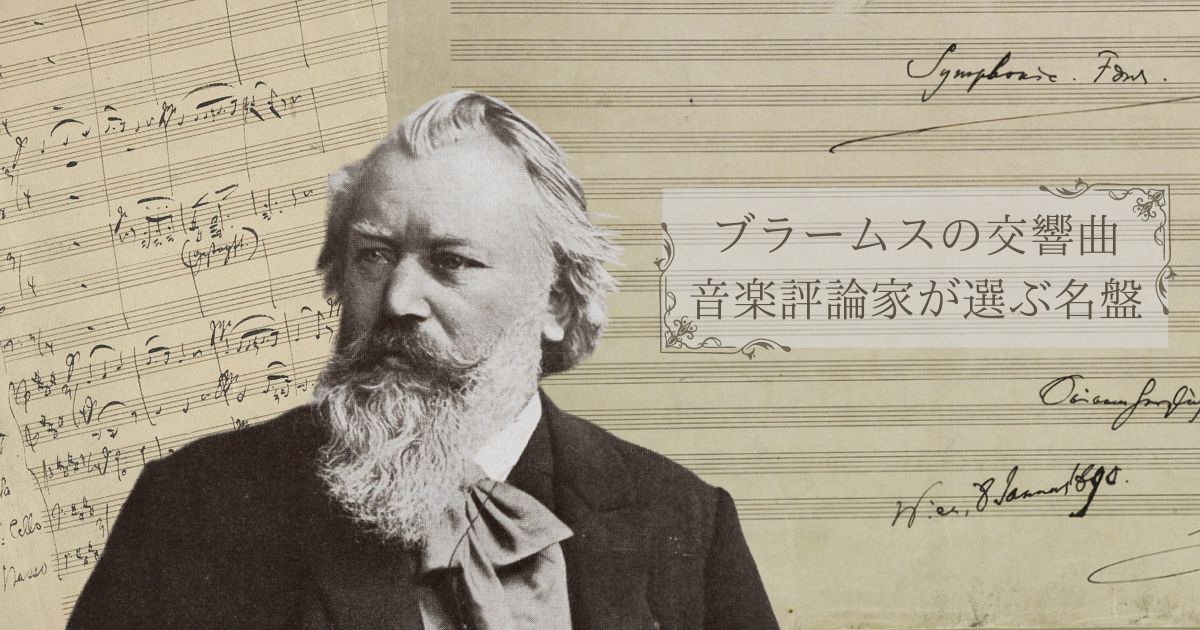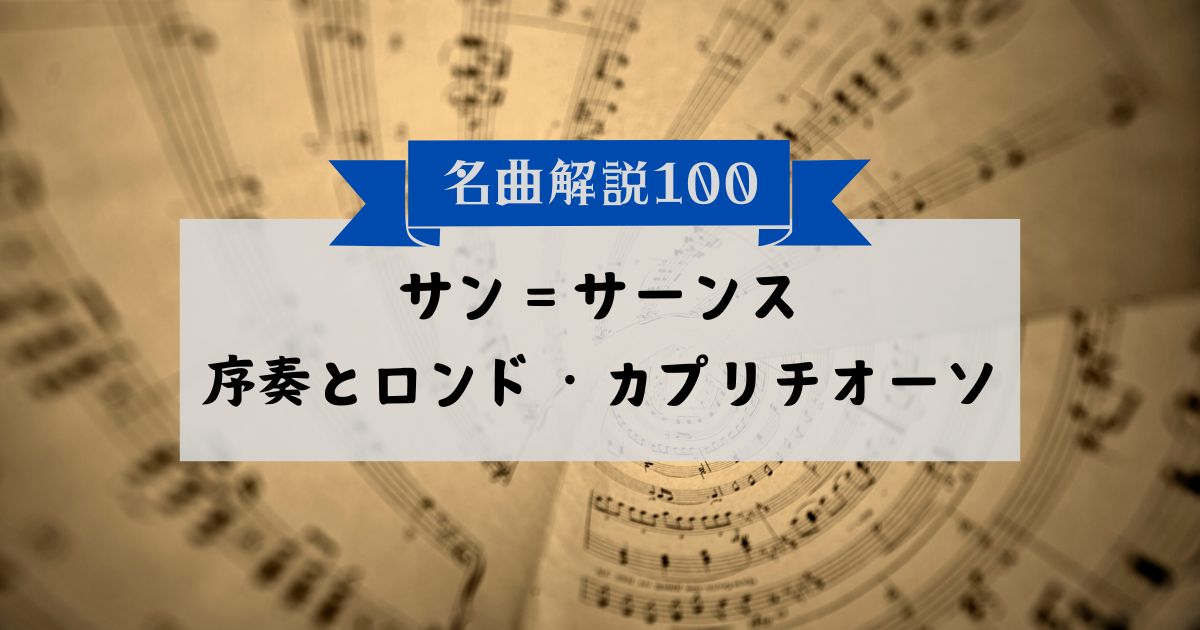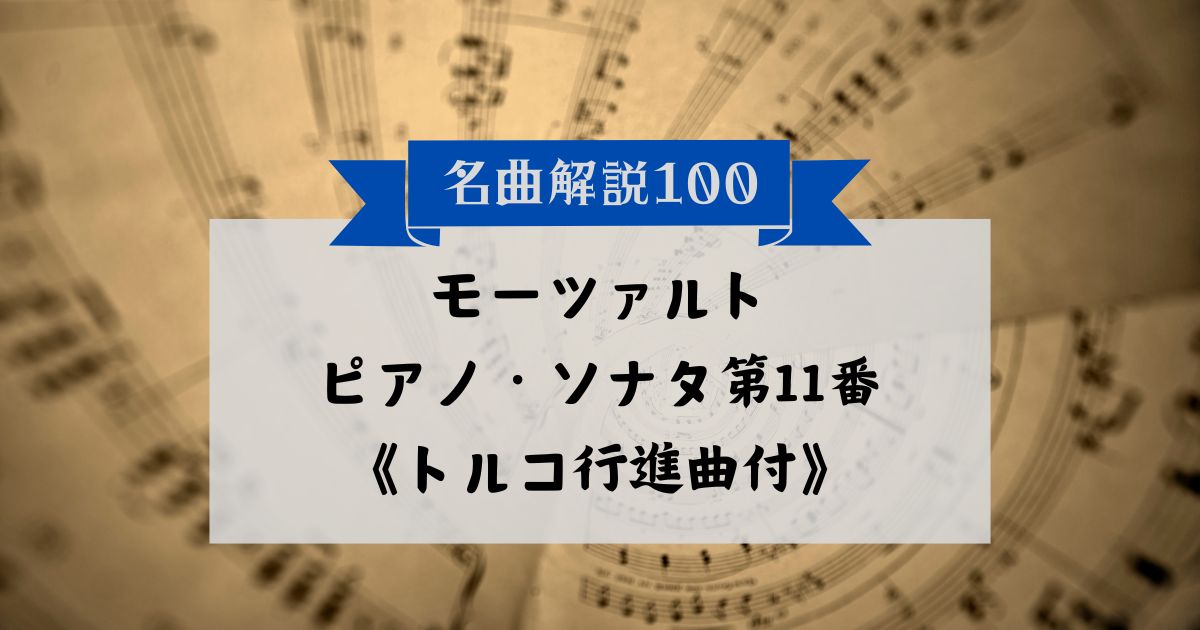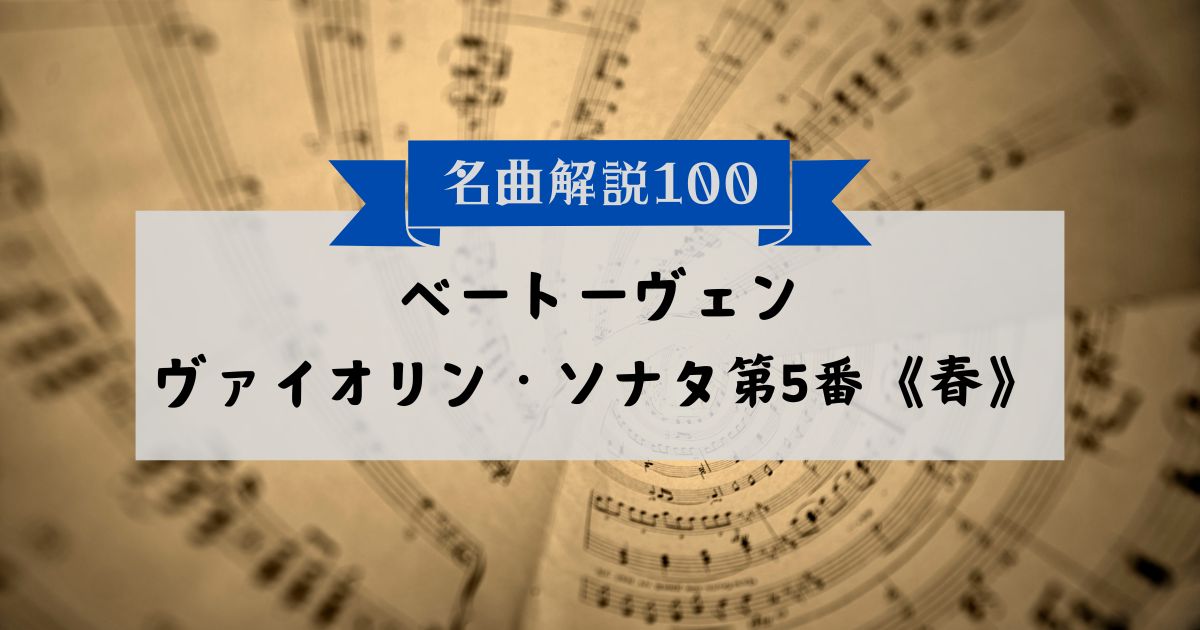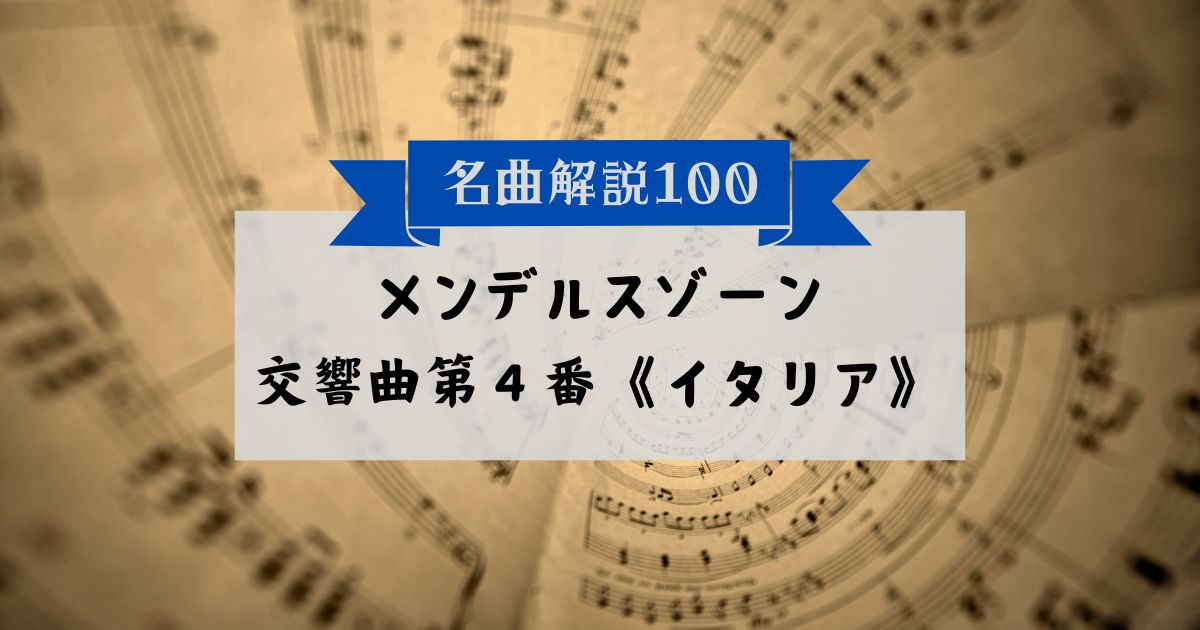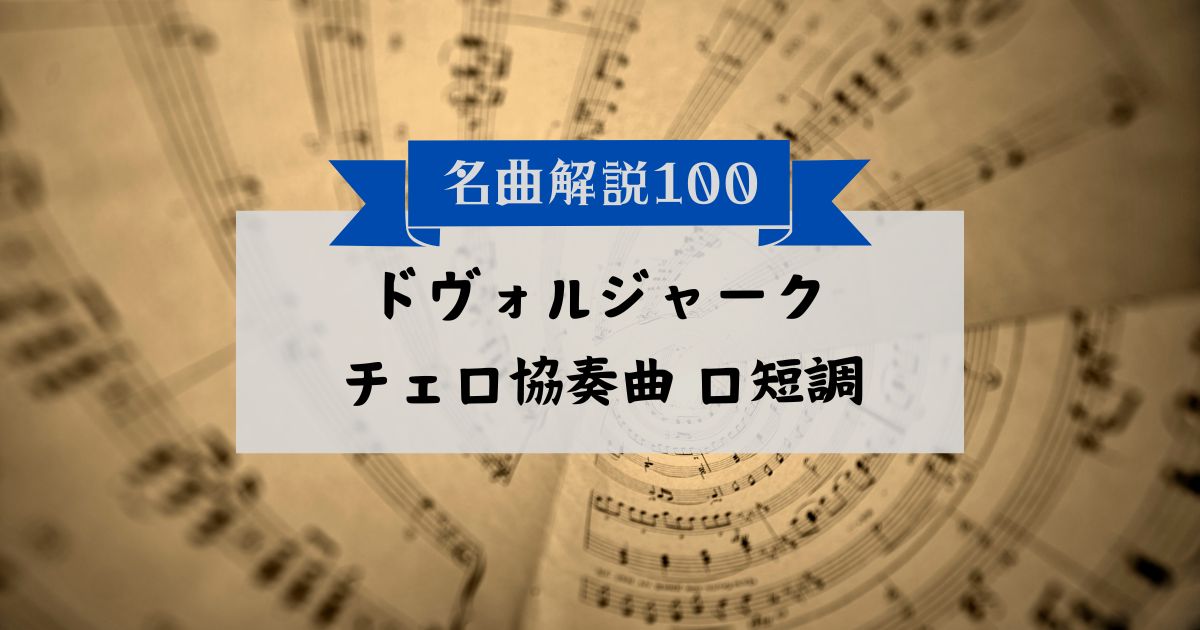
読みもの
2025.11.12
名曲解説100
30秒でわかるブラームス:交響曲第4番
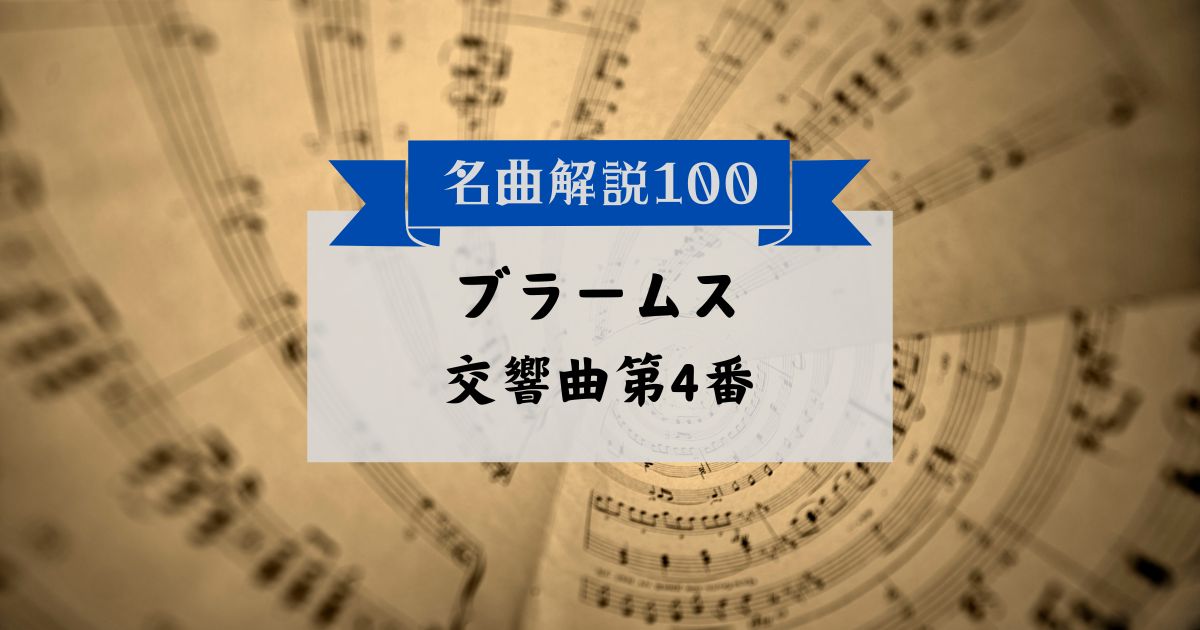
ブラームス:交響曲第4番について30秒で丸わかり♪
ヨハネス・ブラームス(1833~97)の最後の交響曲となったこの第4番は円熟期の彼ならではの渋味をもつとともに、伝統主義者と呼ばれた彼の作品の中でもとりわけ古風な趣を感じさせる交響曲で、第2楽章のフリギア旋法(教会旋法の一種)による主題、第4楽章のヨハン・セバスティアン・バッハの主題によるパッサカリア形式の採用など、古い時代の書法が取り入れられているのが特徴的です。しかしそうした一見古い過去の書法がロマン的な情感の表現のために用いられている点がブラームスらしく、全体として後期の彼特有の孤独な心情を映し出したようなロマン的な傑作となっています。
第1楽章では冒頭から切々たる第1主題が提示されますが、その主題を構成する溜息のような下行3度とそれを裏返した上行6度は楽章全体に大きな役割を果たします。
第2楽章は古風な性格の第1主題と情感に満ちた第2主題を持った緩徐楽章。第3楽章はスケルツォ風の諧謔的な性格の楽章で、トライアングルが効果的に用いられています。
第4楽章はバッハのカンタータの主題に基づくパッサカリア形式のフィナーレで、その凝った変奏法と全体の綿密な構成にブラームスの円熟した筆遣いが窺われます。
ブラームス:交響曲第4番
作曲年:1884~85年
演奏時間:約40分
編成:フルート2(第2はピッコロ持替)、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、コントラファゴット1、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、ティンパニ、トライアングル、弦5部
名曲解説100
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest

イベント
2026.02.05
石田泰尚さんが横浜みなとみらいホールプロデューサー“ラストイヤー”への意気込みを...

読みもの
2026.02.05
スカラ座より熱い!? ミラノ五輪はサン・シーロから始まる

インタビュー
2026.02.05
ケヴィン・ケナーが語るショパン演奏「音楽はアイデアではなく、体験である」

読みもの
2026.02.04
ピアニストの久末航が日本製鉄音楽賞「フレッシュアーティスト賞」を受賞!

レポート
2026.02.04
京都コンサートホール2026年度ラインナップ発表
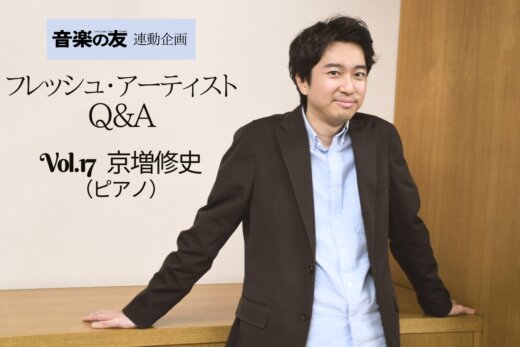
連載
2026.02.03
京増修史さん(ピアノ)、「もう一度聴きたい」と思われるような演奏家でありたい

インタビュー
2026.02.03
ネルソン・ゲルナーが語るショパン演奏と審査で大切なこと「音楽そのものに集中して理...

読みもの
2026.02.01
2026年2月の運勢&ラッキーミュージック☆青石ひかりのマンスリー星座占い