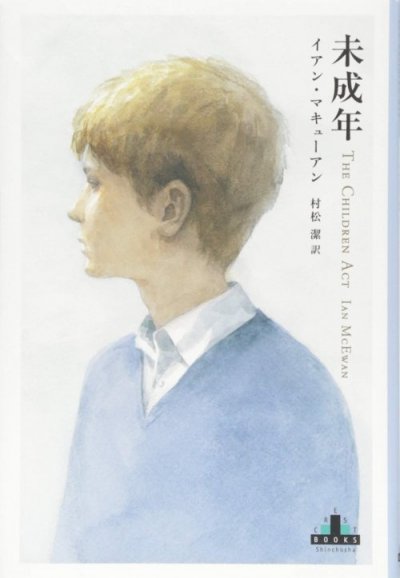アマチュア・ピアニストが限界を突破するとき──イアン・マキューアン『未成年』

かげはら史帆さんが「非音楽小説」を「音楽」から読み解く連載、第2回はイギリスの作家イアン・マキューアン『未成年』。アマチュア・ピアニストである裁判官の主人公が、とある事件を通して「アマチュアの演奏の限界突破」を経験します。作者が描いた「人」と「音楽」との、絶妙な距離感を読み解きます。

東京郊外生まれ。著書『ニジンスキーは銀橋で踊らない』(河出書房新社)、『ベートーヴェンの愛弟子 – フェルディナント・リースの数奇なる運命』(春秋社)、『ベートーヴェ...
バイオリンを、いや、どんな楽器でも、習いはじめるのは希望を秘めた行為であり、それは未来を暗示している
イアン・マキューアン作 鈴木徹郎訳『未成年』(新潮クレスト・ブックス刊)
主人公は、趣味でピアノをたしなむエリート裁判官
この物語において、「音楽」はメインテーマではない。
主人公の人生においても、「音楽」はメインテーマではない。
主人公──フィオーナ・メイは、音楽家になる人生を選ばなかった。小説の中盤に登場する回想シーンで、13歳の彼女はコンサート・ピアニストを将来の夢のひとつに挙げている。その夢はわずか数年のうちに消え、彼女は法学の道を選んだ。
法学。音楽家の伝記において、しばしば才能を阻害する存在として登場する学問だ。ロベルト・シューマンは大学で法学を学んだ。チャイコフスキーもそうだ。
結果的に彼らは、自身の才能に賭けて音楽の世界に舞い戻った。フィオーナはそうではなかった。彼女の才能はむしろ法学の道のほうに開けていた。彼女がしたためた判決文は芸術のごとく賞賛され、いくつかの仕事は彼女の名声を絶頂に押し上げた。
59歳になった彼女は、高等裁判所の裁判長をつとめている。
少女の頃に抱いた夢は、趣味という形で残った。彼女はときおり、法の世界で働く音楽仲間たちとピアノの演奏を楽しむ。いかにもエリートらしい、良質で洗練された趣味として。地質学者である夫は、楽器の演奏はしないが音楽が好きで、妻の趣味を心から応援している。子どものいない裕福で知的なカップル。彼ら夫婦は、長年をかけて、おだやかな愛と信頼を築いてきた。
この物語のメインテーマはふたつある。
ひとつは夫婦関係だ。
シングル・モルトを注いだとき、彼は両足をひろげて、まっすぐに立っていた。空いている片手の指先が頭のなかの曲に合わせて動いていた。たぶん、ほかのだれかといっしょに聴いた曲だろう
すぐれたアマチュア・ピアニストであるフィオーナは、夫の指先のかすかな動きを見逃さない。女の影だ。夫はひるまない。反対する彼女の前で、きわめて冷静に交渉を持ちかける。きみを愛している。きみとの結婚生活は続けたい。でも死ぬ前にもういちど、女性とベッドをともにし、「情熱的な関係」をもちたい。どうかそれを許してほしい──と。
小説『未成年』は、その話し合いのシーンから幕を開ける。
音楽は人生を決して邪魔しない
『未成年』(原題:The Children Act)は、イギリスの作家イアン・マキューアンによる2013年発表の小説である。
このタイトルは、物語に登場する、もうひとつのメインテーマから採られている。
夫の突然の宣言に動揺しているさなか、彼女はある裁判を受けもつ。有名な新興宗教団体に属する少年による輸血拒否事件だ。病床の少年も、その両親も信者であり、信仰を理由に輸血を拒否している。
問題は、少年が「未成年」というにはかなり微妙な年頃であることだ。17歳と9か月。成人年齢の18歳まではあとわずか。しかも、人並み外れた知性の持ち主として学校でも病院でも評判の少年だった。
意志よりも命を保護すべきか。意志を尊重すべきか。尊重するにしても、熱心な信者である両親に育てられた少年のそれは、そもそも本当に「自分の意志」といえるのか。
夫は女と「情熱的な関係」を持つために、スーツケースと一緒に出て行ってしまった。きびしい精神状況のなか、彼女はこの案件の判決を迫られる。これが、『未成年』の核となるストーリーだ。
音楽は、ときおり役目を思い出したようにふっと現れるにすぎない。ある夜、パンとチーズとオリーブと一杯の白ワインとともに、彼女はバッハのパルティータを弾く。仕事や家庭問題、つまりはこの物語のメインテーマに疲れ、しばらく「なにも考えずに」いたいときの現実逃避の手段として。インテリ女性の手すさびとしてのピアノ。人生を邪魔しない程度にひっそりと鳴る音。それがこの小説における音楽の立ち位置だ。
アマチュアだからこそ到達した、音楽との「情熱的な関係」
ところが小説の終盤にいたって、──つまりは夫婦関係と輸血の問題がそれぞれ終わりを見るにいたって、マキューアンの筆はそれまで「メインテーマ」ではなかった音楽のほうへ急激に傾いていく。
ある冬の日、彼女は法曹院で開催されたコンサートで、音楽仲間のマークとともにベルリオーズの歌曲集《夏の夜》を弾く。彼女はその演奏のさなか、「音楽創造の果てしない超空間」を体験する。
マークとちらりと目を合わせ、その目に光るものを見て取ったとき初めて、彼女は自分たちがアマチュアの演奏の限界を突破したことを確信した
ベルリオーズ: 歌曲集《夏の夜》〜「ヴィラネル」(声とピアノのための編曲版)
なぜ彼女は「アマチュアの演奏の限界を突破」したのか。なぜマキューアンは、彼女に限界を突破させたのか。彼女の人生のメインテーマではなかった音楽において、なぜ彼女は高い次元にまで達する必要があったのだろうか。
その謎の鍵は、物語の中盤にある。フィオーナは、輸血拒否事件の判決を下す前、少年をたずねて病院に赴く。少年の病床には、一台のバイオリンが置いてあった。まだ練習をはじめたばかりだという少年は、彼女の前でアイルランド民謡の「サリーの庭」を弾く。そのつたない演奏に、彼女は思いがけず心を掻き乱され、こんな思いを抱く。
バイオリンを、いや、どんな楽器でも、習いはじめるのは希望を秘めた行為であり、それは未来を暗示しているからだ
アイルランド民謡(ベンジャミン・ブリテン編曲)「サリーの庭(柳の庭のほとりで)」
音楽と人の「距離感」を絶妙に紡ぐマキューアンの筆
この病室での思いこそが、彼女に「アマチュアの演奏の限界を突破」させた。17歳の少年がつたない弓さばきで暗示した「未来」を証明できるのは、59歳のアマチュア・ピアニストである自分しかいない。輸血か死かで迷っていた未成年の少年と、法学か音楽かで迷っていた未成年の自分への答えを、自らの演奏でもって示したい。死を選んだらこの未来はやってこない。音楽を選んだらこの未来はやってこない。法に生きる人生を選んだからこそ、自分は「音楽創造の果てしない超空間」に至る演奏をやってのけたのだと。
59歳の矜持をかけたその演奏は、彼女自身が死ぬまでにいちど果たしたかった、音楽との「情熱的な関係」の再構築でもあった。
イアン・マキューアンの小説には音楽がさまざまな形で登場するが、いずれも音楽は主役ではない。しかし、あらためて音楽に着目してみると、音楽と人物との距離感や関係の紡ぎ方の正確さに驚かされる。
音楽をメインテーマにした小説にはない絶妙なバランス感は、ハッピーエンドで終わるとは限らない物語に希望の光をもたらしている。





関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest