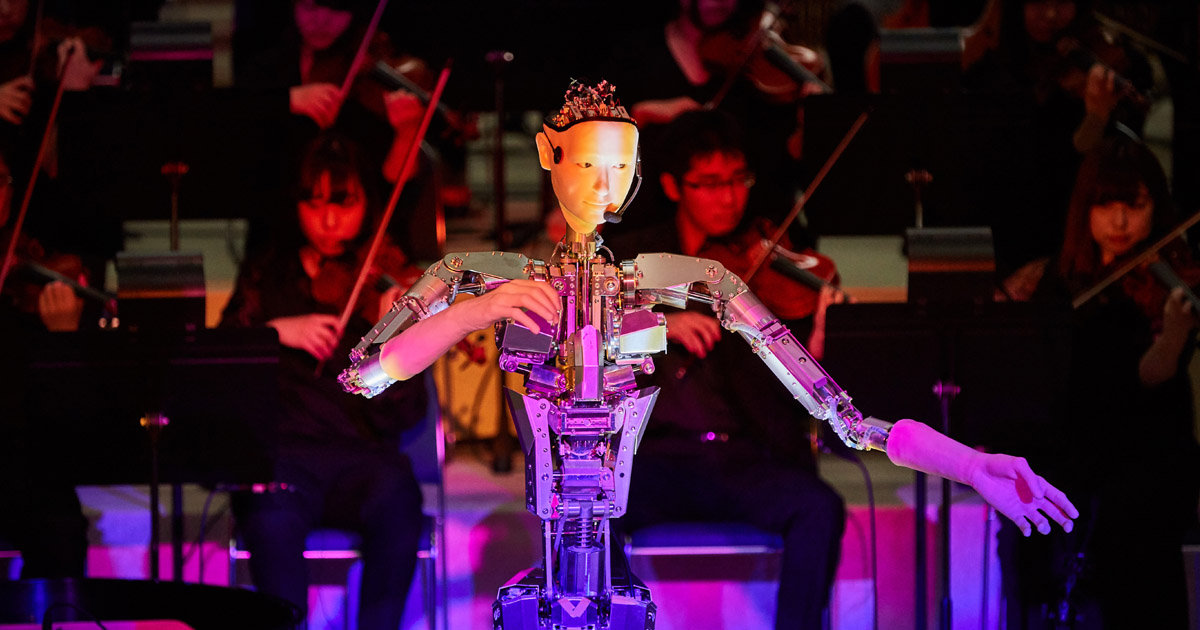第15回〈後編〉音響設計 清水寧さん——西洋的な音の原風景を日本のホールに取り入れたい

クラシック音楽の世界で仕事をする飯田有抄さんが、熱意をもって音楽に関わっている仕事人にインタビューし、その根底にある思いやこだわりを探る連載。
第15回の後編は、国内外のさまざまなホールの音響設計や、欧米での響きの体験から考えた日本のホールの理想像を、音響設計の清水寧さんに伺いました。

1974年生まれ。東京藝術大学音楽学部楽理科卒業、同大学院修士課程修了。Maqcuqrie University(シドニー)通訳翻訳修士課程修了。2008年よりクラシ...
音響設計とは、通訳である
——清水さんはこれまでに、八ヶ岳音楽堂、草津音楽の森国際コンサートホール、福岡シンフォニーホール、東京国際フォーラム、新潟芸術文化会館など、数々のホールの音響設計に携わってこられていますが、「音響設計」とはいったいどのような仕事なのでしょうか。
清水 ひと言で言うなら、「通訳」ですね。音楽家と建築家との間の通訳です。音楽家は「もっと柔らかく」とか「飛んでほしい」とか音に対していろいろな言葉を使いますが、建築家にはなかなか伝わりにくい。そこで私が通訳をするのです。
音楽家の印象や理想を物理量=数値に置き換えて、それを実現できる建築の形を伝えるのです。

東京工業大学工学部 建築学科卒業、同大学総合理工学研究科 社会開発工学専攻修了。1977~2000年ヤマハ(株)建築音響研究室、音響研究所、2000~2003年レンセラー工科大学建築学部 研究准教授、2003~2010年にヤマハ(株)サウンドテクノロジー開発センター 技術担当主管技師、2008~2016年東京工業大学 総合理工学研究科 人間環境システム専攻 連携教授などに携わる。
——音楽家の意図するところを、清水さんはなぜそんなに理解できるのですか?
清水 実は、私自身もチェロを演奏します。若い頃には演奏家への道を考えた時期もありました。また、私はヤマハの建築音響研究室、音響研究所に20年以上いましたので、その間に多くのホールを手がけ、たくさんの音楽家との交流がありました。
ホールではオープン前に試奏会があり、いろんな音楽家に演奏してもらって意見を聴きます。「どうも音に包まれた感じがしない」とか「客席に音が吸われている感じがする」とか、測定だけではわからなかった問題を出してもらい、それを物理量に置き換えて、たとえば吸音材を減らすといった調整を行なうのです。
音というのは目に見えませんし、人によっても意見が違う。とらえどころがないものですが、私は専用のソフトを使って色や分布図へと可視化する研究をし、同時に建物の設計も行なってきました。ただ日本では、工学的・科学的なエンジニアリングが音響設計であると思われがちです。人の思いを建築でどう実現させるか。そうした通訳的な働きかけがなければ、たんなる工学だけで終わってしまいます。

アメリカの公共スペースが教えてくれる「響きの原風景」
——長らくヤマハにいらしたあと、アメリカへと渡られそうですね。
清水 ニューヨーク州の北にあるレンセラー工科大学建築学部の研究准教授として滞在していました。アメリカではホールだけではなく、いろんな公共スペースの音響設計に携わりました。
2001年にニューヨークでテロがありましたね。そのあと、音響面からのテロ対策として研究チームに引き入れられました。スピーチセキュリティという、盗聴を防ぐための技術の研究グループです。音楽ホールでの音響技術は非常に高いので、それが病院、オフィス、軍などでの情報の保護へと応用されました。
そうした公共スペースでの音響研究をしているうちに、教会やアトリウム(大きな建物内の広場)のような音響を、コンサートホールに取り入れられないか考えるようになりました。つまり、コンサートホールだからといって、シューボックス型(客席がまっすぐ前のステージに向いているタイプ)かアリーナ型(客席がステージをぐるりと囲むタイプ)にこだわらないで発想していくのです。
——多様な発想、目的をもってホールを作るということですね。
清水 理想はひとつではないはずです。もちろん、音響設計として守るべき最低限のラインはあります。「響き」と「音量」と「広がり感」。この3つの要素の最低ラインの物理的数値は明確にあるのです。
しかし、それだけで建物の形は決まるわけではありません。最低ラインはクリアしつつも、それぞれのホールの特徴を生かした音響を、一つひとつ作っていくのです。
例えば、八ヶ岳高原音楽堂の空間は「サロン」。身近な音に包まれるような響きを目指しました。草津のホール(草津音楽の森国際コンサートホール)も八ヶ岳と設計者が一緒で、吉村順三先生という有名な木造の建築家によるものですが、拡大されたサロンとしての雰囲気を持ち、豊かな残響を実現しています。
福岡シンフォニーホールは、ウィーンのムジークフェラインのような完全なるシューボックス型を作ろうと目指しました。東京国際フォーラムは、5000席のホールでクラシック音楽ができるかどうかがテーマ。みんなそれぞれ異なるわけです。





——理想的な音響も、多様であることがわかりました。
清水 とはいえ、クラシック音楽の生まれたヨーロッパやアメリカの人たちの間では、「響きの原風景」ともいえるひとつのイメージがあるようなんです。「大きくて人が多く集まる場所=大聖堂的な雰囲気と響きのある場所」というイメージです。
——それは、人々が教会に集うというキリスト教文化に根付いたものですね。
清水 そうなんです。教会は天井が高く、音が空間の上のほうで豊かに響いているけれど、下のほうでは人と人とが普通に会話ができますね。あの「響きの原風景」です。
テロの悲劇があったグラウンド・ゼロには、現在ターミナル駅(ワールド・トレード・センター・トランスポーテーション・ハブ)ができました。それが現代的なデザインによる大聖堂のような建物で、天井の高い大きなロビーはすごく響きがあるけれど、会話しやすくて居心地がいい。スペインの建築家によるものなのですが、空間の下を人々が行き交い、集い、日々いろいろなことをやっている。イタリアのドームなどもそうですね。人が集まるところは響きが豊かです。

音楽ホールを面白くしたい!
——響きの豊かさ=人の集まるところ。その「西洋的な原風景」を取り入れたホールを、日本で作りたい、と清水さんはお考えになられるわけですね。外界から遮断された、集中して音楽を聴くための静かなコンサートホール、というイメージとはちょっと異なりますね。
清水 日本のホールは、ある意味では静かすぎるのかもしれません。あのホールよりもこのホールが静かだとか、残響が長いだとか、そういう「性能」で競い合っている。それがいきすぎると、人が来にくくなっちゃいます。八ヶ岳などでは、あまりに静かすぎるから、遅刻してしまったときにハイヒールを脱いで入る人もいるのだとか。
でも、ウィーンのムジークフェラインなんて、窓ガラスを通じて外の音だって入ってくるんですよ。自然の音が聴こえるのもいいじゃないですか。

清水 アメリカのタングルウッドの野外劇場やロスのハリウッドボウルなどは、音楽の楽しみ方が実に自由で、みんなリラックスしています。
日常生活の中に音楽空間がある、というのがアメリカの考え方。広場でも、響きがいいなと思ったら、そこで音楽が始まっちゃう。
そういうものを見てきてしまうと、静かすぎる日本の現状はキツいですね。
タングルウッド音楽祭の会場の雰囲気
——なんだか窮屈ですよね……
清水 クラシック音楽というと、どうしても年輩の人たちが、ありがたそうに鑑賞するもの、というイメージ。でもそれだけだとつまらないじゃないですか。もっと若い人が来て、楽しい空間として、賑わいのあるコンサートホールがあってもいい。
浦安音楽ホールは、その意味でも「遊び」の要素を取り入れました。扉を開けるとトンネルがあって、歩いて行くと棒の隙間からホールが見えたり、そこから覗くと聴こえ方が違ったり。浦安は、シューボックス的な音も、アリーナ的な音も、大聖堂的な音もあり、場所によって聴こえ方があえて異なるように作ったのです。お客さん自身が好きな音を探してください、と。演奏者にはどこをイメージして演奏したらいいでしょう、といわれましたが(笑)。



私は環境心理学が専門でもあります。人が音を聴いたときに持つ印象や、人が環境の中で音を認知するプロセスなどを研究する学問です。その経験を生かしながら、日本のホールの現状を、なんとか面白くしたい。
——今回のグローバルリング シアターは、その意味でも清水さんにとってのチャレンジや思いの込められた空間なのですね。開かれた公共性の高いスペースだからこそ、難しい面もありますよね。街中を歩く人が、みんなが音を耳にして快適になれるわけではないでしょうし。
清水 同じ音でも、人によって、好きな音にも、聴きたくない音にもなります。公共スペースでは、それをどうするかという問題はありますね。
野外は騒音規制法や環境基準などがあるのですが、不快な人工的ノイズを基準に規制していくと、本来、人が不快とは感じない自然音やサウンドスケープまでもが失われ、賑わいのない静かすぎる街になってしまいます。
いろいろと試行錯誤する余地はあります。音に対する関心、音響に対する人の認知度がまだ低いのです。周りに邪魔にならないように音を出すということが、技術によって可能になってきています。これからそうした開発を、もっと進めていきたいです。






関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest