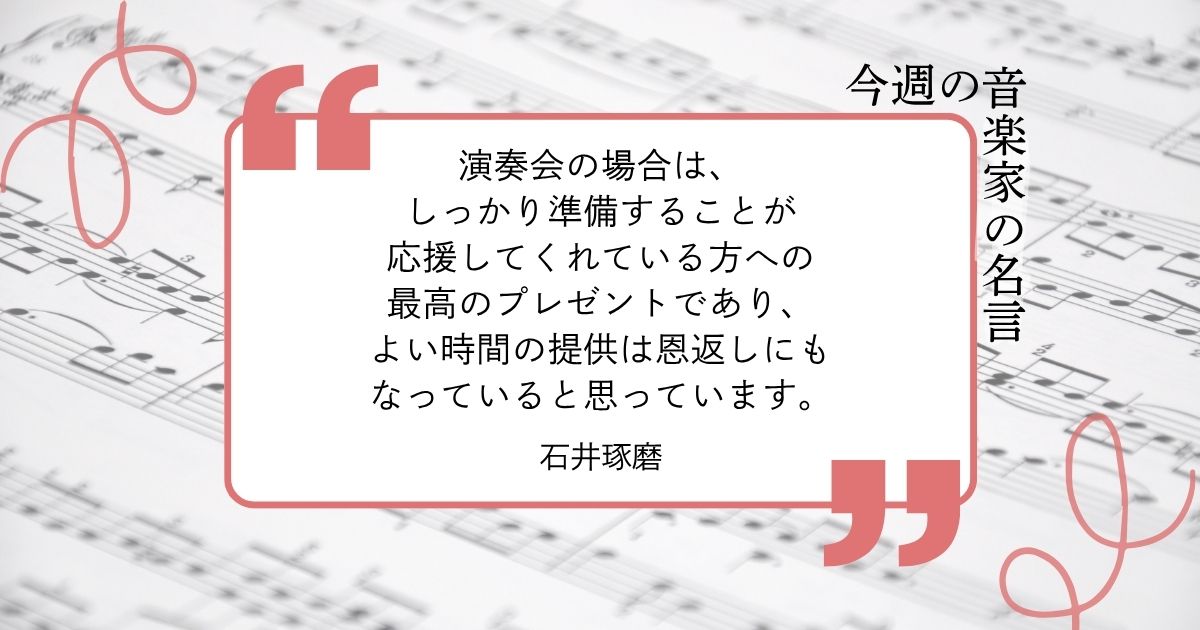母ではない顔をした母に寄せて——ヤマザキマリ『ヴィオラ母さん 私を育てた破天荒な母・リョウコ』

かげはら史帆さんが「非音楽小説」を「音楽」から読み解く連載。
第13回は『テルマエ・ロマエ』などで知られる人気漫画家ヤマザキマリが、自身の母で、札幌交響楽団の創立メンバーだったヴィオラ奏者、山崎量子の半生を描いた『ヴィオラ母さん 私を育てた破天荒な母・リョウコ』。あくまでも「娘」の視点で「母」を綴った文章から見えてくる「ヴィオラ母さん」の顔とは?

東京郊外生まれ。著書『ニジンスキーは銀橋で踊らない』(河出書房新社)、『ベートーヴェンの愛弟子 – フェルディナント・リースの数奇なる運命』(春秋社)、『ベートーヴェ...
うちにいるのは、ライフル銃のケースのような真っ黒くて物々しいヴィオラの楽器ケースを抱え、いつも髪を振り乱してワサワサと動き回り、洗濯石けんで顔を洗うような、ジェンダーの枠を越えて生きる凄まじき母・リョウコだった
ヤマザキマリ著『ヴィオラ母さん 私を育てた破天荒な母・リョウコ』文藝春秋、2019年(以下、すべて本書が引用元)
60年前、地方オーケストラの創設メンバーだった女性奏者がいた
若いクラシック音楽家のキャリアの話題が盛んだ。音大生の就職やキャリア形成に特化した書籍やウェブ上のサービスも増えた。もちろん賛否はあるだろう。しかし音楽大学における女性の比率の高さを思えば、ようやくここまで進んだか、とポジティブに考える方も多いに違いない。多様な進路がありうることを示すのは、業界として急務といえるだろう。
2021年のいま、音楽業界には当たり前のように女性の姿がある。しかし、1世代、2世代前は決してそうではなかった。オーケストラの女性比率は、楽器学習者人口の女性比率の高さに比べていびつなほどに低かった。プロオーケストラによる演奏会は、経済や政治の世界と同じく男性がステージの多勢を占めており、それは東京であろうと地方であろうと同じだった。
だからこそ、彼女の存在は目を惹いた。
1961年、札幌市民交響楽団(現札幌交響楽団)の演奏会。「蝶ネクタイにタキシードで正装した男性メンバー」のなかで、「黒いワンピース姿」のヴィオラ奏者は異彩を放っていた。
彼女の名前は山崎量子。
『テルマエ・ロマエ』などの作品で知られる漫画家・ヤマザキマリの実母である。
「母ではない顔をした母」へのリスペクト
『ヴィオラ母さん 私を育てた破天荒な母・リョウコ』は、山崎量子──「リョウコ」の半生を、長女であるヤマザキマリの目線から描いたエッセイである。
副題が示すとおり、リョウコは破天荒な人間だ。神奈川育ちにもかかわらず、札幌に新しい交響楽団ができると聞きつけ、親の反対を押しきって移住。夫を早くに亡くしながらも、オーケストラ団員の一員として生計を立て、娘ふたりを北海道の大自然のなかで育て、ヴァイオリンを教えるためにワゴン車で僻地まで爆走する。賞味期限切れの乳酸菌飲料を平然と飲み、洗濯石けんで顔を洗い、北国の気候を無視して建てたい家を建てる。その豪快なキャラクターこそが本書の見どころである。
一方で彼女は、その時代だから可能な生き方をした人でもあった。男性と肩を並べて働く女性は少なかったが、オーケストラのポストをめぐる競争は現代のような熾烈さとは質が違っただろうし、育児はずっとおおらかだった。彼女の生き方を、そのまま、21世紀の若い音大生のためのキャリアの教科書にはできない。筆者自身も「多様な悩みを抱えた昨今の日本の女性たちの役に立つかどうか」と冒頭で書いている。「でもひとまず、鼻息荒く駆け抜ける野生の馬のように自分の選んだ仕事をし、子供を育ててきた一人の凄(すさ)まじき女の姿を思い浮かべてもらうことで、自分や子供の未来に対してどこまでも開かれた、風通しの良い気持ちになってくれたら筆者も嬉しく思う。」
実践的ではないかもしれないが、「風通しの良さ」を感じてほしい。それが本書の趣旨だ。
しかし、この「風」はいったいどこから来るのだろうか。
読んでいるうちに、ハッと気づく。風を起こしているのは、リョウコではない。むしろ筆者である娘のマリの側なのだと。
ヤマザキマリにとってリョウコは母親だ。そしてこの本は、あくまでも娘目線からの母親の半生記である。しかし彼女は、母親の「母親としての顔ではない部分」を、(決して具体的に描いていないにもかかわらず)きわめて強く意識している。
本書を読んで感じるのは、著者の目にはとどかない月の裏側に、芸術の宇宙を仰いで生きている山崎量子の姿だ。彼女が仰ぐ宇宙が、どのようなビジョンであったかは描かれていない。どのような個性のヴィオラ奏者であったのか、得意な作品はなんだったのか、どのような芸術観の持ち主だったかもほとんど描かれていない。ただ、ワゴン車や期限切れの飲料や洗濯石けんとは別の場所に、彼女の芸術がゆるぎなく存在していたことは不思議とわかる。
描かないことで、最大限の尊重の意を示す。それがこの本の基本的なあり方だ。
海外演奏旅行から帰ってきたリョウコの姿を、ヤマザキはこう描写する。
我々を迎えにきた時のリョウコはやたらと元気いっぱいで眩しかった。子供にやっと会えた安堵(あんど)の喜びなのだろうけど、その佇(たたず)まいには何か更にパワフルなエネルギーが漲(みなぎ)っていて、私たちを預かってくれた家族に対して恐縮している言葉と、その身にまとった輝きが全くシンクロしていない。
これは、母親を母親としてではなく、多様な面を持つひとりの人間として尊重していなければ成し得ない描写だ。しかしそれは決して簡単ではない。いつまでも子どもを子どもと思いたがる親が多いのと同様、子どもはいくつになっても親に親であることを求めたがるし、ときにシビアにジャッジする。愛してくれたか。向き合ってくれたか。希望や意志を認めてくれたか。充分に愛してもらえなかった遺恨は人生を通して残る。
筆者は、リョウコが100点満点の母親ではなかったと率直に記している。料理は苦手で、夕食はお金を渡されて自力で調達。見かねた近所の人におかずをもらうことも少なくない。放任なように見えながら、漫画やドリフターズを見せたがらない「普通の」(?)教育ママのような側面もある。学校をサボるのは容認されたが、音楽は強制的にやらせる。読者からみても、矛盾を感じさせる面が多々ある。
それにもかかわらず筆者はリョウコを慕い、彼女の人生をリスペクトしている。それは、リョウコが母としての顔だけを見せる母だけでなかったと同時に、娘に対して子どもの顔だけを見せる子どもでいることを求めなかったからだろう。画家になりたいという娘を、14歳でヨーロッパ旅行に行かせ、17歳でイタリア留学を許す。娘が留学先で妊娠し、赤ん坊を抱えて戻ってくると「孫の代までは私の責任だ」と言い切る。言葉の古めかしさとはうらはらに、娘の生き方を尊重しようという意志に満ちたセリフだ。筆者はリョウコを「同志」と呼ぶ。同志とは、互いの人生を認め合う関係の異名であろう。
私がこうして世界のあちこちで暮らし、国境という箍(たが)の意識を持たない人生を送っているのは、明らかにリョウコという人間を間近に見て育ってきたその影響によるものだと思っている
音楽ジャンルの外側から現れたクラシック音楽家伝
ヤマザキは、リョウコのルーツである山崎家の家系や生育環境に関しても、身内だからこそ可能なリサーチ力でもって触れている。祖父はイタリア人の書生を住まわせる音楽好きの道楽者、父はアメリカ駐在を経験した銀行員。あきらかに裕福な一族だ。リョウコ自身も、お手伝いさんに囲まれ、ヴァイオリンを習い、ミッションスクールに通う娘だった。しかし、その環境だからこそ得られた音楽のスキルを武器に、彼女はまったく新しい環境——文化のフロンティアたる北海道に、単身で飛び込んでいった。
本書は、ヤマザキマリが描かなければ、世に知られなかったであろうクラシック音楽家伝、ともいえる。日本の地方オーケストラの創設メンバーとして活躍した女性演奏家の半生記。こうした本が、音楽の専門家ではない著者のペンを介して、音楽ジャンルの外側から現れたことの意味について、いまいちど考えずにはいられない。
いったい山崎量子はどんな音楽家だったのだろう。どんな風に音楽を紡いだのだろう。ヤマザキマリが敬意をもって描写を避けたその演奏に触れてみたくなって、ストリーミングサービスで札幌交響楽団の音源を探してしまった。そんな興味を抱かせてくれる「ヴィオラ父さん」が、これまでどれくらいいただろうか?
岩城宏之(指揮)札幌交響楽団が演奏する武満徹「夢の時」(1982年、札幌市民会館ホールでのライブ録音)





関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest