
演出家・宮本亜門さんが考える、子どもたちに伝えたいこと、音楽と演劇

林田直樹の「レジェンドに聞け!」がスタート!
音楽を取り巻く世界のいま、いい音楽ってなに? 子どもたちへ伝えたいこと、ほか
伝説的な仕事をしてきたからこそのメッセージをいただきます。
第1回は、演出家の宮本亜門さん。
ミュージカル、演劇、オペラなどで、世界を舞台に記憶に残る数々の演出を手がけつづけている亜門さんに、ONTOMOエディトリアル・アドバイザーの林田直樹が迫ります。
「闇」こそ美しい——子どもたちに伝えたいこと

林田 春からスタートしたONTOMOで大事にしようと思っているテーマが、子どもということなんです。未来のために何を残すべきか、伝えるべきか。いま若い人たちに、亜門さんはどんなことを伝えたいですか?
亜門 うまく言えないけど、ポッと出てきた言葉で、これでいいのかどうかわからないけれど、「闇」って言葉かな。
林田 おお。
亜門 人間の裏側にも心の中にも、本当はいろんな死や闇があると思う。そういうものは、生きていく以上、相対的に必ずあるもので、そのことを意識してこそ生きることができる。殺しあうのが命の大切さがわからないからと同じで、闇というと急におびえちゃって、パンと切れちゃったりすることもあるかもしれない。けれど、人間が生きているというのは、絶対的な孤独と闇があるからこそだと思っているんです。
ネット社会は、あまりにも光の中ばかりで、すべてが「夢を追いかけて」「軽やかに」とか、それがうまくいかなかったらダメだ、みたいになっちゃうと、人間の本質とどんどん離れていっちゃう気がして。
その闇は悪い意味で言っているわけじゃないですよ。両方絶対に必要だと思っている。生と死があるのと同じで、光と闇がある。どんな真っ暗な夜でもそうですよ。
林田 つまり、必要な闇ということですか。
亜門 そうです。絶対に必要だと思う。
林田 よく新聞の記事とかで、学校で何か事件が起きると、すぐに心の闇という言葉が出てきて、社会問題みたいな言われ方がされますけど、そういう意味ではないですね。
亜門 まったく正反対です。本当に月も出ない、真っ暗な夜の闇の中で、あなたはどれほど美しさを感じますか、ということ。そういうときこそ感性って働くじゃないですか。虫の音か何かわからないけど、一斉に五感が敏感になっていって、すごく美しいんですよ、それは。そういう闇の夜が必要です。
そういう美しさの感覚って、特に日本人が、コンビニエンスストアの蛍光灯の明かりの中で、闇を知らなくて、だから次の戦争も平気でしちゃいそうな時代にこそ、知っておくべきだと思う。
宇宙は、見事に美しい闇じゃないですか。最近ちゃんと見たことないでしょう、空なんか。街の明かり、ネットの明かりばかり見ているから。それが中心ではないですよと。我々は何もわかりえていないこの巨大な宇宙の中にいる、小さな惑星の小さな人間なんだよ、ということも素敵じゃないですか。

オペラの演出をつづけている理由
林田 ところで、1990年代に「音楽の友」編集部に私がいたころ、亜門さんの対談連載を企画して、さまざまなアーティストをゲストに迎えて組ませていただいたことは、いまの自分にとって、大きな財産になっているんです。
8年間で50本の対談記事のゲストの中には、指揮者のサイモン・ラトルやロリン・マゼール、ヴァルフガング・サヴァリッシュやチョン・ミョンフン、振付家のモーリス・ベジャールやウィリアム・フォーサイス、演出家のパトリス・シェローやゲッツ・フリードリヒなど、今思い返しても、錚々たる人たちがいましたよね。
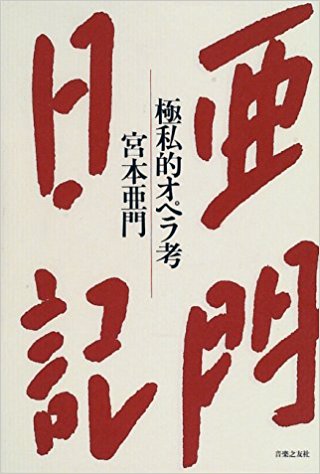
亜門 すごくあのとき面白かったのは、最初はみなさん音楽の素晴らしさを言うんだけれども、話していくうちに、オペラの大変さとか、どうやって観客を増やさなきゃいけないかとか、作りながらの悩みとか、露骨に出てくる。そこにかえって親近感をもちましたね。
林田 いまでもよく思い出すのは、ソプラノ歌手のモンセラート・カバリエと対談したときのこと。大スターなのに、あのときカバリエは自信喪失気味で、すごく神経質になっていて、ホテルの部屋から一歩も外に出られない状態でした。
ところが、亜門さんの「あなたの歌を聴いていると生きていてよかったと思います」という優しい一言で、カバリエの表情がほどけるように柔らかくなり、最後はすごく上機嫌になって買い物に出かけられるほどになった。歌手をあんなに甦らせるなんて、さすが亜門さん演出家だなと思いましたよ。
亜門 あれは彼女の歌で本当に感動したからそう言っただけで。それが伝わったのかなという気がするし。みなさんコンサートでは照明を浴びて、それこそ神のように歌い上げたり指揮をなさる方も多いけど、一人一人会っていくとね、みんな愛おしい人間たちですよね。そこは面白かったなあ。
林田 亜門さんがオペラの演出に常にかかわってくださるのも、新しいオペラ・ファンを作っていくうえで、本当にありがたいことです。
亜門 あまりにもクラシック音楽が素晴らしいので――それは、ただ残っているわけではなくて――時代を越えても存在している理由が、絶対にあるんです。もっといろんな人が聴くべき魅力が詰まっているはずなのにね。それがくやしくて。
聴いてほしい、感じて欲しい、あの瞬間が本当にすごいときがある。というのを知ってもらいたくて。いまでもオペラを作りつづけている理由はそれかなあ。
林田 すごくよくわかります。くやしくて、と亜門さんが言われましたが、こんなに素晴らしいのに、届けたいのに、というくやしさ。すごくあります。
亜門 いまって本当にネットも、テレビのチャンネルも一瞬で変えられてしまう。だからプロデューサーたちも言うけれど、最初の5秒だけでいい音楽か悪い音楽か決めるんだと。
そんなのはまったくばかげたことで、1曲をしっかり聴くっていうことは、ある意味では基本じゃないですか。コンサートでも劇場でも、時間をかけてしんみりそこに入り込む。むしろ瞑想する時間と近い。ある意味教会でもあり、神社でもありという、もっとも大切な場所になってきている気がするんですよ。
林田 すごくわかります。

ショウとビジネスのバランス
林田 ミュージカルや演劇では、いまどんな状況ですか?
亜門 ミュージカルだと、やはり大衆にどう面白く見せるか、考えさせるよりは、とにかくわかりやすく、っていうふうになりかねないですね。エンターテインメントは気を付けないと、ほとんどそうなってしまう。特にブロードウェイで仕事していて思うけど、ショウビジネスという言葉があるなら、ショウよりもビジネスという言葉のほうが上がってきているから、バランスが。
林田 ショウビジネスというのは、ショウとビジネスと二つの性格があるんですね。
亜門 僕はそう思っているけれど。ビジネスがうまくいかないなら、それは成功したとは言えないっていう、アメリカ的な発想になってしまうと、それはいまの視聴率がとれないといい番組ではないというのと同じで、それはまったく意味のない間違いだと思いますよ、両方とも。
いま世界的に、お金を持った人が賢いとか、本当は関係ないはずなのに、そういう間違った基準で物事がはかられてしまうことになっているのは、ミュージカルでも同じです。僕がこんな仕事していていうのもあれだけど、クラシックのほうが可能性があるような気がするんだよなあ。
林田 オペラのすばらしさって、単に芸術というだけでなく大衆的エンターテインメントでもあるところに可能性があると思うんです。モーツァルトにしたところで、最初からそうですよね。
亜門 まったくそう思います。
林田 亜門さんにとって重要な、スティーヴン・ソンドハイムのミュージカルは、どうですか。映画になったり、いろんな局面がありますが、芸術性が高いといわれるじゃないですか。難しいという人もいるけれど。
亜門 ソンドハイムはミュージカルの中でも異色な人で、大衆に迎合するのではなく、というところがあって、その孤高な感覚が僕は好きだし、本質的な人間の裏側の心情というのを、読み解こうとするのはすごいなと思いますけどね。
林田 「リトル・ナイト・ミュージック」も、モーツァルトやシュトラウスに匹敵するくらいオペラ的だと思ったのですが。
亜門 でも、どんどんああいうものがなくなってきましたね。ほとんどのミュージカル・ファンは、ソンドハイムというと、「ええ? 面倒くさい、わからない」となる人が多いです。どこの国に行ってもチケットが売りづらいとなりがちなので。僕の周りの音楽好きのミュージカル・ファンは、オペラに移行していく人が多いですよ、最近では。
林田 ええっ?
亜門 いまの新しいミュージカルではなくて、ソンドハイムとか、ロジャース&ハマースタイン2世も含めてそうだけど、音がリッチな時期というのかな。ていねいに作り上げていった、あの感覚はオペラに期待されるようになってきている。
あとは生の歌の美しさっていうものが――もちろん昔はミュージカルでも生歌だったでしょうけれど――みんなマイクを使うようになって、今度はマイクが中心みたいになってきて。いまのミュージカルはみんな耳が疲れるといって、オペラのほうに行くファンは多いですよね。
林田 そういう意味ではミュージカルもなかなか難しいところに来ている?
亜門 その分、もっと大衆を掴んでいるでしょうね。お客は減っているのではなく増えていると思うし、ただやっぱり受けるものとか、迫力があるリズムとか、そういうものがいまのミュージカルはどうしても求められるからね。
林田 ロックのよく知られた名曲だけでミュージカルを作ったりするじゃないですか。
亜門 ジュークボックス・ミュージカルみたいなものですね。それもパーティとしては楽しい。ミュージカルにはそういうパーティとかフェスティバル的な面白さはもともとあります。ニューヨークで作り上げた、ダンスやオペレッタ、お芝居、と違うものを入れ込んでいるのがミュージカルなので。そういう意味では、その楽しさとして、いろんな形があってもいいとは思います。
ただ、その中での音楽性の比重はだんだんなくなってきていて、ヒットソングが売れればいい、となっちゃいますよね。
オペラとミュージカル、音楽と演劇の境界線
林田 オペラの側の人たちは、ミュージカルに対してまだまだ偏見ももっていると思います。ミュージカルは芸能で、オペラは芸術だ、みたいな。
亜門 僕は生意気だから、ミュージカルでも音の取り方とかうるさくて全部やるんだけど、よほど伝えてあげないと、身体にない、経験にない人たちが多いので。
たとえば、ソンドハイムのミュージカル「スウィーニー・トッド」第1幕ラストのナンバー、3拍子のリズム感の取り方。わざとエレガントな曲の展開になっているがそれはパロディーで、殺人鬼が人肉パイのことをふざけて歌っている。だからそこにどれほどふざけた調子があって、わざとエレガントな顔をしているけれど、ということの意味が本当にわからない人が多い。ワルツを音符で、音節でとらえていくのではなくて、もっと大きなところでとらえていかないと、本当の魅力が出ないじゃないですか。
林田 日本語のミュージカルを、しかも歌の勉強をしてこなかった人たちも含めて、どうやって音楽的にやらせるかっていうのが、これまで亜門さんが直面してきたことなんでしょうね。
亜門 ずっとです。ミュージカルでもオペラでも、大きな壁が目の前に立ちはだかっていると思う。ミュージカルの場合はまだ音楽的なことを言えるんだけど、オペラのときは絶対にそんなことを言っちゃダメなんですよ、稽古場で。マエストロがいる以上、僕が「こう歌ったらどう?」「こういうリズムをつかんでみたら」なんて言ったら大変なことになっちゃうので。
林田 それはデリケートな問題ですね。
亜門 それを言ったら、演出家としては失格になるので。それは言わないんだけど、ただ動きだとか、音について、こういうふうに聴こえませんか? としか言えない。たとえば「フィガロの結婚」の頭、初夜にベッドの寸法をはかるリズムだったら、「なんて微笑んでいて、クスクス笑っているかという、そういうリズムじゃないですか?」とか。そういうふうに言うと、感じやすい人は、音も変わるんです。
林田 まさに、それは音楽の次元ですよね。
亜門 でも、それを感じさせられる演出家か、それとも音符はただの音符と読んでしまうものなのか。面白い演出家って、そこをみんなうまくやっているんですよね。だからその辺は僕はまだまだ勉強中なんですけど。
林田 音楽と演劇の境界線が、一番のキモだったりするわけですよね。なかなか指揮者に神経を使う仕事ですね。
亜門 使いますねえ。でもおかげさまで話せる指揮者が多いので。
林田 逆もあるんじゃないですか。指揮者も演劇に興味をもっていて、演出に何か言いたい人も多いでしょうし。
亜門 やっぱりお芝居に興味がある人のほうが楽しいです。どうしてここにこういう音が来ているんだろう? ということを一緒に探れるというのは、一番幸せなことなので。一音だって意味があるように作りたいじゃないですか。





関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest





















