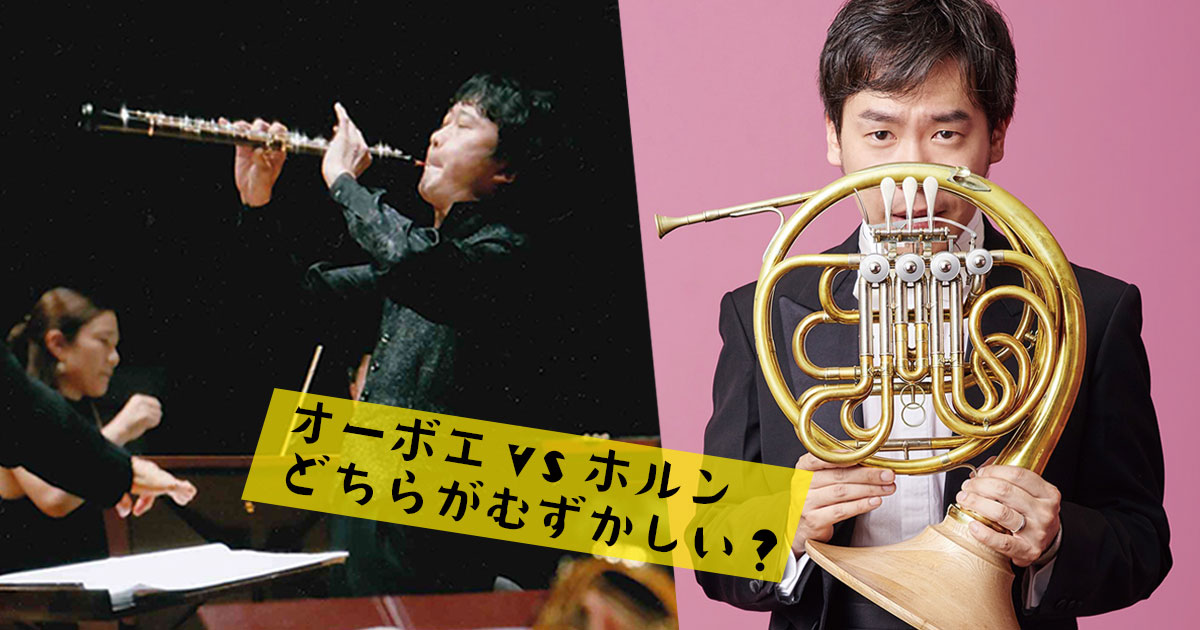『ヘンリー8世』とイギリス史~サン=サーンスとブレイクが描いた王妃の美徳とは?

文豪シェイクスピアの作品を、原作・絵画・音楽の3つの方向から紹介する連載。
第18回は、イギリス史における重要事項が盛りだくさんの『ヘンリー8世』! サン=サーンスのオペラ《アンリ8世》とウィリアム・ブレイクの絵画《王妃キャサリンの夢》から読み解きます。

上智大学大学院文学研究科講師。早稲田大学および同大学エクステンションセンター講師。専門領域は近代イギリスの詩と絵画。著作にシェイクスピアのソネット(十四行詩)を取り上...
16世紀イギリス史の最重要トピックスが盛り込まれたオペラ《アンリ8世》
——秘密は墓場まで持っていく。
思うに、これは人間の美徳のひとつ。ただ、自分のことならともかく、他人様の秘密を黙して語らず、墓場までもっていける人はそうはいない。
たとえば、夫を奪った憎い女の秘密を握りつぶして静かに死んでいく妻は、滅多にいるものではないだろう。また仮にそんなことをされてしまえば、残された側は立場がなくなり、生きてこの世にあるかぎり、罪悪感と敗北感に苛まれ続けることになる。
この意味で、他人の秘密を墓場まで持っていくというのは、己の気持ちひとつでやってやれないことはないにせよ、決して生半可な美徳ではない。むしろそうして敵に塩を送るのは、人間がこの世で示しうるもっとも残酷な美徳にほかならない。
おそらく、観る者誰にも最後にまざまざとそう感じさせるのが、カミーユ・サン=サーンスのオペラ《アンリ8世》である。
本作は、19世紀フランスの作曲家サン=サーンスが、16世紀のイギリス(歴史的には「イングランド」と表記するのが正しいが、慣例にならい国名には以後「イギリス」の語を使用する)を舞台に創り出した全4幕6場の壮大なオペラ。歴史上に実在する国王ヘンリー8世(フランス語のオペラなのでアンリ8世)と王妃キャサリン(仏語カトリーヌ)、王の愛人アン(仏語アンヌ)、そしてアンの元恋人でスペイン大使のドン・ゴメスが織り成す四角関係を軸に、王妃と離婚するための婚姻無効裁判や、ローマ・カトリック教会からの離脱と今に続くイングランド国教会樹立という、16世紀イギリス史の最重要トピックスが次々と扱われてゆく。
サン=サーンス:《アンリ8世》
《アンリ8世》と原作と史実、共通点や相違点は?
これまで紹介してきた数々のシェイクスピア作品からも明らかなように、歴史的真実と芸術的表現は必ずしも一致する必要はなく、サン=サーンスの《アンリ8世》も出来事の時系列がところどころ史実とは異なる。また4人の主役のひとりであるドン・ゴメスなど、まったくの架空の人物だ。

(1832~33年)

リブレット(台本)はサン=サーンス自身が書いているわけではない。また元本についても諸説あって、おそらくは「スペインのシェイクスピア」ともいわれる17世紀の作家ペドロ・カルデロン・デ・ラ・バルカの『イングランドの分裂』(1634年)。
そして、本家本元のシェイクスピアの最後の戯曲、その名も『ヘンリー8世』(1613年、ただしこれは当時の若手劇作家ジョン・フレッチャーとの事実上の共作という説が有力)のふたつがある。
ただ、カルデロンおよびシェイクスピアの原作とサン=サーンスのオペラとの大きな違いはいくつかあって、その最たるものは、オペラではほとんど常識といっていい登場人物の省略。とりわけ、カルデロンとシェイクスピアの作品双方において、そして史実においても、聖職者かつ王の腹心でありながら国の内外で陰謀術数をめぐらし、王のドス黒い猜疑心や嫉妬心をあぶり出す重要な役割を担うウルジー枢機卿が出てこないことだ。
なるほど、ひたすら政治的に複雑な暗躍をする脇筋は、ほかの舞台芸術よりひときわ感覚にうったえるオペラには不向きではあるけれど……。
もちろん共通点もある。イギリス史におけるヘンリー8世といえば、キャサリンとアンを含め、生涯に全部で6人の妃を娶ったことで有名だが、シェイクスピアもカルデロンもサン=サーンスも、後の4人の存在については触れていない。ちなみにサン=サーンスの《アンリ8世》は、約4時間の超大作。もしも残りの妃たちまで扱えば、完全に1日がかりになってしまうから当然といえば当然か。


また6人の王妃たちは、ひとりふたりの例外を除けば概ね不幸な最期を遂げている。なかでも子(後のエリザベス1世)まで為しながら、実の兄を含む複数名との無茶苦茶な姦通罪の疑いで処刑された2番目の王妃アンの死は、かなり悲劇的でドラマティックだ。このアンの処刑についての叙述は、カルデロンの『イングランドの分裂』には見られるものの、シェイクスピアとサン=サーンスの作品には出てこない。
その事情は察するまでもない。シェイクスピアの『ヘンリー8世』は、エリザベス1世没後の作品ではあるけれど、女王の治世に生き、女王の従兄弟がパトロンである一座にいたシェイクスピアが、母の処刑というエリザベス1世にとってもっとも忌まわしき過去に敢えて言及するはずがない。翻って、芝居のかなりの部分が私腹を肥やす権力者ウルジー枢機卿の破滅の物語となっており、性格形成への遠慮からか、女王の父ヘンリー8世が進行役のようになってしまっているのも、むべなるかな。
「王妃の処刑」を省略して国教会樹立をクライマックスに
筋書き通りに芝居の見どころを追ってみれば、さらによくわかる。第1幕第4場、ウルジーの大邸宅で催された宴で、ヘンリー8世はアンを見初め、共にダンスを踊る。このウルジーの館のシーンに関しては、ロンドンのグローブ座での上演中(1613年6月29日)に大砲を使用した演出がたたって火事となり、グローブ座そのものが全焼してしまったという大変有名なエピソードがあるけれど、王とアンの出会いの場面自体は、19世紀イギリスの画家ダニエル・マクリースの絵画そのままに、あくまで王の側からの懸想。まるでシンデレラストーリーは突然に……といった趣だ。

(1835年、個人蔵)
そのまま第2幕と第3幕の婚姻無効裁判を通じて王妃キャサリンが次第に退けられ、やがて、第4幕でアンが正妃となって華麗なる戴冠式を迎えたあと、第5幕終盤で王女エリザベスの誕生がひとしきり祝われる。
She shall be—
But few now living can behold that goodness—
A pattern to all princes living with her,
And all that shall succeed.
この姫こそは――
今生きている者は殆どその栄光を目の当たりにはできますまいが、
姫と同じ時代を生きる君主、そして後に続く
全ての君主たちの鑑とおなりあそばすでしょう。
国教会樹立後、今や聖俗の両面で国王を支える立場となったカンタベリー大主教クランマーの口から、来たるエリザベス1世の御世の輝かしきことが予言され、後のことは一切触れずにそこで幕引き。急転直下の王妃アンの凋落と処刑という史実を知る者からすれば、まったく尻切れトンボもいいところのハッピーエンドである。
だからだろうか。舞台の最後の最後は「この芝居がここにおいでの皆様全員にご満足いただけることは十にひとつもございますまい」というエピローグで締められる。これは当時の芝居につきものだった謙遜交じりの常套句ではあるけれど、不都合な真実に触れずじまいの作者の危惧と弁明が微塵も込められてないと、いったい誰がいい切れるだろう。
このように、シェイクスピアの『ヘンリー8世』の裏側には、致し方ない事情がいろいろと潜んでいる。が、後世かつ無縁の外国人であるサン=サーンスまでもが、オペラにするにはうってつけのドラマ性をもつ「王妃の処刑」を省いているのはなぜなのか。
ヨーロッパの多くの人が知っている、歴史的にあまりに有名な後日談の省略。これはどう考えても、それ以外の、つまりは王妃処刑以前の重要な出来事に焦点を当てるため。やはりカルデロンとシェイクスピアがともにプロットの中心に据えている宗教上の対立——イギリスにおいては国王夫妻の離婚問題として顕在化し、国教会成立という結実をみた「宗教改革」をクライマックスシーンとするためだ。
16世紀イギリス音楽を研究し、イギリス史の核心を突くサン=サーンス
実際、フランス人であることが俄かに信じがたいほど(失礼!)、サン=サーンスは《アンリ8世》において、イギリスの歴史に真摯に取り組み、その表現に全精力を注いでいる。
たとえば、それまでもっぱら筆の速さで鳴らしていた彼は、この《アンリ8世》作曲に関しては意識して腰を据え、ウィリアム・バードの「カーマンの笛」その他の16世紀イギリス・ルネサンス音楽を地道に勉強することから始めている。そして、それらのモチーフが前奏曲や第2幕最後のバレエシーンなど随所に散りばめられ、16世紀の宮廷の臨場感を高めていることは、サン=サーンス研究で知られるイギリスの音楽学者ヒュー・マクドナルドが折に触れ指摘してきたとおりだ。
ただし、フランス人サン=サーンスがイギリス史の核心部分をこれ以上なく鋭く突き、熱く盛り上げているのは、終盤でイングランド国教会樹立が高らかに宣言される《アンリ8世》第3幕だろう。ここはもともと王妃との婚姻無効裁判シーンで、主役たちによる長大なアリアや重唱、そして居並ぶ廷臣たちによる合唱が、それぞれ証言や弁論ないし賛否の意として機能していて大変わかりやすい。
一貫して王妃を弁護するスペイン大使ドン・ゴメスが(王妃はスペイン生まれ)、このままでは戦争も辞さない旨訴えたところで裁判は紛糾し、頑として離婚を許さぬローマ教皇特使によって、ついにアンリ8世は破門宣告を受ける。本オペラではこの瞬間をもって、王が新教イングランド国教会を樹立し、続いて臣民たちの王への忠誠と愛国心の表明として、荘厳なアンサンブル・フィナーレ「かくして事成りき!(C’en est donc fait!)」が歌われる。第3幕最後のこの大アンサンブルこそは、国教会樹立すなわちイギリス宗教改革の歴史的意義を、サン=サーンスという作曲家自身が理解し重視していた何よりの証だ。
サン=サーンス《アンリ8世》より「かくして事成りき!」
王妃カトリーヌのアリアとブレイクの絵画《王妃キャサリンの夢》
しかしながら、最大の見せ場であるこのアンサンブルに加わらない——いや、到底加わることなどできず、とてもいたたまれずに、その場をそっと立ち去る人物がふたりいる。
それはもちろん、事実上離婚された王妃カトリーヌとドン・ゴメス。失意の王妃はロンドンを去り、イングランド東部のキンボルトン城での蟄居隠遁を余儀なくされて、その孤独な日々の中で徐々に命をすり減らしていく。
第4幕第2場が始まって間もなく歌われる王妃のアリア「もう二度と会うことはないでしょう(Je ne te reverrai jamais)」の痛切な響き、哀切な望郷の調べは、幸過ぎ去りしこの世で彼女に遺された時間の短さ、儚さを伝えて余りある。
サン=サーンス《アンリ8世》より「もう二度と会うことはないでしょう」
このアリアはオペラ《アンリ8世》独自のものだが、シェイクスピアの『ヘンリー8世』に相当する箇所はないのかと問われれば、実はある。確かにある。それは第4幕第2場。キャサリンが眠りに落ち、白いローブをまとった6人の天使たちから月桂冠を被せてもらう夢を見る場面だ。
No? Saw you not, even now, a blessed troop
Invite me to a banquet; whose bright faces
Cast thousand beams upon me, like the sun?
They promis’d me eternal happiness,
And brought me garlands,
見えなかった?たった今、天使たちが私を
祝宴に招いて、その輝く顔から無数の光を投げかけてくれたの、
まるで太陽みたいによ?
そして月桂冠を持ってきて、
永遠の幸福を約束してくれたわ、
「天使たち」に「祝宴」に招かれ、「永遠の幸福を約束」されることが何を意味するかは、いうまでもないだろう。今生での苦悩と引き換えに、至福の最期を迎えんとする王妃のビジョン——おそらくは『ヘンリー8世』のなかでもっとも聖なるこの場面を絵にしているのが、イギリス・ロマン派の詩人にして画家ウィリアム・ブレイクである。

(1825年、ワシントン・ナショナル・ギャラリー蔵)
いささか独特な画風なので好き嫌いは分かれるだろうが、イギリスの数多の芸術家のなかでも、彼ほど宗教的な人物はいない。そういっても過言でないほど、詩にせよ絵にせよ版画にせよ、ブレイクの作品世界には常に聖なるものへの憧れが横溢していて、この《王妃キャサリンの夢》とて、もちろん例外ではない。
シェイクスピアのテクスト上では6人となっている天使たちの数は、ブレイクの絵ではさらに多くなっており、床から天井まで螺旋状に描かれている。これら螺旋状の天使の群れは、カウチの上で両手を広げ天を仰ぐキャサリンの姿と相まって、鑑賞者の目にはあたかも被昇天(聖母マリアの昇天)図のように映る。
カトリーヌが魅せる復讐と美徳
ただし、ブレイクの描いたこのシェイクスピアのキャサリン王妃以上に、最後になって聖母もかくやの徳の高さを見せるのが、サン=サーンスのオペラの中の王妃カトリーヌだ。
彼女から愛する夫を奪い、新たに妃となったアンヌは、元は彼女付きの女官。昔の恋人ドン・ゴメスとの仲を取り持ってやったのは、主であったほかならぬカトリーヌであって、親切かつ慎重な仲介役だった彼女は、当時の恋文をまだ手元に持っていた。
オペラの終盤、アンヌはその露見を恐れて密かにカトリーヌの元を訪れ、新妻とドン・ゴメスとの仲を訝しく思うアンリ8世もあとを追ってやってきて、さかんに探りを入れるのだが、カトリーヌは頑として口を割らない。
そして4人の心理的葛藤がもつれあう四重唱として響き渡るなか、カトリーヌは最後の切り札といっていいはずの証拠の手紙をみずから暖炉の火にくべて燃やした後、息絶える。

彼女が「裏切ったことは決して許さない」とアンヌを責めながらも、真実を何もいわずに死んでいったのは、とりもなおさず同郷のスペイン大使ドン・ゴメスを守るため。でも、果たして本当にそれだけだったか。少なくとも結果的には、カトリーヌは愛する夫を奪った憎い女に永遠に恩を売り、冷たい夫には真実を永遠に伏せることで心の平安を奪う格好になった。ただ黙して語らず、静かに死んでいくことで。
「秘密を墓場まで持っていきおったな!」
こんなふうに王は苛立ち、新たな妃は怯えきったまま《アンリ8世》の幕は下りてゆく。
裏切りの代償として生きてこの世にあるかぎり続く、怒りと苛立ち、怯えと恐れ——。どうやら人間の美徳とは、完璧な復讐に必要なものでもあるらしい。





関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest