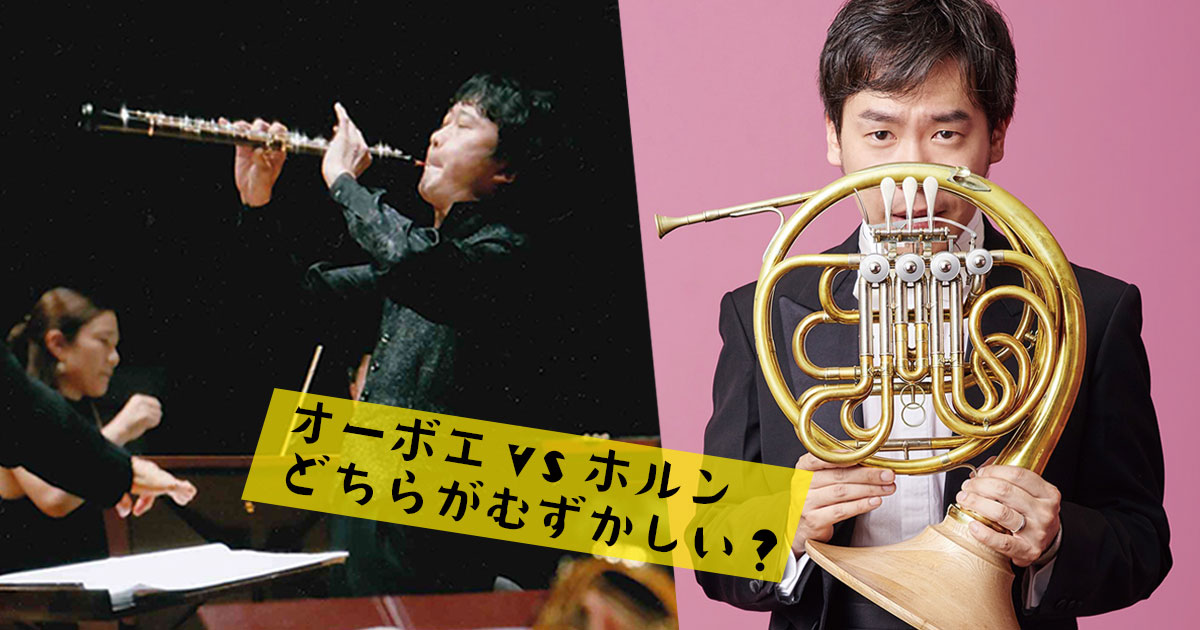『ヘンリー5世』でシェイクスピア、ウォルトン、ギルバートが描いた「不都合な真実」

文豪シェイクスピアの作品を、原作・絵画・音楽の3つの方向から紹介する連載。
第20回は『ヘンリー5世』の「アジンコートの戦い」を中心に、ローレンス・オリヴィエの映画とウォルトンによるその音楽、そしてギルバートの絵画から読み解きます。英国史上もっとも輝かしい瞬間のひとつとされる「アジンコートの戦い」。その背後に隠された「不都合な真実」と王が抱える苦しみとは?

上智大学大学院文学研究科講師。早稲田大学および同大学エクステンションセンター講師。専門領域は近代イギリスの詩と絵画。著作にシェイクスピアのソネット(十四行詩)を取り上...
名優が魅せたヘンリー5世の憂いと苦悶
今でもずっと忘れられない光景がある。
あれは1997年の夏。シェイクスピアが活躍していた16世紀当時の劇場そのままに、ロンドンのテムズ川南岸サザークに再建されたグローブ座のこけら落とし『ヘンリー5世』上演中のこと。
まさしく16世紀風の、地面むき出しの土間の立見席(要するに1番安い席)の1番前に陣取って、当時の庶民よろしく張り出し舞台にかじりつくように芝居を観ていると、中盤あたりで背後の観客席から結構なブーイングと、続けて確かにそうとわかるフランス語のヤジが飛んできた。
声のする2階椅子席のほうを振り返れば、そこにはフランスからと思しき団体客。なるほど、シェイクスピアの『ヘンリー5世』は、中世の英仏百年戦争に基づく愛国的な歴史劇で、フランスは敵。とりわけ劇中盤の第3幕は、略奪など諸々の戦争犯罪への明らかな言及があり、「イギリス兵ひとりはフランス兵3人に匹敵する」(第6場)といった高言が飛び出すなど、フランス人ならとても黙ってはいられない場面が多々ある。
ただ地の利もあって、この時は文字どおり役者のほうが一枚上手。主役ヘンリー5世を演じていたマーク・ライランスは、件のフランス人団体客のほうに向かってやおら膝を折り、うやうやしく一礼して、いとも自然かつ優雅にその場をとりなしてしまった。主演だけでなくグローブ座の芸術監督も兼ねていた当代きっての名優の矜持、そこから生まれる観客との自由気ままな関係をも楽しめる余裕が、一斉の拍手を誘ったことはいうまでもない。

しかし実のところ、ライランスの『ヘンリー5世』で、25年が過ぎた今も本当に忘れられず、折に触れ思い出すのは、名優が見せた余裕ではなく苦悩。はしたなくも「かぶりつき」の至近距離で見ていたせいで、ライランス演じるヘンリー5世に終始つきまとって離れなかった憂いと翳り、芝居が進むにつれて深まっていった苦悶の表情が、強烈に印象に残っている。
それこそが王者の悲哀というものであり、「王の責任」の重さという『ヘンリー5世』ならびにシェイクスピアの歴史劇の核心を突く演技であったと気づいたのはいつだったか。今にして思えば、あのときのライランスはたしかに、そして完璧に、王の苦悩と絶望を表現していた……。
ローレンス・オリヴィエが最高と絶賛したウォルトンの映画音楽
先に述べたとおり、シェイクスピアの『ヘンリー5世』は、たしかに愛国的な作品で、ほぼ全編を通じて、国家の称揚と輝かしい軍事的勝利のイメージに満ちている。ために、ヘンリー5世が形勢不利に陥った自国軍に向かって叫ぶ「もう一度あの突破口へ突撃だ、諸君、もう一度(Once more unto the breach, dear friends, once more;)」という第3幕第1場の有名なセリフは、第二次世界大戦中に徹底抗戦のスローガンとして使われたほど。
もっと有名な例を挙げれば、先のライランスの大先輩にあたるシェイクスピア俳優、かのローレンス・オリヴィエ監督・主演の映画『ヘンリー5世』が制作・公開されたのも、やはり第二次大戦中(1944年)のこと。これが国威発揚のための事実上の国策映画であったことは、やはりオリヴィエ制作の映画《リチャード3世》を取り上げた以前の連載「『リチャード3世』の名場面を絵画と映画で読み解く〜作曲家ウォルトンが描く王冠」でも触れたとおり。
『リチャード3世』でもそうだったが、オリヴィエがらみのシェイクスピア作品に欠かせないのが、同時代の作曲家ウィリアム・ウォルトンの音楽で、それはもちろん『ヘンリー5世』も例外ではない。国王の戴冠であれ戦争の勝利であれ、王者の輝かしい栄光というものを余すところなく表現する古風なまでの壮大さが、ウォルトンの音楽の最大の魅力。この意味で、同種の特徴をたたえる国民的作曲家だったエドワード・エルガー亡きあとの20世紀半ばにあって、ウォルトンほど『ヘンリー5世』の映画音楽に相応しい人物もいなかった。そういっても過言ではないだろう。
ウォルトン:映画『ヘンリー5世』
事実、ウォルトンの作った『ヘンリー5世』の付随音楽を「今まで聴いてきた映画音楽の中で最高」とオリヴィエが絶賛していたというのは、後年『タイムズ』紙が報じたウォルトン夫人の弁(1987年12月29日付)。おそらくこれは誇張でもなければ、内輪褒めでもあるまい。時代の制約はうんと考慮しなければならないが、今日的観点からすると、なにしろ不自然なセットの多用が目につく『ヘンリー5世』の映画としての完成度は、随所で映像をドラマティックに盛り上げるウォルトンの音楽の力に負うところが大きい。
セットではなく、アイルランドで何百人もの地元の人びとをエキストラに雇ってロケを敢行した「アジンコートの戦い」のシーンにしても同じこと。打楽器と金管楽器が華やかに打ち鳴らされるウォルトンの音楽がなかったら、史実とはいえ、敵の騎兵の足を止めるべく地面にひたすら杭を打ち込み続ける土方めいたイングランド歩兵の姿や、人馬が入り乱れるばかりの地味で粗いカット割りの映像を、どれだけの人が見続けていられるだろう。
映画『ヘンリー5世』のトレイラー
アジンコートの戦いを華やかに表したウォルトン
実際には1415年10月25日、フランス北部アジャンクール(英語読みだとアジンコート)で行なわれたこの英仏決戦での勝利は、もう長いこと、イングランドの歴史上もっとも輝かしい瞬間のひとつに数えられてきた。無理もない。なにせ4対1と数のうえで圧倒的に優位だったフランス重装騎兵部隊を相手に、ウェールズ由来の長弓(成人男性の背丈ほどもある大きな弓で、引き絞るのに約30キロもの力を要し、結果として抜群の破壊力を誇る)を駆使した泥臭い弓兵戦法で、ヘンリー5世率いるイングランド軍は奇跡的に圧勝したのだから。
その栄光の瞬間を表現したウォルトン作曲の「アジンコート・ソング」は、映画『ヘンリー5世』の中でもとびきり華やかな1曲。全部で2時間あまりの映画の最後部、フランス軍伝令が現れて「勝利は陛下のものです(The Day is yours.)」とヘンリー5世に告げる1時間48分を過ぎたあたりで、画面いっぱいに映し出される白地に赤十字のイングランド国旗「セント・ジョージ・クロス」の映像とともに、バーンと一気に流れだす。
ウォルトン:映画『ヘンリー5世』より「アジンコート・ソング」
元来ウォルトンが映画音楽を映像と切り離すことに否定的だったことを考えれば、国旗の画像と抱き合わせの「アジンコート・ソング」の使用はあまりに決定的。本ナンバーが映画『ヘンリー5世』最大のテーマ曲であることを表して余りある。映画のサウンドトラックを指揮したミューア・マシソンが、ウォルトン本人の許可を得て後に編曲した《ヘンリー5世組曲》(1963年)でも、全5曲の大トリを飾っているのは当然だ。
ウォルトン:《ヘンリー5世組曲》
ギルバートが大胆な構図で描くアジンコートの戦い
しかし今も昔も、現実の戦場にウォルトンの雄渾な調べが流れてくるわけではない。むしろ19世紀イギリスの画家、ジョン・ギルバートの描いた《1415年10月25日、アジンコートの戦いの朝》のように、目の前には音らしい音もなく、寒々とした光景が広がるばかりのはずである。
ギルバートはシェイクスピア作品に基づく文学的絵画を数多く手がけているが、この絵は戯曲『ヘンリー五世』の一場面ではなく、史実としてのアジンコートの戦いを後世の視点から描いたもの。いわゆる「歴史画」だ。
タイトルにもなっている1415年10月25日からさかのぼること約2週間前、セーヌ河口アルフルール(英語読みではハーフラー)攻略中のヘンリー5世旗下イングランド軍では、実は疫病が流行して兵力が削がれており、これ以上被害を大きくしないため、ヘンリー5世は退却戦を余儀なくされていた。しかもその退却行軍の途中、目的地であるフランス最北端カレーの50キロ手前では、すでにフランス軍が待ち受けていたのである。そんな想定外の不利な状況下で雌雄を決することになってしまったのが、史実としての「アジンコートの戦い」の背景にほかならない。

このイングランド軍のいささか不都合な真実を、後世の画家ギルバートは、決戦の日の朝の必勝祈願という状況設定により、臨場感と迫真性たっぷりに描くことに成功している。
歴史的テーマにふさわしい重たげな色づかいに、広範囲の漸次的なキアロスクーロ(陰影法)。そしてそれらを最大限に活かす大胆な構図が、水彩・油彩を合わせれば400点をゆうに超えるギルバート作品に共通する特徴。
本作の場合、そのおかげで真っ先に目に飛び込んでくるのが画面右手前の騎兵たち。馬上の男たちはもちろん、彼らが跨る軍馬の毛並みを見れば、画中の命あるもの誰も彼もがひどく疲れ果てているとすぐにわかる。さらに遠く近くに目を凝らせば、曇天の下にちらつく赤や黄色の軍旗もまた、揃いも揃って見るも無残なボロ切れ状態。
軍旗までこれでは、歴戦の雄たる騎兵たちが追い詰められ、疲れ切っているのも無理はない。画面左奥、徴兵されて連れてこられたと思しき一兵卒たちにいたっては、もはや残された力の限りに深々と祈りを捧げることしかできない極限状態なのだと納得もいく。
こんなふうに皆が気落ちし、疲労困憊しているなかで、可能な限り兵力を温存しながら退却しつつ、生還のために戦い続ける。それが兵以上に将たる者にとって、一体どれだけ重い苦難としてのしかかり、その肉体以上に精神にどれほどの負担を強いることか——。
華やかな英雄譚に仕上げながらも不都合な真実を突き付けるシェイクスピア
歴史的事実として、ヘンリー5世はあらゆる戦いのなかでももっとも困難といわれる退却戦のなかでアジンコートの決戦の日を迎えたのであり、シェイクスピアはその史実をもとに、先の「もう一度突破口へ突撃だ」をはじめとする『ヘンリー5世』の数々の力強い名セリフを生み出した。
史実上でも作品中でも、アジンコートの戦い当時のヘンリー5世を取り巻く状況は、基本的に苛酷を極める。そもそも彼の場合、簒奪者の息子(父ヘンリー4世は王家の血筋とはいえ、元は前王リチャード2世の臣下であり、反乱を起こして即位した)という出自からしてそうなのだ。自己の王位の正統性を主張するなら、力を示すしかない。誰よりも優れていると証明するため、勝ち続けるよりほかはない。そんな苛酷な人生がどこにある?
ことほどさように、ヘンリー5世という国王に関しては、本来何もかもが決して綺麗事ではない。だからこそ、シェイクスピアは各幕の冒頭におそろしく修辞的な序詞をつけ、史劇としての『ヘンリー5世』を全体として華やかな英雄譚に仕上げながらも、ギルバートの絵画同様、こんなセリフでひどく不都合な真実を突き付けずにはいられなかった。
I am afeard there are few die well
that die in a battle; for how can they charitably
dispose of anything when blood is their argu-
ment? Now, if these men do not die well, it
will be a black matter for the king that led them
to it,
どうせ戦ではほとんど誰もろくな死に方なんか
しちゃいない。だって血を流すのが何より肝要な場面で、
何をどうやって慈悲をもって片づけられるっていうんだよ?
でもって、ろくな死に方しなかった奴らがいるとなれば、
そいつはもうそういう目に遭わせた王様に大いに問題があるわけさ。
これはアジンコートの戦いを目前に控えた第4幕第1場、下級兵士に扮して野営地を回っていたヘンリー5世に、そうとは知らぬ一兵卒が投げつける言葉。疲れ切った兵たちを励まし、その本音を探るつもりが、思いがけず自己の責任を問われる格好となり、続けて王である彼もまた、たまらず本音を吐き出してゆく。
Upon the king! let us our lives, our souls,
Our debts, our careful wives,
Our children, and our sins lay on the king!
We must bear all. O hard condition!
王の責任か! 我ら一同の命も、魂も、借金も、
心配してやまない妻も、子らも、犯した罪までも、
すべて王の責任にすればよい! 我ら王は
すべてを背負わねばならぬ。おお苛酷なことよ!
これは王の苦悩と絶望の告白だ。ヘンリー5世がどんなに力強く仲間を鼓舞したところで、ギルバートの絵のように身も心もボロボロになってまでフランスと戦うことの意味と意義を疑う兵士たちを黙らせ、「血を流すのが何より肝要」な戦争への不満と反対の声を完全に押し殺すことはできない。彼だけでなく、いつの時代のどの国の為政者にも、それはおそらく絶対に、そして永遠に不可能なこと。シェイクスピアはヘンリー5世に「We(我ら王は)」という一人称複数で敢えて語らせることで、暗にそのことを伝えているのだろうか。
今から四半世紀も前の舞台で、名優ライランスが確かに表現していた王の苦悩と絶望。その憂いと翳り。それは第二次世界大戦中、国威発揚のために作られた映画でヘンリー5世を演じるオリヴィエの整った顔には、残念ながらほとんど見られない。むしろ映像ではなく音楽に、《ヘンリー5世組曲》でいえば国王本人ではなく、王の若き日の悪友の死を表現した荘重な第2曲「パッサカリア、フォルスタッフの死」や、フランス王女への求婚をイメージした繊細な第4曲「彼女の柔き唇に触れて別れん」に認められるものだ。
ウォルトン:《ヘンリー5世組曲》より第2曲「パッサカリア、フォルスタッフの死」、第4曲「彼女の柔き唇に触れて別れん」
派手で晴れやかな金管と打楽器を封印したこれら2曲は、映像と音楽の不可分を主張していたウォルトン自身が初めから、弦楽のみでの演奏を許可していた。そうして盟友オリヴィエが図らずも忘れてしまったもの、本来『ヘンリー5世』にあって然るべき憂いと翳りを結果的に人知れず補っているところもまた、いかにもウォルトンの音楽らしい。





関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest