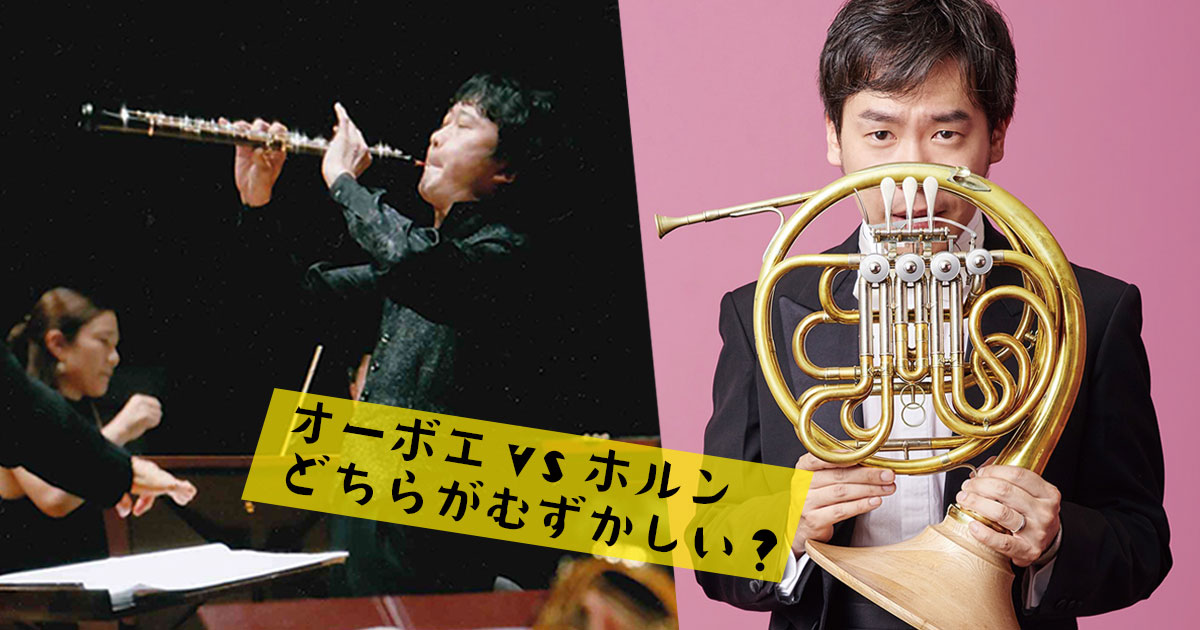シェイクスピア『ヘンリー4世』で描かれた人生の転機とエルガーの音楽

文豪シェイクスピアの作品を、原作・絵画・音楽の3つの方向から紹介する連載。
第9回は、『ヘンリー4世』でひときわ人間味あふれる登場人物・フォルスタッフに着目。ヴェルディのオペラ《ファルスタッフ》も傑作ですが、今回はあえてエルガーの音楽作品を取り上げフォルスタッフの主題を聴き、さらにロバート・スマークの絵画から読み解きます。

上智大学大学院文学研究科講師。早稲田大学および同大学エクステンションセンター講師。専門領域は近代イギリスの詩と絵画。著作にシェイクスピアのソネット(十四行詩)を取り上...
登場人物のキャラが立つ『ヘンリー4世』
人生の転機——それは必ず誰のうえにも訪れる。問題は実際に転機が訪れたとして、今がそのときと気づくことができるかどうか。
別に焦ることはない。変に身構える必要もない。にわかに変わり始めた潮の流れを見定めて、そのまま舵を切る船乗りの如きリアリストでありさえすれば、次や先の道にいたずらに迷わずに済むのだろう、きっと。
たとえていうなら、最後の最後でこう信じるしかない展開になっているのが、全2部からなるシェイクスピアの歴史劇『ヘンリー4世』。この芝居に基づいて作られた、近代イギリスを代表する作曲家エドワード・エルガーの交響的習作《フォルスタッフ》も然り。
ともにテーマは、いつか来ると誰もがわかっていた転機の訪れ。それが分かつ人生の明暗である。
国王の名前を冠したシェイクスピアの歴史劇は、実は時系列では書かれておらず、基本的に子孫が先でご先祖が後。前回取り上げた『ヘンリー6世』3部作が最初の作品群で、それから5、6年の月日が経ち、劇作家として脂の乗り切った時期に書かれたのが、『ヘンリー4世』全2部だ。ヘンリー6世の祖父ヘンリー4世と、ハル王子こと若き日の父ヘンリー5世が登場する。
だから芝居としては、『ヘンリー6世』よりあとに書かれた『ヘンリー4世』のほうが俄然面白い。何が違うって、登場人物の性格形成のレベルが段違い。今風にいえば「キャラ立ち」が凄いのだ。
「人間らしさ」を体現するフォルスタッフ
その最たるものが、『ヘンリー4世』1部・2部を通して登場するフォルスタッフという大酒飲みの巨漢の騎士。彼はハル王子の、いわば飲む・打つ方面専門の悪い遊び仲間で、舞台上で機知と滑稽を振りまいては、観客を笑いの渦に巻き込んでゆく。いやそればかりか、いつのまにか深い思索の淵へと引きずり込まずにはおかない。
たとえば『ヘンリー4世』第1部・5幕1場の最後で、王に対し挙兵した反乱軍と、それを迎え撃つハル王子の軍勢がイングランド中西部シュールズベリーで雌雄を決する場面。ここは舞台のクライマックスとなる重要な戦闘シーンなのだが、従軍中のフォルスタッフはあろうことか「名誉が何だ? たかが言葉だろ」と、王位継承者として国のために戦っている最中のハル王子を尻目に毒づく。あまつさえ、戦場で死んだふりまでして生き延びようとするのだから、「名誉が何だ?」という独白は間違いなくフォルスタッフの本心。そんなものどうだっていいと、でっぷりとした腹の底から思っているのがよくわかる。
こんなふうに、なりふり構わず生き延びようとするフォルスタッフを、騎士の風上にも置けぬ浅ましいヤツと見切りをつけるのは簡単。ある意味それで当たり前だし、そこは読者や観客の完全なる自由だ。けれど、彼が実のところ体現しているのは人間的臭味。つまりは、情けなくて駄目なところまで含めた「人間らしさ」というシェイクスピア劇の醍醐味にほかならない。
だからエルガーも、彼をテーマにその名も《フォルスタッフ》という曲を書いた。全4部からなる本作の第1部には、それぞれフォルスタッフとハル王子を表現する2つの主題が登場するが、いかにもエルガーらしい優雅で壮大な調子で、さまざまに装飾を施され繰り返されるハル王子の華やかな主題に比べて、冒頭に置かれたフォルスタッフの旋律は何ともユニーク。
のっしのっしと巨体を揺らして歩くが如き低音のバスクラリネットは、名誉やら騎士道やらの綺麗事に命まで懸けて生きる意味を見出せず、面倒なことは全部後回しにして生きる男の、横柄なまでの無頓着ぶりを表して余りある。
ハル王子に訪れる転機
しかし、人間どうしたって好き勝手には生きられない。仮に今までずっとそうしてこられたからといって、それが永遠に続くわけがない。誰のもとにも転機が、それぞれの背負う現実と向き合う瞬間が必ずやってくる。『ヘンリー4世』第1部・1幕2場で、フォルスタッフらと放蕩に耽っているはずのハル王子が退場間際、くしくも最後に醒めた目でこう告げるように——。
I‘ll so offend to make offence a skill;
Redeeming time when men think least I will.
私が悪い遊びに耽るのは 一種の手練手管、
皆が思いもよらぬときに 一気に時を償うのだ。
父王や周囲の心配をよそに、フォルスタッフらとつるんでは居酒屋に入り浸り、放蕩者を絵に描いたような生活を送っていたハル王子。だが、それはあくまで仮の姿であり、周囲を煙に巻くためのポーズであるという言質がこれ。
そもそも「時を償う(Redeeming time)」とは、初めユダヤ教徒としてキリストを迫害しながら後に回心した聖パウロの言葉(『エフェソス人への手紙』第5章16節)であって、やがて「パウロの回心」ならぬ「ハルの改心」のシーンが訪れることは、この時点でわかる人にはわかる仕組みだ。
実在のハル王子、すなわち即位前のヘンリー5世のご乱行を裏付ける決定的な史実は見あたらない。が、うつけものと呼ばれながら、のちに天下人まで上り詰めた本邦の織田信長よろしく、シェイクスピアのハル王子はやがて王位継承者としての自覚のもとに正道に立ち返り、中世イギリス最大の英雄ヘンリー5世として、対仏百年戦争の輝かしい勝利を手にすることになる。その重要な伏線として、シェイクスピアはわざわざ聖パウロの言葉をお借りしてまで、ハル王子に「時を償う」と、言質めかしてきっちりいわせているのである。
ヘンリー5世となったハル王子、フォルスタッフへの態度が物議を醸す
シェイクスピアが冷たいほど鮮やかにこの伏線を回収するのは、芝居の最後の最後。『ヘンリー4世』第2部・5幕5場の、ヘンリー4世崩御にともなう新国王即位の場面である。
——お前など知らぬ。
ヘンリー5世即位の報に接するや否や、昔のよしみでの昇進を期待し、急ぎロンドンに駆けつけたフォルスタッフを、かつてのハル王子ことヘンリー5世はこういって突き放す。
さらに「私は生まれ変わった、かつての私は捨てた、同じく昔の仲間も捨てる」とまで言葉を重ね、フォルスタッフを徹底的に打ちのめす。これは更生や改心というより、むしろ変節や転向といったほうがしっくりくるくらいの人間性の急変で、この態度は人としていかがなものかという議論は昔から絶えない。
絵画と音楽に描かれるフォルスタッフの末路
ただ、この場面を絵画化した18世紀イギリスの画家、ロバート・スマークの《譴責(けんせき)されるフォルスタッフ》が示すとおり、ハル王子はもはや王。まごうことなき為政者だ。王冠とガーター頸飾を身に着け、王笏(おうしゃく/杖)を手にする彼の背、すなわち画面の背景には、今に続く王室付属聖堂たるウェストミンスター・アビーと思しき建築物の姿も見える。

代々の国王の戴冠式を行なうこの場所で、いったん王として聖別されたら、言葉は悪いが決して普通の人生は送れない。王になる前のように、二度と自分の好きなようには生きられない。
それは誰よりハル王子自身が知っていたこと。「お前など知らぬ」と吐き捨てた瞬間、彼はフォルスタッフ含め、それまでの自身の過去すべてと本当に決別したのだ。そしていずれ「時を償う」と述べていたとおり、今このときを自身の転機と見定め、背負うべき王国という現実に回帰したのである。
芝居の流れ同様、エルガーの《フォルスタッフ》も、自らの背負う現実に回帰するハル王子の主題を、最後に繰り返して終わってゆく。この曲にひときわ強い思い入れを抱き、イギリス最古の伝統ある音楽専門誌『ミュージカル・タイムズ』(1913年9月1日号)に自ら解説文まで寄稿したエルガーの言葉を借りれば、ハル王子の主題のリフレインは「強固な現実主義者の勝利」を示したもの。正直、人としてどうかとは思うが、やはりハル王子並みの冷徹なリアリストでなければ、最後に勝つことなどできないのだろう、きっと。
エルガー《フォルスタッフ》の終曲「フォルスタッフの否認と死」





関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest