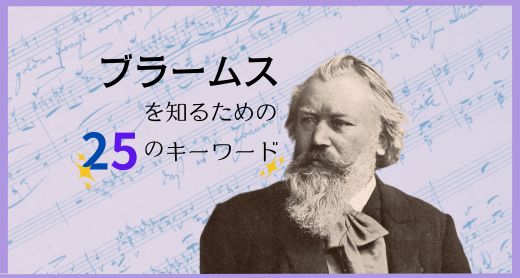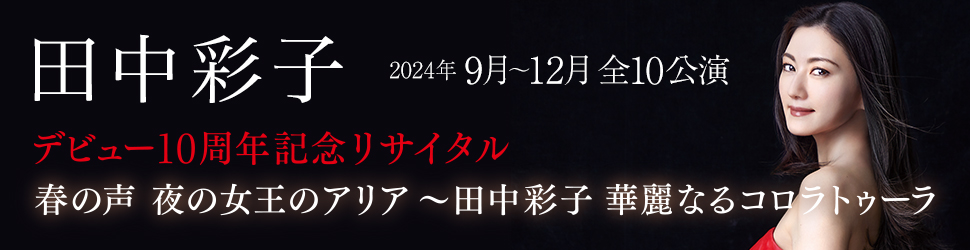ジャズピアニスト大西順子〜ピアノとの出会い、小澤征爾・村上春樹との逸話、音楽観

ジャズピアニスト大西順子——言わずと知れた近年のジャズ界をリードする存在ですが、クラシック音楽ファンには、2013年に小澤征爾指揮サイトウ・キネン・オーケストラと《ラプソディー・イン・ブルー》で共演した印象が残っている人も多いかもしれません。
華やかなイメージがありながら、自らのピアノや音楽に妥協せずに、引退や活動休止も挟みながら新しいことに挑戦してきた大西順子に、そのピアノや音楽への思い、クラシック音楽をどう見ているかを伺いました。

大学院でインドのスラムの自立支援プロジェクトを研究。その後、2005年からピアノ専門誌の編集者として国内外でピアニストの取材を行なう。2011年よりフリーランスで活動...

1967年京都生まれ。東京に育つ。1989年、バークリー音楽大学を卒業、ニューヨークを中心にプロとしての活動を開始。1993年1月、デビュー・アルバム『ワウ WOW』がスイングジャーナル誌ジャズ・ディスク大賞日本ジャズ賞を受賞。1994年4月、セカンド・アルバム『クルージン』が米国ブルーノートより発売。5月、NYの名門ジャズ・クラブ“ビレッジ・バンガード”に日本人として初めて自己のグループを率いて出演。2000年3月突然の長期休養宣言。2007年、活動再開。2009年7月にアルバム『楽興の時/Musical Moments』をリリース。2010年3月には新作『バロック』をニューヨークでレコーディング。2012年夏、突然の引退宣言。
2013年9月「サイトウ・キネン・フェスティバル松本」へ出演。小澤征爾氏の猛烈な誘いに負け、一夜限りの復活とし出演を決める。小澤征爾率いるサイトウ・ キネン・オーケストラと大西順子トリオの共演は、大きな話題に。最新アルバムは2021年12月リリースの『Grand Voyage』。
幼少期に出会い離れられなくなったピアノ
——幼少期から振り返って、ご自身とピアノの関係はどう変化していますか?
大西 遠のいたり近づいたり角度がかわったり、いろいろなことがあった間柄です。ただ、好きだということは変わりませんね。
——ピアノが好きだと感じた最初の記憶はありますか?
大西 ありますよ! 父親が自衛隊だったので官舎に住んでいた時期があって、上の階の家のお嬢さんがピアノを習っていたのですが、聴こえてくる音に憧れて、しょっちゅうそのお宅にお邪魔してピアノを聴いていました。4歳頃ですね。そうしたらその家のお母さんが、こんなに好きなら習わせたらと親に言ってくれて、近所の教室に通うようになりました。
最初は、続くかわからないからと、オルガンをレンタルしました。ずっとそこから離れないので、ようやくアップライトピアノを買ってもらったら、余計離れなくなってしまって、ピアノに鍵をかけられたこともあったらしいです(笑)。
新編成したカルテットでの大西順子さんのピアノ(2021年2月)
本場ニューヨークで接した「きれいごとでは収まらない」ジャズ
——やがてジャズに目覚め、高校卒業後、ボストンのバークリー音楽院に留学されます。多感な時期にアメリカで受けた刺激は、今思い返すと、どのようなものでしたか?
大西 やはり大きいですね。当時はまだソビエトがあって、大学には亡命してきている学生もいれば、東南アジアのお金持ちのお坊ちゃんもいて、普通の都立高校生だった私からするとカルチャーショックでした。
私は、ベルリンの壁が崩壊したと同時にプロになって、1989年にニューヨークに移りました。当時は景気がとても悪く、ベトナム戦争の影響も引きずっていて、街角で身体に障害を抱えた帰還兵の方が物乞いをしている姿も見かけました。治安も悪く、街が暗かったですね。
ライブハウスの仕事は夜ですから、終わるのは深夜2時。今のおしゃれなイメージからは程遠いブルックリンに住んでいたので、地下鉄で帰るのが本当に怖かったです。二度と日本に帰れないんじゃないかと思いながら暮らしていました。
大西さんが当時共演していたジャズメンより、ベティ・カーター(ヴォーカル)、ジョー・ヘンダーソン(テナーサックス)
国内の景気は悪いから、お金を稼ぐために海外ツアーをするのですが、東ヨーロッパに行くと、壁崩壊前から、こっそりラジオの電波を拾うとか、地下壕でジャズ喫茶をやるとか、命がけで西側のジャズを聴いていた人たちがたくさんいました。彼らはようやく壁が崩壊したので、たいしたもてなしはできないけれど、とにかくコンサートをやるんだ! という熱意をもって、モダンジャズの巨匠をたくさん招待していたんです。
私も仕事でツアーに参加しましたが、日本で生活していたら見なかったものをたくさん見たように思います。街はインフラが整っていないし、お客さんも貧相な出で立ちなんですけれど、そんな中でもジャズに憧れ、求めている人の熱気を二十歳くらいで感じたことは、人生を左右したと思います。

——暗い時代のアメリカを肌で感じたことは、音楽に影響していますか。
大西 そうですね、それが良かったかわかりませんし、私がやっている音楽は個人的な趣味によるものではありますけれど。
今アメリカでジャズをやっている若い子たちは、譜面はもちろん読めるし、クラシックの素養があってクリーンな生活をしているタイプばかりです。
でも、私が若い頃一緒にやっていたミュージシャンは、ふた回りくらい上の1940年代から活動していた世代で、兵役やドラッグを経験し、必ず一度他人を疑うみたいなところのある人ばかりでした。でも、仲間と音楽をつくる喜びがいつもそこにあるという感じです。とはいえ、いろいろな人種がいるので差別もあって、音楽があればきれいに混ざり合うとも限らず、ドラッグでつながっているような人も見てきました。
——きれいごとばかりではない現実がそこにあったのですね。
大西 きれいごとでは全然おさまらないです。当時80歳くらいのミュージシャンには、手紙を書いても字が読めない人がめずらしくありませんでした。教育を受けていないから。でも、音を出したら尊敬せずにはいられないんですよね。
歴史を学び、その音でないといけない音を弾く
——これまでのご活動のなか、ご自分のなかで一貫して変わらないことはありますか?
大西 幸か不幸かそういう時代に演奏活動を始めたので、まだジャズを作り上げた人たちが存命で、ギリギリ共演できました。同じステージで一緒に音を出したときの感覚は、言葉にできないものがあります。
ジャズにも成り立ちがあります。それはもとはミュージシャンが育つなか、仲間内で普通に起きてきたことで、それを担った人たちが、いわゆるレジェンドといわれる存在です。だから後の時代の私たちは、そこに敬意をもち、勉強しなくてはいけません。
最近はジャズといっても幅広く、何をもってジャズなのかよくわからなくなっています。でもそこには、勉強しておくべき歴史が必ずあります。コード進行に沿って譜面にないことをちょっと弾けただけで、ジャズミュージシャンになれたと思ってはいけないんですよね。なにがわかっていないのかは、ちゃんとしている人たちからはすぐに見抜かれてしまいます。
そういうことがあるので、私は掘れるだけ掘って、一から勉強して、インプロビゼーションでも、もうその音でないといけないというようなものを弾くんだ、という心構えを持ち続けています。
これはあくまで私のスタンスですけれど。かつてそういう現場に出会ってしまっているので。
——ジャズ界全体は、そのあたりが変わってきていると感じますか?
大西 まあ、そうですね。広まるというのは、そういうことだとも思います。それを否定はしませんが、私のスタンスは変わりません。一番いいのは、私の演奏を聴いて、もっと勉強しなきゃと思ってくれるミュージシャンが出ること。それで報われる気がします。
——伝統を大事にしながらも、大西さんは常に新しいことにも挑んでいらっしゃるイメージです。
大西 それもやはり、私が尊敬する人たちのスタンスが、そうだったからでしょうね。自分でやっていこうとしないとだめです。
でも、たとえば今回のカルテットは、パーカッションがあったらもっとかっこいいんじゃないかなと思って大儀見元さんに入ってもらったら、トリオのときのサウンドがぱっと変わったという感じ。意図して新しいことをしようとしなくても、新鮮に思っていただけることも多いです。

カルテットの新譜『Grand Voyage』リリース記念ライブ映像(2021年12月)
小澤征爾、村上春樹が誘った一夜限りの復活
——ところで、クラシック音楽ファンにとってはやはり、一度引退を宣言されたのち、2013年のサイトウ・キネン・フェスティバルで小澤征爾さんと《ラプソディ・イン・ブルー》を共演され、一夜限りの復活を果たした出来事が印象的です。振り返って、どんな経験でしたか?
大西 小澤さんが、やりたいようにやっていいと言ってくださったのは、本当にありがたいことでした。
クラシックの方々からすると、正直、賛否両論だったんだと思うんです。なにしろ、格式あるフェスティバルのトリにジャズピアニストが出てきたのですから。でも、それをまとめられたのは、やはり小澤さんだったからで、とても貴重な経験をさせていただきました。
小澤さんはいろいろなことに好奇心がある方だから、長くアメリカにいらっしゃる間に古い音楽もたくさんお聴きになっていて、ブルースにも強いリスペクトがあります。トラディショナルを学ばない人間はダメだという強い信念をお持ちでした。
小澤さんが私と一緒に音楽をやりたいとお感じになるのは、私がトラディショナルをちゃんと勉強しているからだ、とおっしゃったことを今も覚えています。その共通言語があったからこそ、気にかけていただけた。自分のやってきたことが伝わった瞬間でしたね。
——しかも、その共演をつないだのが、村上春樹さんだというのもすごいですね。
大西 つないだというか……思いついたことをつぶやいたら現実になった、という感じだと思いますけれど(笑)。
引退を宣言したあと、最後のライブに春樹さんが小澤さんを連れて聴きにきてくださったのですが、MCで引退すると話していたら、突然、小澤さんが立ち上がって、「おれは反対だ!」とおっしゃって。そのまま打ち上げにもいらして、ずっと私を説得していました。
春樹さんはそんなことは関係なく、とても気持ち良さそうに打ち上げのお酒を飲んでいて、ふと「小澤さんと大西さんが《ラプソディ・イン・ブルー》やってるの聴きたいなぁ」っておっしゃったんですよ。それに小澤さんが飛びつかれたんですね。私は引退すると言っているのに!
結局、春樹さんはリハーサルからずっと見ていらして、公演後、熱のこもった文章を書いてくださいました。

インプロビゼーションはピアノのテクニックとのせめぎ合い
——最近は、オーケストラのプロデュースもされています。どんな考えから始められたのですか?
大西 トランペットの広瀬未来、テナーサックスの吉本章紘、ベースの井上陽介が作曲に長けているので、思う存分、大きな編成で曲を書いたらどうかなと思い、無理強いしました(笑)。彼らはもっといろんな曲を書くべきだと思っています。私は彼らの曲のファンだということですね。
メンバーは、彼らが信頼できるミュージシャンを選んでいて、そこに私からの、ピアノはスガダイローさんがいいとか、ソロを取れるメンバーを集めてほしい、というリクエストを取り入れてもらっています。最近は吹奏楽の普及からビッグバンドが人気になっていて、譜面が重視される演奏が増えていますが、やはりジャズの醍醐味はインプロビゼーション(即興)ですからね。
大西順子 presents THE ORCHESTRAの演奏とインタビューの映像
——大西さんの演奏は、優れたテクニックとパワーが魅力ですが、一方でインプロビゼーションのとき、浮かんできた音楽が演奏のテクニックに制限されることはあるのでしょうか?
大西 そうですね、もちろん制約を受けるところもあるとは思いますけれど、私はわりと、人前で無謀なことをやるタイプです(笑)。
使ったことのないフレーズやボイシング(コードの構成音の重ね方)を発見するとやってみたくなるのですが、反射神経がよかった若い頃と違って、一発で成功する確率は極めて低い。でも、やってみて、できなかったら持ち帰って練習します。
ピアノに求める音、クラシックとの関係
——以前、ピアニストとしてはやはり大きな手が欲しいとおっしゃっていました。今や性別は関係ないといえる部分も多いとは思いますが、それでも、技術、感性の面で、女性としてジャズピアニストであることに思うところはありますか。
大西 感性については、女性……というか、自分でよかったと思っていますね。ただ、肉体的な面では、ピアノという大きな楽器を弾くにあたっては、体の骨組みが大きいほうが有利なのは確かなので、女性の中でも小柄な私はより努力が必要です。筋力や手の柔軟性を維持するため、自分なりの練習は毎日丁寧にやっていますが、かなり工夫が必要です。
大西順子カルテット「Wind Rose」
——求める音とはどのようなものですか? また、それをどのようにつくっていくのですか?
大西 私たちのなかでアフリカン・タッチと呼んでいるような、重たい音が好きですね。今の若い子たちからはあまり望ましく思われていないらしいんですけれど(笑)。
ただ、実際に自分が思っている音が出ているかは、自分では聴くことができません。録音のときはそれに近いことができるけれど、やはりマイクを通した音ですので。そうすると、指の感触など、体で感じることを頼りにつくっていくことになります。
——以前、クラシック曲からどちらかというと苦手な曲で遊んだという楽曲を録音されています。逆に今後、好きなクラシック作品を取り上げてみようという考えはありますか?
大西 日本ではロシア音楽が人気ですが、一部の作品は、バターとホイップクリームの上にさらにサワークリームみたいな、ちょっと胸焼けしそうな感じで、私は苦手だったりするんですよね。そんな作品で遊んでみたのが、『Very Special』に収録したチャイコフスキーの「舟歌」でした。
チャイコフスキー:舟歌(ピアノ曲集『四季』第6曲より)〜アルバム『Very Special』より
大西 逆に、たとえばJ.S.バッハなんかはすごく好きです。クラシックでは、いろいろな作曲家が多旋律の曲を書いていますが、ジャズのインプロビゼーションで、3声、4声のメロディがぐにゃぐにゃ動く演奏をするのは至難の技なんです。
だから、そういう音楽を勉強したいといつも思っています。ドイツ音楽はロマン派にもそういうところがありますよね、たとえばシューマンとか。そのあたりの音楽は好きです。好きな曲は遊ぶのではなく、参考にしたい。
——ロマン派でいえば、美しい主旋律に目がいきがちなショパンにも多旋律が組み込まれていたりしますよね。バッハが大好きだったようですし。
大西 そうなんですよ、ピアノ・ソナタ3番の途中なんて、バッハを真似したのかなと思われるところがありますよね。
ジャズでは、左手と右手が赤の他人みたいな演奏をすることを「インディペンデンス」といいますが、そんな多旋律の演奏がアドリブでできるといいなと思います。今、ドラムはインディペンデンスが発展したスタイルになってきていますけれど、ピアノの場合は指が10本あるから、さらに高度なことができるんじゃないかと考えています。でも、それをやりすぎると、グルーヴ感がおざなりになってしまう。その兼ね合いも難しいですね。
——この先音楽家としてやっていきたいこと、目指したいことはありますか?
大西 常に時代の流れに即していないことをやり続けて、ここまで来てしまったので、今後もそれを続けていけたらいいですね(笑)。
——時代の流れに即さなかったとしても、それしかやりたくない、自分に嘘をついてやったことで評価されても気持ち悪い、という感覚でしょうか……。
大西 うーん、そもそも残念ながら、私にはそれ以外できないんですよ。テレビのために何分でこういう演奏をしてといわれても、そんなことはできない。それを楽しくやれる人はやればいいと思うんですが、私は楽しくないんですよね。それで、好きなように弾けるライブとレコーディングだけで生きている人間です。これからも自分の思うことを、ギリギリ生活ができる範囲で(笑)貫いていきたいです。
関連する記事
-
読みもの室内楽に取り組むにあたって考えること。そして梅雨に始めた新しい趣味
-
インタビュー日本音楽コンクール&ピティナ特級の連続優勝で話題! 鈴木愛美さん(ピアノ)
-
レポートピアニストの辻井伸行がドイツ・グラモフォンと日本人初のグローバル専属契約
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest