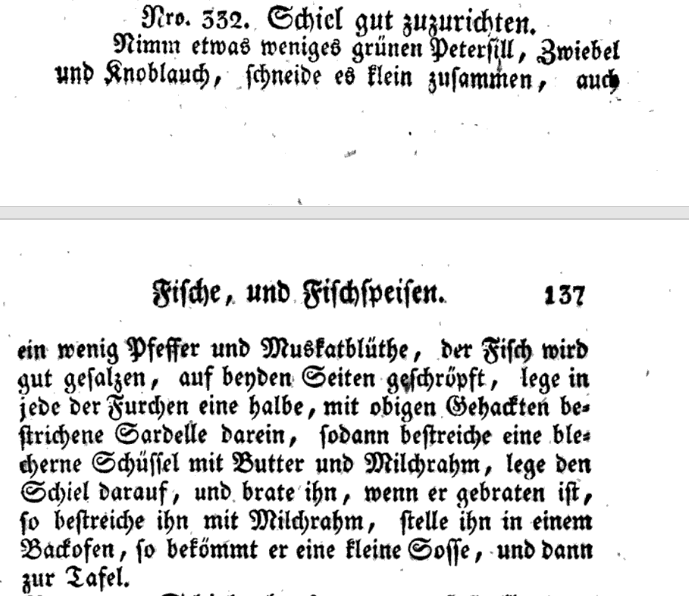音メシ!作曲家の食卓#1 ベートーヴェン~ドナウ川の魚を偏愛した「魚喰い」

歴史料理研究家の遠藤雅司さんが、作曲家をその食卓からクローズアップ。毎回、実際に再現したレシピもご紹介します。人間の根源的な欲求=食のエピソードからは、大作曲家の人間くさい一面が見られるかも!?

歴史料理研究家。国際基督教大学教養学部人文科学科音楽専攻卒。2013年から世界各国の歴史料理を再現するプロジェクト「音食紀行」をスタートさせ、実食イベントやレストラン...
ナポレオンの大陸封鎖令でウィーンの食生活がガタ落ち
1792年、ドイツ西部(当時はウィーンを帝都とする神聖ローマ帝国の一部)のボンから新たな才能を持った人物がウィーンにたどり着きます。〝楽聖〞の名で知られるルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンその人です。聴力を失いながらも交響曲第5番《運命》や《第九》といった名曲を世に送り出した、音楽史に残る大作曲家です。
20代だったベートーヴェンがウィーンで音楽家としてのキャリアを積み上げ始めたころ、ナポレオン戦争(1796~1815)によってヨーロッパ諸国の経済状態は長期にわたって落ち込みました。
オーストリアでは、ナポレオンが発令した大陸封鎖令(1806年)によって食糧の供給がとどこおり、さらにウィーンはフランス軍に2度も占領されたため、市民の食生活は厳しいものになりました。レストランのメニューが減ったり、味が落ちたと言われています。

シェフ・ベートーヴェンの残念な夜会
ナポレオンによってウィーンの食が危機に陥っている時期、ベートーヴェンは飲食のこだわりは少なからずある人物でしたので、自分で料理を作ろうと思い立ちました。
そんなベートーヴェンが友人たちを家に招いて晩餐会を開いたことがありました。友人のイグナーツ・フォン・ザイフリートによると、その日の夕食は次のようなものだったそうです。


まず、ベートーヴェン宅に着いた面々は、寝間着に身を包み、もじゃもじゃ頭にナイトキャップをかぶり、腰には青いエプロンを巻いて、かまどのまわりで四六時中忙しく動き回るベートーヴェンの姿を発見します。それから1時間半以上待たされて料理が提供されました。その料理とは――スープは「浮浪者」が食堂で施しとして食べる残り物を想起させるひどいもので、牛肉は半分ほどしか火が通っていない生焼き状態、野菜は油と水が合わさったものの中を漂っていて、牛肉と別にローストした肉は、煙突の中で燻製にしたのではあるまいかという状態の出来栄えだったそうです。
1. スープ―食堂での施し風
2. 牛肉のロースト―レア
3. 野菜―油と水の中の漂い
4. 牛肉料理―煙突燻製風
参加したザイフリートたちに同情するほかないのですが、当のベートーヴェン本人はすべての料理を大いに味わい、その会合を心の底から楽しんでいたそうです。とはいえ、その後幸運なことに、ビストロ・ベートーヴェンによる料理イベントの開催はなくなりました。ベートーヴェンは永久に包丁を封印したのでした。
コーヒー豆を60粒数えるエピソードは理にかなっている
ベートーヴェンの飲食の逸話で一番有名なのが、コーヒー豆を60粒きっちり数えてから豆を挽いてコーヒーを淹れるというものです。実際のところ、ベートーヴェンがコーヒーだけの朝食をとっていたことは、複数名の証言からわかっています。
また、「無給の秘書」であるアントン・フェリックス・シンドラー著「ベートーヴェン伝」にも2回も記されています。シンドラーは、ベートーヴェンの死後、件の「会話帳」に故意に言葉を書き足して改竄を行なった人物ですが、このコーヒー豆を60粒数える逸話はどうやら本当のようでした。

ベートーヴェンの弟ニコラウス・ヨハンが1822年の会話帳に、「今日はうちで食べればよかったのに、2時まで待っていたんだよ。朝用に120粒の[コーヒー]豆があるよ」と記しています。
実際、コーヒー豆を60粒計量すると、およそ8グラムとなります。市販のドリップパックは8グラムから12グラムですから、ベートーヴェンがのやり方は理に適っていたものなのかもしれません。コーヒーは粉を1とすると、お湯を15から16の比率で抽出するとおいしく味わえるので、コーヒー豆60粒(コーヒー粉8グラム)にはおよそ120~130ミリリットルのお湯を入れてみるとよいでしょう。

ドナウ川の魚を地産地消していたベートーヴェン
美食家にはほど遠い偏食家ベートーヴェンの大の好物は、ドナウ川で獲れる魚でした。「魚喰いの古代ギリシア人」を意識したのか、ベートーヴェンの友人のヨーゼフ・カール・ベルナルドは、ベートーヴェンに古代ギリシア語の「魚喰い(イクテュオファゴス) ἰχθυοφάγος」をドイツ語読みした「魚喰い(イヒテュオファーゲ) ichthyophage」というニックネームを与えたそうです。
魚の中でも特に、鯉、カワカマス、燻製にしんがベートーヴェンの大好物ですが、それ以外にもドナウ川で獲れる淡水魚を「情熱」的に味わっていました。ドナウ川産の魚たちを「地産地消」していたのです。
メンデルスゾーン家と関わりの深い男爵家の料理本レシピ
今回は、当時のドナウ川に棲息していた魚で、かつ現代の日本でも入手できるスズキを使った料理を紹介します。スズキをおいしく味わう方法が、ベートーヴェンが生きていた1822年(初版1810年)に刊行されたウィーンゆかりの料理書に記されています。
少量のグリーンパセリ、タマネギ、ニンニクをみじん切りにし、両面に塩をまぶした魚にコショウ、メースを少量かけ、いくつかの箇所に切り込みを入れ、上記の刻んで混ぜ合わせたスパイスと野菜とアンチョビを切り込みに入れる。その後、ブリキ製のボウルにバターとミルククリームを塗り、[魚の]片面をクリームに浸すように置き、焼く。色づいてきたところで魚にまたミルククリームを塗り、オーブンに入れる。これでソースめいたものができる。あとは食卓に出せばよろしい。
(テレジア・バラウフ(ムック)『ウィーンの女性料理人かくあるべし』)
この料理書の作者テレジア・バラウフ(ムック)は、ウィーンのアルンシュタイン男爵に仕えていた料理人です。この男爵の妻、ファニー・アルンシュタインは、ウィーンでは有名なサロン主催者でした。

ファニー・アルンシュタインはウィーン楽友協会の成立にも関わっており、おそらく、宮廷楽長アントニオ・サリエーリとも繋がりはあったことでしょう。また、ファニーは音楽の才能があったようで、ファニーのいとこのレア・ザロモンは、なんとメンデルスゾーンの母親でした。ヴァイオリン協奏曲で有名な作曲家フェリックス・メンデルスゾーンの姉ファニーの名前は、まさにファニー・アルンシュタインにちなんで名付けられたのだそうです。
音楽と密接なかかわりを持つアルンシュタイン家の料理人が書いた料理本に登場したスズキ料理を、ベートーヴェンはレストランや自宅で家政婦に作らせて味わっていたかもしれません。


この料理のもう一つの特徴はジャガイモです。上記のレシピには一言も触れられていませんが、当時、ジャガイモを添えるのが通例でした。中世のヨーロッパには存在しなかったジャガイモが18世紀以降、急速に普及し、日々の献立に登場するようになるのです。事実、ベートーヴェンの「会話帳」にも、肉の付け合わせとしてジャガイモが出てきます。
ドナウ川の魚たちへの偏愛ぶりは、ベートーヴェンの身体に影響を与えたかもしれません。19世紀前半、ウィーンにも産業革命の動きが起こり、工場がドナウ川近辺に建設された結果、工場排水がドナウ川に注がれていきました。直接的な原因かどうかはわかりませんが、工場排水まみれの魚を食べた結果、ベートーヴェンの身体に異変が起きていったのは容易に想像できます。ベートーヴェンが魚狂いの偏食家だったことは、死亡後に魚の請求書が届いた一件からも明らかでした。
【材料】(4人分)
スズキの切り身 4枚
ジャガイモ 2個
コショウ 小さじ1
メース(ナツメグで代用可) 小さじ1
バター 10g
アンチョビ 10g
グリーンパセリ 1枝
タマネギ 1/2個
にんにく 1片
ミルクソース
・牛乳 50ml
・生クリーム 30ml
【作り方】
1. グリーンパセリ、タマネギをみじん切りにし、ニンニクはすりおろす。
2. 鍋にジャガイモを皮ごと入れて、浸るくらいの水を注ぎ、ゆでる。竹串がすっと通るくらい柔らかくなったら火からおろす。荒熱がとれてから手で皮をむき、1cm程度の輪切りにする。
3. スズキの切り身の両面に塩(分量外)をまぶし、コショウ、メースをかける。
4.スズキの皮目に切り込みを入れ、アンチョビを挟む。
5.耐熱容器にバターを塗って、4のスズキを並べ、1のパセリ、玉ねぎ、ニンニクをふりかける。その上に2のジャガイモを並べる。
6. 牛乳と生クリームを混ぜたミルクソースを 5 に注ぎ、180℃に予熱したオーブンで40分焼いて完成。
【POINT】
*ミルクソース以外にレモンソース(レモン1/2個を絞ってつくる)で味わっても楽しい。
*スズキ以外の川魚を入手できたら、それで作ってもよい。
*メースはニクズクの種子のまわりを覆っている網目状の赤い皮=仮種皮を指す。





関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest