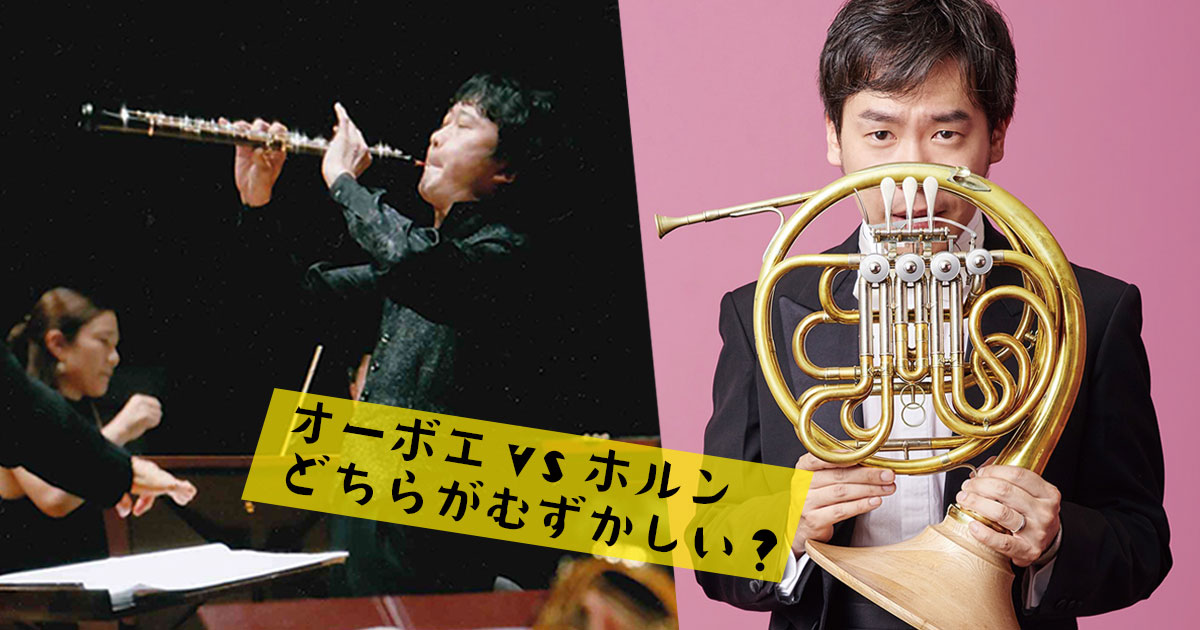『十二夜』最後に道化フェステが歌うシェイクスピアの人生観〜儚い今を楽しむにかぎる

文豪シェイクスピアの作品を、原作・絵画・音楽の3つの方向から紹介する連載。
第11回は、前回に続き シェイクスピアの中でも音楽との関りがもっとも深い『十二夜』を掘り下げます。今回は、男装して奇妙な三角関係を生み出してしまうヴァイオラと、劇の最後に道化師フェステが歌う劇中歌に注目! 19世紀イギリスの画家フレデリック・リチャード・ピッカースギルによる2枚の絵と、アイルランド人作曲家スタンフォードの歌曲《だって毎日毎日雨が降るからさ》から理解を深めます。

上智大学大学院文学研究科講師。早稲田大学および同大学エクステンションセンター講師。専門領域は近代イギリスの詩と絵画。著作にシェイクスピアのソネット(十四行詩)を取り上...
男装してシザーリオと名乗り、恋愛関係もこじらせるヴァイオラの立ち位置
あの人は賢いから道化を演じられる、上手にとぼけるにも知恵が要るから
およそ人間の機知というものについて、シェイクスピアの『十二夜』のこの一節ほど、本質をさらりと突いた表現を他に知らない。
男に変装し、公爵オーシーノの従者となった娘ヴァイオラが、道化のフェステとひとしきり言葉を交わした後に語る独白の一部だが、なるほど真の偉人が決して偉ぶったりしないように、本当に賢い人は案外そうとは見えないもの。
道化という商売柄、フェステが何も知らないふりで「今楽しけりゃ今笑えることがあるだろ」=人生無駄に悲しんでたってしょうがないさと、この世の真理を歌にのせ軽やかに説いていたのは前回紹介したとおり。彼みたいに見て見ぬふり、知っているのに知らないふりで何かと「上手にとぼける」人物には、大抵それなりの理由があるか「知恵」がある。
そもそも冒頭の独白を含む第3幕第1場は、互いに知ってはいても直接話したことのなかったフェステとヴァイオラが、初めて1対1で会話する場面。主筋・脇筋問わず登場人物が数多いる『十二夜』のような芝居で、こうしてわざわざ1対1の場面が設けられている以上、ふたりの対話シーンにはもちろん特別な意味がある。
ヴァイオラとオーシーノ、そしてオーシーノが想いを寄せる伯爵令嬢オリヴィアの三角関係をベースに、オリヴィアの家の執事や食客までもがそこに絡んでくる『十二夜』の話の筋は、まったくもってややこしい。事の発端と問題の根は、ヴァイオラが男装してシザーリオと名乗っていることにあるのだが、その事実を知るのはヴァイオラ本人のみ。そして彼女があくまで男としてシラを切り通しているせいで、オーシーノもオリヴィアも事の真相に気づかぬまま、お門違いの相手に一方通行の恋心を抱き続ける。まずこの点からいって、ひとり真実を知りながら「上手にとぼける」ヴァイオラにも、フェステと同じく知恵者の立場が与えられているといっていい。
2枚の絵に描かれたヴァイオラの表情から本心を読み解く
このヴァイオラの立ち位置をきちんと踏まえて描かれているのが、19世紀イギリスの画家フレデリック・リチャード・ピッカースギルによる2枚の絵、《オーシーノとヴァイオラ》と《ヴァイオラと伯爵令嬢》である。
前者は1850年頃、後者は1859年の作ということで、2枚の絵の制作年代には開きがあるものの、ヴァイオラ(=シザーリオ)の服装がほぼ同じであることからいって、両者が事実上の二幅一対である点はほとんど疑いの余地がない。描かれている場面も、前者(左下)はオーシーノがヴァイオラにオリヴィアへの恋の使者を頼む第2幕第4場、後者(右下)はヴァイオラが頼まれたとおりオリヴィアに主人の気持ちを伝える第3幕第1場であるから、時系列的関連があり完全に辻褄があう。

(1850年頃、個人蔵)

(1859年頃、個人蔵)
というわけで、この2枚が二幅一対であるという大前提で改めて両作を並べて見ると、構図の要がヴァイオラの立ち姿にあることは一目瞭然。オーシーノは傷心の主君として、オリヴィアは恋する女として、それぞれ事情は異なれど、すがるようにヴァイオラを見つめている。つまりはふたりとも、初めからヴァイオラに心をあずけているのだ。
特にオーシーノがベンチに腰掛けていることにより、恋のメッセンジャーに乗り気でない従者のヴァイオラを自然と仰ぎ見る格好になっている《オーシーノとヴァイオラ》は上手い。今はヴァイオラのほうがオーシーノを心ひそかに追っていても、いずれ彼のほうで彼女を追うようになる芝居の結末をも予感させる。
しかし、画家ピッカースギルの創意がひときわ光り、2枚が対であることの最大かつ決定的な証となるのは、ヴァイオラの姿や装いよりも、むしろ顔のほうかもしれない。
恋しいはずのオーシーノからも、同じ女として想いを受け止めるわけにはいかないオリヴィアからも、等しく顔を背けるヴァイオラの仕草。とりわけその憂い顔は、彼女の本心の可視化といってもいいだろう。
道化フェステとひとしきり話した直後、冒頭の独白部分を「あの人はいかにも賢くバカな真似をしてみせるけど、賢い人たちがバカな真似をしでかしては、せっかくの知恵が腐る」と、ちょっぴり毒を吐いて締めくくるヴァイオラは、単にフェステの賢さに感心しているのではない。同時にオーシーノとオリヴィアの本来あるまじき「バカな真似」、自分という傍らの従者の正体を見抜けずに生じる数々の勘違いに、ほとほと呆れ果ててもいるのである。
換言すれば、これは一種の共感。本当のことを知っていながら、それを決して口には出さず、どこか醒めながらいつも演技しつづける——。この意味で、劇中ずっと男性を装ったままのヴァイオラと、請われるまま臨機応変にいくつもの役を上手に演じてみせるフェステは、実は同類にほかならない。やや専門的かつ批評的な見地からみても、彼らはともに本来の役と別の役を兼ねる重層的キャラクターで、劇中にあって芝居や演劇そのものを至上命題とするメタシアター的な登場人物だ。
実際、タイトルの十二夜(クリスマスシーズンの最後を飾る公現祭の夜を指すが、劇中で十二夜の祝祭に直接言及する箇所はない)さながら、飲めや歌えのお祭り気分に溢れた芝居のなかで、変に浮かれることも妙にふさぎ込むこともなく、つと我にかえり、ふと警句めいた本音をひとりごちたりするのは、いつもヴァイオラとフェステ。彼らふたりだけである。
物語の最後にフェステが歌うのはシェイクスピアの人生観?
しかし、フェステはさすがに道化だけあって、ヴァイオラより文字どおり役者が一枚上。ヴァイオラが難破の際に生き別れた双子の兄と再会することで、彼女とオーシーノとオリヴィアの奇妙な三角関係は解消され、オリヴィアはヴァイオラの兄と、ヴァイオラ自身もオーシーノと結ばれ大団円となるのだが、ここ一番とばかり、芝居のラストにあたりフェステはいよいよその本領を発揮する。
というのも、登場人物がみな退場したあと、彼はひとりぽつねんと舞台に残り、こう歌って幕を引くのだ。
When that I was and a little tiny boy,
With hey, ho, the wind and the rain,
A foolish thing was but a toy,
For the rain it raineth every day
But when I came to man’s estate,
With hey, ho, the wind and the rain,
Gainst knaves and thieves men shut their gate,
For the rain it raineth every day.
But when I came, alas! to wive,
With hey, ho, the wind and the rain,
By swaggering could I never thrive,
For the rain it raineth every day.
But when I came unto my beds,
With hey, ho, the wind and the rain,
With toss-pots still had drunken heads,
For the rain it raineth every day.
A great while ago the world begun,
With hey, ho, the wind and the rain,
But that’s all one, our play is done,
And we’ll strive to please you every day.
おいらが ほんのガキだった頃なんてさ、
ヘイ、ホー、風に雨で
バカやっても いいかげんですんだもんさ
だって 毎日毎日 雨が降るからさ。
そんで おいらが 大人になったらよ、
ヘイ、ホー、風に雨で、
泥棒やならずもんは 閉め出しよ、
だって 毎日毎日 雨が降るからさ。
そんで おいらが ああ!嫁なんかもらっても、
ヘイ、ホー、風に雨で、
ふんぞり返ってみせたって どうにもこうにも、
だって 毎日毎日 雨が降るからさ。
そんで おいらが 床に着いたら
ヘイ、ホー、風に雨で
飲んだくれと まだ酔っ払ってら
だって 毎日毎日 雨が降るからさ。
昔むかしに この世がはじまり、
ヘイ、ホー、風に雨で
それでよし、これで芝居も終わり、
われら 毎日毎日 皆々様に楽しんでもらうため 努めるまでさ。
芝居の最後を飾るこのフェステの歌が、シェイクスピア自身の手によるものかどうかについては、いろいろと議論がある。最後に「皆々様」うんぬんと、古くからの民族劇にみられる幕引きの常套句めいた謝辞がある以上、やはり過去の作品からの一部借用という通説を信じるしかないのだろう。
が、本当に大切なのはそこじゃない。歌詞の出どころじゃなくて内容だ。
この劇中歌の最大の特徴は、最終漣を除いて各連2行目と4行目できっかり繰り返されるリフレイン。「雨」と「風」が人生における苦難の象徴であることはいうまでもなく、「ほんのガキ」の頃から「大人」になっても、それらはリフレインさながら何度でも訪れる。
何人たりとも人生の雨風を避けて通ることはできない。表向きどんなに澄まして晴れやかな顔をしていても、本当は誰の人生もどしゃぶり続きで泥まみれ……と、まぁ、なかなかほろ苦い真実が歌われているというわけだ。
喜劇である『十二夜』がめでたしめでたしではなく、ちょっぴりほろ苦い真実の歌で終わる理由は、ひとつしか考えられない。どんな祝祭も必ず終わる——それが作者シェイクスピア自身の人生観で、人は儚い今をうんと楽しむにかぎるし、それには金以上に頭が、知恵が要る。だからこそシェイクスピアは、機知の権化みたいな道化フェステを最後まで舞台にひとり居残らせ、この歌をしんみりと歌わせることにしたのだろう。
道化師フェステの雰囲気がよく表れたスタンフォードの歌曲
とはいえ、重たい真実なら軽やかに、つらい事実もつとめて明るく冗談交じりに伝えるのが道化の身上である。しんみりした歌をあんまりしんみり歌っては芸がない。前回紹介した《おお僕の恋人》同様、この最後の劇中歌にも多くの音楽家が曲をつけている(ちなみにほとんどが第4連を割愛している)けれど、19世紀末のアイルランド人作曲家チャールズ・ヴィリアーズ・スタンフォードの《だって毎日毎日雨が降るからさ》みたいに、むしろうんと軽快なリズムにのせて歌ってほしい。
チャールズ・ヴィリアーズ・スタンフォード《だって毎日毎日雨が降るからさ》
ところどころ長調と短調を行ったり来たりして、ほろ苦い人生の真実をコロコロ笑い飛ばすようなスタンフォードの曲調。それはまさにフェステの雰囲気。何度か繰り返し聴いているうちに、何でも知っている道化にからかわれているみたいな気になって、いつのまにかいろんなことがどうでもよくなってくるから不思議だ。
「だって毎日毎日雨が降るからさ」、人生無駄に悲しんでたってしょうがないか、と。





関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest