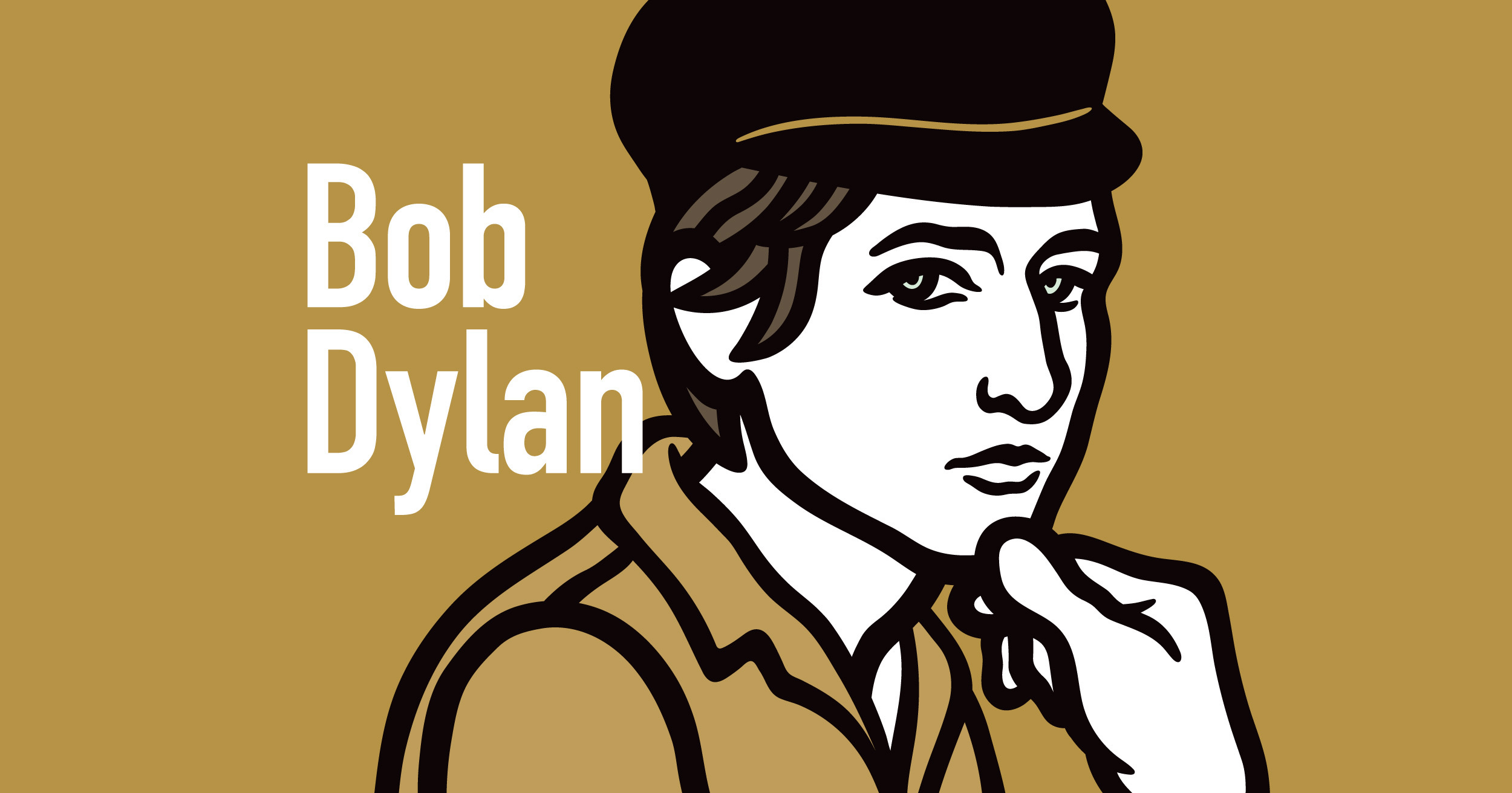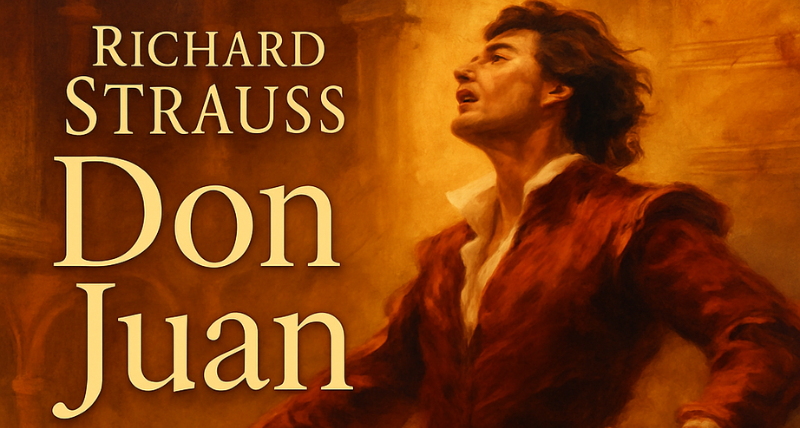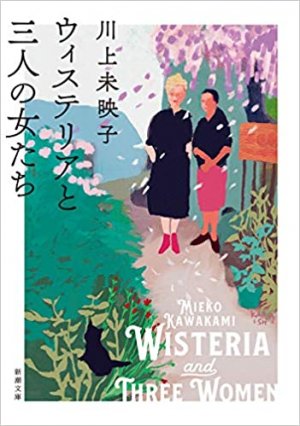なぜ彼女たちはベートーヴェンの「最後のピアノ・ソナタ」を聴いたか──川上未映子『ウィステリアと三人の女たち』

かげはら史帆さんが「非音楽小説」を音楽の観点から読む連載。第15回は、芥川賞作家の川上未映子の短編集『ウィステリアと三人の女たち』から表題作を取り上げます。ヴァージニア・ウルフの名作『波』からの影響を紐解きつつ、主人公と、主人公が出会う2人の女性が聴いた「ベートーヴェン最後のソナタ」の謎に迫ります。

東京郊外生まれ。著書『ニジンスキーは銀橋で踊らない』(河出書房新社)、『ベートーヴェンの愛弟子 – フェルディナント・リースの数奇なる運命』(春秋社)、『ベートーヴェ...
ふたりはベルベット生地の小さなソファにそれぞれ腰掛けて、ベートーヴェンを聴く。ピアノ・ソナタ第三十二番、第二楽章。ベートーヴェン最後のピアノ・ソナタ。
——川上未映子『ウィステリアと三人の女たち』新潮社、2018年
私は立ち上がり、歩み去りました──私、私、私。バイロンでも、シェリーでも、ドストエフスキーでもない私、バーナードである私です。私は自分の名前を一、二度口に出してみたほどですよ。ステッキを振りながら店に入り──音楽が好きなわけでもないのに──銀のフレームに入ったベートーヴェンの肖像画を買いました。
——ヴァージニア・ウルフ『波〔新訳版〕』森山恵訳、早川書房、2021年
「銀のフレームに入ったベートーヴェン」への憧れと疑念
往々にして、作者は自分の「最後の作品」を知らない。
ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンもまた然り、だ。1822年、彼はハ短調のピアノ・ソナタ『第32番』を作曲した。今日ではベートーヴェンの「最後のピアノ・ソナタ」として知られる曲である。荘重なハ短調で始まり、穏やかなハ長調で閉じられる全2楽章のこのソナタは、まさに巨匠のライフワークの「最後」を飾るにふさわしい風格を感じさせる作品だ。
しかしベートーヴェン自身は、この作品を人生最後のピアノ・ソナタだと確信して作曲したのだろうか? その可能性は高くない。晩年の彼がピアノ作品の作曲に積極的でなかったのは確かだが、はっきりと断筆宣言を行なったわけでもない。そのうちまた書くかもしれないし、もう書かないかもしれない——おそらく、それ以上のことは考えていなかっただろう。第32番のソナタに老いの境地や死の予兆を見出すのは、後世の人びとの手前勝手な夢想にすぎない。
20世紀の英国モダニズムを代表する作家ヴァージニア・ウルフは、1931年発表の小説『波』において、こうした夢想を痛烈に皮肉っている。主要登場人物のひとりバーナードは、自分自身の人生を物語としてまとめあげることを志す男だ。彼は街の表通りのとある店で「銀のフレームに入ったベートーヴェンの肖像画」を買う。バーナードにとってベートーヴェンは、バイロンやドストエフスキーと同じく、さまざまな伝記作家の手によって人生を物語化されている理想の人間だ。
しかしバーナードは、そんなベートーヴェンに憧れる一方、ひとの人生をペンでまとめあげる行為の暴力性に疑念を抱いてもいる。「混沌とした日常を横断してローマ街道のように敷きつめられるフレーズ」を彼は嫌い、理想の物語と現実の人生のはざまで苦悩する。「だめだ。まだだめだ! 私は自分自身をひとつにまとめられませんでした。自分が見分けられませんでした」——バーナードの悲嘆の叫びは、ほかの登場人物のモノローグと「波」のように重なり合い、岸の上に砕け散る。
実験的な小説として後世の作家に大きな影響を与えた『波』は、現代日本の岸辺にもさまざまな形で流れ着いている。川上未映子の短編集『ウィステリアと三人の女たち』所収の表題作もまた、そのひとつだ。

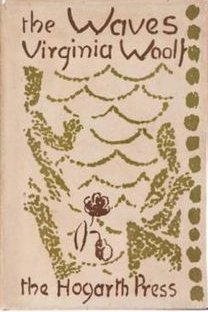
彼女たちが聴いた「最後」であると同時に「最後」ならざるピアノ・ソナタ
「ウィステリアと三人の女たち」の主人公は、結婚して9年になる38歳の専業主婦である。子どもはいない。欲しくないわけではなかったが、自然に任せたままでは妊娠できず、検査を受けようと夫に提案する。ところが夫はそれを拒否する。
「何かをはっきりさせるにはそれなりの責任が生まれる」と夫は言う。検査をすれば、自然妊娠できなかった原因が明るみに出てしまう。検査をしなければ、もし最終的に子どもができなくても、原因があったのか、なかったのかを曖昧にしておける。プライドが高い夫が、男性不妊の可能性を恐れていることに主人公は気づいているが、説得して押し切る勇気も気力もない。夫の圧に負けた彼女は押し黙ってしまう。
そんな折、隣の家の解体工事がはじまる。その家には老女がひとりで住んでいたはずだが、ほとんど交流がなく、最近は姿も見かけなくなっていた。ある日、ひょんな動機から解体途中の家のなかに入っていった主人公は、この家をめぐる過去の物語に思いを巡らせる。それは、かつてここで英語塾を開いていた老女——通称「ウィステリア」と、イギリス人の女性英語教師との美しく幸福な日々だった——。
それは、主人公が解体中の家に残された家具や生活の残骸から創り上げた物語なのか。それとも、この家でかつて本当に起きた出来事が彼女の意識に憑依したのか。どちらなのかはわからないが、彼女にとってはどちらであっても構わない。「何かをはっきりさせるにはそれなりの責任が生まれる」——夫のその弁解めいたセリフを逆手に取るかのように、彼女は夢想とも事実ともつかないウィステリアと英語教師の物語に意識をゆだねていく。
彼女の頭のなかで、ウィステリアと英語教師は「深い色をした二脚のソファ」に座り、レコードを聴いている。
ふたりはベルベット生地の小さなソファにそれぞれ腰掛けて、ベートーヴェンを聴く。ピアノ・ソナタ第三十二番、第二楽章。ベートーヴェン最後のピアノ・ソナタ。
ウィステリアは同性の英語教師をひそかに愛している。しかし彼女は、ふたりの関係を「はっきりさせる」ことを恐れ、相思相愛の可能性に賭ける勇気を持てずにいた。彼女は結局、教師に自分の心を告げることができず、その片想いは実らないまま終わっていく……。
そのロマンティックな悲恋物語は、表面的には主人公の人生とは何らかかわりがない、「銀のフレームに入った」劇中劇のように見える。しかし両者は、潜在的には非常に強く共鳴しあっている。愛の真相をはっきりさせないまま人生をやり過ごす。ウィステリアのその臆病さは、不妊検査を恐れる主人公の夫の臆病さであり、夫を説得する勇気を持てない主人公の臆病さそのものだからだ。
主人公は解体中の家のなかから「二脚のソファ」と「レコードプレイヤー」らしきものを発見するが、レコードのタイトルは見ていない(少なくとも小説中には具体的に描写されていない)。ではなぜベートーヴェンの第32番のピアノ・ソナタが、このふたりの、そして彼女自身のBGMとして選ばれたのか? それは、このソナタが「最後」であると同時に「最後」ならざる作品だからだ。
事実としてはまぎれもなく「ベートーヴェン最後のピアノ・ソナタ」である。しかしまだ人生の中途の道にいたベートーヴェン自身にとっては「最後かもしれないピアノ・ソナタ」であって、決して「最後のピアノ・ソナタ」ではない。不妊は完全には確定しておらず、愛は完全には破れてはいない。万事は曖昧なまま、ただ、確実にゆっくりと終焉へと、死へと向かって進んでいる。ハ長調の第2楽章は、その象徴として彼らの背後で静かに鳴り続けている。
解体中の家のなかで、主人公とウィステリア、ふたりの想いが「波」のように重なり合う。「自分自身をひとつにまとめられませんでした。自分が見分けられませんでした」──この短編の主人公には、『波』のバーナードのような悲愴感はまったくない。むしろ彼女は、自分の人生とこの家の思い出を重ね合わせることに、熱っぽい快楽を覚えているように見える。
庭の小さな水たまりが示すもの
蓮實重彦氏が指摘しているとおり、「ウィステリアと三人の女たち」は、ウルフの『波』から強いインスピレーションを受けている作品である。登場人物のひとりウィステリアは、大学時代にウルフの作品を夢中になって読んだという設定であり、作中には『波』から引用したフレーズも登場する。
ウィステリアと英語教師が聴いたベートーヴェンもまた、『波』からの意図的な引用であろう。ウルフは『波』を書くにあたって、ベートーヴェンの弦楽四重奏曲からインスピレーションを受けたと語っている。異なる人生を歩む6人の登場人物が放つ戯曲のようなセリフの群像と、散文による間奏部分が響き合うさまは、たしかに音楽的であり、その巧みな技法は「ウィステリアと三人の女たち」にも色濃く反映されている。
『波』はウルフの最後の小説ではない。ウルフはその後、小説『歳月』『幕間』ほかさまざまな作品を精力的に手がけている。ただしこの小説を書いてから10年後、彼女は川への入水という方法で自ら人生の幕を引いた。
波の内に沈んでいった彼女の最期と、10年前の小説とを重ね合わせるのは、ヴァージニア・ウルフの人生を「銀のフレーム」に入れて安易に物語化する悪しき行為だろうか? その答えをここで探ることは避けたいが、「ウィステリアと三人の女たち」の作品中に垣間見えるウルフの死の影については触れておきたい。主人公が老女ウィステリアの家に入っていったとき、家の庭には「三日前の雨の小さな水たまり」が残っていた。それこそがウルフの入水による自死の暗示であり、彼女の小説『波』が時代を越えて21世紀の日本の岸辺まで打ち寄せた痕跡であり、ベートーヴェンの『第32番』が「最後のピアノ・ソナタ」という物語をまとって鳴り始める予兆だった。





関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest