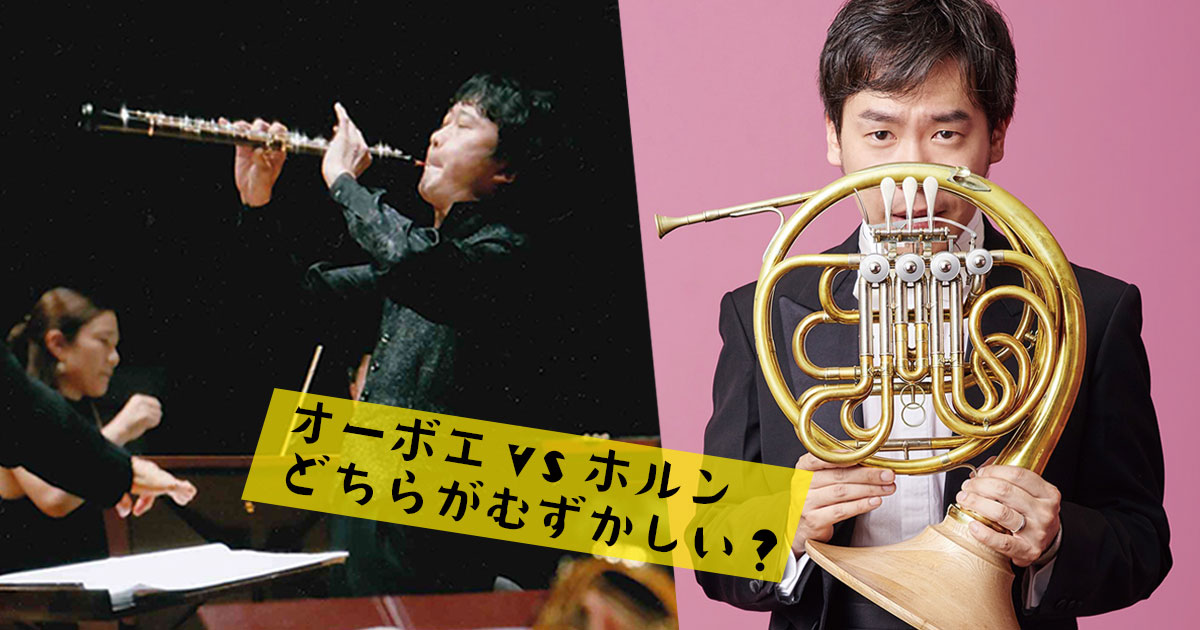道化師フェステがシェイクスピア『十二夜』のカギを握る! 劇中歌も隠れた見せ場に

文豪シェイクスピアの作品を、原作・絵画・音楽の3つの方向から紹介する連載。
第10回は、『十二夜』の登場人物、道化師フェステに注目! 演技だけでなく歌や踊りも求められる高度なこの役、物語でどのような役割を果たしているのでしょうか? フェステが歌う劇中歌と、ウォルター・デヴァレルの絵画から読み解きます。

上智大学大学院文学研究科講師。早稲田大学および同大学エクステンションセンター講師。専門領域は近代イギリスの詩と絵画。著作にシェイクスピアのソネット(十四行詩)を取り上...
道化役は一番の芸達者が演じる!?
歌って踊れるなんて、当たり前。もはや芸人並みに「笑い」も取れなきゃ人気者にはなれないから、今どきのアイドルはつらい。でもこれ、何もアイドルに限ったことでもなければ、今に始まったことでもない。
歌って踊れて笑いも取れる——。実のところ、これは16世紀のシェイクスピアの時代から少しも変わらぬ、優れた役者の条件。少なくともシェイクスピア劇には、顔や姿なんて二の次でいいから、この条件を兼ね備えていないと絶対にできない役がひとつある。
それは道化。奇抜な衣装や滑稽な言動でおバカを装い、そのじつ高い教養と深い知恵で雇い主に「笑い」を提供するのがヨーロッパ宮廷文化における道化の役割。多くが宮廷や貴族の館を舞台とし、恋を語るにもいちいち機知が不可欠のシェイクスピア劇には、重要な脇役として数多の道化が登場する。
なかでも、喜劇『十二夜』に登場するフェステは別格。一座のなかでも一番の芸達者が演じるのがお約束で、いわば演者を選ぶ難役だ。
というのも、道化はそもそも歌や踊りといった芸事を人前で披露するのが商売で、その素晴らしさゆえに、主人はじめ周囲への自由(=無礼)な言動を許される。要は「喋り」以上に音楽やダンスのプロであることが重要かつ大前提なのであって、相当なエンターテイナーでなければとても務まるものではない。
高い歌唱力まで求められるフェステ役
『十二夜』では、主役のひとりオーシーノ公爵が開幕冒頭、しかも開口一番「もしも音楽が恋の糧ならば続けておくれ(If music be the food of love, play on)」と告げるとおり、「音楽」が芝居全体の基調をなし、話全体の屋台骨ないし通奏低音として機能している。そして、いくつもの劇中歌の歌い手として、事実上それを一手に引き受け支えているに等しいのが、道化フェステなのである。
だからまず、フェステ役は歌がうまくなくちゃいけない。それも、ちょっとやそっとじゃ許されない。できることならプロの歌手並み、はっきりいって、歌だけで銭取れるレベルじゃないと。
初めからこうまで具体的に注文せざるをえないのは、第2幕第3場のせい。オーシーノが片思いしている伯爵令嬢オリヴィアの叔父とその仲間(注:どちらも酔っ払い)に「何か1曲歌ってくれよ」、「恋の歌がいい、恋の歌たのむよ」とリクエストされ、酒場の流しの歌手よろしくフェステがその場で歌ったら、「最高にうまいな、おい」「実に後引く声だねぇ」と、口々に絶賛されるシーンがあるのだ。
歌の上手さはもちろん、声質まで……。ある意味これは気の毒。フェステを演じる側にしてみれば、どうして脚本の段階でこんなに役のハードルを上げてくるのか? と、シェイクスピアを恨みたくなるかもしれない。
が、これは必ずしも脚本を書いたシェイクスピアのせいともいいきれない。原因は彼個人というより、彼の生きていた時代に、つまりは歴史にあるというべきか。
フェステが歌う劇中歌も重要な要素に
『十二夜』が書かれた16世紀ルネサンス期は、イギリス音楽の黄金時代。正確には、器楽伴奏付き独唱歌曲の一種であるリュート歌曲が大流行した時代で、シェイクスピアもショービジネスに従事する人間の常として、自分の芝居にさかんにこの流行を取り入れた。
その最たる例が、他のどの作品よりも「音楽」をフィーチャーし、有名な劇中歌の多い『十二夜』なのである。実際、先の場面で酔っ払いたちに請われる形でフェステが歌う「おお僕の恋人(O mistress mine)」は、歌詞の軽やかさや座りの良さも手伝って、芝居の主筋とはまた別次元でのひとつの見せ場であり、聴かせどころといっていい。
O mistress mine,where are you roaming?
O stay and hear! your true-love’s coming
That can sing both high and low;
Trip no further,pretty sweeting,
Journey’s end in lovers’ meeting?
Every wise man’s son doth know.
What is love? ‘tis not hereafter;
Present mirth hath present laughter;
What’s to come is still unsure:
In delay there lies no plenty,
Then come kiss me,Sweet and twenty,
Youth’s a stuff will not endure.
おお僕の恋人、どこに行くんだ?
待って聞いて!真実の恋人が 僕が来たんだ
高くも低くも歌えるから。
もう遠くに行かないで、とっても可愛いんだ
旅の終わりは恋人たちの出会いだろ?
賢者の息子はみんな知ってるんだから。
恋ってなんだ? この先なんかありゃしないだろ。
今楽しけりゃ 今笑えることがあるだろ。
先のことなんて 知ったことか。
ぐずぐずしてちゃできない なんにも
だからキスして、甘く何度も
若さなんて 長く続くもんか。
「おお僕の恋人」には、今も昔も多くの作曲家が曲をつけているが、やはりシェイクスピアと同時代のロンドンに生きていたリュート歌曲の大家、トマス・モーリーの軽快なメロディが個人的にはしっくりくる。
トマス・モーリー「おお僕の恋人(O mistress mine)」
「先のことなんて知ったことか」「だからキスして」と、まるでたたみかけるように恋の刹那を煽る詩に、切なすぎるメロウな調べは何だかそぐわないから。
道化という俗世の真の知恵者が、何も知らないふりしてコロコロ陽気に「今楽しけりゃ今笑えることがあるだろ」といってくれているのである。ここはありがたくお言葉どおり、甘く軽やかなメロディに身を任せ、「若さ」も何も「続く」ものなどありはしない現実をいっとき忘れるに限る。そして「今」を、人生をうんと楽しむに限る。
とはいえ、叶わぬ恋というつらい現実に真実どっぷりひたっている最中は、モーリーの「おお僕の恋人」みたいにあんまり軽い歌は聴きたくないものだろう。『十二夜』の登場人物でいうなら、オーシーノがまさしくそう。彼は熱い想いを寄せるオリヴィアに、兄を亡くしたばかりで喪に服している最中だからという理由でまったく相手にしてもらえない。そしてその憂さを晴らすよりも、むしろそれに浸ることで己の愛をひとり深めようと、「来たれ死よ」という歌をフェステに歌わせる。
ロジャー・クィルター「来たれ死よ」
「来たれ死よ、来たれ死よ/わが身を糸杉の棺に横たえよ」と始まるこの歌は、何とも悲しい失恋ソング。とくに19世紀末から20世紀にかけて活躍したイギリスの作曲家、ロジャー・クィルターの憂愁なる嘆きの調べにのせて聴いたなら、オーシーノの恋に万が一にも見込みはないのだと誰しも察しがつく。
恋の三角関係をにおわせるのもフェステ
事実フェステは、オーシーノの想いが決して叶わないとわかっていながら舞台上でこの曲を歌い、傍らの従者シザーリオも観客もそうと知りつつ、フェステの声に耳をかたむける。その場面を選び抜き絵画化したのが、19世紀半ばのイギリスの画家ウォルター・デヴァレルの作品《十二夜、第2幕第4場》にほかならない。
まず、なぜ早くも芝居の第2幕でオーシーノの失恋が確定し、オリヴィアが彼を受け入れることはないと、観客含め誰も彼もがわかってしまうのか? それはすでに第1幕で、オーシーノの恋の使者としてやってきた従者シザーリオをひと目見るなりオリヴィアが心奪われ、「これは運命だわ」と完全にのぼせあがってしまっているから。
しかしこのシザーリオ、実はれっきとした女性なのである。本当の名はヴァイオラといって、航海の途中で難破したあげく、オーシーノの領地にたどり着き、見ず知らずの土地でひとり果敢に生きていくべく、男装しオーシーノの従者として仕えることになった。そして女と名乗れぬまま、主君である彼を愛するようにもなってしまう。

左からヴァイオラ、オーシーノ、フェステ。
そう、デヴァレルの描いた《十二夜、第2幕第4場》の絵の中で、叶わぬ恋に身をやつしているのはオーシーノだけではない。フェステの「来たれ死よ」の歌に耳を傾け、片恋の憂さを晴らすよりも、そこにどっぷり浸ることで己の愛をひとり深めているのは、シザーリオと名乗っているヴァイオラも同じ。
ただし画面の左端、心ここにあらずのオーシーノを男の姿でじっと見つめるヴァイオラの目線は、まっすぐで熱い。これは女の目。それも恋に恋するのではなく、愛したなら愛されたいと一途に願う、意志ある女のまなざしだ。

想う人には想われず、想わぬ人には想われて……という、オーシーノとオリヴィアとヴァイオラが織りなす恋のトライアングル。女が男のふりをする異性装がもたらした、奇妙な三角関係の行き着く先やいかに?
これを芝居のもっとも早い段階で見抜いて、恋の勝者を勘のいい観客ににおわせるのが、ほかならぬ道化のフェステ。歌って踊れて笑いも取れて、話の先までにおわせるとは、まったく道化も楽ではないが、そのあたりの詳細はまた次回。





関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest