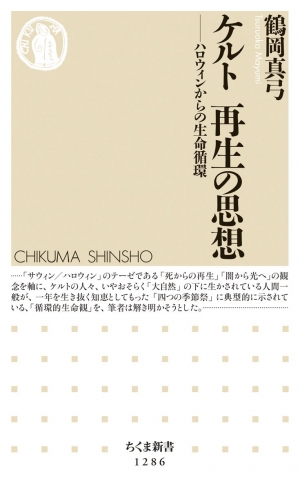ケルトの死生観に見るハロウィン。生と死の狭間でどんな音楽を聴く?

ハロウィンの起源はケルト文化にあり。
神は自然に宿り、「死」と「生」は地続きであると考えるケルトの文化は、日本人にも馴染みやすい。その考え方は、現代を生き抜くヒントにもなるかも。
一味違うハロウィンを味わいたいあなたへ、ケルト音楽の素敵なバンドをご紹介。

1966年千葉県生まれ。日本大学文理学部出身。 メーカー勤務を経て96年よりケルト圏や北欧の伝統音楽を紹介する個人事務所THE MUSIC PLANTを設立。 コンサ...
クリスマスやバレンタインデーに続かんとばかりに空前の盛り上がりを見せる「ハロウィン」だが、実はその起源はヨーロッパのケルト文化にあることはあまり知られていない。
ケルトの暦において1年は10月31日に終わり、11月1日に始まる。すべての亡くなった者たちが、この日によみがえると信じられてきたのだが、実はこれがハロウィンの起源「サウィン」。現在ハロウィンを象徴する存在となったジャック・オー・ランタンも、もともとはアイルランドでカブを使って作られていたものがアメリカに渡り、当時生産量が多かったカボチャが使用されるようになったのだと言う。
「ケルト」とは何かと言われれば、「アイルランド、それからスペイン、フランスの一部、スコットランド、ウェールズなどに伝わる古代の文化」と説明されることが多いが、私は「ケルト」は古代の歴史だけではなく、今、現在を生きぬくための新しいものの考え方を教えてくれる哲学みたいな存在ではないかと常に感じている。
キリスト教が伝わる以前の、神様は自然の中に宿るという考え方。またこの世とあの世は連続的であるとし、「死」と「生」の境界線がはっきりしないという考え方。何事も断定しない、世界は変化の中にこそ存在するのだという考え方は、現代を生きる私たちが忘れた重要な何かを教えてくれる。

ケルトの暦において1年は4つの季節――冬「サウィン」、春「インボルク」、夏「ベルティネ」、そして秋/収穫の季節「ルナサ」――に分かれる。ハロウィンはこの「サウィン」が起源で、ここで収穫の秋が終わり冬が始まり、死者の魂がこちら側である私たちの世界に戻ってくるというのだ。そしてその瞬間、「過去」「現在」「未来」の垣根はすべて吹き飛び、ありとあらゆるものが混ざり合う中で、本当の再生が始まるとされている。
ケルト暦については鶴岡真弓先生の『ケルト 再生の思想〜ハロウィンからの生命循環』(ちくま新書)に詳しい。鶴岡先生によればヨーロッパそしてアジアの周辺諸国には、そういった古代人の考え方を象徴するような始まりも終わりもない回転を表現する紋様を表現した遺跡がたくさん残されているという。確かに死者がこの世に戻ってくるというコンセプトは日本のお盆や先祖を敬う気持ちにも通じるし、ケルト模様のいくつかは日本の縄文土器の模様を思い出させる。
さらにケルト人の、合理主義ではなく、明瞭な答えやシステムなどを求めないところも日本人と非常によく似ている。ケルト人は文字を持たなかった。書いて断定してしまうのではなく口承の文化を重要視した。そして、どちらかというと以心伝心的なもの……例えば「なんとなく肌があう」「気配」といった、断定できない何かを重んじてきた。
そういう人たちが実は世界の中心部ではなく周辺、特に島国には多数存在していて、日本とアイルランドはその代表格だと言えるだろう。この2つの国は遠く離れているけれど、お互い響き合う何かを持っているのかもしれない。
そのせいか日本人のケルト文化への興味はつきない。懐かしさや既知感。例えばぼんぼりの明かり。障子を通した光など直接光ではない光を美しいと感じる心。日本の神話/伝説の中にも、ケルト同様、死後の世界=異界的存在に対して恐怖だけではなく「親しみ」を表したものが多い。
生きている者も死をはらんで生きているし、死んでしまった者たちもまるでまだ生きているかのように人々の間にいつまでも存在している。面白いことにこの感覚は、ケルトの歴史を勉強したり、アイルランドの伝統音楽や文学、映画に触れたりするときばかりではなく、現代を生きるアイルランド人たちの中にも十分息づいていて、アイルランド人と話しているとそんなことをふと感じる瞬間が何度もあるのだ。
せっかくの機会だから、ここで、このケルトの死生観が感じられる音楽を1つ紹介しておこう。スコットランドの3人組、LAUが、2007年に発表したデビューアルバムに収録された『Unquiet Grave』。死んだ恋人に生き返ってほしいと墓地にずっと座り続ける男、そして死んだ恋人のほうは「これではゆっくり眠れないではないか」と答えるという内容の歌だ。古くからあった伝統歌の歌詞にLAUのシンガー、クリス・ドレヴァーが新しいメロディを付けた。「12ケ月と1日で死者は語り始める」と繰り返される歌詞が印象的。この「静かならぬ墓地」は伝統音楽を歌うシンガーたちの中では非常にポピュラーな題材で、他のヴァージョンはジョーン・バエズ(アメリカ出身の女性ミュージシャン、シンガーソングライター)の歌唱などでも知られている。





関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest