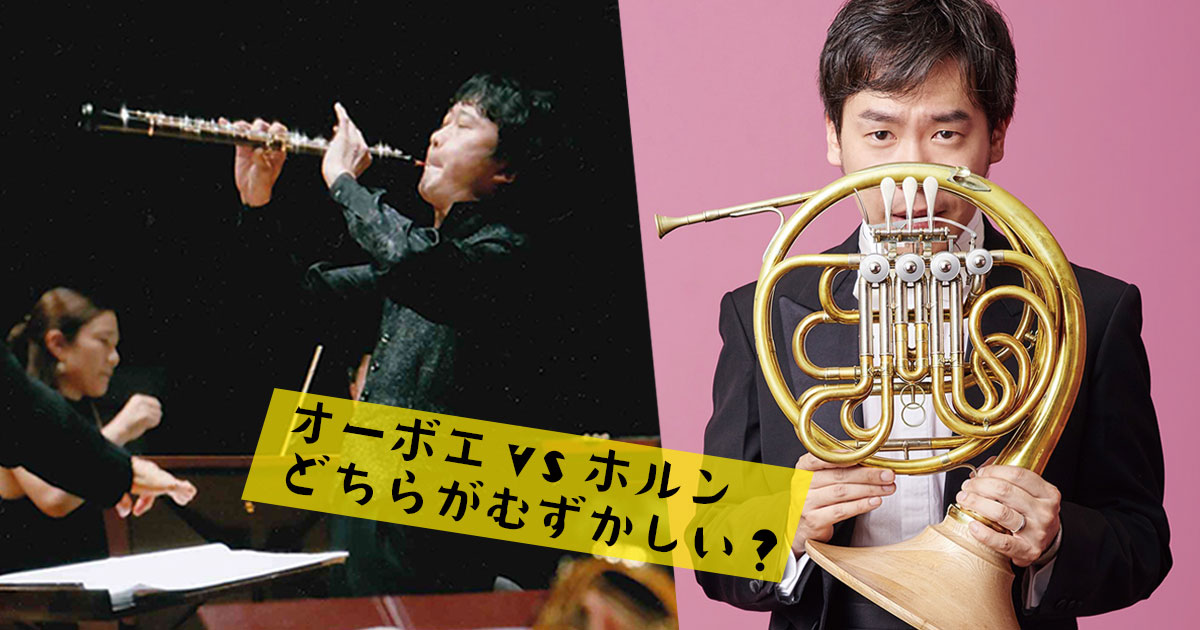『ヘンリー6世』に描かれる権力闘争を吹奏楽曲《剣と王冠》と「赤と白の薔薇」の絵から読み解く

文豪シェイクスピアの作品を、原作・絵画・音楽の3つの方向から紹介する連載。
第8回は、『ヘンリー6世』における権力闘争に着目します。グレグソン編の吹奏楽曲《剣と王冠》でトランペットのファンファーレが暗示するものとは? そして、アーサーペインの絵画《テンプルの庭で赤と白の薔薇を選ぶ》では、薔薇の描写からどのような人間関係が読み取れる? 歴史的事実とともに考察します。

上智大学大学院文学研究科講師。早稲田大学および同大学エクステンションセンター講師。専門領域は近代イギリスの詩と絵画。著作にシェイクスピアのソネット(十四行詩)を取り上...
英仏歴史的因縁に早くも目を付けたシェイクスピア
誤解と誇張を恐れず、敢えていおう。
——かつてフランスはイギリスだった。
嘘じゃない。表現としていささか度を越し、正確さを欠くという非難は真摯に受け止めるが、これはある意味ある面で本当のこと。
少なくとも中世の一時期、北はノルマンディーから南はガスコーニュにいたるフランスの約西半分に相当する地域が、英仏海峡をまたいでの諸々の相続や婚姻等によりイングランド王家の家産となっていたことは事実。海のむこうのブリテン島本土の領土(現在のスコットランドとウェールズを除く)も加えれば、イングランド王の統治領域は、パリを擁するイル・ド・フランスを中心としたフランス王のそれをはるかに凌ぐ時期があった。

出典:Hélène Adeline Guerber, The Story of Old France (1910)
これは今日なお、何かにつけて対立しがちな英仏の歴史的因縁の最たるもの。フランス側にとっては不愉快極まりない、苦い史実でしかないだろうが、イギリス側にしてみれば事あるごとに思い出し、口の中でゆっくり飴玉でも転がすみたいにいつまでも味わって浸っていたい、甘美なる過去といっていい。
ゆえにイギリスでは昔から、中世の英仏関係を扱った芸術には事欠かない。実際、「百年戦争」と呼ばれる長期間にわたる断続的な対仏戦争と、その余波として生じた「薔薇戦争」と呼ばれる内乱状態を経て、海外領土の完全喪失と引き換えにブリテン島内に久方ぶりの安定がもたらされた16世紀、過去の栄光を振り返るに早すぎることはないといわんばかりに中世を舞台とした歴史劇『ヘンリー6世』3部作をものしたのがシェイクスピアだ。
グレグソンが原典に忠実な構成で表現した「始まりの予感」と「終わりの始まり」
それに基づき、現代イギリスを代表する作曲家エドワード・グレグソン(1945~)が吹奏楽曲《剣と王冠》を上梓したのは歴史的にみればごく最近、20世紀末のことである。
《剣と王冠》は、かつてシェイクスピアの各歴史劇のために作曲された劇音楽を、グレグソンが吹奏楽向けに3部構成の組曲として再編成したもの。なぜわざわざそんなことをしたかといえば、それが200名の大規模合同バンドで当時国内ツアーを企画していたイギリス空軍音楽隊の、たっての希望だったから。
となれば必要なのは、大編成のバンド演奏でこそ映える楽曲の華やかさと力強さ。つまりは軍隊の覇気と勇気をおのずと鼓舞するような、ダイナミズムとスケールの大きさだ。
なるほど、もともと壮大な歴史劇の光景を表現するために作られた音楽が下敷きになっているだけあって、グレグソンはこの要求に第1楽章の冒頭から十二分に応えている。2本のトランペットが重なり合って響き合うファンファーレは、まさに血沸き肉躍る「始まりの予感」。このうえなく高らかで、これ以上ないほど確かな戦いの合図というものだろう。
しかし合図だけあって、冒頭のファンファーレはいかにも短い。その後に続くのは対仏百年戦争最大の英雄、快進撃に次ぐ快進撃で、一時はついにフランスの王位継承権をも手中に収めたイングランド国王、ヘンリー5世へのレクイエムである。
グレグソンの楽曲の基になっているシェイクスピアの『ヘンリー6世』第1部でも、芝居はヘンリー5世の葬列の場面から始まる。とりわけ王の急死を悼む実の弟、摂政ベッドフォード公の「あまりに名高く、ために長く生きられなんだヘンリー5世よ、イングランドがかつてこれほど価値ある王を喪ったことはなかった」という決定的な台詞は、観客に波乱のドラマを予感させずにはおかない。決して無視できない重要なオープニングだ。
それをきちんと拾い上げることから始めている《剣と王冠》の構成は、シェイクスピアの原典に極めて忠実。この後も芝居の筋書きどおり、フランスへの行軍とオルレアンでの敗退が表現され、先のレクイエムが繰り返されたあと、第1楽章は再び華やかなファンファーレで幕を閉じてゆく。
ただし、最後にシンフォニックに響き渡るトランペットの音は、冒頭のそれとはちょっと違う。これはまさに「終わりの始まり」を示すもの。なにせシェイクスピアの『ヘンリー6世』第1部の流れに即していえば、第2幕第4場から第3幕第1場にかけてやにわに頭角を表し始め、ヨーク公爵に叙せられるリチャード・プランタジネットの、フランス遠征からの凱旋を表現している部分なのだから。


ヨーク公リチャードの凱旋が、なぜ「終わりの始まり」なのか。それはまず、彼が百年戦争の末期にあって、事実上の司令官を務めるほど優秀な軍人かつ将の器であったばかりか、まがりなりにも前王朝(プランタジネット家)の血脈を汲んでいたことに起因している。
その実力と血筋を頼みに、ヨーク公はやがて故ヘンリー5世の足元にも及ばない息子ヘンリー6世に反旗を翻し、それが薔薇戦争という大内乱を引き起こして、国内を未曾有の大混乱に陥れることになった。そして、自ら引き起こした血みどろの権力闘争のなかで、彼自身滅んでいくのである。これが百年戦争中にヘンリー5世がついにパリにまで押し広げた一大王国の「終わりの始まり」でなくて、一体何だというのか——。
薔薇戦争と紅白の薔薇の真意
そんな中世最大の権力闘争の首謀者にして犠牲者、つまりは薔薇戦争の中心人物であったヨーク公リチャードの姿を、シェイクスピアの原作に基づき色鮮やかに描出しているのが、19世紀末から20世紀前半のイギリスの画家ヘンリー・アーサー・ペイン(1868~1940)の絵。その名も《テンプルの庭で赤と白の薔薇を選ぶ》にほかならない。

ロンドン旧市街シティにあるテンプル地区は、中世以来の歴史を誇る法曹の園。インナー・テンプルなど同地区に4つ存在する各法曹院の敷地内には、ヘンリー・ペインの絵さながら、今も美しい庭が存在するが、画中で「赤と白の薔薇」が摘み取られているのには、すこぶる中世的な理由がある。
というのも、赤い薔薇は国王ヘンリー6世を頂点に戴くランカスター家、対して白い薔薇は王に反旗を翻したヨーク公リチャードを擁する前プランタジネット王朝傍系ヨーク家の、誰もがよく知るシンボルだった。内乱にしては妙に雅な「薔薇戦争」の名称が、ランカスターとヨークという互いに相争う2つの名家がそれぞれ色違いの薔薇を徽章としていたことに由来するのは、もはやいわずもがな。
ヘンリー・ペインの絵は、シェイクスピアの原典以前に、まずはこの歴史的知識を大前提として描かれたもの。残念ながら、中世イギリス史にちらとも興味と関心を持てない鑑賞者は、手に白薔薇を持ち眼前の男に突き付けている人物が、白薔薇を目印とするヨーク家の頭領ヨーク公リチャードだとは永遠にわからないかもしれない(知識があればあったで、ランカスター家めいた真っ赤な衣装のせいでヨーク公とは思えないかもしれないが)。
翻って、この絵が基づくシェイクスピアのテクスト部分についても同じことがいえる。
If he suppose that I have pleaded truth,
From off this brier pluck a white rose with me.
私が真実を述べていると信じてくださる方は、
どうかこの白薔薇を共に手折っていただきたい。
もしも中世イギリスにおける紅白の薔薇の意味を知らなかったら、『ヘンリー6世』第1部の第2幕第4場で、ヨーク公リチャードが政敵サマセット公を含む諸侯らを前にこう述べるシーンは、なんだかロマンティックな場面と勘違いされるかもしれない。
グレグソンの《剣と王冠》第1楽章最後のファンファーレが「終わりの始まり」とはなかなか気づいてもらえないのと同様、白い薔薇を共に手折ることが徒党を組むことを意味し、手折った薔薇を突き付ける仕草が、敵に啖呵を切っているに等しいなどとは夢にも思わないだろう。
ことほどさように、イギリスの芸術と歴史は切っても切れない関係。誤解と誇張を恐れずいえば、別れたくても別れられない、離れたくても離れられない「歴史」という深い縁で、文学も音楽も絵画もみんなつながっている。





関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest